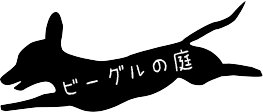その日は、澄み渡るような青空だった。夥しいほどの銃声や兵士たちの怒号も、今や耳には入ってこなかった。目の前に広がるのは赤く染まった地面、そして赤い海の中に倒れ伏した男。その傍らには、彼が撃たれた衝撃で手から滑り落ちた脇差が寄り添うように横たわっていた。
男の傷は深く、ひと目見ただけでその命の灯火が消えてしまったことが分かる。刀の時代が終わろうという中で自分を使い続けてくれた主を守ることができなかった絶望が、疲れた心を抉っていく。呼吸の仕方を忘れてしまったかのように、国広は呆然と主の骸を見つめていた。
程なくして、彼――新撰組副長・土方歳三は部下たちの手によって運び出され、五稜郭に埋葬された。そして自分もまた、彼と共にこの地で永遠の眠りにつく。敬愛する主の側で永きに渡る刀生を終える、それは多くの者に贋作ではないかと疑われた自分の身に余る幕引きだ。なんの不満もない最期、のはずだった。
唯一つの心残りが、薄れゆく意識の中で刀の身にあるはずのない心の臓を締め付けた。
「約束、守れなくてごめんね……」
***
本丸の朝は早い。今日も出陣のために戦装束に身を包んだ堀川国広は、自室にて最後の仕上げとなる赤い紐を手首に結んだ。朝の冷たい空気が少しばかり眠気を纏った意識を覚醒させていく。
刀剣男士として現世に顕現されて早三ヶ月が経とうとしている。歴史修正主義者との戦いは苛烈を極め、己が顕現されてから今に至るまでに片手で数えきれない程多くの仲間が戦場でその命を散らしていった。国広自身一月ほど前の出陣の際に敵の槍に腹を貫かれ、重傷を負って帰還したことも記憶に浅くない。
一度は消えた身である自分が此度は人としての肉体を得て刀を振るい、歴史を守るために戦う――それをこの上なく誇らしく思っている。現存していない自分に限らず、今の世で美術品として生き続けていた刀剣たちも、それは同じ気持ちであろう。刀の本分は敵を斬り、主を扶けることだ。だから、たとえ時間遡行軍と斬り結んだ末にこの身が朽ちようとも、いやそれこそが最大の誉である、とばかりに刀剣男士たちは死を恐れない。それは刀として生まれた者の本能であり、勿論国広の中にも根付いていた。
しかし、その本能に抗うように、まだ終わるわけにはいかないという衝動が心の中に杭を打ち込んでいる。今度こそ守ってみせる、言い聞かせるようにそっと呟くと、部隊長が何か言ったかと気遣わしげに尋ねてきたので、なんでもないと答えて気持ちを切り替えた。
珍しく手傷を負わず無事に本丸に帰還すると、近侍より急ぎ鍛刀部屋に来るようにと連絡があった。まさか――逸る心に突き動かされ、着替えることも忘れて目的の場所へ駆けていく。扉の向こうで懐かしい気配を感じる。――あれから三百年以上も生きている彼は、もう自分のことなど忘れてしまったのではないか、という不安が頭をもたげて途端に体が重くなるが、彼に逢いたい気持ちを奮い立たせて震える手で戸を開けた。
「おっ、誰だ?オレは和泉守兼定。かっこ良くて強い!最近流行りの刀だぜ」
自信に満ち溢れた表情で自己紹介をした彼は、国広の姿を認めると羽織った外套と同じ浅葱色の瞳を大きく開いた。
「久しぶりだね、兼さん……」
変わらない凛とした佇まいと美しい容貌を前にして、少しの気恥ずかしさを感じて目を伏せる。
「お前、国広、なのか?」
そうだと答える間も無く、ぐっと彼の逞しい腕の中に抱き込まれた。どくどくと早鐘のように聞こえる鼓動は、刀剣男士として生まれた彼が今ここに生きている証である。
「本当に、国広だな?夢じゃねえ、よな……?」
「うん。兼さんの相棒で土方歳三の脇差、堀川国広だよ」
「こんなところでお前にまた会えるなんてよ……主には感謝しねぇとだな」
「ごめん……あの時兼さんにまた会いに行くって言ったのは僕の方なのに、随分と遅くなっちゃったね」
暖かい体温に全身が包まれて浸透した頃にようやく力強い腕の中から解放されると、兼定の指が優しく国広の眦に触れる。
「なーに泣いてんだよ。こうしてまた会えたんだから構わねえって。これからまたかっこ良い相棒と一緒に戦えるんだからよ、ここは笑って喜ぶところだろぉ?」
自分でも気づかないうちに涙を流していたようだ。頬を伝う雫を拭く兼定の瞳も先ほどより潤んで見え、彼もまた国広との再会を待ち望んでくれていたのだと胸が温かくなった。
***
慶応元年(一八六五年)、春――
金属同士がぶつかる激しい音が、朝の眩しい空気に響き渡る。
人には触れることも姿を見ることも叶わない二柱の付喪神が、今日もその武を高めるために刀をとり、手合わせを行なっていた。
「そーら目潰しだ!」
その大きな掛け声と共に大柄で艶のある髪を長く伸ばした付喪神が地面を蹴り上げ、砂埃が宙を舞う。しかし、その動きは読んでいたとばかりに、彼とは対照的に小柄な付喪神が体を倒してひらりと躱すと、距離を一気に詰める。そのまま一閃を放とうとする構えに、背の高い付喪神も打ってこいと言わんばかりに迎え撃つ動きをとる。けれど、実際には一閃を放つと見せかけて足払いをかけられ、僅かばかり体勢を崩してしまう。その隙を見逃さなかった小柄な付喪神は、刀を握った相手の手首を峰で叩く。からんと音を立てて刀が地に伏した。
「畜生、今日も勝てなかったか!」
打たれた手を悔しそうに見つめた兼定を、国広はいつものように宥めた。
「今日はかなり惜しかったよ。足払いが決まらなかったら、押し切られてきっと僕の方が負けていたと思う」
「てめえはいつも惜しかったーだの次は負けるかもーだの言うがよ、なんだかんだ一度も負けたことねえよな……」
少し拗ねたような表情を浮かべる相棒は、どう言ったら納得して機嫌を直してくれるだろうか。昨年の池田屋事件で名を上げた僕たちの主が属する新撰組は、その活躍の場を広げていった。主と共に実戦で活躍する兼定の腕前が、日に日に洗練されているのを誰よりも国広は実感している。こと手合わせになると彼が負けてしまうのは、いつも主が彼を振るう姿を側で見ているが故に、なんとなくではあるが動きが読めるからに他ならない。そして、その有利さえも打ち破って自分を負かす力を近いうちに身につけるのであろう、と国広は確信している。それが誇らしくもあり、同時に何故か少し寂しくもあった。
「こう見えても兼さんよりずっと長い時間を生きているからね。でも、きっとすぐに追い抜かれてしまうと思うよ。それに、手合わせはあくまで修練なんだから、結果にそこまで拘る必要はないんじゃないかな」
「いーや、相棒に一度も勝ったことがないなんて本差の名が廃るぜ!いいか、絶対にてめえから一本とってやるからな、その時には一人前の相棒としてオレのことを認めろよ?約束だからな」
別に一本をとるまでもなく国広は彼のことを立派な相棒として認めているのだが、一度言い出したら聞かないのが彼の性分だ。ここは素直に彼の言葉に乗ることにしよう。
「分かった、約束だね。楽しみにしているよ。」
「華麗に一本決めてやるからな、楽しみにしてろよ!」
どうやら彼の機嫌も良くなったようで一安心した。ならば自分も、と口をつく。
「僕からも一つ約束してもいいかな?」
「ああ?なんだよ……」
怪訝な表情を浮かべながらも、言ってみなと次の句を促される。
「兼さんが僕から一本とるまでは、兼さんの側で支えさせて欲しいんだ」
一瞬呆気に取られたような顔をした兼定は、すぐに人好きのする笑顔と共に国広の頭を力強く撫でた。
「ばーか、あったりめえだろ!そもそもお前が側にいねぇと一本とれねえしよ」
「あはは、本当だね!」
「よぉし、そうと決まれば修練あるのみってな!」
思えばこの前後の時期が二柱の付喪神にとっても、彼らの主にとっても一番幸せな時間であったのかもしれない。その後数年で新撰組がどのような末路を辿るのかを、彼らは知る由もなかった。
きっとすぐに兼定に負ける日がやってくる、という国広の予想は大きく外れることとなる。組織内での粛清、戊辰戦争への参戦で局長をはじめとした多くの隊士を失った新撰組は、敗戦を重ねて北へと向かった。そして戦況が悪くなるにつれて、二柱の間で行われる手合わせの機会も減っていった。激しい戦闘の中で傷ついた刀身を修理するために離れていたことがあったのも一因であるが、何より厳しい状況の中で苦しむ隊士たちを横目に自分たちだけ楽しく打ち合おう、という気持ちになれなかったことが大きかった。
一度、こうなれば兼定に勝ってもらおうと意図して打ち合ったこともあったが、手ぇ抜かれて勝っても意味がねえと酷くお叱りを受けることになってしまった。そうして約束が果たされることがないまま、兼定と国広は主と共に蝦夷地に渡ることになる。
そして、運命の日は残酷にやって来る。戦況の悪化を感じた主は、その日小姓である市村鉄之助を呼び出した。曰く、遺品としてこれらの品を親類に届けてほしい、と。その中には兼定の本体である打刀も含まれていた。
「冗談じゃねえぞ、ここまで来てオレだけおめおめと帰れるかよ!頼む土方さん、最後まで一緒に戦わせてくれよ……!」
悲痛に顔を歪めて叫ぶ彼の声は、主に届くことなく虚しく響く。一度は断った鉄之助であったが、土方の決意がどうあっても変わらないことを悟ると渡された品を受け取り、出発支度を始めた。
「兼さん……どうやら、ここでお別れみたいだね」
出来るだけ胸の内を悟られないように、極めて冷静に話したつもりであったが、口をついた声は震えていた。互いの修理のために一時的に離れるのとは違う、再会の保証のない別れになる。それを頭では理解しているが、己の心はその事実を認めたくないと叫んでいる。
「ふざけるんじゃねえよ、まだ約束を果たしてねえだろうが……」
ああ、どうかそんなに悲しい顔をしないで欲しい。たとえどのようなことがあろうとも兼定には笑っていて欲しいと思うのは、己の我儘であろうか。
「そんな悲しい顔をしないでも大丈夫だよ。きっとまた会える、だからその時まで待って欲しいんだ」
「オレたちは刀だ、人間のように自分の意志で動けるわけじゃねえ。てめえがいくら会いたいと思ったとしても、そう易々と会いに来れるわけじゃねえんだぞ……」
「……そうだね、兼さんの言うことは正しいよ……でも、それでも僕は絶対、兼さんにもう一度会ってみせるから」
終ぞ明るい表情を見ることはできなかったが、兼定はしばらく黙った後に渋々と言った顔で頷き、国広の手を力強く握りしめてくれた。帰ってこれるようにと念じる強い想いが、皮膚を伝って体中に染み渡っていく。
「……わかったよ、絶対だからな。絶対に帰って来い。待ってるからな」
これ以上別れを惜しむ時間は許されなかった。自分の手を包む温もりが、名残惜しさを漂わせながら離れていく。鉄之助は兼定を手に陣を出立し、国広はみるみると遠ざかっていく彼の後ろ姿をただ見送ることしかできなかった。きっともう一度会える、という一縷の希望だけを胸に抱いて――。
***
兼定が本丸に来てから三週間、国広は幾度も彼と出陣する機会を得た。いや、正確に言えば審神者に頼み込んで同じ部隊で出撃することを認めてもらったのだ。僕の申し出に思うところはあったようだが、最後には分かったと頷き、兼定の出陣の折には国広も同じ部隊に編成することを約束してくれた。
だから国広は主の思いに応えるべく、戦場では兼定と抜群の連携をとって活躍した。最初こそ人の身に慣れずに戸惑うこともあった兼定であったが、一度戦場に出ると水を得た魚のように駆け回り、次々と敵を斬り伏せていった。その姿を一番近くで見守りながら、共に刀を振るい彼の背を預かる瞬間は何ものにも代え難い。
刀であった頃は共に主の腰に差されていたといえ、有事の際に主が振るうのは必ずどちらか一振りだ。特に国広が振るわれるのは兼定を扱うことが難しい室内などの狭い場所での戦闘に限られていたため、こうして共に戦うことができるなど夢のようである。何より、かつて守れなかった約束を今こうして果たすことができている。一度は守れずに朽ちた身であるが、刀剣男士としてもう一度心と記憶を持って生まれて兼定と再会を果たしたからには、今度こそ約束を守ってみせる。たとえ、彼がそのことを忘れてしまっていたとしても。
再会した二人は本丸唯一のかつて同じ主に仕えた大小として、戦では毎回と言っていいほど戦果を上げ、本丸で過ごす時も都合が合う限りは一緒に過ごすようにしていた。せっかく数々の名刀が揃っているのだから、彼らと交流を深める方が良いのではないかと最初は遠慮していたのだが、そんな考えはお見通しだと言わんばかりに彼の方から呼びつけてくれるので、ついついその言葉に甘えて共にいる時間を満喫してしまう。気づけば国広の方から何かと兼定の世話を焼くような形に落ち着いていった。
今日は出陣もないので食事の用意や洗濯など家事に精を出しているうちに、あっという間に夕刻を迎えた。兼定は自室にいるのかなと思い様子を伺うために廊下を歩いていると、お目当ての人物が向こうから歩いて来るのが見えた。
「よお、もう用事は済んだのか?」
「うん!ここのところ雨が続いていたから、今日はやっと洗濯ができてすっきりしたよ」
「そりゃよかったな。それならよ、夕飯までの時間ちょっと付き合ってくれねえか?」
「ええ?もちろん大丈夫だけど、何するの?」
わざわざこんな風に頼み込んでくるなど珍しいので何事なのかを聞きたかっただけなのだが、国広の言葉に兼定は押し黙ってしまう。何かまずいことを口にしてしまったのだろうか。慌てて気に障ってしまったならば謝ると話し出そうとする前に、兼定が口を開く。
「……道場行くぞ。手合わせ、してくれよ」
そう言って真剣なまなざしで見つめる兼定を前に、動揺した体は岩のように動かなくなった。どうして、と聞こえないように小さな声で呟く。兼定が顕現して三週間、かつて交わした約束のことはお互い一度も口にしなかった。勿論国広は別離から今に至るまで一度たりとも忘れはしなかったし、だからこそ主に頼み込んで必ず共に出陣するようにお願いをしたのだ。
けれど、兼定が覚えているのかは分からなかった。前の主の亡骸とともに葬られて刀生を終えてから本丸に顕現されるまで一瞬であった自分とは違い、あれから兼定は現在に至るまで三百年以上も生き続けているのだ。その年月は、たった十年にも満たない間だけ共にあった脇差との約束を忘れ去るには十分な時間である。そう思ったからこそ、国広は自分からこの話を決して出そうとはしなかった。彼が覚えていなかったとしても、かけがえのない思い出として自分さえこの胸に刻んでおけば良い。それで十分だと思っていたのに――。
「なんだよ、まさか忘れちまったなんてこと言わねえよな?ちゃあんと顕現されてからも他の刀剣たちと手合わせして腕を磨いたんだぜ、今度こそは負けねえからな」
「……勿論、覚えているよ。僕、約束破っちゃったし、あれから随分長い時間が経っているから、兼さんはもう忘れちゃったんだろうなって思ってた」
「ばぁか、相棒との約束を忘れるわけねえだろ?たとえ何百年経ったとしても、オレがオレである限りな。また会えてからずっと一緒に戦って、その上何かとオレの世話焼いてるとこ見たら、お前だってちゃんと覚えてるんだなって気づいていた。わかったらとっとと行くぞ」
自信満々な表情で笑いかける兼定の表情は、綺麗な夕日を浴びて眩しかった。立派に成長した彼に、まだ相棒と呼んでもらえるのが誇らしい。ならば、彼の期待に応えられるように精一杯の力を出そうと思う。
夕焼けに赤く染まった道場は、静かに二人の来訪を受け入れた。常は何人かの刀剣男士たちが集まり互いの腕を磨くべく打ち合って賑やかなはずの場所は、違うところに迷いこんだのではないかと思うほどの静寂に包まれていた。まるで、二人がここで雌雄を決することを待ち望んでいたかのようにすら感じる。
深呼吸をした兼定がゆっくりと刀を構えるのに合わせ、国広もそれに倣う。少しばかり肌寒さを感じる空気が、今の自分には心地良い。
「わかっているとは思うが、手加減なんてするんじゃねえぞ。尤も、手加減する余裕なんてくれてやるつもりもねえがな」
「当然だよ。兼さんの強さは誰よりも解っているつもりだから。全力を出して勝ってみせるよ」
「言うじゃねえか。なら、何の遠慮もなくいかせてもらうぜ」
示し合わせたかのように視線を交わした瞬間、勝負は始まった。兼定が国広に向かって迷いなく鋭い突きを放つ。それを刀身で受け流すと、息をつく間もなく斜めに斬り上げられたので、一歩下がって一閃を躱す。反撃の隙を与えないと言わんばかりに、何度も襲い来る気迫のこもった猛攻に堪らず距離をとる。しかし、国広の得物は兼定よりも短いので、距離を空ければこちらからの攻撃が届かない。このまま攻撃を避け続けても、不利になるのは膂力・体力共に劣る自分の方だ。何より、攻めに転じなければ勝つことはできない。
覚悟を決めると、兼定の繰り出した突きを今度は上身で受け止める。ともすれば力負けして柄から手を離してしまいそうなところを、指が軋むほど強く握り締めて衝撃に耐える。そして国広は、足をばねのように使って思いきり跳躍する。上空からの攻撃に備えて兼定が構えをとるが、予想を裏切るように国広の体はそのまま兼定を飛び越えて彼の背中側に着地する。不意をつかれた兼定が構えながら素早く振り返るのに合わせて、刀を振る……そう見せかけて、いつかのように足払いをかけた、つもりだった。国広の脚は虚しく空を切り、僅かばかり体勢が崩れたその頸に、冷たい感覚が張り付く。すぐに理解した、兼定の刀が国広の頸にぴたりと押し当てられたのだと。
「一本とったり。……随分とかかっちまって悪かったな」
「さすがだね……本当に、強くなったと思う。僕、兼さんの相棒になれて良かった」
兼定の不意を付けたのは確かだ。彼の目は思いがけない動きに驚きの色を見せていた。にも関わらず、その先の行動を読まれて対応されたのだ。完璧なまでの、敗北だった。
思った通り、彼は国広など追い越して誰にも決して遅れを取らない程の力を身につけてみせた。もう、僕が彼の側にいる必要もないのだろう。一人でだって十分に強い彼には、国広なんかよりもっと頼れる仲間がたくさんいるのだ。彼の側にずっといたい、誰にもその場所を受け渡したくないという心が決意を鈍らせようとするけれど、兼定のためにこの感情は押し殺さなければならない。
「おいおい、これで晴れて一人前になれたとはいえ、そんな過去形で話されたら兼さん寂しいぞ?」
「ううん……確かに僕達は相棒だったけど、兼さんは一人前のかっこ良くて強い刀になったんだ。僕が支える必要もない、立派な刀に……同じ主の腰にある大小でもなくなった今、僕が相棒である理由なんて、もうどこにもないんだよ」
「……お前に認めてもらったことはすげえ嬉しいぜ。オレたちが約束を交わしてから気付けば三百四十年も経っちまった。あの時はこんなにかかるなんて思ってもみなかったから、余計にな」
「……」
「でもな、一人前になったからってお前の相棒を止めるつもりはねえ。確かにオレは一人でも強くなったが、国広とならもっと強くなれる。何十年、何百年と経とうが、和泉守兼定の相棒は、堀川国広だけだって決まってるんだよ」
「……そんなこと、ないよ……」
どうして兼定は、こうも国広が欲している言葉と次々とかけてくれるのだろう。彼の優しさに甘えてはいけないと思うのに、国広の心臓は喜びに震えている。
「……国広。約束を果たしたら伝えたかったことがあるんだ。聞いてくれるか……?」
夕日で赤く色づいた兼定の顔はいつになく真剣な色を浮かべている。その貫くようなまっすぐな視線に、国広は頷くしかない。
「お前がいなくなってから、オレは土方さんの遺品として三百年以上過ごしてきた。オレがしっかりと存在することで、土方さんや新撰組のことを後世にも伝えられるようにしゃんと生きてきたつもりだ。でも、心にはどこか穴が空いちまったみてえだった。当然だよな。生まれてから一人になるまでほとんどの時間を共に過ごした主も相棒も、いなくなっちまったんだからよ」
解ってはいたことだ。だけど、こうして兼定の口から己がいなくなったことで彼を傷つけてしまったと聞くと、どうにもならなかったとはいえ自分自身にこの上ない無力感を感じてしまう。もう一度会えるなんて希望を持たせてしまわなければ、彼がここまで傷つくことはなかったのではないか。後悔の気持ちが押し寄せて頭の中を一杯に満たして行く。
「別にそのことで土方さんや国広を責めてるわけじゃねえからな。オレ達は精一杯生きて、戦った。その結果がどうあれ、文句はねえよ。オレが言いたいのはな、いなくなってから国広の存在がどれだけ大切で、かけがえのないものだったのか思い知ったってことだ。オレの隣には、いつだって国広がいた。それが当たり前だと思っていた、今思うと馬鹿野郎と叱ってやりてえくらいだな。その気持ちに気づいてから、会いたくてたまらなかった。絶対忘れねえって思ってるのに、時間が経つにつれてお前の声やどんな風にオレに笑いかけてくれてたのか思い出せなくなっていくのが、辛かった。だから、本丸に来て国広を見た時、すげえ嬉しかったんだ。朝起きてお前と一緒に飯食って、一日の終わりに今日はどんなことがあったと話す、そんな何でもない時間を過ごせることを幸せに思ってる」
兼定の言葉が、ゆっくりと国広の心に染みていく。いなくなってしまった後、彼がこれほどまでに自分を想ってくれていたなんて、考えてもみなかった。自分のことなんて忘れているかもしれない、などと考えていた己を殴ってしまいたいくらいだ。嬉しさと情けなさでぐちゃぐちゃになった感情が、止め処なく溢れて国広の頬を濡らしていく。
「……ありがとう、兼さん。あなたにこんなにも想ってもらえているなんて、僕は幸せ者だね。僕も、別れてから消えてしまうまでの間、兼さんのことを思い出しては会いたくて仕方なかった。意識がなくなる最後の瞬間まで、兼さんとの約束のことが頭から離れなかった。それはここに生まれてからもずっとそうだったよ。兼さんに会うまでは今度こそ死ねないって思っていたからこそ、厳しい戦いの中でも生きて帰ってくることができたんだと思う。本丸で兼さんと会えて、約束を果たして、何気ない時間を一緒に過ごせて、今僕はとても幸せだよ。兼さんの相棒は僕だけだって言ってくれて、すごく嬉しい」
精一杯、自分の想いが兼定に伝わるように言葉を紡いでいく。兼定もまた国広の言葉を受けて抑えられなくなった感情が溢れたのだろうか、碧い瞳から静かに雫が降りて引き締まった頬に落ちて行く。ひとしきり涙を流し合った後、少し照れ臭いように見える表情で兼定が話し出す。
「悪い、もう一つだけ伝えたいことがある。言わねえまま後悔するなんざごめんだから、言わせてくれ。確かにお前のことを最高の相棒と思っているが、人の形で生まれたことでもう一つ、分かった感情がある。……オレは、国広のことが好きだ」
今、彼はなんと言ったのだろうか。好き……というのは、相棒として、戦友としてということなのだろうか。いや、そうに違いない。早とちりして熱くなっていく体を何とか鎮めなければ、と思っていたところに、お前の考えなどお見通しだと言わんばかりの追撃がくる。
「言っておくが、相棒として好き、ってのとは違うからな……言い方を変えるわ、オレはお前に惚れてんだよ、心の底から」
「な……なんで、相棒としての好きじゃない、って思ったの」
「本丸でこの姿で生まれてから、今まで抱いていた感情が恋だって自覚したんだよ。国広の笑顔を一番近くで見ていたい。抱きしめたい。触れ合いたい。これが人の言う愛おしいってことなんだなって。だから、オレと恋仲になってくれねえか」
「……夢じゃない、んだよね……?」
「あったりめえだろ、こちとら何百年越しの一大決心の告白だぞ。夢であってたまるかよ。……んで、返事は」
「……嬉しい、です……僕、人の形をして生まれてから兼さんのことを想う度に、幸せだっていう気持ちと同時に胸が苦しかった。これが人を好きになることなんだなって理解して、兼さんに会えてからますます想いは強くなっていったけど、相棒としてだけで十分すぎるほど幸せだって思っていたから、言い出せなかった。僕も、兼さんのことが大好きだよ」
そう言い終わると同時に、先ほどの手合わせと告白の緊張から汗ばんだ腕に強く抱き締められる。国広も、そっと兼定の背中に腕をまわす。小さな体躯は兼定の大きな体にすっぽりと入ってしまい、彼の鼓動が耳に響いてくる。
「国広。……待っててくれて、ありがとな。今、きっと世界一幸せだわ」
兼定の温もりが離れていくのを名残惜しそうにじっと見つめていると、そっと頬に手が添えられる。ゆっくりと目を閉じると、唇に温かな感触を感じた。優しい口付けが、角度を変えて幾度も国広を包んでゆく。永遠に感じられるほどの愛しい触れ合いの後、国広は誰にも見せたことのない極上の笑みを浮かべて呟く。
「ありがとう、兼さん。……僕も、今が一番幸せ」
***
――それから一週間後の、雲一つない澄んだ青空に包まれた昼過ぎ。
兼定の元に、朝方出陣した部隊の隊長から一本の脇差が届けられた。手に受け取った刀身は真っ二つに折れ、宿っていた魂の存在はすっかり消え失せてしまっていた。見間違えるはずもない、誰よりも愛おしい脇差。呆気なく訪れた二度目の別れに、焼けた鉄の棒を肌に押し当てられたような痛みが心臓を締め付ける。
済まなかったと涙ぐむ仲間に、お前のせいじゃねえとかける言葉に嘘はない。誰もが戦場では懸命に刀を振るって命を燃やすが、その結果力及ばずに命の炎が燃え尽きてしまったとしても、戦争というのはそういうものだ。それが今回は国広だったというだけで、誰の責任でもない。分かっているのに、瞳から流れ落ちる雫は止められそうにもない。
――国広。一緒に過ごしたのはひと月にも満たない時間だったが、今までの生で一番幸せな時間だった。それは己が死ぬまで変わることはないだろう。お互い約束を果たし、気持ちを伝え合ったのだから、前に比べれば悔いはないはずだ。
一週間前に想いを通わせた時に見た幸せそうな笑顔が、頭から離れそうにない。今度こそは死ぬその瞬間まで、その愛しい姿を忘れることなく脳に焼き付けてみせる。そして何より、一人前だと認められた自分が、彼の分まで歴史を守って戦い抜いてみせる。たとえかつての主や相棒が失われる歴史でも、その先でもう一度巡り会えたのだから。誓う相手はもう傍らにはいないが、どこかで見守ってくれているような気がして、心の中で強く誓いを立てる。
耳に光る飾りが、分かったよと応えて揺れたように、感じられた。