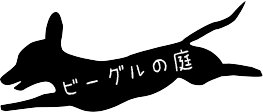本作は、石田スイ先生著「東京喰種 トーキョーグール」及び「東京喰種 トーキョーグール : re」の世界観を元にした二次創作となります。原作とは一切関係はございません。
●簡単に設定を紹介(原作を読んだことがあるので知っているよって方は読み飛ばしてください)
・「喰種」:見た目は人間と変わらないが、人間を喰べる食人種。人間よりも身体能力に優れ、気配を探れる他に怪我の治りも早い。赫子という捕食器官を使って戦闘が可能。
人間を喰べることでしか生きていけない(例外として水とコーヒーだけ飲める)が、一回食べたらひと月くらい活動できる。人間の食べ物はめっちゃまずく感じる上に吐き気を催し、無理やり食べると体調不良になる。喰種捜査官から追われ、駆逐される対象なので大多数は人間に紛れて生きている。捕食時や赫子を使った戦闘時には目が赤くなる。
・「喰種捜査官」:人間を食べる喰種を捜査・駆逐する人たち。喰種対策局(通称「CCG」)に所属する国家公務員で、捕まえた喰種の赫包という部位を加工して作った武器で喰種と戦う。階級があるが作中では詳しい言及はないので割愛。長曽祢さんが上等捜査官、兼さんと加州くんと大和守くんが一等捜査官。長曽祢さんがこの中では一番階級が上。
・「赫子」:喰種の捕食器官。これを使って戦う。次の四種類に分類される。
羽赫:肩からガス状に出る。機動力が高いのが特徴。堀川くんの赫子はこれで、固有能力として短時間なら飛行が可能。
甲赫:肩甲骨から出る。硬くて重量があるのが特徴。
鱗赫:腰から触手みたいに出る。威力の高さが特徴。
尾赫:尾骶骨から尻尾みたいに出る。バランス型なのが特徴。
***
人生には、時として大きな選択を迫られる瞬間がある。例えば進学や就職、結婚など前もって分かっているものであれば、そこに向けて覚悟を決めるだけの時間がある。けれでも、中には唐突にやって来ては突きつけられ、一つを選ばざるを得ない時がある。そんな時、人は何を思って一つの決断をするのだろうか――。
遅くまで働いた身体は程よい疲れに満たされ、帰って熱いお風呂に入ればぐっすり眠れるだろうと確信して僕は家路を急いだ。
僕、堀川国広は本丸総合病院に勤める研修医だ。志望は内科医で、担当している患者さんたちからの評判も悪くはないと自負している。とある理由から医学の道に進み、必要な知識や経験を余す所なく吸収しようと日々働きながら学んでいる。
何の変哲もない普通の真面目な医者見習い、そう思われているに違いない。実際ほとんどその通りなのだ、或る一点を除いては。
間もなく春が終わり雨季に入ろうかという空から降り注ぐ雨が、靴をじわじわと濡らして足までも浸食して来る。重たくなっていく靴に少しでも早く駅に着きたいという気持ちが勝り、いつも使う大通りではなく細い道を抜けていくと、ふと一本入った道から人の気配を感じる。夜が更けたこの時間に人が通ることはほとんどないはずだ。
珍しいな、と思ってちらりと覗くと、傘もささずに大柄な男がその身体を引き摺りながらよろよろと歩いている姿が目に入ってくる。僕よりも二回り近く大きい体から、ぽたぽたと水滴が落ちているのが見える。
最初、彼の服に染みてこぼれ落ちた雨粒なのだと思った。しかし、よくよく見れば赤黒い色を帯びたそれは、水滴などではない。紛れもない、男の血液だ。僕は職業柄血を見慣れているけれど、そうでなければ見た者が驚き叫ぶであろうほど、その身体は赤く染まっている。ふと目が合った男は、掠れた声で言葉を紡ぐ。
「……オレは……こんなところで、くたばるわけには……いかねえんだ」
暗闇の中でもはっきりと分かる浅葱色の瞳に鋭く貫かれる。その強い燃え盛るような意志がジリジリと伝わってきて、はっとして意識を失い傾いた身体を支えると、鞄の中にあったタオルで傷口を止血する。
酷い怪我だ。一体どんなことをしたらこんな傷を負うのだろうと思いながら男の身体を楽な体勢に変えると、力を失った彼の手からカランと音を立てて棒状のものが滑り落ちる。
――嫌な感じがする。でも、それが何なのかを確かめなければいけないような気がして、僕は恐る恐るそれを手に取る。
嗚呼、やはり――噂には聞いていたそれは、喰種から剥ぎ取った赫包を加工して作られる、対喰種用の兵器だ。ということは、この男は喰種対策局、通称CCGの捜査官なのだろう。
普通に考えれば、助けるべきではない。僕は喰種、彼らに駆逐される側の立場なのだ。ここに十人の喰種がいれば、十人が彼を見捨て、それどころか意識を失っている彼を格好の獲物だと喜んでその肉を貪るだろう。それだけではない、ここで彼が生き延びれば、自分や他の喰種がその手に掛かって将来死んでしまう可能性さえあるのだ。
だが、僕の心は不思議とそのような気持ちが湧かなかった。そればかりか、今もこの手は必死に彼を助けようと応急処置を進めている。
生きたい、という強い炎を宿した瞳が、頭の中から離れない。何故たった今出会ってただ一言声を聞いただけの彼に執着するのか、解らない。きっと喰種といえど医者見習いの端くれとしての矜持なのだろうと自分を納得させ、ここでできる限りの治療を終える。
救急車を呼べばいいのだろうが、その往復の時間を待つ間にも彼の命の灯火は燃え尽きてしまうかもしれない。それほどまでに深いこの傷は、じわじわと彼の命を蝕もうとしている。
かといって彼を抱えて地上を走ることは、人間より膂力に優れる喰種の身には可能だが、些か目立ちすぎてしまう。
選択肢は一つしか残されていないことを悟り、僕は彼を背負うとゆっくりとその体を傷つけないように肩から羽赫を展開し、雨空へと飛び立った。
***
目が覚めた時にオレが感じたのは、まず身体中に響く鈍い痛みだった。その痛みが意識を失うまでの記憶を蘇らせ、自分が生きていることへの驚きとそれ以上の喜びを感じる。
あの夜オレが相対した喰種は手強かった。何度も死を覚悟しながらも致命傷を食らわせた時は、オレもすでに奴の攻撃によって血に濡れていた。このままではまずいと思って助けを呼ぶために携帯を探すが、激しい戦闘の中でどこかに行ってしまったらしい。
仕方なく雨の中重い身体を引き摺って大通りまで助けを求めようと歩き出した辺りで、記憶は途切れている。視界が悪い中人通りのなさそうな道で倒れただろうによく助かったものだと、自分の幸運を心の中で褒め称える。
目覚めたところを看護師に見つかり、すぐさま担当医がやってきて念入りに体の調子を調べられる。人一倍頑丈な自覚があったのだが、それでも退院までには少なくとも一ヶ月はかかると言われて柄にもなく落ち込んでしまう。
喰種捜査官として戦うために日々己を鍛えることを欠かさないオレにとって、一ヶ月のブランクは痛すぎる。ようやく一級捜査官まで昇進したというのに、このままでは同期の清光や安定に差を開けられちまうと不機嫌さを隠さずにふて寝していると、病室の扉から見知った顔が現れた。
「ようやく目覚めたか。気分はどうだ?」
「最悪だぜ……体の痛みは我慢できるが、あと一ヶ月も病院生活なんて耐えられねえよ、長曽祢さん……」
兼定と同じくらい大柄で黒髪に金の混ざった派手な見た目をした男は長曽袮虎徹と言い、オレの頼れる上司であり仕事上のパートナーだ。と言っても、長曽祢さんはオレを信頼してくれているので、四六時中一緒に捜査するということはせず、時には単独行動で仕事をすることを認めてくれている。
今回も、そうやって単独で捜査を進めている時に標的の喰種と遭遇し、彼の到着が間に合わないと判断して一人で戦ったのだ。てっきりお叱りの言葉を受けるかと思ったが、そんな予想に反して彼はオレを褒めてくれた。
「一ヶ月か、短気なお前には辛いだろうな……しかし、よくやったぞ和泉守。おれが着くのを待っていては、奴を取り逃して更なる犠牲者を生みかねないところだった。お手柄だな。上には良く報告しておくから、お前は治療に専念して早く復帰するんだぞ?」
尊敬する長曽祢さんに褒められれば悪い気はしない。解りましたよと照れ臭さを隠すように頭を掻きながら返事をすると、そうだと思い出したように話を切り出される。
「お前の怪我、中々酷かったみたいだが運よく見つけて病院まで運んでくれた人がいたそうでな。しっかりと応急処置もしてあって、それがなければ命も危なかったかもしれないと先生が言っていたぞ」
そういえば、意識を失い倒れる前に誰かと目が合ったような気がする。きっとそいつがオレを助けてくれたに違いない。記憶が正しければ病院に近い場所ではなかったような気がするが、大柄なオレのことを運んできたというのだから相当体格が良い人物だったのだろうか。
思い出そうとするが、記憶に靄がかかったようにぼんやりとした影しか頭に残っておらず、どんな見た目だったかすらも分かりそうにない。
「そりゃあ助かった、オレの日頃の行いが良い結果かもな?……冗談はさておき、どこのどいつなのか知ってるのか、長曽祢さん」
「いや、それが本人が大したことじゃないのでと言って名乗らなかったらしくてな……しかしだな、噂によるとこの病院で働いている先生だそうだぞ」
「血まみれのオレを運ぶのが大したことじゃないって、随分とすげえ先生だな……とにかく、命の恩人とあっちゃ礼をしないと気が済まねえ。長曽祢さん、悪いがどの先生か探り入れてもらえねえか?」
「……おれも暇ではないんだがな。ともあれ大事な後輩の命の恩人だ、探してみようじゃないか」
「サンキュー、オレの方も探してみるから分かったら教えてくれ」
「ああ、ではおれはそろそろ仕事に戻る。ちゃんと安静にしていろよ」
自分を助けた人物がどんな奴なのか興味を持ったオレは、その日から初めて喰種ではなく人を捜査することになった。
すぐに見つかるだろうと思った目的の人物の捜査は、思ったより難航した。事情を知っているだろう医者はすぐに目星がついたが、個人情報なのでと頑なに教えては貰えなかった。
有効な手がかりを失いどうしたものかと思っていたところで、長曽祢さんが他にも事情を知っていそうな看護師がいると教えてくれた。彼女もまた医者と同様に教えることはできないと拒んだが、オレが粘り強く何度も聞くのでとうとう諦めて、私が言ったことは内緒ですよと前置きして耳打ちされる。
命の恩人の名は、堀川先生というらしい。この病院で働いて二年目の研修医をしており、同僚からも患者からも評判は悪くないとのことだ。これだけの情報しか教えては貰えなかった。
名前さえ分かれば十分だ、と思っていたが、物事はそう上手くいくものではないらしい。
研修医というのは色んな科で研修があるので日によってどこで働くか変わるらしく、どこにいけば会えるのかは一患者のオレには分からない。流石にシフトを教えてもらうなんてことは、知り合いでもない限り難しいだろう。名前も分かったというのに、状況が好転しないのがもどかしい。
そうこうしているうちに目が覚めてから二週間が経ち、リハビリが本格的に始まった頃、チャンスは突然オレの元に降ってきた。
リハビリで体を動かして多少の疲れを感じたオレは、昼の時間を過ぎて人が少なくなった食堂で冷たい飲み物でも買おうと歩いていた。近くのテーブルでコーヒーを飲みながら遅めの休憩をとっていた若い医者二人の元に、同じような年齢をした医者がカップを手に話し掛けているのが聞こえる。
「あっ、鯰尾先生、骨喰先生、お疲れ様!横良いかな?」
「おっ、堀川先生!どーぞどーぞ、夜勤で救急行ってたんだって?忙しかったみたいだね、お疲れ様~」
「……お疲れ様、堀川先生。昨晩は搬送が多くて忙しかったと聞いている、しっかり休んだ方が良い」
親しげに話している様子で、どうやら彼らは同期のようだ。
――いや、そんなことより。今、堀川先生と言ったか?
間違いようもない、オレの命の恩人と同じ名前。そう呼ばれた彼は研修医と言われても何ら不思議でない、それどころか学生にすら思える年齢に見える。ようやく見つけたという喜びから自然と足が彼らのテーブルに向かい、その姿を近くで捉えた瞬間に声を掛ける。
「あんたが堀川先生か?」
振り返った彼は、突然話しかけられたこともあって少々驚いたようだが、オレの姿を認めるとハッとして一瞬体が強張ったのを見逃さなかった。
「え、えーと……はい、そうです」
「ようやく見つけたぜ。あんた、怪我したオレを手当してこの病院まで運んでくれたそうじゃねえか?礼がしたくて探してたんだ」
「う、うーんと、僕ですか……」
「ああ、この病院には堀川先生は一人しかいねえって聞いてる」
「参ったな……教えないでいいって言ったのに……」
「オレがどうしても教えて欲しいって頼んだんだ、教えてくれた人に罪はねえよ」
「……はい、確かにあなたをこの病院まで運んだのは僕です。でも、医者として当然のことをしたまでなので、お礼なんて大丈夫ですよ」
ようやく認めたその姿を改めてつむじから足の先まで見る。身長は、せいぜいオレの肩と同じくらいだろうか。オレの体を支えたであろう腕は、薄く筋肉はついているが一般的な成人男性と比べれば細く見える。自分を運んだくらいだから上背のある男を想像していたが、目の前の彼はその想像とはかけ離れていた。
「いーや、命を助けてもらったんだ、礼をしなきゃオレの気が済まねえ。とりあえず退院したら、飯でも奢らせてくれ」
「……うーん、患者さんにそんなことしてもらうのは……」
断っても譲らないオレをどう納得させようかと思案している様子に、横に座って黙って見守っていた二人の医者が助けの声を掛けてくる。
「良いじゃん、堀川先生。別に直接担当している患者さんじゃないんだし、退院した後に奢ってもらうくらい大丈夫だって」
「……あまり勧められないが、堀川先生が助けたのだからそれくらいしてもらっても良いんじゃないかと思う」
二人の援護射撃とオレの譲らないぞという眼差しに折れたのか、仕方ないと頷く。
「よし、決まりだな。これ、オレの電話番号。仕事の後でいいから一度掛けてきて履歴に残して置いて欲しい、退院の日が分かったらこっちから連絡するから」
解りましたと微笑む顔に満足し、そういえば仕事以外で誰かと出かけるなどもう随分とご無沙汰だったことを思い出す。弾む気持ちからか病室までの道のりはいつもよりいくらか明るく感じられた。
***
助けてしまったことは仕方ない、早くこのことは忘れていつもの日常に戻ろう――そう努めて過ごしていたのだが、意地悪な神様はどうやらそれを許してくれないらしい。
忙しい夜勤が明けてなおも休むことなく昼過ぎまで働いていたから、僕はいつもより疲れていた。だから、食堂で同期の鯰尾くんと骨喰くんを見かけて話しかけた近くに彼がいたことなど、全く気が付かなかったのだ。
「あんたが堀川先生か?」
そう話しかけられて声のする方に顔を向けると、思わずぎょっとして体が強張ってしまった。せっかく忘れかけていたのに、あの夜見つめられた彼の切長の碧い瞳が鮮烈な記憶として頭の中を駆け抜けていく。
できる限り関わりたくない。そんな僕の気持ちなど知らずに、彼はお礼がしたいからと食事に誘ってきた。無論、僕は喰種なので人間と食事など本来できないからという理由もあるが、それ以上に喰種捜査官である彼と席を共にするなどしたくない。
何で助けてしまったんだろうなと思いながら、その誘いを断ろうと上手い言葉を探すが、彼は譲りませんとでも言いたげに固く腕を組んで黙っている。そんな僕らを見かねた二人に食事くらい行ってきたらと言われたら、頷くより仕方ない。
結局、連絡先をもらってその場は収まった。このまま電話しないでやり過ごしてしまおうかとも思ったけれど、あの様子だと電話をかけなければまた僕を探しにきてはその理由を問いただされかねない。
仕事を終えて家に着いた後しばらくの間黙って握りしめていた携帯電話のボタンを、ゆっくりと押していく。彼の気が変わってくれないだろうかと願いながら、無機質に聞こえるコール音が耳に流れてきた。
それから二週間後、仕事終わりに携帯を確認すると例の彼からメッセージが届いていた。そういえばそろそろ退院する頃かと思い開くと、予想通り明日退院するので近々で空いている日を教えて欲しいという内容だった。
残念ながら彼の気が変わることはなかったようだ。観念して候補日を伝えると、あっという間に約束が取り付けられる。ボロを出さないように今から聞かれそうなことをシミュレーションしなければと、ぐっと腹に力を入れた。
待ち合わせたのは、僕の行きつけの喫茶店だ。堀川先生の好きなところで良いと言われたので、芳醇な香りが漂う濃厚な味わいのコーヒーが飲めるここが真っ先に思い浮かび、素直にそう伝えた。
もっと高いもんで良いのに、と返事を返されるが、僕にとってはどんな高級寿司だろうが分厚いステーキだろうが、等しく食えたものではない。唯一人間と同じ食せるものといえば、水とコーヒーだけである。それならば、せめてそれを味わえる店に行きたいと思うのが普通だ。
待ち合わせ場所に行くと、すでに背の高い紺色のスーツ姿の男が立っているのが見えた。端正な顔立ちにすらりと長く鍛えられた手足、艶のある漆黒の髪を肩の辺りで束ねた彼は遠目にもよく目立つ。まるでテレビの世界から出てきたように華やかで人目を惹く存在に、思わず見惚れてしまう。
側を通る女の子たちが振り返ってはヒソヒソとカッコ良いねと話しているのも頷ける。そんな彼と二人で食事をするというのは、僕たちの事情を抜きにしても気が引けてしまう。
声を掛けるのを躊躇っているうちに、彼の方が僕に気づいたようだ。目を輝かせてこちらに歩いてくる。
「よぉ、お疲れさん」
「あ、すみません、待たせてしまったみたいで……お仕事中でしたか?」
「いや、これから出勤。つってもまだ外を彷徨き回るのはダメだって言われたから、調べものとかに回されてるけどな……別に急ぎじゃないからゆっくり飯食おうぜ」
スマートに店の扉を開いてエスコートしてくれる彼に今更嫌だとも言えず、気付かれないように少し肩を落としながらコーヒーの香り漂う店内へと足を向けた。
相変わらず、この店のコーヒーは香りも味も素晴らしいものだ。だからこそ、この後その味わいも吹き飛ぶようなものを口にしなければならないことに気持ちが沈む。昼ご飯を、と言ったからには何かしら食べないと不自然だろう。覚悟はしてきたが、久しぶりに人間の食べ物を食べるのは憂鬱だ。
正面に座る和泉守さんは、見ているこっちが満たされるくらい美味しそうにハンバーグを食べている。ハンバーグを口に運ぶ度に目を煌めかせるその姿をずっと見ていたいと思ったが、食わねえのかと促されたので気づかれないように深呼吸をして、ようやくサンドイッチを口にする。
久しぶりの不味い感触に吐き気がとめどなく溢れ出てくるのを気取られないよう、ごくりと一気に飲み込む。人間と共に生きる以上は何度も経験しなければいけないとはいえ、何度食べてもこの不快感は慣れるものではない。
早く全て胃に流し込んで、このどうしようもない腐った脂のような味わいが残る口を、コーヒーのほろ苦い味で洗い流したい。そう思って次々に口に入れては飲み込んでいく。
そんな僕を怪しんではいないだろうかと彼の様子を垣間見るが、少し驚きはしたものの微笑ましそうな顔で見つめられる。
「なんだ、腹減ってたのか?いい食いっぷりで何より」
「ええ、まぁ……このお店は結構美味しいと評判なんですけど、気に入って頂けましたか?」
「おう、このハンバーグも肉汁たっぷりで旨いし、コーヒーも程よい苦味が口に広がって旨い!良いとこ教えてくれてありがとな、また来るわ」
「気に入って頂けて良かったです。……その後、体の調子はどうですか?」
「お陰様で、なんの支障もなく動けてるぜ。まだ激しい運動は控えろって言われてるけど、この分だと完治も近そうだ」
「良かったです、後遺症が残らないか心配していたので……」
「誰かさんが手当してくれたお陰かねぇ」
「いえ、とんでもないです。……手術を担当された先生の努力の賜物ですよ」
「ふーん……まぁそう言うことにしておくか。ところで、よくオレのこと病院まで運べたよな。威張って言うことでもねえが、オレ結構重てえぞ?そのほっせぇ腕で支えられたのか不思議だぜ」
想定されていた質問が飛んでくる。そう疑問に思うのも当然だろう、僕の背格好では彼を背負えば自身が隠れてしまうほどの身長差があるのだ。普通に考えれば意識のない大柄な彼を背負って運ぶのは大変なはずだ。喰種の膂力を持ってしてでなければ、そんなことは中々できないだろう。
用意した答えは少し無理を感じるものだが、こう返すほか仕方ない。
「……医者は患者さんを運んだり支えたりすることもあるので、見た目より力持ちなんです。こう見えて少しは鍛えているんですよ?……あまり筋肉がつく体質じゃないのが残念ですが」
「それはそうかもしれねえが……オレが倒れていたところってそんなに病院の近くでもなかった気がするんだよ。それだけの距離を雨の中歩いて運ぶの大変だっただろ?済まなかったな」
実は歩いてではなく飛んで運んだのだとは口が裂けても言えない。何とかこの話題から離れようとするが、彼のことをよく知らない中で捻り出した質問は、あまり知りたくないことだった。
「いえ……あれだけ大きな怪我をされたのもお仕事の中でですよね。……怖くないんですか?喰種と戦うの」
「まぁ、怖くないって言うのは嘘になるな。オレだって死ぬのは怖い。でも、オレたちが戦うことで、何事もない平和な暮らしを少しでも守ることができる。そこらへんで遊ぶガキや、毎日遅くまで家族のために働いてる大人や、定年迎えてのんびり過ごす老夫婦……そういった当たり前の、でもかけがえの無い日常が送れない世界なんて嫌だろ?だから、そのためにオレの力が役に立つってなら、それは誇らしいことなんだって思うぜ」
やはり、聞かなければよかった。彼はこの上なく素晴らしい志を持って、その身と武器一つで自分より身体能力に優れた喰種と戦う立派な青年だ。その命を懸けた働きに賞賛の声がかけられることは少なくとも、たくさんの人の平穏を守るために傷つくことすら厭わないのだろう。
そんな彼を助けることができて良かったと思う温かさと、これから彼によって捕まったり、殺されてしまう喰種がいるのだろうと胸を突き刺す痛みが入り混じる。
「だから、助けてもらって本当に感謝してる。医者ってすげえよな、人の命を救うことでそいつの未来の可能性を繋ぐんだ。あんたが雨の中必死に手当して病院まで運んでくれたおかげで、オレはまた多くの人を守るために戦うことができる。結果としてあんたもたくさんの人を救ってるんだ」
「和泉守さんはすごいですね、見知らぬ誰かのために命を懸けるなんてそう簡単にできることじゃないです。……それに比べれば、そんなに褒めて頂けるような人間じゃないですよ、僕は」
「……先生は何で医者になろうと思ったんだ?」
僕が、医者になった理由。それは彼のように多くの人を助けるんだという大義があってのことではない。
かつて、僕は浮浪児だった。親の顔も知らず、似たような境遇の喰種で集まっては生きるために人を狩り、分け前を貪る。今思えば人どころか獣に近いような生活だったが、それを疑問にも抱かなかった。それ以外の道など知らなかったのだ。
ある時、喰種同士の縄張り争いに巻き込まれてしまった僕は、命からがら逃げおおせた。他の仲間たちがどうなったのかは知らない。僕自身もボロボロになって、これはいよいよ死ぬかもしれないと路地でぐったりと寝ていたところに、一人の喰種が近づいてきた。
――殺される、そう思って体を竦めた僕を、その人はエメラルド色の宝石のように綺麗な目を心配そうに歪めて見つめていた。
「……大丈夫か?怪我をしているようだな。……うちに来て手当しよう」
普段であれば見知らぬ喰種相手に無遠慮に近づかれて大人しくなどしていないのだが、その時の僕には抵抗する気力すら残されていなくて、黙って彼の背中に背負われた。
彼の家には、もう一人彼の兄だという逞しくも明るい喰種がいた。二人に手厚く看病されて、数日経った頃には僕の体はすっかり元気になっていた。帰る場所はあるのかと聞かれて、迷った末に首を横に振ると、それならば兄弟として一緒に暮らそうと言われる。
断ることもできたが、僕はこの数日ですっかり彼らの与えてくれる温もりに浸ってしまった。戸惑いながらも頷けば、うんうんと目を細めて笑いかける二人に、生まれて初めて胸の奥が温かい不思議な感覚を知った。それが嬉しい、と言う感情なのだということも、後々彼らに教わったのだ。
名前は何と言うのだと聞かれても、名付ける親もいなければ名乗りあうような関係の者もいなかった。今まで身を寄せ合っていた仲間も同様で、お互いに名前をつけて呼び合うようなこともなかった。
正直に話せば、では今から名前を付ければ良いのだと豪快に笑う長兄によって、僕は「堀川国広」と言う名前を貰った。
「国広」というのは、長兄と次兄と揃いの名前だ。彼らもまた血のつながった兄弟ではないが、兄弟なら揃いの名前がいいとつけたらしい。
「堀川」は、幸運にも優しい次兄に拾われた通りの名前がそうだったことから付けられた。大切な兄弟に貰った名前は、少し擽ったくも僕の心を温かく包んでくれた。
名前と家族、その両方を貰っただけでも十分すぎるほど幸せだというのに、兄たちは僕に学校に通ってみてはどうかと言ってくれた。自分達は通えなかったが、たくさんの人と交流を持ち、学びを得るというのはとても素晴らしいことである、と。
人間と関わったこともない僕は最初は頷かなかったが、学校に通っていたという兄の友人の喰種の話を聞き、その話を聞いて嬉しそうにしている兄の顔を見て、自分が兄の分までたくさん学んでお返しをしようと学校に通うことを決めた。
兄のツテを借りて戸籍を得て中学校に入学した僕は、慣れない中で人間との交流や勉学に勤しんだ。特に勉強に関しては今まで全く触れていなかったこともあり、周りに追いつこうと寝る間も惜しんで机に向かっていた所を、よく兄たちに心配されたものだ。
そうこうしているうちに学年でも上位となるまで成績を伸ばし、高校は学区内でも有数の進学校に受かることができた。合格発表を知った時に僕よりも大喜びして抱きしめてくれた兄たちの顔は、未だに忘れられない宝物だ。
その頃だっただろうか、医者になろうと決意したのは。
僕達喰種は、病気になっても病院に行くことができない。理由は単純、人間に正体がバレてしまうリスクがあるからだ。喰種の体にはRc細胞というものが人間と比べて極端に多いため、検査でもされてそのことが分かればあっという間に喰種だと気付かれてしまうのだ。
だから、病気や怪我をしても病院に行くことはできない。ただじっと寝て症状が治まるのを待つか、悪化して死が訪れるのを待つか。それが、人間を食べることでしか生きられない咎を持って生まれた喰種に定められた宿命とでも言うのだろうか――
一度次兄が風邪を拗らせて病に伏せった時、僕と長兄は懸命に看病した。看病をしながら、何度も思った。なぜ、人間のように薬をあげることができないんだろう。自分の無力さが、悔しかった。幸い次兄は快方に向かって今も元気に暮らしているが、もしまた病気に罹らないという保証などどこにもない。
兄に助けられて学校まで通わせてもらったのだ、恩返しするならこれしかないと思い、僕はその日からますます勉強に勤しんだ。持ち得る時間のほとんどを机に向かって過ごした結果無事に医学部に受かり、優秀な成績を収めることで学費も大幅に免除してもらうことができた。そして今、医者見習いとして働くに至る。
こんなことを彼につらつらと話すわけにはいかない。医者は多くの人を治すのが仕事だし、今はそうして働いているが、元々は兄の助けになりたいというごくごく個人的な理由だ。あまり誇らしげに語れるようなことでもない。
「残念ながら、和泉守さんのようにたくさんの人を助けたい、っていう立派なものじゃないんです。身内が病気になった時に助けられるようにって、それだけで……」
「何でだよ、大切な人を助けたいっていうのだって立派な理由じゃねえか。それにきっかけはどうあれ、結局オレみたいな見知らぬ人間も助けてるんだから、カッコ良いと思うぜ」
あまりにもはっきりとした口調で恥ずかしげもなく褒めてくれるので、何だか自分がすごいことをしているのだと錯覚してしまいそうになる。兄弟以外でここまで褒められたのなんて、もしかすると初めてかもしれない。
彼のまっすぐとした言葉が心に響いて、背筋がピンと伸びたような感覚になる。
「そこまでハッキリと褒めてもらえると、何だか照れますね……和泉守さんはいつもこんな感じなんですか?」
「オレか?そうだな、思ったことはハッキリ伝えるようにしてるぜ。嘘ついてもすぐバレちまうってのもあるけどな」
快活に笑う彼と話すのは心地よい。その明快な物言いが少しだけ長兄に似ているからだろうか。
すっかり打ち解けた僕たちは、彼の仕事が始まる時間ギリギリまで色々なことを語り合った。帰り際に彼の方から、せっかく仲良くなれたんだからまた飯でも行こうぜと言われた時は、二つ返事で分かりましたと返していた。
今日ここに来るのが気乗りしなかったというのが嘘みたいだ。彼が僕らの敵である喰種捜査官であることを忘れたわけではないが、たまに会って話すくらいは、許されてもいいと思いたい。
***
オレの命の恩人は、想像よりもずっと小柄で細いがとてもいい奴だった。まぁよく考えれば、雨の夜に血まみれで倒れていたデカい男を手当して、その血で服が汚れるのも厭わずに病院まで運んでくれたんだから、悪い奴であるはずもないか。
オレのようにたくさんの人のために命を賭けれるのはすごいことだと真剣な面持ちで言われたことは、思ったよりオレの心に響いて背筋の伸びるような気分になる。確かにオレは喰種捜査官の中では珍しく、身内を喰種によって失くしたというわけではない。ただこの恵まれた肉体を何かの役に立てようと思って、捜査官養成所の門を叩いた。
捜査官の仲間以外で面と向かって仕事のことを褒められたのは初めてのことだったので、柄にもなく照れてしまった。
この仕事に就いてからは、自分が喰種に狙われ、恨みを買いやすい立場であることを自覚しているので、職場以外で人と接することを避けていた。学生時代からの付き合いがあった友人とも、気付けば疎遠になっていた。
だから、年の近い堀川と何でもないことを話す時間はとても楽しかった。彼は医者らしく聞き上手で、オレが話すことに一つ一つにうんうんと相槌を打って続きを促してくれる。
本当はもっと話したかったのだが、オレの仕事の時間もあったので解散することになり、また飯でも行こうと誘ってもちろんと爽やかな笑みで返された時は思わずにやけてしまったのではないかと思うほど嬉しかった。
それからオレたちは忙しい合間に時間を見つけては、美味しい料理に舌鼓を打ったり酒を飲みながら会話に花を咲かせたりした。と言っても堀川は酒を飲めないらしく、もっぱら酌をしては酒でご機嫌になったオレの話を嬉しそうに聞いているのだが。
一度酔っ払って足元がおぼつかなくなってしまった時は、肩を支えてオレの家まで連れて帰ってもらったこともある。小さい身体で懸命に力を入れて支えてくれる姿にいつぞやの時みたいで済まねえなと言ったら、本当だよと笑って許してくれた。その後の記憶は曖昧だが、頬を緩めてくしゃりと笑う顔だけは、しっかりと頭に残っていた。
最初は「和泉守さん」、なんて他人行儀な呼び方で呼んでいた堀川も、オレの気を遣わない態度を感じてそんな壁を作る必要はないんだなと分かってくれたようで、いつしかオレのことを「兼さん」なんてあだ名で呼ぶようになった。その特別な呼び方が存外気に入ったので、オレの方も国広と彼を下の名前で呼ぶようになった。
あんなに職場以外の関係は持たないようにしていたのがバカらしくなるほど、国広と一緒にいる時間は普段命懸けで働くオレを癒してくれた。こいつのいるこの世界を守るためにも、前よりも頑張れる気がした。分野は違えど、お互い多くの人を助けるために働いているのだと思うと、自分も負けてはいられないと気が引き締まる。
そんな心地良いぬるま湯のような生活がいつまでも続くと、思っていた。
***
その夜は、疲れがあったのでいつもより油断してしまっていた。本来なら夕方には仕事を終える予定だったのが、急患のオペが発生したことで手術を担当する先生の分の業務を僕が請け負うことになり、気付けば日付が変わってしまっていた。
まもなく冬を迎えようとしている肌寒さの中、数駅先の家までの道のりを歩くのは少々辛いものがある。タクシーで帰ろうかと思い大通りを見渡すが、今日に限って中々捕まえられずに諦めて夜道をとぼとぼと歩いていた。
大通りを曲がって少し細い道に入った時、向こうから人影が歩いてくるのが見えた。疲れた頭はその姿を認識してはいたが、気配を探ろうとまでは気が回らなかった。
だから、その男が異常な気配を漂わせていることに気付くのが遅れてしまった。近づくその目は赤くギラギラと獲物を探すように輝いており、腰の辺りから触手のようなものが蠢いてその体から見え隠れしている。赤い瞳に赫子、紛れもない、喰種だ。
初めて見るその顔に、恐る恐る話しかける。
「あの……どうかしましたか?もししばらく食事していないってことなら、分けてもらえるツテを知っていますけど……」
そう宥めるように話しかけるが、男は黙って僕の目を見つめている。僕が喰種であることはもちろん向こうも分かっているはずだ。
男の口元がニヤリと歪んだのを視界に捉えた時には、右腕を熱い感覚が貫いていた。
「ククク……!バカだなお前、こんな無防備に夜道を歩いて!格好の獲物だぞ?俺が食いたいのは人間じゃない、喰種さ!人間は食い飽きたからな、たまには共喰いするのも悪くないと思ってなぁ」
彼の鱗赫に貫かれた腕がジクジクと痛み、全身を重たくさせる。腕から瞬く間に流れ出る血液と共に、自分の体を動かす原動力までもが失われていく気がする。
こういった喰種を捕食する喰種の存在は、珍しいものではない。人間を食べれば足がつくからと、人よりも味は落ちるが共喰いをして食いつなぐ者がいることは知っている。
噂によれば、喰種を捕食することでより強い喰種へと進化を遂げる者もいるとのことだ。どんな理由があるにせよ、だからこそ喰種は人間のように簡単に同族を信用したりはしないのだ。
「大人しくしてくれるんなら、楽に殺してやるぜぇ?」
ビュンビュンと風を切りながら触手状の凶器を振り回して、愉快な笑みを浮かべた男が近づいてくる。少しでも触れればたちまち肉が削がれてしまうと思い、その場から逃げるように距離を取るが、果たして手負の身で逃げ切ることができるだろうか。
僕も短時間なら飛行できるとはいえ、向こうも鱗赫を使って跳躍することができる。血の跡と臭いを辿られてしまえば、追跡は容易いだろう。ならば、戦うか。
人間であろうと喰種であろうと、無闇に傷つけたり命を奪うことは僕の信条に反する。しかし、目の前に迫る相手は本気で僕を殺して捕食する気なのだ。喰種と戦うことは久しくしていないが、こんなところでむざむざと殺されるわけにはいけない。
応戦するしかないかと立ち止まり拳にぐっと力を入れた時、目の前に迫る鱗赫が真っ二つに斬られるのが見えた。
「グッ……!!だっ、誰だ!?俺の食事を邪魔するクソ野郎は!」
「クソ野郎はてめえの方だ」
そう低い声が答えると、勢いをつけて大きな影が男の懐に素早く入り込み、手に握った剣状の武器を斜めに一閃する。斬られた部位の回復を待たずに、男の体がバターのように切られて呆気なく両断される。
腹に響くほどの悲痛な断末魔をあげながら、ゆっくりと二つに割れた体が肉塊となり地面に落ちていくのを、呆然と眺める。その見事な太刀筋に思わず見惚れてしまった。本当ならば、この場を一刻も早く立ち去るべきだっただろうに。
「チッ、殺さずに捕まえろって怒られちまうかな……まぁ民間人が襲われてたって言えば許してくれるか。おい、大丈夫か?」
近づいてくる見上げるほど大きな影と、凛とした声が見慣れた姿と重なる。まさか、こんな偶然があっていいのだろうか――
「……ッ、国広、か?なんでこんなとこに……んなことより腕、怪我してるじゃねえか!」
「……兼、さん」
僕の血だらけの腕を見て慌てて駆け寄ってくるのは、間違いようもない大切な友人だ。何だってこんな時に会ってしまったのかと運命を呪わずにはいられない。とはいえ、彼がこの場に来たからこそ僕は助かったわけではあるのだが。
「クソッ、あの野郎、国広に怪我なんかさせやがって……とにかく、止血して病院行くぞ」
「ううん、僕なら大丈夫だよ。助けてくれてありがとう、後は自分で止血して手当しておくから……」
「あぁ?何言ってやがる、こんなに血が出てるのに何でだよ」
病院で治療を受けることができない理由など、言えるはずもない。幸い兼さんはあの男が僕のことを共喰いするために襲ったのではなく、人間を食べるために襲ったのだと思ってくれている。何とかして納得してもらわなければ。
「……今日は、病院が急患が多くて大変だったんだよ。だから、僕の怪我で忙しい先生たちの手を煩わせるわけにはいかない。僕だって医者だから、このくらいなら自分で処置できるから心配しないで」
果たしてこの言い訳で通用するだろうか。訝しげに僕を見つめている彼の瞳はあまりにも綺麗で、まるで僕の心の内までも身透かされているような気がして冷や汗がじっとりと背を濡らす。
「……仕方ねえな。そこまで言うなら、オレんちまで来い。その方が近いし、ちゃんと手当できる道具もある。いいな?」
有無を言わせないという厳しい表情で諭されては、頷かざるを得ない。ここからならば、僕の家よりも兼さんの家の方が近いと言うのも事実だ。優しい兼さんは、怪我をした僕のことを放っておくことなどできないのだろう。今ばかりは、その優しさが胸に染みて痛いくらいだ。
断る理由を探せずに、黙って彼の広い背中を追いかけて歩く。僕がただの人間だったのなら、何の迷いもなく彼の誘いを受けることができるのに。人間が、羨ましいな――
忘れていた腕の痛みが、今頃になってじんじんと体を蝕んでいた。
***
夜の見回りというのも、オレたち喰種捜査官にとっては大事な仕事の一つだ。喰種は人目を偲んで夜に人を襲うことが多い。そのため、オレたちは交代で夜の街に目を光らせては、その被害を少しでも減らそうとしているのだ。
今日はいつもであれば帰ってもおかしく無い時間だったが、何か嫌な感覚がどろりと胸に纏わりつくような気がして、念入りに見回りを進めていた。特に大通りから一本入ったような細い道は危ない。そう思って該当する場所を隈なく見ていったところで、遠くに不審な男の姿が目に入った。
異様な雰囲気を醸し出しているそいつの腰辺りから、得体の知れないものが生き物のように蠢いている。男は少し前に立っている影に近づいて一瞬立ち止まると、腰から生えたその触手のような、それでいて切っ先の尖った凶器を素早く振り下ろすのが見えた。
間違いない、喰種だ。そう思った時には駆け出していた。襲われている方が男から距離をとったのを見て、無事であることに一安心する。とは言え喰種から丸腰の人間が逃れるのは不可能に近い、一刻も早く助け出さなければ。
少し走ったところで、距離をとって逃げていたはずの影が足を止めてしまう。喰種に襲われた恐怖のあまり足がすくんでしまったのだろうか。だが、この距離からならば男よりも疾く一撃を繰り出せる。
走りながら力強く振るった武器で、襲い掛かろうと振り回された鱗赫をそうはさせないとばかりに斬り落とす。目の前の獲物に夢中になっていた男はオレの接近に気付かなかったようで、驚愕に赤い瞳をカッと見開いた。
間髪入れずにその懐に入り込み、ガラ空きになった胴を一太刀で斬り捨てる。反撃の間も無くその身体が二つに割れて、しばらくの断末魔の後に沈黙したことを見届ける。隙をついた攻撃であっさりと倒せたことに、思わず安堵の息を漏らした。
本当はできる限り喰種は生きたまま捕獲するようにと言われているのだが、襲われている民間人を助けるので精一杯だったのだ、きっと長曽祢さんならよくやったと笑って許してくれるだろう。
助けた人物の無事を確認するべく近づいていけば、その顔はよく知る者だった。
「……ッ、国広、か?なんでこんなとこに……んなことより腕、怪我してるじゃねえか!」
呆然とした顔でオレを見つめている国広の右腕は、暗闇でも分かるほどのドス黒い鮮血で染められている。それを目にした瞬間、今しがた自分が殺した喰種に対して、例えようのないほどの殺意が沸々と湧き上がる。喉の奥まで熱くなり、ドクドクと脈が速まっていく。相手はもうすでに、死んでいるというのに。
何とか己の内で煮えたぎる怒りを抑え込んで国広を病院へ連れて行こうとするが、その必要はないと珍しく突っぱねられる。確かに国広は医者だが、利き腕を怪我した中で自分で手当をするのは大変だろう。
それに、彼の血の臭いに惹き付けらた別の喰種が宵闇に紛れてやって来て、その肉を引き裂こうと襲ってくることが起こらないとも限らない。
オレの命に代えても、絶対にそんなことはさせない。国広はオレが守ってみせる。そう決意して、オレの家で手当をするということで些か強引に国広を家まで連れていった。
家に着いて傷口を消毒するために、引き裂かれて血に汚れたシャツを脱いだ国広の体は多少の筋肉はついていれども細かった。自分の周りには鍛えているものばかりということもあるが、この薄い体など喰種の赫子にかかれば容易く貫かれて餌になっていただろう。
自分が着くのがもう少し遅ければ、確実にそうなっていた。血溜まりに倒れて虚ろな目をした国広が喰種に無惨に喰べられている姿が頭をよぎり、思わず体が震えてしまう。包帯を巻くオレの手の震えに気づいた国広が、心配そうに見上げてくる。
「あの、兼さん……大丈夫?僕、自分でやろうか?」
「ああ、済まねえな……大丈夫だ、怪我人は大人しくしてろよ」
腕にグッと力を入れて、無理矢理に震えを止める。握った国広の腕は、オレが力をこめればたちまち折れてしまいそうだ。
「こんなもんかな……あんまり無理に動かすんじゃねえぞ」
「うん、ありがとう。兼さん、包帯巻くの上手だね。……ちょっと意外かも」
「カッコ良くて強いオレは何だってできるんだよ。……まぁ、本当は昔から喧嘩とかしてしょっちゅう怪我してたから、だけどよ」
「あはは、兼さんらしい理由だね。でも、もう大人なんだから無茶しちゃダメだよ?」
「うるせえ、んなこたぁ分ぁってるよ」
たわいも無い会話。それができることがこの上なく嬉しい。失われていたかもしれない日常。国広がいない、日常。半年前まではそれが当たり前だったはずなのに、今では考えられない。掴んだ腕から伝わる国広の体温。温かいそれを、もっと感じたい。
――気が付けば、腕を引いてその華奢な身体を抱き締めていた。
「あ、あの……兼さん、どうしたの?もしかして、兼さんもどこか怪我しちゃったの?」
とくん、とくんと心臓の音が体温と共に伝わってくる。その音は徐々に速まっていき、国広がオレの抱擁に少し緊張していることが解る。
生きている。当たり前のそれが寸分狂えば失われていたのだと思えば、抱き締める腕の力が強くなる。今日ほど自分の働きを褒め称えたいと思うことは、二度と無いかもしれない。それほどまでに、国広はオレの中で守りたい、愛おしい存在になっていた。
今日のことがなければ、この気持ちに気付くことはなかったかもしれない。だが、気付いてしまった以上はもう止まることなどできない。
ゆっくりと抱き締めた腕を緩めて、少し困ったように眉を下げた顔を見つめる。このまま友人として過ごすことだってできる。だが、火のついた心がそれは嫌だと燃え盛り、胸の内を焦がしていく。ただの友人では、もう我慢できないのだ、と。
「国広……」
「うん、どうしたの?」
「オレは、お前が好きだ」
「……えっと、突然どうしたの?もちろん僕だって、兼さんのこと大切だと思ってるよ」
「……そうじゃねえんだ。友達としてじゃねえ、一人の男として、お前に惚れてる。……だから、オレと付き合って欲しい」
「え……」
国広の言葉が詰まる。たった今まで仲の良い友人だと思っていた男に告白などされたのだから、無理もない。ひょっとして冗談なのではないか、と訝しむ目つきに、そうではないのだと伝える。
「言っておくがオレは本気だ、もしここで断られたとしてもそんな簡単に諦めるつもりはねえからな」
「……なんで、僕なんかを……兼さんなら、もっと素敵な人がたくさんいるよ」
「オレにとって、お前以上に一緒にいて嬉しい奴なんていねえよ」
「……こんな僕にそこまで言ってくれるのは嬉しいよ。でも、ダメだよ」
「……ダメだって、何がだよ」
「僕なんか、兼さんに相応しくない……いつか必ず後悔する日がやってくる。兼さんに、そんな辛い思いはさせたくないんだ。兼さんに並び立つところなんてない僕がこうして友達でいられるだけでも、十分すぎるよ」
国広は、少し自己評価が低いきらいがある。数えきれないほど良いところをたくさん持っているのに、自分なんてと思っている。そんな謙虚なところも含めて好いているのだが、今は少しばかり素直に己の良さを認めて欲しい。オレは、この半年間色んな国広を見て来て、その上で愛おしく思っているのだから。
「オレの隣にいて欲しいのはお前だ、誰がなんと言おうが関係ねえよ。国広の良いところも悪いところも、そういうの全部引っくるめて好きだ。……今日、お前を助けられて本当に良かった。オレが駆けつけるのが遅れて、もしお前が死んじまってたらって思ったら、ゾッとした。お前を失いたくない。だから、今オレの想いを伝えたいと思ったし、できることなら応えて欲しいと思ってる」
「……何で……?僕なんか、兼さんに何もあげられないのに……」
潤んだ瞳が震えて、そこから一筋の雫がつうと静かに落ちていく。その涙が、どんな光景よりも美しいものに見えてならない。
「馬鹿、もうたくさん貰ってるよ。お前の笑った顔が見れるだけで、見てるオレまで嬉しくなる。だから、そんなこと言うな。……釣り合うとかそんなんじゃなくてよ、お前がオレのことどう思ってるのか、知りたい」
俯きながら苦しげに顰められる眉から、国広が今胸の内で自分の気持ちに葛藤していることが伝わってくる。しかし、その熱を孕んだ瞳は、決してオレの想いを嫌がっているわけではない。
否、それどころかオレのことを多少なりとも想っている、けれど何かが邪魔をしてその気持ちを受け入れることができない。そんな苦しみが見てとれる。
オレへの気持ちを受け入れられない理由があって、それを話せないのかもしれない。けど、そんなことオレにとってはどうだっていい。大事なのは、国広がオレを想っているかどうか、それだけだ。それ以外のものなど捨ててしまえ。
「国広、お前もオレのことが好きだろ?……お前が何を隠しているのかは知らねえが、その気持ちだけは隠せやしねえよ」
「う、嘘……」
「お前のことずっと見てきたんだ、それくらい解る。好き合った者同士、恋仲になったって何の問題もねえよな?」
紅く染まった頬が、オレだけをまっすぐ映し出す大きな瞳が、オレへの想いを表している。返事を待たずに、色づいた唇に自分のそれを押し当てた。
柔らかい、それでいて弾力のある唇を食む。角度を変えて口付ける度に、閉じた合わせ目から薄く声が漏れ出てくる。それが堪らなくオレを昂らせて、強引に隙間をこじ開けて中へと舌を侵入させていく。
国広の咥内は熱く、差し入れた舌が蕩けてしまいそうなほどだ。居心地の悪そうに収まっていた舌をすかさず捕えて、思い切り吸い付く。ちゅっちゅと音を立てて耳を犯す淫らな動きに、堪らず国広がオレの胸に添えた手に力を入れる。初心な反応がオレを余計に滾らせていることなど、国広は知るまい。
国広の抗議に耳を貸すことなく舌を絡ませていけば、観念したのか次第に彼の方からも絡ませて来てくれる。唾液を絡めて、啜って、互いの味を堪能していく。
キスとはこんなに気持ち良いものだっただろうか。蜂蜜よりも濃厚に感じる、深く染みるような甘さ。まるでキスを覚えたての高校生のように、夢中で国広の唇を貪った。
一体どれほどの間そうしていたのだろうか、ようやく顔を離した時には互いの舌が唾液によって作られた糸で結ばれていた。その淫らな光景にこの上なく興奮して、情動のままに国広をベッドの上に押し倒す。すっかり火照った体に纏わりつくシャツが邪魔で、乱暴に釦を外して脱ぎ捨てた。
のし掛かろうとしたところで、国広の視線が一点に集中していることに気が付き、その部分を自分も目で追う。脇腹から、腹の中心にかけて引かれた線。肌に馴染んだそれは、国広によって命を救われたその日についた傷跡だ。
「……傷、残っちゃったんだね。綺麗な身体なのに……」
悲しそうに見つめながら、そっと触れられる。もうすっかり塞がったそこは、撫でられても痛みなど感じない。感じるのは、少しばかりの擽ったさと、それ以上の愛おしさだ。
「国広が助けてくれた証だろ。これ見る度にお前のこと感じられるから、オレは好きだぜ?」
「……もうっ、そんなことばっかり言って……」
恥ずかしそうに顔を背けようとしたところを、両手でがっちりと薄い頬を捕まえる。閉じ込めた顔にそっとキスをすると、照れながらも微笑んでくれて、オレの口も自然と弛んだ。
もっと触れるようなキスで包みこんでやりたいという気持ちはあるが、熱を帯びた下半身はこれ以上我慢できそうにない。耳元に顔を近づけて、低く囁く。
「……国広。今からお前を抱く。……いいな?」
その言葉にピクリと身体が強張るのを感じたが、しばらくの沈黙の後、息を漏らしながらうんと頷く声が聞こえた。
できる限り優しく抱いてやりたい。昂る熱がそれを許してくれるだろうかと思いながら、ゆっくりと滑らかな肌に舌を這わせていった。
***
顔に温かい光を感じて、緩慢とした動きで目を開ける。少々寝不足の頭はいつもより重たいが、そんなことを容易く打ち消してしまうほどの温かい感触が腕の中にある。
オレの胸にもたれかかるようにしてすやすやと寝息を立てている存在に、胸がじわじわと幸福で満たされていくのを感じる。怪我をしているのに少し無理をさせすぎてしまっただろうか、オレが身動きしても起きる気配はない。
その首や胸にはいくつもの赤が散りばめられていて白い肌に綺麗なコントラストを描いており、昨夜の情交が夢ではないのだと語りかけてくる。
愛おしい恋人と身も心も結ばれて迎えた朝とは、少し気怠くもこんなにも心地良いものなのか。生まれてからこの方、最も記憶に残る最上の目覚めとなったことは間違いない。
いつもなら目が覚めればすぐに起きて鍛錬に励むのだが、今日ばかりは横で眠る恋人を抱きしめて二度寝に浸るのも悪くはないだろう。そう思って寄り添う身体を起こさぬようにそっと抱き寄せると、再び温いまどろみの中に落ちていった。
***
兼さんの気持ちを、受け入れるべきではなかった。
頭ではそう分かっていても、彼と恋仲になって過ごす日々があまりにも幸せすぎて、僕の頭から理性を奪い取っていく。
あの日、兼さんから想いを伝えられて、この上なく優しく愛してもらって――。僕の心は、すっかり彼に囚われてしまった。
喰種に襲われて怪我をした僕を気遣って、しばらくは自分の家に寝泊まりしろ、帰りはできる限り迎えに行くからと言ってもらえたことが嬉しくて、思わずその優しさに甘えてしまった。
今思えばそれが良くなかったように思う。毎日彼の顔を見て、今日はこんなことがあったとたわいも無い会話を楽しんで、抱きしめられて。兼さんとそんな時間を過ごす分だけ、どんどん彼に惹かれていく。離れたくない、もっと一緒にいたいという気持ちを抑えきれなくなっていく。
あんなに嫌だった人間のご飯を食べることだって、そのためなら何とでも無いことのように我慢できた。それどころか、兼さんが僕のために慣れない料理を作ってくれることが、堪らなく嬉しかった。それを美味しく味わうことのできないこの身が恨めしかったけど、僕が食べるのをうんうんと嬉しそうに目を細めて見つめる兼さんの顔を見れば、そんなことすらどうでもよくなった。
本来人間のご飯を食べた後は、見つからないように吐き出さなければ体に不調をきたしてしまうのだが、兼さんが一生懸命作ってくれたご飯にそんなことなどできるはずがない。無理やり水で流し込んで消化しては体調を崩す僕を心配そうに気遣ってくれるので、申し訳ないなと思いながらもそれをやめることはできなかった。
兼さんと出会うまでの僕は、どんな風に過ごしていたっけ。そんなことすら思い出せないくらい、僕の生活には自然と兼さんがいて、それが当たり前のようになっていた。しばらくの間、と言っていたはずなのに、いつの間にかよほど忙しく無い限りは兼さんの家で過ごし、半ば同棲しているような生活になっていく。
遅くまで働く兼さんのために何かできないかと本を片手に料理を始めて、美味しいのかも分からないそれをもぐもぐと食べながら旨いと頭を撫でて褒めてくれる手が、好きだ。疲れて帰ってきた僕をおかえりと出迎えて抱きしめてくれる腕が、好きだ。熱のこもる視線で貫かれた後、頬に手を添えてそっとキスしてくれる唇が、好きだ。
気が付けば、兼さんを構成するもの全て、一部の隙もなく好きで好きでどうしようもなくなってしまった。だからこそ、僕の胸は温かく、そして或ることを思い出すたびに、針で全身を刺されたように苦しくなる。
兼さんは人間、しかも喰種捜査官だ。対して僕は喰種。それが、変えられない現実。
だから、いつまでもこうして過ごすことなどできないのだ。大切な兄弟と偶に会っては互いの近況を話し、優しい恋人と毎日のように顔を合わせては一緒の時間を噛み締める。
この幸せな生活は、いつまでも続かない。そんなこと僕が一番よく分かっているのに、それを手放すことができない。僕の我儘が、いずれ兼さんを深く傷つけてしまうことになるというのに――
***
先日喰種組織の重要人物を捕らえることに成功してからというもの、職場にいる同僚たちは皆ピリピリと緊張した空気を纏っていた。今回の成果で、捜査が一気に進展するのではないかという予感がした。だから、長曽祢さんからその情報を教えられた時も、オレは驚きはしなかった。
「先日捕えた複数の喰種への尋問により、ついに喰種の一大グループの拠点と構成メンバーを割り出すことができた。ついては次の金曜日の夜二十二時より奴らのアジトへ突入作戦を決行し、一網打尽にする。詳細は追って伝えるが覚悟して各自備えて欲しい、との上からのお達しだ」
「そりゃあ嬉しい知らせだな。もちろん長曽祢さんも参加するんだろ?」
「ああ、おれだけではない、加州や大和守も出る。敵の数は30以上いるとのことだからな、こちらも相応の戦力で挑まなければ返り討ちに遭うだろう。敵の中には過去に複数の捜査官を殺害したことのある猛者もいるのだ、覚悟して挑んで欲しい」
「……なるほどな、それを聞いちゃ余計に負けらんねえよ」
オレは捜査官になるまでは、喰種に対して特別な憎しみを抱いたことはなかった。両親も健在で、親しい友人やその周りの人が被害を受けたこともなかったので、喰種が存在するという実感すらあまり湧いていなかった。
だが、捜査官になって時に仲間が喰種との戦いで散っていくのを見て、何とも思わないほど薄情な人間にはなれない。志なかばで仲間が死んでいくのを目の当たりにする度に、喰種を憎む感情は強くなっていった。だから、過去に仲間を手にかけたことのある喰種などに、絶対に負けはしないという闘志が心に火をつけた。
「意気込むのはいいが、ほどほどにな。熱くなりすぎれば周りが見えなくなる。そういった時ほど危険だぞ」
「へいへい、了解」
「……お前も大切な恋人がいるのだろう?悲しませるようなことをするなよ」
「……誰から聞いたんだよ、長曽祢さん」
「ははは、前にこっそり加州が教えてくれたのだ。あの和泉守に恋人ができて、しかもベタ惚れなんだとな」
「……あの野郎、覚えてろよ」
別に隠していたわけではないが、オレたちの仕事は命を落とす危険性のあるものだ。それが分かっているからこそ、大切な人を作らなかったり、あえて近しい人を遠ざけて危険が及ばないようにする者も少なくない。
だから、結婚でもしない限りは職場ではその手の話はできる限り避けている者が多いのだ。尤も、オレの上司や同期はそんなことなど気にしていないようだが。
「いいじゃないか、大切な人ができるのは良いことだとおれは思うぞ。守るべきものがあるからこそ、人は強くなれる。実際、最近のお前は特に強くなってきたように感じる」
「……長曽祢さんには敵わねえな。心配しなくとも、オレはそう簡単にくたばるタマじゃねえ。今回だって、ちゃあんと戦果をあげてみせるさ」
「お前はそれでいいかもしれないが、お前の恋人は自分の知らないところでお前が傷ついたり、命を落とすようなことになれば辛いだろう。今回は特に危険な任務になるんだ、心残りのないようにするんだぞ」
そう言い残すと飲んでいたコーヒーの空き缶をゴミ箱に捨てて、長曽祢さんは立ち去っていった。
心残り、か。この仕事をやっているんだ、いつだって死ぬ覚悟はできている、とまではいかないまでも、その可能性があることは承知の上だ。
だが、国広はどうだろうか。オレの仕事が危険を伴うことを理解はしてくれているが、ある日突然オレが死んでしまうことなど、考えたことがあるのだろうか。もしそうなってしまったら、あいつはどんな風に思うのだろうか。
突然一人残されて悲痛に暮れる姿が頭をよぎり、慌ててその想像を頭から振り払う。そんな悲しい思いなどさせてたまるかと思うが、戦場では何が起こるかなど保証できない。ならば、オレに何ができるのか。
前もって、近々大事な仕事があると伝えてしまおうか。関係者以外に情報を知らせることは決して許されはしないが、詳細は一切話さずにただこの日に大きな仕事があるのだと伝えることくらいならば、許されるはずだ。長曽祢さんも、暗にちゃんと伝えておけと言っていたではないか。
国広に心配をかけてしまうことは間違いないが、万一突然オレがいなくなることに比べればいくらかマシなように思う。丁度今日は夜勤もないので夜には国広も帰っているだろう。その時にこのことを話そうと決心すれば、張り詰めた心もいくらか軽くなったように感じられた。
***
今日は僕の方が早く帰ってきたので、何か兼さんの好きなものでも作っておこうか――そう思って台所に立って下準備を進めているところに、がちゃりと玄関のドアが開く音が聞こえた。
お帰りなさいと廊下をパタパタと小走りで進んで目にした顔は、珍しく浮かない表情だった。何か仕事で嫌なことでもあったのだろうか。
僕も兼さんも、互いの仕事については自分から話さない限りは聞かないようにしている。機密事項が多いだろうし、必ずしも聞いて気分の良い話ばかりでは無いことが分かっているからだ。
だから、心配ではあったけれどそれを僕の方から聞くのは憚られた。本当に辛い時は、僕のことを頼ってくれると信じている。今自分にできるのは、疲れているだろう兼さんを少しでも癒せるように、美味しい(自分では分からないが、いつもそう言って食べてくれているので真実だと信じたい)料理を振る舞うことくらいだ。
そう思って彼の鞄を預かってリビングに向かおうとしたところを、トントンと肩を叩かれる。
「……ちょっと話したいことがあるんだけどよ。飯食う前にいいか?」
「うん、もちろんいいよ」
良かった、きっと僕に話してくれる気になったのだろう。頼られたことが嬉しくて足取りが軽くなるが、兼さんの表情から察するにあまり良い話ではないのだろう。緩んだ顔を引き締めて、二人で座るには十分な広さのソファに並んで腰掛ける。
相変わらず兼さんの表情は厳しく、どこか思い詰めたような気配を感じたが、すぅと大きく息を吸って吐いた後に、ようやく口を開いてくれた。
「実はな、次の金曜日の夜にちょっとデカい仕事が入っちまってな……その夜は帰れそうになくてよ。せっかくの休みの前の夜だからどっか飯でも食いに行こうかって話してたのに、済まねえな」
「なんだ、そんなことなら全然いいよ。最近お仕事大変そうだね、頑張るのもいいけどほどほどにね」
果たして、本当にそんなことを話したかったのだろうか?互いの仕事で予定が狂うことは珍しいことではない、そういう特殊な仕事をしているのはお互い様なのだから。都合ができた時はすぐに連絡するようにしているので、そのことで喧嘩をしたこともない。
わざわざこんなに暗い表情を浮かべて話されたことは、記憶を遡っても見つけられそうになかった。
「……それだけ?なんだか兼さん、辛そうな気がするから」
「ああ、そんだけだ。お前も研修医から一人前のお医者様になって忙しくなったからな、ここ最近は一緒に飯行くのあんましてなかったろ?だから残念だと思ってな」
そう言って僕の頭をくしゃくしゃと撫でながら笑う顔は、どこかぎこちなさを感じる。嘘を言っているわけではない、だけど肝心なことを話してはいないのだろう。
兼さんの言葉から、それが何なのかを探る。
大きな仕事、と言ったか。わざわざそう口にしたからには、大規模な戦闘があるということなのではないだろうか。今まで仕事の前に「大きな」と付いて話したことなどなかったはずだ。万一のことがあった時のために、僕にそれとなく教えたのだろうか。詳しく話すことは、きっとできないだろうから。
喰種と戦う兼さんの身に何かあったら、と考えたことがなかったわけではない。喰種の中にはとんでもなく強い者もいる。そういった者と敵対すれば喰種ですら呆気なく殺されてしまうのだ、喰種よりも身体能力に劣る人間なら尚更だろう。そうならないように兼さんが懸命に己を鍛えていることは承知しているが、それでもどうにもならない時だってあるかもしれない。
兼さんが、喰種に殺されてしまう――
そんなこと、あっていいはずがない。誰かのために命を懸ける優しく強い彼が、ただ己の食欲を満たすために殺戮を繰り返す喰種に殺されるなど、そんなの認めない。
自分だってその喰種の一人だということは解っている。解ってはいるが、どうしようもないのだ。僕だって、できることなら人間に生まれたかった。喰種だからこそ出会えた大切な人たち、兼さんだってその内の一人なのだということは理解している。
でも、人間に見つからないように息を潜めて生きていくのだって、時に喰種同士の争いに巻き込まれることだって、本当は嫌だ。友達と学校帰りに買い食いしたり、大人になれば仕事終わりに同僚とお酒を飲みながら労ったり、そんな些細なことすら僕には叶わない。
どんなに頑張っても人間にはなれないし、人間を喰べることでしか生きていけない。せめてもの免罪符として、兄弟と共に人を殺さずに食いつなぐことくらいしか、僕にはできない。
無闇に人を傷つけたり、殺したりしないという考えは兄弟から教わったものだ。兄たちと出会うまでは好き勝手に人を襲って喰べていたし、それ以外の方法など思いつきもしなかった。
僕たちは、不幸にも自ら命を絶ってしまった人や、安楽死した人のご遺体を斡旋する喰種の業者の手を借りて生きている。人間の中でも他人を殺し傷つける犯罪者を狩ったこともあるが、そう都合よく何度も遭遇できるわけではない。
無論、どんな人であれ人間からすれば人を食べているということに変わりはないし、許容できることでもないだろう。それでも、せめて平穏に暮らしている人の命を奪うことはしたくないのだ。だから、食事も最低限の月に一度に留めている。自己満足と言われればそれまでだが、誰彼構わず襲って食らう獣のようにはなりたくないのだ。
この喰種の体を誇らしいと思ったことなどなかった。でも、自分が喰種であったからこそ、あの時兼さんをすぐに病院へと連れていけたのだ。そして今回だって、この力を使えば兼さんの助けになれるかもしれない――
そんなことを考えているうちに、普段なら兼さんと話しながら過ごす夕食の時間を終えてしまった。一緒にいる時間は大事にしたいと思っていたのに、物思いに耽ってしまったと反省しながら食器を片付けて洗っていると、ふと背中に温かい感触を感じる。
もしかして、片付けくらいオレがやると言ってくれるのかもしれない。疲れているだろうからせめてこれくらいは僕にさせて欲しいと思い振り返ったところで、唇が何かに塞がれる。
それが兼さんの唇だと気付いた時には片手でがっしりと腰を掴まれ、もう片方の手で仕事は終わりだとばかりに取手を下げて水が止められる。そのまま抱きすくめられて、啄むようなキスをされる。
濡れた手で彼に触れれば服を濡らしてしまうと両手が宙を彷徨っている間にも、段々と口付けが深くなっていく。ここでこのままするのかという抗議の目線を送れば、仕方ねえなというように眉を顰めて唇が解放される。
一先ず手を拭かなければ、とタオルに手を伸ばそうとした時、急に体が宙に浮き上がった。予想していなかった動きに思わず体が強張ったが、そんなことは気にせずに僕を横抱きにした兼さんによって、少し歩いたところで先ほどのソファに寝転がされる。
起き上がる間も無く兼さんが上に乗ってきて、僕の唇に獣のように噛み付いてきた。一部の隙もないほどに舐め回された後、下顎を掴まれて強引に口を開けられる。
差し込まれた舌は熱く、絡め取られた僕の舌が溶けてしまいそうなほどだ。吸い付かれて唾液を流し込まれれば、たちまち腹の奥から体が熱を帯びてくる。幾度となく彼と抱き合った身体が、この先に待つ快楽を期待して疼くのを感じる。
そのまま情動に流されそうになるが、自分たちがソファの上で、まだ汗をかいた体を洗っていないことを思い出して何とか堪える。
「んっ、兼さん……まだ、お風呂入ってないよ……?」
「後で一緒に入ればいいだろ」
「でも、ここソファだし……」
「悪い、待てねえ。たまにはベッド以外でするのも悪くねえだろ」
そう言うや否や耳朶を舐められ、シャツの裾から入り込んだ大きな手に胸の飾りを弄られれば、慣れた身体が快感を拾い上げて堪らずに嬌声が上がる。ここまでされてしまっては抵抗する気持ちもどこかへ去ってしまい、僕は目の前の快楽に身を任せた。
***
「堀川先生、ちょっといいですか」
看護師に呼ばれて立ちあがろうとした時、腰の痛みが体中に響いて一瞬たじろいでしまった。大丈夫ですかと心配する彼女に、慌てて立ち上がり要件を聞く。
昨晩は激しく抱かれたので、いつも以上に腰が辛い。次の日に仕事がある時は無理のないようにしているのだが、そんなことも忘れたかのように夜がとっぷりと更けるまで体を繋いだ。僕の方は意識も曖昧なほどで、風呂に入れてもらったところまでの記憶はあるが、その後のことは覚えていない。
あんなに性急に、かつ何度も求められることは中々ない。やはり、昨日の自分の推測は正しいのではないか、そう思えてくる。彼が後悔を残さないようにする人間であることは、僕がよく知っている。
兼さんの力になる、そして絶対に死なせはしないと誓ったはいいが、詳細など何も知らない僕に一体何ができるだろうか。聞いたところで、兼さんは決して教えてはくれないだろう。金曜日まであと何日もあるわけではないのだ、急がなければ間に合わなくなってしまう。
喰種の情報を探るには、喰種に聞くのが一番だ。丁度今日は集会の日だということを思い出して、時間に間に合うように仕事を終えるためにもいつも以上に気合を入れるぞと顔をバシバシと叩いた後、診察室へと足を向けた。
喰種には、互いに縄張りというものがある。僕のように人間を襲わない者はともかく、そうでない者たちはおおよその範囲内で人を狩っては捕食する。
だから、自分の縄張りに入って獲物を狩る喰種を許しはしないし、そうならないように予めここで狩りをすると意思疎通をする必要がある。それに、捜査官が探りを入れている、等の情報も生き抜くためには重要だ。
故に、同じ地域に属する喰種は定期的に集会を開き、互いの情報交換を行っている。毎回必ず参加する必要はないが、情報という武器を得るためにもこぞって参加する者は多い。僕はしばらく忙しかったので参加できていなかったが、今日ばかりはそうも言ってはいられない。
暗くなった人目の着きにくい広場に、それぞれフードや仮面で顔を隠した怪しげな者たちがぞろぞろと集まってくる。簡単に互いを信用しない喰種は、己の顔や名前を明かすことはしない。顔を隠し、必要であれば通り名で呼び合う、それがここでのルールだ。例に漏れず僕も黒い狼を模した面をつけ、その輪の中に入っていく。
リーダー格の無機質な黒い面をつけた喰種が、周りを見渡した後に話始める。この一週間でこんなことがあった等の情報を簡潔に伝えられる。何かこれ以外で知っていることはないかと切り出されたので、すかさず手を挙げて話を切り出した。
「最近CCGに何やら動きがありそうだと小耳に挟んだのですが、誰か詳しく知っている人はいませんか?」
情報の提供元は話せないから、どこでそれを聞いたのだと聞かれれば上手く誤魔化さなければいけない。そう思いながら恐る恐る周りの喰種の反応を伺う。
一体何のことだと訝しむ者が多い中、もしかしてあのことかと漏らす声を僕は聞き逃しはしなかった。声がした方に顔を向け、話して欲しいと先を促す。
「先週くらいに、捜査官が隣の区で集まってた奴らを見つけて、そのうちの何人かが捕まったって聞いたぜ。中にはデカいグループに入ってる奴もいたらしいから、尋問されて居場所を吐かれちまったかもって話だ」
「……その居場所っていうのはどこですか?」
「あぁ?なんでそんなこと聞く必要がある?」
「……」
「助けようってなら、悪いこと言わないからやめときな。それに奴らは30人以上いるからな、捜査官の方が返り討ちに遭うかもしれねえぞ?中には今まで捜査官や気に入らない喰種を何人も殺してきたっていうヤバい強さの喰種もいるって話だしな」
そんなにたくさん、しかも強い喰種もいるのか――ならば、なおさら黙っているわけにはいかない。
「……お願いします。どうか場所を教えて頂けないでしょうか?」
僕の必死の懇願に少し戸惑ったようだが、別に僕がそこで死のうがどうでもいいと判断したのかあっさりと教えてくれた。隣の区の使われなくなった廃病院、確かに喰種が身を隠すにはうってつけの場所だ。
ありがとうございますと丁重に礼をして、集会の解散を見届けるとすぐにその場を後にした。後数日しかないが、できる限りのことを尽くそう。戦闘から遠ざかって久しい体の調子を、何とかして戻さなければ。
喰種と敵対すれば、兄弟や仲間にも迷惑がかかってしまう。彼らに何も告げないことを申し訳なく思うが、これは僕一人で、やり遂げなければいけない。
例えどんな喰種が相手であろうと、絶対に兼さんを殺させはしない――
***
決戦の日は、雨季が近いからか生憎の雨模様だった。こんな日に作戦決行だなんてついてないなー、と愚痴る同期を横目に、手早く武器の最終調整を行う。
確かに雨だと視界が悪いが、それは向こうも同じことだ。それに、ざあざあと止まらない雨音に紛れて突入すれば、少しは奴らの意表をつけるかもしれない。そう思えば、着ている合羽から滴り落ちる雨も悪いものではない。
司令官が突入後の各々の動きを最終確認し、空気がピリピリと張り詰めていくのが分かる。この作戦が成功すれば、この区での喰種の活動は一気に抑えられることができるだろう。そう思えば、武器を握りしめる手に自然と力が篭る。
オレは長曽祢さんと共に、使われなくなった古びた病院に突入した後階段で一気に三階まで昇り、その階にいるかもしれない喰種を倒して制圧する。それがオレに課された役割だ。場合によっては臨機応変な対応も必要だが、一先ずはそれを第一目標として頭に刻み込む。
時計を確認した司令官が覚悟はいいかと全員を見渡した後、一瞬静寂が辺りを支配する。それを切り裂くように、突入!という声が響き、皆が一斉に音を立てないよう静かに走り出す。まるでかつての世の合戦のようだ。
入口に何人もの捜査官が雪崩れ込み、入った後はそれぞれの担当の場所に散っていく。遅れを取らないように、少し前を走る長曽祢さんの背中にしっかりと付いていく。
三階についたところで、同じく三階を担当する別のペアと二手に分かれて廊下を駆ける。ゆっくりと扉に手をかけて、一つ一つの部屋をしらみ潰しに調べるが、喰種の気配は感じない。収穫がないまま突き当たりの角を曲がろうとした辺りで、向こうに人の気配を感じる。
咄嗟に身を後ろに退けば、先ほどまで自分がいた場所にいくつもの弾丸が飛んでくるのが目に入る。曲がり角を利用して奇襲してくるとは、中々いい判断だ。そう思いながら武器を展開して構える。
そっと顔を覗かせれば、角の先には喰種が二体。二対二、長曽祢さんとオレならば決しては負けはしないと己を奮い立たせながら、先ほど弾丸を発射してきた右側に立つ鉄仮面をつけた喰種に斬りかかる。奴は恐らく中・遠距離から攻撃するタイプだ、距離を詰めればこちらが有利になるはずだ。
そんなオレの予想通り、鉄仮面は距離を取ろうと後ろに下がりながら背中の羽赫から弾丸を放つ。唸り声を上げながら黒い粒がいくつもオレの視界を覆っていく。それを全て撃ち落としながら近づくオレに、鉄仮面は焦りを感じたのか鋭く尖らせた羽赫を振るって接近戦を挑んでくる。
こちらの土俵に持ち込んでしまえばオレが勝つ、そう思ってその攻撃をいなしているところに、後ろから長曽祢さんの叫び声が聞こえてくる。
「和泉守!二階で戦っているチームが苦戦しているとの連絡を受けた!ここは任せてもいいか!?」
振り返る余裕はないが、この分だとどうやら長曽祢さんはもう一人の喰種を斃したようだ。流石は長曽祢さんだ。であればこの鉄仮面と一対一、負けてやるつもりなど毛頭ない。
「ああ、行ってくれ長曽祢さん!オレもここを片付けたら向かう!」
「分かった、無理はするなよ!」
廊下を駆けていく音が遠ざかっていく。鉄仮面は長曽祢さんを行かせないとばかりにいくつもの弾をその背に向かって打ち出すが、生憎その攻撃は想定済みだ。武器を回転させて盾の如く使いその全てを弾き飛ばすと、その勢いのまま懐に入り込む。
空気を切り裂く音を響かせながらオレを二つに割ろうと振り下ろされる刃状に変形した羽赫を体を滑らせて躱せば、目の前にあるのはガラ空きの胴体だ。両手で思い切り剣を左から右へと振れば、その骨ごと腹の辺りを一刀両断した。
タダでは死なない、と最期の力を振り絞って放たれた弾丸が一発だけチリッと肩を掠める。その攻撃を最後に鉄仮面は倒れ伏して動かなくなった。勝利を確信して、荒くなった息をゆっくりと整えた。
肩の傷は、少し痛むが大したことはなさそうだ。これならば問題ないと立ち上がり、念のため奥の部屋まで調べてから下へ加勢に行こうと歩き始めたところで、前方の天井がミシリと音を立てて歪んだのが目に入った。
ドォン、と雷が落ちたような轟音が鳴り響き、上からの圧力に耐えかねた天井が大きな穴を開け、巨大な影が勢いを付けて降って来る。それが床にぶつかった凄まじい衝撃に、オレが立つ床もミシミシと揺れて地震が起きたような感覚に襲われ、堪らずしゃがみ込む。
埃が舞ってよく見えないが、自分より数メートル先に、膝をついた巨体がいるようだ。ひび割れた床に押し付けられた逞しい腕の先にいるのは、先ほどまで一緒に集まっていた捜査官の一人だ。大きな手に握りつぶされて無惨にもひしゃげた体が、彼がもう息をしていないことを語りかけてくる。
「……なんだ、ここにもいたのか、虫ケラが」
まるでゴミでも見るかのような冷たい一瞥をくれたそいつは、恐らく資料にあった喰種だろう。本名は分からないが、通称・大太刀。その名の通り、大太刀のような長く鋭利な赫子を持ち、捜査官を何人も殺害したことがある凶悪な喰種だ。
大半の喰種が顔を隠すために付けている仮面も付けず、獰猛な獣の如き赤い瞳を輝かせ大きな口の端をニタリと歪ませた顔は途轍もなく醜悪だ。
まさか一人の時に鉢合わせてしまうとは、と自分の運のなさを嘆くが、かといって目の前で仲間が無惨に殺されたのを見て黙って逃げるような真似はしたくない。そんなことをするくらいなら、死んだ方がマシだ。
建物の中ならば獲物が長い分奴の方が不利だと思っていたが、先ほど上の階から床をぶち破って来たことを考えれば、壁や床、天井なども平気で破壊しながら攻撃できるだろう。こんな滅茶苦茶な敵を相手に、果たしてどう戦うべきか。
武器を構え、大太刀の動きを窺う。悠然と腕を組んで立つその姿には、一部の隙も感じない。ピリピリとした空気が肌に刺さる。オレの全身、細胞に至るまでの全てが、こいつは危険だと訴えかけてくる。
少しでも対応を誤れば命など簡単に摘み取られてしまう状況に、ゾクゾクと体の芯まで冷えていく。これでは体が強張って動きが鈍くなってしまう。向こうが動かないのであれば、先手必勝、それから相手の対応を見るべきだ。
ぐっと強く握りしめて、下から掬い上げるように斬りあげる。風を切って唸りをあげる一閃は、奴の腰から生えた凶器によっていとも容易く受け流される。バランスを崩しかけた体に迫る衝撃を感じて、咄嗟に後ろに跳び下がる。
ドォンと凄まじい音を立てながら、先ほどまで自分が立っていた床が大きくひび割れながら破壊されていく。一瞬たりとも遅れれば、ああなっていたのはオレの方だろう。息つく暇もなく襲いかかってくるそれは、まるで死神の持つ鎌のようだ。触れるもの全ての命を刈り取りとるような、鋭利な殺意を纏っている。
「どうした、逃げてばかりでは俺は殺せないぞ?」
「チッ…!」
そんなことは言われなくとも分かってる。だが、壁を削りながら迫ってくる大太刀を掻い潜り奴の体に一太刀を入れるビジョンが想像できない。銃撃が飛び交う戦場を防具も着けずに走り抜けるようなものだ。何か、こいつの動きを少しでも止められさえすれば。
オレがそんなことを考えながら下がっていく間にも、間の距離が着々と詰められていく。奴はオレよりもデカいのだ、このままではすぐに追いつかれて易々とミンチにされてしまう。攻めることも退くこともできないのならば、負傷を覚悟で攻め込むしかあるまい。
睨むようにその瞳を見据えたオレに、奴がニヤリと笑って跳躍し、一気にオレの眼前まで迫る。対するオレもその心臓をひと突きにしようと構えたが、どうしたわけかちらりと横を見た大太刀は急に足を止め、勢いよく後ろに跳んで下がった。
明らかにオレを次の一撃で仕留めようという表情だったのに何故――そう思った瞬間、先ほどまで奴の立っていた場所にいくつもの鋭い音が突き刺さる。
それは蒼く煌めく粒だった。壁に床にと刺さったそれは、明らかに大太刀を目掛けて放たれたものだ。
「……誰だ、邪魔をするのは」
忌々しげに殺気を放ちながら弾丸が放たれた方角を見やる大太刀に遅れて、オレもそちらをゆっくりと見つめる。大太刀の鱗赫によって壊された壁から、雨が降りしきる夜空が見える。その場所に立つ、小柄な人影。
目深に被ったフード付きの体の線すら隠すような外套と、顔を覆う狼の仮面のせいで何者なのかは全く分からない。ただ、背中からゆらゆらと揺れて見える羽赫が、そいつが喰種であることを教えてくれる。先ほどの鉄仮面の黒く燻んだものとは違い、蒼くもやもやと儚く見える羽赫はどこか美しささえ感じられる。
先ほどまで命のやりとりをしていたのも忘れて、思わず見惚れてしまった。
「……貴様も喰種だろう?邪魔だてするな、さもなくば殺すぞ」
今にも襲いかかりそうなほど苛立ちを含んだ声に、しかし狼の面は黙ったままだ。一瞬の静寂の後、大太刀の方が痺れを切らして己の武器を振り下ろす。
その攻撃を舞うようにひらりと躱した狼は、背中の羽赫を鋭利な形に変化させて太い腕を切り刻んでいく。だが、その程度の傷では奴の動きを止められないだろう。
黙って見ている場合ではない。喰種と共闘するなどと思いつつも、ここが好機と捉えてオレも手に持った武器を大太刀の顔めがけて振り上げる。二方からの攻撃に対応するのは不利だと判断した大太刀は、まずはオレから片付けることを選んだようだ。
オレの武器の切っ先を右手で掴むと、掌から血が溢れるのも構わずにガッチリと握りしめたまま、空いた左手で造られた拳がオレに迫って来る。大柄な体から放たれるそれが急所に当たればひとたまりもない、なんとかして体を捻って衝撃に備えようとする。
しかし、いつまでもその瞬間が訪れないので、渾身の力を籠めて武器ごと奴の手から逃れた。
ゴトリ、と鈍い何かが落ちる音がした。その塊は、拳を握ったままの奴の左腕だ。肘の辺りからスッパリと斬られた断面が、オレに向いているのが見える。
左腕を斬られたにも関わらず、大太刀の表情に焦りや不安などは見受けられない。ただ、自分の腕を斬り落とした者へ復讐しようとする怒りが、地響きのように轟々と伝わってくる。
「気が変わった、まずは貴様から殺す」
低い声でそう口にした瞬間、大太刀が狼の面に向かって跳躍する。暴風のように荒れ狂う鱗赫を、狼が背中の羽赫を広げて素早く躱していく姿は圧巻だ。己の攻撃が当たらないことに苛立ちを感じた大太刀の背中の筋肉が、ボコボコと怒りをあげて隆起している。
奴はかなり怒っている。だから、オレへの注意が先ほどよりも向いていない。
今が、最大のチャンスだ。狼は懸命に猛攻を掻い潜っているが、羽赫は常に赫子を放出する分長くは戦えない。近いうちに赫子が尽きてしまう、その前に決着を付けなければオレたちに勝ち目はないだろう。
狙うは心臓、もしくは首だ。大太刀はオレよりも上背があるので狭い室内で首を斬るのは難しい、であれば心臓に一点集中するより他ない。
武器の出力を最大まで上げて、大太刀に向かって駆ける。集中しているからか、大太刀と狼の攻防が酷くスローモーションに感じられる。自分の息遣いの音すら、鮮明に聞こえる。瞬く間に大きく近くなった大太刀の体。このまま、このまま心臓さえ貫けばこちらの勝ちだ。だから、どうか気付かないでくれ。
そんなオレの願いを嘲笑うかのように、オレの方へギョロリと視線を向けた大太刀が狼に向けられていた矛先を翻し、黒い影が眼前へと迫ってくる。しかし、オレはもう奴の心臓を貫くべく突きを放っている。今更避けることなどできない。
――嗚呼、ここで死ぬのか。せめて、相打ちとなってこの凶悪な喰種を道連れにしてみせよう。
済まねえな、長曽祢さん。すぐ駆けつけるって約束したのによ。あんたの判断は間違ってねえ、どうか悔やまないで欲しい。
清光に安定。誰が上等捜査官に一番早く昇進するかって競っていたのに、どうやら脱落しちまうことになりそうだ。てめえらはちゃんと生きて続けろよ。
そして、国広。……帰れなくて、ご免な。きっとオレのことを想って涙してくれるだろうお前には、どうか誰よりも幸せになって欲しい。愛するお前を最後に思い切り抱けて良かった、今までありがとな。
走馬灯のように駆け巡る想いを胸に抱きながら、今まで喰種と戦ってきた中で一番鋭く何物をも貫くような突きを放つ。それが大太刀の逞しい胸に当たり、分厚い肉を押し、心臓の部位に勢いよく血を滲ませながらめり込んでいく様に、一安心する。
これでオレの最低限の役割は果たした、後は頼れる仲間たちに任せよう。そう思い、目を閉じる。
唸りを上げて、大太刀の鱗赫が体にぶつかり骨がへし折れる音が聞こえる。メリメリと引き裂くような音が、その凄まじい威力を物語っている。
――だというのに。オレの体には、ちっとも痛みなど感じない。もしかして、あまりの衝撃に痛みを感じることすらできないのか。それならば、苦痛を感じることもなく逝けるのだろうか。そうであれば、せめてもの慰めだな。
そう思って、きつく閉じていた瞳をゆっくりと開ける。オレの渾身の一撃は確かに大太刀の心臓を貫き、呻き声を上げながら奴の体から命が急速に失われていくのを感じる。確かにオレの一撃は決まった。それは間違いない。
……なのに。見下ろしたオレの体に傷などない。紅く染まり、風穴でも開けられたか、下手すれば真っ二つに割られでもしたのだろうと想像していた体は、目を閉じる前と何も変わってはいない。
だとすれば、先ほど聞こえてきた衝撃音は何だったのだ。オレの空耳、と片付けるにしてはハッキリと耳に流れ込んできたあれは。
忘れていたかのように、じっとりと汗が次から次へと噴き出てはオレの体を濡らしていく。乱れた息が、煩いくらいに思考を妨げてくる。
オレが無傷であるのなら、考えられるのは一つではないか。
ゆっくりと振り返る。先ほどまで一撃たりとも攻撃を食らっていなかった黒く小さな影が、ひび割れた壁にもたれるように倒れている。その腹から、夥しいほどの血が真っ赤な湖のようにじわじわと広がっていく。ひゅうひゅうと、面から微かに聞こえる苦しそうな息遣いが、狼の命が潰えていないことをオレに教えてくれる。
……オレを、庇ったのか。
てっきり大太刀に私怨がある喰種が、この機に乗じて仇を討たんと戦っていたのだと思った。でも、それならば、こいつが捜査官であるオレを庇う必要など、どこにもないではないか。
こいつは何者だ、そう考えた時に、嫌な想像が頭をよぎる。
そんなはずない、考えすぎだと笑い飛ばしたいのに、どうしてか確信を持つように背筋がゾクゾクと凍っていく。
嫌だ、と思うけれど、確かめなければいけない。オレの嫌な予感が、どうか違っていて欲しいと、僅かな可能性に縋るように。
一歩一歩踏み締めて近付き、震える手で血が飛び散った狼の面に手を掛ける。ほとんど力を入れていないのに、それはいとも簡単に顔から剥がれるとその素顔を晒した。
嗚呼、やはり。嫌な予感というものほど当たるというのは、どうやら本当らしい。
癖のある前髪も、くりくりと大きい瞳も、小さな、しかしそれでいて整った鼻筋も、柔らかい唇も――その全てが、オレのよく見知った愛しいものであった。唯一オレの記憶と違う、喰種であることを証明する赤く染まった瞳が、ゆっくりと開かれてオレを視界に捉える。一瞬安心したような顔を浮かべるが、すぐに切なげに眉が下がる。
「……かね、さん……無事で、よかっ、た……ごめん、ね……」
絞り出すように血を滲ませながら話す国広に、何か返事をしなければと思うのに、言葉は喉から出てくるのを拒んでいる。
「……僕は、もう、助からない……から、僕の赫子……かねさんの、武器に、してくれないかな……そしたら、死んでも兼さんのこと、守れるから……」
どこか満足げに頬を緩ませると、ゆっくりとその瞳が閉じられて意識が失われる。慌てて首に手を当て脈をとる。弱々しいが、まだ脈はある。――生きている。
助けなければ。しかし、どうすればいいのか。国広がオレを助けた時とは状況が違う。オレは国広のように医学の知識もなければ、治療の道具も持っていない。早くしなければこの命は失われていくというのに。
そう思っていたところに、二つの人影が近づくのを感じて咄嗟に顔を上げる。国広と同じような背丈で外套を着て、それぞれ鬼の面を被った、二人の喰種。彼らは、一体何者なのか。
向こうもオレをの姿を認めて殺気立つが、オレに国広を傷つける意志がないことを悟り、一先ず矛を収める。
「……そこ、退いてくれる?」
向かって左の、黒髪の方がハッキリとした口調で話しかけてくる。どこかで聞いたような声音だ。用があるのは国広の方だということなのだろうが、何者かも分からぬ者にそう易々と国広に近づかせるわけにはいかない。背に庇うように国広を隠すと、もう一人の銀髪の方が口を開く。
「……ここで揉めている場合じゃない。早くしないと堀川が死ぬ。俺たちなら治療して助けられる。堀川を助けたいだろ」
有無を言わせないという口調でオレを避けて国広に近づいたそいつらは、手早く止血を行うとだらりと力の抜けた体を肩に担ぎ、大太刀によって開けられた壁から立ち去ろうとする。
「……待て、国広をどこに連れていく気だ」
「残念だけど、人間には教えられない。でも、必ず堀川の命は助けてみせるから安心しなよ。それじゃあね」
その言葉を最後に、ふわりと飛び降りて見えなくなる。ドンドンと音がするのは、赫子を使って壁を降りていく音だろうか。
――国広が、喰種だった。その事実を呑み込めない頭がガンガンと鳴り響き、その場に呆然と立ち尽くすのがやっとだった。
その後のことは、記憶にない。どうやら此度の作戦はオレたちCCG側の勝利に終わり、10名を越える喰種を捕獲し、それとほぼ同数の喰種を駆逐した。奴らのグループは崩壊し、この地区の喰種の活動は弱まることとなるだろう。ほとんど完璧と言っていい、勝利だ。
オレたちが斃した大太刀は赫子を無事に摘出できたので、強い武器になるだろうと喜ばれた。オレ一人で奴を斃したと思われたので、局に戻った後に長曽祢さんはこの上ない賛辞をオレにくれて、間違いなく昇格するだろうと労った。清光と安定はどこか少し悔しそうだったが、オレの戦果を褒め称えてくれた。
なのに、オレの気持ちは晴れなかった。あんなに昇格を夢見ていた自分が馬鹿に思えるほど、そんなことはどうでも良かった。
――国広。あれからどうなったのか、オレには分からない。何日か経ってから職場である病院に勇気を出して訪ねてみたが、急なことだが辞められたのだと残念そうに看護師に説明された。
国広の家にだって行った。生憎ほとんど同棲のような生活をしていたのはオレの家の方で、合鍵など持っていない。必死にチャイムを鳴らすが、帰ってくるのは静寂だけだった。
家に帰る度に、そこに国広がいないという事実が、国広が間違いなく喰種でオレを庇ったあの夜の出来事が現実だということを突きつけてくる。
オレは、なんと愚かだったのか。こんなことにすら気付かずに、ただただ幸せばかりを享受していた自分に嫌気がさす。
思い返せば、オレが手料理を振る舞った後はいつも体調を悪くしていた。最近忙しいから、と申し訳なさそうにしていた言葉をそのまま信じていた。今なら解る、国広はオレが作った料理だからと無理やり食べていたのだろう。喰種の体にとっては、毒でしかないそれを。
告白した時だって、理由は明かさなかったが恋仲にはなれないと拒まれた。それでも国広がオレのことを好いているという気持ちは分かっていたから、半ば強引に体を繋いだのだ。きっと国広はいずれこうなることが分かっていたから、気持ちを押し殺そうとしたのだろう。
オレが人間で、しかも捜査官なんて仕事をしているのだから、喰種である自分とは生きる世界が違う。国広はそう思っていたのだろう。
それでもオレが傍にいることを望んだから、オレのことを愛しているから、一緒にいてくれた。一体どれほど苦しい想いを抱えながら、オレと過ごしていたのだろうか。
残酷なまでに国広の気配を残す部屋にいると、気が狂ってしまいそうだ。
オレは捜査官、喰種を捕らえ、場合によっては殺すのが仕事だ。それが平和な生活を守るために必要なことであり、オレたちの正義だ。だから、国広だって、オレたちの敵の一人なのだ。
そんなこと、解っている。解っている、のに。そのことを考えるだけで、引きちぎられてバラバラになったように胸が激しく痛む。
オレにとって、自分の正義は大事なものだ。それを誇りに思っているから、捜査官の道を選び、今日まで続けてきた。
けど、国広だって、大切なんだ。傍にいて欲しい、かけがえの無い存在なんだ。どちらか一つしか、選ぶ道はないというのなら――
そんなことを考えていると、ベッドの上に転がっていた携帯がピロンと音を立てて思考を中断させる。急な召集の可能性もあると思い、すぐさま画面を確認する。
そこにあった名前は、あの夜以降一度も連絡することがなくなった恋人のものだ。震える指で、恐る恐るメッセージを開く。
『直接会って話がしたい。そこで、何もかも話させて欲しい』
簡潔な文章が綴られていた。無事だった、生きていたのだと安堵して、体から一気に力が抜ける。国広の方から会いたいと言ってきてくれたのだ、オレもそれまでに覚悟を決めなければいけない。何を選ぶのか、その答えを。
***
目が覚めた時に最初に目に入ったのは、見慣れない天井だ。自分の家でも兼さんの家でもない。病院、というわけでもなさそうだ。
てっきり自分は死んだとばかり思っていたが、体は重いけれどなんとか動かすことができる。ここが天国や地獄でない限りは、まだ生きているのだろう。
ゆっくりと、腹筋に力を入れて上半身を持ち上げる。瞬間、激しい痛みに体が割れるような感覚に襲われるが、それでもなんとか起き上がる。腹の奥から、ズキズキと痛みが全身を駆け巡る。それが、あの時兼さんを庇って大太刀の一撃を食らったことが夢ではないと教えてくれる。
湧き出てくる脂汗が顎から滴っていくのを感じながら、ぜえぜえと息を吐く。ここはどこなのだろう。そして、死にかけだったはずの僕をここまで運んで治療したのは一体誰なのだろう。ぐるぐると包帯で巻かれた腹を見据えて、心の中で独り言つ。
まさか、兼さんか……いや、そんなことあるまい。喰種だと分かった僕を助けるなど、喰種を憎む彼にできるはずなどない。それに、彼にここまでの治療ができるとも思わない。であれば、残る可能性は――
そこまで考えたところで、ガチャリと音を立てて後方の扉が開く。まだ痛みに痺れる体をぎこちない動きで振り返させる。
「おっ、ようやく起きたね。おはよう、堀川。まだ体痛むでしょ、ゆっくり寝ときなよ」
嬉しそうに笑いかけながら現れたのは、鯰尾藤四郎。僕が勤める病院で共に働く同僚で、彼の兄弟である骨喰も含めて医大時代からの同級生だ。そして、僕が喰種であると知る数少ない友人であり、彼もまた喰種である。
「鯰尾くん……ごめん、世話かけちゃったみたいだね。僕のこと心配して助けてくれたんだよね、ありがとう」
「そりゃあいきなりあんなこと言われたら心配するよ~。でも、間に合って良かった」
あの夜死ぬことすら覚悟していた僕は、事前に鯰尾くんと骨喰くんに連絡を入れたのだ。自分はもしかすると帰れなくなるかもしれない、もし明日になっても僕から連絡が来なかったら、申し訳ないが病院に上手く伝えておいてくれないか、と。
優しい友人は、そのメッセージからなんとか僕がいるところを割り出して駆けつけ、死に体の僕を連れ帰ってくれたのだろう。その心遣いに、思わず目頭が熱くなっていく。
「本当にありがとう……。二人が来てくれなかったら、間違いなく死んでいたと思う。感謝してもしきれないな」
「いいっていいって、長い付き合いなんだからこれくらいはね」
「僕にできることがあったら、何でも言ってね。……あの、鯰尾くん、僕が倒れてたところ、なんだけど。他にも誰かいた……?」
あの後兼さんがどうなったのか気になって、思わずそう言葉が口から発せられた。
「……あぁ、いたよ。どこかで見た顔の捜査官さんがね。最初は堀川の顔見られたわけだし殺そうと思ったけど、なんか訳ありなんだなって分かったから、放置して堀川だけ連れ出したよ」
「……そっか」
「向こうも堀川のこと庇うような素振りをしてたんだけど……もしかして、前にちょっと話してた恋人って、あいつのこと?」
「……」
僕の沈黙を肯定と捉えた鯰尾くんは、ふうと息を吐きながら、少し悲しみを含んだ瞳で僕を見つめる。
「なるほどね……人を好きになるのは堀川の自由だし、とやかく言うつもりはないよ。でも、あいつは捜査官で、堀川は喰種。その様子を察するに、そのことは黙っていて、あの夜にバレちゃったんだよね?あいつを守るために戦ったんでしょ、それくらい解る。なら、きちんとケジメはつけないといけないんじゃないかな」
「……そう、だね。鯰尾くんの言う通りだよ。僕は、兼さんを騙していた。喰種なのに、捜査官のことを好きになって、恋仲になって。こんなこと、許されるはずないのにね。……報いを受ける時が来たんだ」
「あのさ、別に捜査官を好きになったことを責めてるわけじゃないから。誰かを好きになる気持ちって、そんなことくらいじゃ止められないでしょ。堀川は、喰種の情報を漏らすような奴じゃない。そんな心配はしてないよ。問題なのは、これからどうするのかってことだよ。今までのこと、それにこれからのこと、話さないと。このままお別れしたら、きっと堀川は後悔するよ」
鯰尾くんの優しくも僕を諌めるような言葉が、胸に染みていく。許されないことをした僕を責めるどころか、心配してくれているのだ。
僕の周りは、どうしてこんなにも優しい人が多いのだろう。きっと兄弟も心配しているに違いない。そう思うと、自分が情けなくなって、堪えていたはずの涙がぽろぽろとこぼれ落ちて布団までも濡らしていく。
「ありがとう、鯰尾くん……僕、兼さんに正直に話すよ。今まで僕がしでかしたこと、ちゃんと謝りたい。その先をどうしていきたいのかはまだ分からないけど、会って話したい」
「うんうん、そう思えるなら良かった。だけどまずは、ちゃんと休んで体を治さないとだね。堀川、本当に酷い怪我だったんだから。あっ、それに目覚めたんだから堀川の兄弟にも連絡しないと。俺、電話してくるね」
そう言うとパタパタという音とともに、鯰尾くんは走って行った。
心配をかけてしまった兄弟や友人に、ごめんなさいとありがとうを言おう。そして、ちゃんと動けるようになったら、大切な恋人に、会いに行こう。
それから三週間余りが経ち、すっかり元の調子を取り戻した僕は、鯰尾くんと骨喰くん、それに僕の看病をしてくれた彼らの兄弟にお礼をして家に戻った。
あれからすぐに兄弟は駆けつけてくれて、長兄は無事で良かったと大いに喜び、次兄は無茶をするんじゃないと怒ったけど、その目には嬉し涙がきらりと輝いていた。再び兄弟に会えると思っていなかった僕も、喜びの余り嬉し涙を流した。
そして、これはかなり勇気が要ったけど、兄弟に自分の恋人のことを正直に話した。僕の拙い話が終わるまで、二人は黙って聞いてくれていた。兄弟の縁を切られてもおかしくないことをしたのだ。その反応を恐々と伺ったが、長兄はその大きな手で僕の頭をわしゃわしゃと撫でてくれた。
自分達に話すのは勇気が要っただろうに、よく話してくれた。たとえどんな人間であろうとも、兄弟が好いたのだから悪い者であるはずがない。そして好きな者を守ろうと戦った兄弟は間違ってなどいない。そんなお前を誇りに思う。だから、胸を張ってちゃんと恋人と話して欲しい。
そう、力強く僕を応援するかのように言ってくれた。触れられた頭から、じわじわと暖かさが伝わってくる。
その話を聞き終わった後、次兄も口を開く。自分は手放しで賛成はできない。だが、一番大切なのはお前の気持ちだ。だから、お前のやりたいように生きればいい、と。
糾弾されても仕方ないことなのに、友人と同じく、兄弟も僕のことを理解して、尊重してくれた。本当に僕は人に恵まれていると、改めて強く実感したものである。
あれから、ずっと兼さんのことを考えていた。万一何か勘づかれるようなことがあってはと勤めていた病院を辞めたので、幸い考える時間はたくさんあった。
今、兼さんはどうしているんだろう。きっと、僕の正体を知って、ショックだったに違いない。自分の恋人が憎むべき喰種だったのだ、その衝撃は察するに余り有る。
許して欲しい、などと過ぎたことは望まない。僕はそれだけのことを彼にしてしまったのだ。せめて、彼の心が僕と出会う前の安らぎを取り戻せるようにしてあげたい。そのために、僕に何ができるのか。
助けてくれた友人や、心配をかけてしまった兄弟には申し訳ないと思うけれど、兼さんと一緒にいられない世界で生きていくことは辛い。それほどまでに、彼の存在は僕の中で大きく、欠かすことのできない大切なものになっていった。
様々な感情がせめぎあう頭の中をなんとか整理して、机の上に置かれたままの携帯を手に取る。メッセージを送る、そんないつも当たり前のように行っていた行動を取るのに、途轍もない勇気が要って思わず文字を綴る指が震えてしまう。
普段の倍以上の時間をかけてようやくメッセージを入力すると、その勢いのまま送信ボタンを押す。
どうか何でもいいから返事が返ってきますようにとの願いは、想像以上に早く叶えられた。時間にすればわずかな間だったけれど、それは僕にとって永遠のように長く感じられた。
『分かった。三日後の夜、オレの家に来てほしい。待ってる』
簡潔に、待ち合わせ場所と時間を伝える文章が返ってきた。
とにかく、兼さんは僕に会ってくれるのだ。それだけでも、この上ない喜びを感じて体がじんと熱くなっていく。罵られて、お前の顔など見たくもないと言われてもおかしくない。なのに、彼は僕と会って話をしてくれるというのだ。
浮かれている場合ではない、その日までに覚悟を決めて、彼に伝えたいことをまとめなければ。熱を持った顔を左右に振って、兼さんのことを想いながら、その日は眠りについた。
三日なんて随分余裕があると思っていたのに、気が付けば当日になっていた。久しぶりに兼さんの顔が見れる、そう思うと心臓が勝手にバクバクと鼓動を速めていく。いけない、僕はもうただの恋人として彼の家を訪れるわけではないのだ。ぱしゃぱしゃと傘を叩く雨音が、僕の心を鎮めてくれる。
目的はむしろその逆、今までのことを詫びて、別れを告げるために、僕はここに来たのだから――。
あっという間に辿り着いた見慣れた扉を前に、先に進むことを躊躇してしまう。ここに踏み入れば最後、もう僕と彼の関係は以前のようにはいかない。甘く、優しさに浸っていた時間は終わりだ。それがどうしようもなく辛くて挫けそうになるのを、心の中のもう一人の自分に叱咤される。
恐る恐るチャイムのボタンを押した後、緩慢な手つきで合鍵を使い扉を開く。ガチャリ、と無機質に響く音が、今はもの悲しく聞こえてしまう。開いた扉の先の廊下は暗く、突き当たりの部屋から漏れる光が、彼がそこにいるのであろうことを教えてくれる。
ゆっくりと、されど一歩一歩確実に、歩を進める。彼の気配を感じてリビングへと繋がる扉の前で立ち止まってしまうが、これ以上待たせるわけにはいかない。
汗ばんだ手を服で拭いて、ドアノブを下げて押していく。開いた扉の先に懐かしい顔が見えて、思わず頬が緩んでしまう。
ああ、兼さんだ。あの夜からひと月ばかりが経っても、その精悍な顔つきは変わらない。ただ、少しばかりやつれてしまっただろうか。その理由が自分にあるような気がして、腹の奥がグッと痛みを覚える。廊下から現れる僕を待ち構えるようにして凛と立っている彼の目を、すっと見据える。
「久しぶり、兼さん……」
「……ああ」
「少し、痩せちゃった?ちゃんとご飯食べないとダメだよ?」
「……」
思わずいつものように話しかけてしまった僕を、兼さんは黙って見つめる。ああ、そうだ。こんな風に話しかける資格なんて、僕にはないじゃないか。
「……ごめんね。今まで黙っていたこと、謝っても許されることじゃないのは分かってる。でも、それでも謝らせて欲しい。本当に、ごめんなさい」
自己満足だって、分かっている。こんなことで許されるはずではないことも。それでも、深く傷付けてしまった彼に謝らずになどいられなかった。
「どうやったらこの罪を償えるかって、ずっと考えてたんだ。兼さんを傷付けてしまった過去は変えられない。僕にできることは、何だろうって……ねぇ兼さん、僕が兼さんにあげられるものなんて、何もないんだ。だから、こんなもので申し訳ないけど……どうか、僕を殺して欲しい」
――そう。僕が罪を償うために捧げられるものなど、この命くらいだ。他には何もない。どうせ兼さんの傍にいられない世界で生きていくことなどできやしないのだ、ならばこの命を差し出すことくらい、どうということはない。
兼さんが、息を呑む音がする。俯きながら一気に話したので、それを聞いている表情を見るのが怖かった。おずおずと顔を上げると、眉を顰めて悲しそうに歪んだ瞳が視界に入る。
ああ、また僕は兼さんを傷付けてしまった。いくら僕が憎い喰種であったとして、優しい兼さんが恋人であった僕をその手にかけるなど、できるはずがないではないか。そんなことすら思い至らずに、勝手に命を絶って欲しいなどと喚いてしまった僕は、なんと愚かで自分勝手なのだろう。
僕なんかのために兼さんの手を血で染める必要なんて、ない。僕が勝手に自分で死ねばいいだけだ。なんだ、簡単なことじゃないか。人を騙した身勝手な喰種が死ぬ。それでおしまいだ。こんなことも思いつかなかったなんて、僕は馬鹿だなぁ。
そう決意すれば後は実行するだけだ。踵を返し、この部屋を離れてどこか人目につかないところで決行しようと歩き出す僕の足が、止まった。
……否、止められた。僕の腕を掴んで離さない腕によって。振り解こうとするよりも先に、強く引っ張られて、逞しい二本の腕の中に抱きすくめられる。
「行かせねえ。……どこにも行かせねえぞ。死なせてたまるかよ」
僕の考えていることなどお見通しだとばかりに、きつく抱きしめてくる腕があまりにも温かくて、この優しい空間に留まりたいという気持ちが腹の底から湧き出てくる。それを振り払うように胸を押し返そうとするが、鍛えられた筋肉に覆われた胸は、僕の抵抗にもびくともしない。
「離してよ、兼さん……僕は喰種なんだ、あなたと一緒にはいられない。……あなたの傍にいられないなんて、僕には耐えられない。だから、行かせてよ……」
「勝手なことばっか言ってんじゃねえよ。オレがお前を殺せるわけねえし、みすみすお前が死ぬのを見過ごすわけもねえ。オレはお前に生きていて欲しい。……一緒にいられないなんて誰が決めたよ」
「……ッ、僕は、人間を食べることでしか生きられないんだ!兼さんが命をかけて一生懸命守っている、人間を!そんな僕が、どの面下げて兼さんの傍にいれるっていうの?僕が人間だったら何の気兼ねもなく一緒にいられるのに、そう何回、何十回、何百回と思ったよ!でも、僕は喰種なんだ……それが、変わらない現実なんだよ……!」
こんな、こんな風に激しく気持ちをぶつけるつもりなんて、なかったのに。心の底に押し込めていた思いが、後から後から噴き出ては喉から言葉として発せられていく。
「僕が喰種でさえなければ……でも、僕が喰種だったからこそ、初めて出会った時に兼さんを助けられた。喰種と戦っている兼さんを守ることができた。結局、僕が喰種だったからこそ、今ここでこうして兼さんと一緒にいられる。……笑っちゃうよね」
腹の底でとぐろを巻いて煮詰まっていた感情を言葉に乗せて、全て吐き出した。もう、十分だ。だから、分かってよ、兼さん。僕を、このどうしようもない現実から、解放させてよ。
「……国広。お前が喰種だって知った時は、確かにショックだった。だが、それでも、オレのお前に対する気持ちは変わらねえ。……いや、それどころか、前よりももっと、お前のことが好きだって自信を持って言える」
「……そんなの、嘘だよ。だって、兼さんは立派な捜査官だもの。僕なんて、憎いはずだよ」
「嘘じゃねえ。オレは、たくさんの人を守るために戦う自分に誇りを持っていたし、仲間が殺されていく度に喰種を憎む気持ちを持っていたことも事実だ。……だけど、そんなものよりもお前を愛おしく想う気持ちの方が、ずっと強かった」
ああ、ダメだよ。兼さんは、日の光の当たった場所で笑っていて欲しいんだ。僕のような日陰者の方に堕ちて来ては、いけないんだ。
「お前が喰種だろうと構わねえ。オレはこれからもずっと国広と一緒に生きていきたい、そう思ったから捜査官も辞めた」
「……なんで、そんなこと……兼さん、あんなにお仕事頑張っていたじゃない……」
「喰種を倒すことに命を懸けている奴らに混じって喰種と一緒に生きていくなんて、そんな半端な気持ちでできる仕事じゃねえからな。オレはお前と生きていく道を選んだ。言っておくが、生半可な気持ちで選んでねえからな。お前が人間を食べないなんて抜かした日にゃ、そこらへんの腐った根性した奴をぶちのめして嫌でもお前の口に突っ込む。それくらいのことだってしてやる覚悟はできてんだよ」
兼さんの覚悟を持った強い意志を表す碧く煌めく瞳が、僕の全身を貫く。あの夜、生きたいと力強く見つめられた時のように。思えば、あの夜彼の瞳に貫かれた時から、僕はきっと兼さんに惹かれていたのだろう。あの時兼さんを助けるという選択をした時には、こうなることも決まっていたのかもしれない。
「だから、これからもずっとオレたちは一緒に生きていく。……嫌だなんて言わせねえぞ。お前は命懸けでオレを助けたんだ、お前の命、オレが貰うぜ。その代わり、オレの命をお前にくれてやる」
その言葉に対して口をつこうとする前に、兼さんの唇が僕のそれに重ねられて、塞がれる。奪うような口付けに、呼吸すらできない。僕の何もかも、兼さんに吸い取られてしまうような、感覚。抵抗する腕の力が、段々と弱まっていく。それを感じた兼さんが、隙間から無理やり押し入るように舌を差し入れてくる。
拒むべきだと頭では分かっているのに、兼さんの舌に自分のものを吸われ、舐め取られ、嬲られることに身体は悦びの声をあげている。もっとその蕩けるように甘い唾液が欲しいと、自ら兼さんの舌を絡め取っては舐め啜る。いつの間に、僕の身体はこんなにもはしたなくなってしまったのだろうか。
すっかり抵抗する力を失った僕を見た兼さんは、唇を解放してくれたかと思うと膝の裏を持ち上げて抱き上げてきた。ずんずんと歩いて行った先は、慣れ親しんだ寝室だ。
ベッドの上に放るように降ろされて抗議の声を上げようとするが、それより早くベッドに縫い付けるように兼さんに上から押さえつけられる。反論は聞かねえとばかりに再びキスされて、咥内をじわじわと貪られていく。しっかりと張ったはずの理性の糸が、少しずつ兼さんによって焼かれて細くなっていく。
邪魔だと言わんばかりにやや乱暴に着ていたシャツを剥ぎ取られて、外気が肌に触れる。その身体に新しくできたものを見て、兼さんは唇を離し、その部分をじっと見つめる。
脇腹から胸にかけて抉れるようについた、大きな傷。それはひと月経った今ではもう痛みも感じないが、喰種の再生力を持ってしても、完全に塞がることはなかった。それほどまでに深い傷だった。
「これ、消えねえのな……お前の綺麗な肌に痕つけちまって、ごめんな。でも、オレとお揃いみたいで、ちょっと嬉しいかもしんねえ」
そう嬉しそうに眺めながら、傷跡を優しくなぞられる。少し擽ったいけれど、兼さんに触れられているのだと思えば、不思議と心地よささえ感じるのだから世仕方ない。指では飽き足りなくなったのか、そこに唇が当てられ、そっと舐め取られていく。
本来そこは何とも感じない場所のはずだが、幾度も兼さんと睦み合ってきた僕の肌は敏感になっており、擽ったさの中に快感が混じり合って思わず声が漏れてしまう。
「……んっ……」
「何だ、傷痕舐められただけで感じちまったのか?」
「ち、ちがっ……」
「こんなに乳首勃ってるのに、んなこと言っていいのか?」
見せつけるように摘まれた胸の飾りは、確かに天を向くように勃ち上がっていた。碌に触れられてすらいないのに形を変えてしまう自分が恥ずかしくて、思わず顔を逸らそうとする僕を、顎を掴んでしっかりと固定される。
「国広、お前の身体を誰がこんな風にしたか忘れたとは言わせねえぞ?今からたっぷり、お前の身体はオレのもんだってこと、分からせてやる。だから、目ぇ逸らすんじゃねえよ」
獰猛な獣のように光った目で言い聞かせるように見つめられれば、言われた通り目が離せなくなってしまう。そんな僕の様子に満足げに口の端を歪ませると、摘んだままの尖りを押しつぶすように捏ねられ、その片方に唇を寄せてぷくりと腫れた乳暈ごと吸い付かれる。
「うっ……ん、ふうっ、兼さん、だめぇっ……!」
「うるせえ、やれ喰種だからダメだだの、んなこと考えられなくしてやるよ」
両手で何も出るはずもなければ柔らかくもない胸を楽しそうに揉まれたかと思えば、先端をぐっと引っ張られてその先っぽに舌をグリグリと押し付けられる。手で塞ぐことすら忘れられた口から、哀れなほど嬌声が漏れ出てくるのを抑えられない。
乳首を噛まれて、取れんばかりに指で引っ張られて、痛いはずなのに感じるのはビリビリと痺れるような快感ばかりだ。幾度も弄られたそこは、痛みさえも快楽へと感じるようにされてしまった。何度も何度も、ここを弄られるのは気持ちいことなんだって、兼さんに教え込まれた。僕の身体は、正直にその教えを守っている。
赤く腫れ上がった芽は、兼さんの舌と指に嬲られて、嬉しそうにてらてらと濡れている。視覚からも、触覚からも犯されるような感覚に、急速に下半身に熱が集まっていく。早く兼さんに触れてほしいと、布地を押し上げるように主張する部分が目に入り、ますます顔が熱くなっていく。
「こっちも触ってないのに気持ちよさそうだな、国広?」
目ざとくそれを見つけた兼さんに、服の上からさわさわと撫でられるだけで、気持ちよさにビクビクと腰が震えてしまうのを止められない。この大きな手で、もっと触れて欲しい。気が付けば兼さんの手に押し付けるようにはしたなく腰がゆらゆらと揺れていた。
「ははっ、そんなに強請らなくても、ちゃんと可愛がってやるから安心しろよ」
ベルトを外して脱がそうとする兼さんの手の動きに合わせて腰を浮かせば、下着ごと一気に剥ぎ取られる。ぷるんと上向いた性器が、物欲しそうにとろとろと先走りで粘ついている。そこにゆっくりと手を這わせると、上下に擦られる。
待ち望んでいた快感に、腰から下の感覚がなくなりそうなほどの愉悦に襲われる。兼さんの大きな手に扱かれて、嬉しそうに粘つく汁で自身を濡らしていく。裏筋を強めに押されれば、衝撃に思わず背が反り返る。
――気持ちいい。しばらくこの快感を味わっていなかったからか、急速に絶頂が近づいてくるのが分かる。
「うぅぅぅっ……、かねさ、んぅ、僕、もう、いっちゃ……っ!」
「ああ、イケよ。ちゃんと見ててやるから」
低い声で耳元で囁かれれば、それすらも快楽として掬い上げてしまう。先端を指の腹で回すように押されて、はちきれんばかりに溜まっていた欲望が勢いよく上り詰めて顔を出す。びゅくびゅくと、白い飛沫が僕の腹を濡らしていく。意識が白く塗りつぶされるほどの強い感覚に、薄い腹がひくひくと痙攣する。
はぁはぁと息を吐く僕を横目に、兼さんが服を脱いで一糸纏わぬ逞しい身体を惜しげもなく晒していく。
今更ながら、兼さんはなんと綺麗なのだろう。僕の薄い体とは違う、鍛え上げられた筋肉に覆われた彫刻のように美しい肉体も、肌にさらりと流れ落ちる漆黒の髪も。切れ長く鋭い瞳も、乱れた息を零す唇も。腹に引かれた傷痕すら、その体を美しく飾る装飾品のようで。そう自覚するだけで、僕はさらに昂っていく。
僕の顔の横に膝をついた脚の間から、逞しい体格に見合った長大な陰茎が雄々しく勃ち上がっているのが見える。
「国広。……オレのも気持ちよくしてくれるか」
返事の代わりにゆっくりと身体を起こし、その陰茎を握る。僕の指では周り切らないほど立派なそれがこれから自分を貫くのだと思えば、腹の底がかっと熱くなるのを感じる。鈴口から滲み出た液体を竿全体に塗り広げ、むわりと雄の匂いを放つ先端をそっと口に含む。
僕の口では到底収まりきらないほどの質量を、喉を小刻みに動かして咥内に埋めていく。喉奥を突くほどの長さに思わず嘔吐きそうになるが、必死に舌を伸ばして脈動する筋の一つ一つを愛撫する。
根元にどっしりと重く鎮座している双球を掬い上げるように持ち上げて撫でるように揉んでいけば、擽ってえとどこか嬉しそうな声が降ってくる。
初めは口の中に収めることすら一苦労だったこの行為も気付けば慣れたもので、喉を締めて兼さんに気持ちよくなってもらう術を覚えた。ちゅうちゅうと吸い取るように窄めていけば、兼さんの顔から余裕が消えて眉間に皺が寄っていくのが見える。どくどくと早まる脈動が、限界が近づいていることを示している。
このまま口の中に出してもらおうと吸い付こうとしたのを拒むように兼さんが腰を動かし、ちゅぽんと音を立てて解放された猛りが反り返る。
「……どうしたの?気持ちよくなかった?」
「んなわけねえだろ、すげえ気持ちよかったぜ……ただ、このままだと口ん中出しちまうからな」
「いいよ?僕の口の中に出しても」
「……言ったろ、お前の身体が誰のもんか分からせてやるって。だから、こいつはお前の下の可愛い口にぶち込んでやるよ」
愉しそうにくつくつと笑った兼さんによって再び押し倒されると、両脚を大きく広げられる。ベッドサイドの容器に手を伸ばして、中の液体を指にたっぷり絡ませくちゅくちゅと響く音に、下腹部がじわりと熱くなっていく。
そっと、冷たい感覚が後孔に触れる。
それが兼さんの指だと、散々押し入られたことのある僕の窄まりは理解しているようで、押し入ってくる指にきゅうきゅうと絡みついていく。ローションの滑りを借りてあっけなく根元まで入り込んだ指を、内壁が待ちきれんばかりに食い締める。
「流石にひと月ぶりだときついな。ちっと我慢してくれよ」
確かに久しぶりに拓かれる中はきつく、兼さんの指が出入りするたびにじんじんと痛みが伝わってくる。でも、それでも構わない。兼さんに与えられるものなら、痛みであろうとも僕はそれを喜んで受け入れるから。
そんな気持ちに応えるようにもっと欲しいと絡みつく肉襞が徐々に柔らかく解されて、それに合わせて中に入れられた指の本数も増えていく。バラバラに動かされたことで隙間ができ、それを確認した指が引き抜かれる。
食い締めるものを失った窄まりが、ヒクヒクと物欲しそうに震えているのが分かってしまって、恥ずかしさに目を瞑る。閉じた瞼の上を、そっと触れる温かい感触。兼さんが優しくキスを落としてくれたおかげで、強張った身体から力が抜ける。
「国広。……挿れるぞ、なるべく力抜けよ」
ぬるりと湿った先端が押し当てられるのを感じて、慌てて顔を上げる。
「あ、待って兼さん……ゴム、着けないの?」
「ああ……悪いな、今日ばかりはお前の中にたっぷり出して、オレがどれくらいお前に惚れてるのか教え込んでやるよ。覚悟しな」
今までゴムを着けずに挿入された経験はなかった。僕の身体を気遣って、どんなに激しく抱かれた時もちゃんと中に出さないようにしてくれていたのだ。直接熱に貫かれることを想像して、身体がびくりと震える。
ゆっくりと中を押し拡げるように入ってくる生身の灼熱に、初めて感じる隔たりなき剛直に、甘く切ない刺激がビリビリと身体中を駆け巡る。身体の中を直接焼かれるような、激しい衝撃に背が弓なりに反る。あんな薄い膜一つなくなるだけで、こんなにも熱く激しい脈動を感じることができるなんて思いもしなかった。
直接触れ合うことができる悦びに、ぎゅうぎゅうと僕の中が兼さんの昂りを絞りとるように淫靡に蠢き、飲み込んでいく。ひと月ぶりに狭い肉襞を侵食されて痛みを覚えているはずなのに、それ以上の快感が僕の思考までも溶かしていく。
ゆっくりと抽送が開始されれば、兼さんが出ていく度に離さないと縋る内壁が引き攣れて捲れ上がる。張り詰めた亀頭で突かれグリグリと押し回されるたびに、理性の糸が音を立ててプツプツと切れて解けていく。
口から漏れ出る、止めようのない淫らな嬌声。それが他人事のように感じられるほど、意識が快楽で犯されていく。熱に侵された胎内は、最早僕と兼さんの境界などないかのように錯覚してしまうほどだ。浅い所にある膨らみを目ざとく抉るように擦られれば、頭がおかしくなるほどの法悦に全身が浸る。
「ああっ、かねさ、かねっ、さ……!そこ、きもちい、よぉ……あ、あっあっ、ああああ!!いっちゃ、いっちゃう、からぁっ……!」
「っ国広……国広、国広……!オレも、イクぞ……お前ん中に、全部出すからな……!」
一気に早くなった律動に、僕の身体は嵐の中で飛ばされる木の葉のように頼りなく、快楽の渦に呑みこまれる。一際強く、奥を叩きつけるように突かれた衝撃に、背を仰け反らせながら再び訪れた絶頂に身を任せる。
「ぁあ、……ぁうッ……ぁああ……ぁあああああああ!!」
前から白濁を迸らせたのと同時に、中で己を差し貫いた肉槍を食い締める。腹の中が、じわじわと灼熱に染められていく。僕の中を兼さんの色に塗りつぶされていく感覚に、視界が明滅する。
この瞬間、兼さんに愛され、満たされ、侵された僕は、名実ともに彼のものになったのだろう。別れを告げようなどと思っていたのが、馬鹿みたいだ。離れられるわけ、ないじゃないか。こんなにも、強く、僕を抱きしめて、愛してくれる人から。
ぐりぐりと押し付けられるように残滓まで残らず吐き出された胎が、歓喜に震えている。最愛の人の精を飲み干す幸福を知ってしまえば、もうこの味を知らなかった頃の自分になど戻れはしない。汗ばんだ兼さんの肌を慈しむように掌でなぞれば、その上から大きな手が重なってくる。
「はぁ……すげえな、中に出すのって……気持ち良くて腰が溶けちまいそうだ」
「うん……僕も、気持ちよかった……それに、すごく嬉しいんだ。お腹の中まで、兼さんを感じられて」
そっと腹を撫でながら呟けば、兼さんの目が嬉しそうに細まっていく。
「そりゃ良かったぜ……なんせこれから一杯出してやるんだからな、ちゃあんと全部溢さず飲み込めよ?」
その言葉と共に、胎内に埋まったままの怒張が再び熱を持ち、首をもたげていく。ぐいぐいと押し上げられれば、僕の身体も熱を持ち始めていく。僕だって、ひと月会えなかった寂しさの分、もっともっと兼さんのことを感じたいのだ。
「……お手柔らかに、お願いします」
「そいつは無理な相談だな。今日ばかりはお前の言うことは聞いてやれねえ。オレの気がすむまでたっぷり抱いてやるよ」
ぐっと腰を抱き抱えられると、再びゆっくりと抽送が始まっていった。
それから果たして何度腹の中に兼さんの精を浴びたのだろうか。数えることすらできないほど快楽に支配された脳は、幾度も絶頂に揺さぶられて考えることを放棄してしまった。
ただただ兼さんに与えられる底知れぬ快楽に酔いしれ、喘ぎを上げることしかできなくなった躰は彼の言う通り、もう僕のものではない。兼さんの逞しい屹立を呑み込み、吐き出される精をしゃぶる後孔は、兼さんのための孔だ。そこに雄を突き立てられ、削られてしまうほど擦られてしまうための孔だ。
幾度も吐き出された精液が結合部からぐちゅぐちゅと淫らな音を響かせている。肌と肌がぶつかる乾いた音と混ざり、この上ない淫猥なハーモニーを奏でる。
欲望を受け止め続けた僕の腹は、うっすらと膨らんでいる。それほどまでに兼さんが僕の身体で気持ち良くなってくれたのだと思えば、堪らなく嬉しい。
それでもなお、兼さんは僕の肉襞を掻き分け、奥を穿つ。不意に中の動きが止んだかと思えば、何度も突かれて弛んだ壁のさらに奥へと捩じ込むように剛直が腹を押し上げていく。曲がった細い道を強引に拓かれて、思わず全身が恐怖に震えた。触れられるはずのない、最奥――。
その扉に今、兼さんが辿り着いた。
「あ、……待って、かねさ、……そこは、だめ……――、ぐっ、……ぅあ……」
静止しようと絞り出した声は、いつの間にか悲鳴へと姿を変えた。腹を破かれたような衝撃に、意識が飛びかける。先ほどまで感じていた快楽など比較にならないほど激しい官能の波が押し寄せて、躰が戦慄く。
「国広……お前の一番奥まで貫いて、可愛がってやりたい……いいだろ?」
まるでおもちゃをねだる子供の様な無垢な瞳に懇願され、たじろいでしまう。
大好きな兼さんにそんなことを言われれば、断れるはずもない。いや、むしろこんな喰種の僕が兼さんにあげられるものがあるなら、喜んでその願いを受け入れるべきだ。
脆く敏感な内臓を直接掻き回されることを、僕の本能が恐れている。この先を許してしまえば、果たしてどうなってしまうのか、と。
でも、僕だって望んでいるのだ。兼さんと、どこまでも深く繋がりたい。まるで一つになってしまうような極上の快楽に身を委ねて、僕の最奥に子種を解き放って欲しい。
「……いいよ。来て、兼さん……僕の一番奥まで」
微笑みながらそう返せば、兼さんの表情がきゅっと引き締まる。脚を肩につかんばかりに折り曲げられ、ずぶりと刀で刺し貫かれるように最奥が暴かれる。固く閉じられていた壁を押し拡げ、張り詰めた肉棒でぎっちりと埋め尽くされ、雁首の全てが結腸の中に嵌まり込む。
「っぐ、……ひぅ……ぅうう……ぁあ……」
頭の先から爪先まで貫くような痺れに、身体の震えが止まらない。喉の奥から、僕の意志など関係なく湧き出る呻き。壊れてしまうのではないかと思うほどドクドクと脈動する心臓の音が、耳に纏わりつく。
「ひっ……ぁぁ、はぁっ、……ぅ、うあああああ!」
開始された激しい抽送に、堪らず叫び声を上げる。臓腑が抉られ、結腸の入口を擦られ、脳髄を焼くような快感が全身を支配する。このまま兼さんに突き殺されてしまうのではないかと思うほど、強すぎる快楽に震えながら絶頂を繰り返す。
僕の性器からは、一滴たりとも迸りなど零れていない。ただ胎の中をびくびくと痙攣させては、快楽の潮流に飲み込まれていく。
ぎちゅぎちゅと聞いたこともないような音を立てて、兼さんの昂りが奥を穿つ。その動きに合わせて、躰を強烈な痺れが駆け抜けていく。五感の全てで兼さんを感じられる幸せに酔いしれてしまえば、もう戻って来れないかもしれない。目の前がチカチカと光って、意識が遠のきそうになる。
最奥にぐぷりと怒張を叩くように嵌め込まれれば、どこからが僕でどこからが兼さんなのか、曖昧になっていく。
「国広っ……くに、ひろ……もう、離さねぇぞ……! だからッ……どこにも、いくな……!」
「あ、あああっ……!ごめん……、な、さい……、ぅっ、もう、……っ、どこにも……いかな……からぁっ……!あ、ッあ……――、あああ、んああああ!」
兼さんの肉棒の形に開かれた結腸の中に勢いよく欲望が飛び散り、敏感な中の壁をぱしゃぱしゃと音を立てて叩きつけていく。薄い膜を焼かれていく感覚に、躰が悦びの声をあげながらガクガクと震える。
「ぁあああ、あ、……つい、あつい、よぉ……!ぼくのなか、とけちゃうっ……はぁぁぁ……」
どぷどぷと大量の白濁を注がれて、身体の一番深い場所まで兼さんの子種にたっぷりと満たされていく。それがすうっと浸透して、僕の中に馴染んでいくのが堪らなく心地よい。ふわふわとした毛布に全身を包まれたみたいだ。身体の中で兼さんを感じない場所など、もうどこにもない。
「はぁっ……はぁ……兼さん……僕、兼さんのことが好き……兼さんが大好き、です」
それは、ずっと言えなかった言葉だ。心の内に押しとどめて、封印して、ずっと仕舞っておくはずだった、言葉。でも、もうそんなことをする必要はない。
兼さんの想いを、温もりを、感じて。この上なく優しく包まれてしまえば、それに応えられぬ道理などない。僕だって、兼さんのことが、誰よりも大好きなのだから。
「……ようやく言ってくれたな。ありがとう、国広。すげえ嬉しい。……約束してくれ、これからもずっと一緒にいるって」
「……うん、約束」
そっと小指を絡めて、生涯の誓いを立てる。そこには証人も祝福もないけれど、確かな証がこの指に刻まれたのを感じて、ゆっくりと瞳を閉じた。
***
胸に預けられた温かい体温が、オレの心を温めてくれる。大分無理をさせてしまった国広は、深い眠りに誘われたようで目を覚ます様子はない。
そっと薄く膨らんだ腹を撫でる。その中にあるのは、幾度も吐き出されたオレの欲望に他ならない。身体の奥深くまで受け入れてくれたことが嬉しくて、思わず頬が緩む。もう、この身体の隅々まで、オレのものだ。
好きだと初めて言ってもらえた時は、嬉しくて堪らなかった。今まで国広がその言葉をオレに投げかけてくれなかったことに、不安を感じていなかったわけではない。ちゃんと態度で示してくれていたとはいえ、それでも言葉で証明して欲しいのが人間のサガだ。
今なら、それを口にすることを己に禁じていた国広の気持ちが理解できる。ずっと、喰種である自分がオレと共にあることに、葛藤を感じていたのだろう。それをもっと早く気付いてやれれば良かったが、結果的にこうして想いを交わすことができたのだから良しとしよう。
国広が散々悩んでいたように、喰種の国広と人間のオレが一緒に生きていくのは大変だろう。思いもよらない出来事を目の当たりにすることだってあるに違いない。
それでも、たとえこの先にどんな困難が待ち受けていようと、国広と共にいられるのなら、乗り越えられる。ハッキリと、確信を持ってそう言える。悲しい結末を迎えようとも、それでもオレはこの選択に微塵も後悔などしない。腕の中に何よりも大切な国広がいて、笑って、生きていける。
それだけで、この道を選んでよかったのだと、死ぬまで忘れはしないだろう。