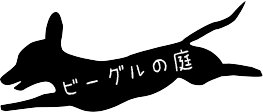とん、と微かに聞こえた戸を閉める音で、兼定は目を覚ました。顔を右に傾けると、もぬけの殻となった布団が視界に入ってくる。ということは、今のは国広が部屋を出ていった音か。
暗闇の中時計を確認することはできないが、しんと静まり返っているところを見るにもう真夜中だろう。寝つきがいい国広が途中で目が覚めて出ていくなんてことは珍しい。昨日から今日にかけて長時間遠征に行っていたため疲れてぐっすりと眠っていたと思っていたが、逆に目が冴えてしまったのかもしれない。兼定の方もこのまま再び眠りにつくのは難しいように思えたので、厨房で水でも飲もうと体を起こす。
月夜に照らされた廊下を歩いていくと、ふと庭の片隅に建てられた石碑のようなものの前に手を合わせている人影が見える。こんな遅くに何をしているのかと、縁側に置かれた草履をつっかけてその人物に近づいていった。
祈り終わったのかすっと振り返ったのは、先ほどまで己の隣で寝ていた国広だった。透き通った湖のような色をした瞳が、大きく開かれて兼定を捉える。
「んなとこで何してんだ?てっきり厨房にでも行ったのかと思ってたぜ」
「あ、兼さん……ごめんね、起こしちゃったかな。ちょっと手を合わせてただけだよ」
「気にすんな、水が飲みたくなっただけだ。……オレはよく知らねえけどよ、この石碑はなんかご利益でもあんのか?」
前からこの庭の隅っこに存在していたのは知っていたが、これが一体何なのかは知らなかった。よく見ると、細かく字が彫られている。
「……これはね、慰霊碑なんだ。前にこの本丸を治めていた審神者の、ね」
「へえ、オレらの前にも別の審神者が本丸として使ってたのか。でもよ、審神者が亡くなる度にいちいちこんなもん建てるのか?墓はまた別にあるんだろ?」
「……いや、普通はこんなものは作られないよ」
風雨に晒されて色褪せてしまったのであろう石碑を、国広はじっと見つめる。その瞳は、どこか寂しそうに見えた。
「この審神者はね、禁を破り歴史を変えるために刀剣男士の力を使ったんだ。政府からしたら、裏切り者ってことだね」
「……なんでだよ。そいつは歴史を変えないために、審神者になったんじゃねえのかよ」
兼定の今の主は、歴史を守るために戦うことに誇りを持っている。いい歴史も悪い歴史も、その時を懸命に生きた人々が紡いだもの。それをどうこうするなどというのは、彼らを侮辱する行為に等しい。だから、自分は審神者になったのだ。以前、兼定にそう語ってくれた。だからこそ、兼定もそんな主のために命を懸けて戦っている。
「もちろんそういう気持ちはあったんだと思うよ。僕も主さんから聞いただけだから詳しくは知らないけど、その審神者は恋人の命を救うために歴史を変えようとしたんだって。事件に巻き込まれて亡くなった、最愛の人を死の運命から救うために」
ずしり、と腹の奥が重たくなった。その審神者のことは全く知らないが、大切な人を何とかして助けたいと思う気持ちは痛いほど理解できる。兼定の、前の主。彼が戦死した戦場に刀剣男士として赴いた時、兼定は思わず涙したから。
「……結局、そのことが政府に知れて処分されてしまった。悲劇を繰り返さないために、そしてその魂を鎮めるために、この慰霊碑が建てられたんだって」
名も知らぬ審神者に、少しばかり同情する。だが、兼定にはそんなことよりずっと気になることがあった。
「……まさかお前、まだ前の主を助けたいなんて思っちゃいねえだろうな」
「ううん、それはないよ。僕には、今の主さんや仲間達、そして兼さんがいる。それに、土方さんは一生懸命生きた。それを僕がどうこうする権利なんて、あるはずないよ」
「それなら、いいんだけどよ……」
「……僕がここを通る度に手を合わせるのはね、自分への戒めのためなんだ。人の心はうつろうもの。また歴史を変えたいなんて思いが湧かないように、ってね」
国広はそっと立ち上がると、本丸に向かって歩き出す。兼定も、その背中に続いた。
「なあ、国広」
「なあに、兼さん」
「こいつに頼るのも悪かねえがよ、まずはオレに相談しろ。お前が道を踏み外しちまうと思ったら、オレがぶん殴ってでも止めてやる。その代わり、オレが間違えそうになった時は、お前が止めてくれよ」
相棒を、真っ直ぐと見つめる。ありがとう、と嬉しそうに笑う顔は、晴れ渡る空のように清々しいものだった。