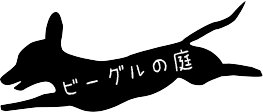最近、気付いたことがある。それはきっと国広だけでなく、この本丸に住まう多くの刀剣男士達もそうに違いない。
国広たちを率いる審神者は、一段と綺麗になった。勿論昔から愛らしい容姿や立ち振るまいをしていたけれど、この数ヶ月で目に見えてその美しさは増していったように思う。
理由は、すぐに分かった。彼女がキラキラと光り輝く瞳でその姿を追っているのをよく目にしたから。その相手とは、国広の大事な相棒、和泉守兼定だ。当然、その隣にいることの多い国広には彼女の想いを察することは容易だった。
兼定と話す時の彼女は、今まで見たことない、周りに花でも舞っていそうなほど幸せな雰囲気を醸し出している。そんな彼らの姿を微笑ましく見守ることができたら、どれだけ良かっただろうか。
国広と兼定は、世間一般的に言うところの恋仲だ。本丸に顕現してもう片手で数えられぬほどの年月を過ごしているが、そういう仲になったのは僅か半年ほど前の出来事である。相棒として過ごすことが当たり前で、兼定のことを誰より大切に思うのも当然そこから来るものだと思っていた。
だが、昔馴染みの加州に勧められて今俗世で流行っている『恋愛ドラマ』というものを観て。そこで繰り広げられる恋物語が、登場する人々の感情の動きが、心当たりがありすぎて。
――ああ、そうか。この胸のうちにあるのは、恋情だったのか。
そんなことに今更ながら気付いてしまって。どうしたものかと悩むうちに、当の兼定から似たような話を切り出されたのだ。
お前のことは相棒として大事に思っていたが、どうもそれだけじゃねえって気付いちまった。
その言葉を掛けられた時のことは今でも忘れられない。全身から止めどなく湧き出てくる、高揚感。自分もそうなのだと目一杯気持ちを伝えれば、切長の目が目尻に少しばかりの皺を作りながら細められて。それだけで胸が感じたことのない温かい感覚に包まれた。
と言っても恋人になったからといって、特別何かが大きく変わったわけではない。時折人目のつかないところでこっそり唇を合わせたり抱擁するくらいだ。それだけで十分、二人の心は満ち足りた。
そんなところに、審神者の恋慕を知ってしまったものだから。どうしたらいいのだろう、と国広はここ最近そればかり考えている。
審神者が国広たちの関係に気付かないのも無理はない。誰かがいる前では以前と何ら変わらずに過ごしているのだ。恋人らしいことをするのは、あくまで完全に二人きりの時だけ。
兼定はどうやら審神者の想いには気付いていないらしい。恐らく、主が自分に特別な好意を寄せるなど考えたこともないんじゃないだろうか。
とはいえ、国広の口からそれを兼定に伝えるのは辛いものがある。
主がまだ僅かに幼さ残る頃から仕え、その成長を見守って来たのだ。国広にとって相棒に負けないくらい、主は大切な存在だ。自分達がこうして再び会うことができたのだって、主のお陰だ。戦いから戻ってきた自分たちを真っ先に出迎えて、少しでも負傷していれば資材や札を惜しまずに使って労ってくれる。そんな心優しい主の幸せを願わないはずがない。
――それに。兼定は、主と結ばれた方が幸せかもしれない。国広の刀身は既にこの世のどこにも存在しない。故に、この戦いが終われば恐らくこの身も心も跡形もなく消え去ってしまうだろう。そんな残酷な未来が待ち受けている自分なんかとより、今を確かに生きている主と共に在ることが兼定のためには良いのかもしれない。
そう思い至る度に、腹の底がずしりと重石でも乗せたかのように重くなる。けれど、国広にとって一番大切なのは己の幸せではない。言うまでもなく、兼定の幸せだ。かつて一人遺して寂しい思いをさせてしまった、ただ一人の相棒の幸せだ。
ならば、辛いだの嫌だのと我儘を言うべきではない。国広は、兼定の幸福が成就されるように行動するべきだし、心より忠誠を誓う主の願いを叶える手伝いをするべきだ。
そう決心してしまえば、腹に響く痛みが少しだけ和らいだ気がした。
それから国広は、心を鬼にして兼定と一緒の時間を削り、その分の時間を主と過ごせるように立ち回った。最初はあまり気にしていない様子だった兼定も、日に日に怪訝な顔をして国広を見つめるようになって来たのをひしひしと感じている。その様子を見ると少しくらいは自分も、と甘える気持ちが湧き出て来そうになる。
ダメだダメだ。主は国広の気遣いにとても感謝してくれており、兼定と一緒に過ごす時間をこの上なく満喫しているのだ。
(心を殺せ、堀川国広。お前は、鬼の副長の懐刀だったではないか。これくらい耐えられず、何とする。)
かつての主の厳しい一面を頭の中に思い描くことで、何とか己の欲求を抑え込む日々が続いた。そんな中で痺れを切らして来たのは、兼定の方だった。
遠征から帰ってきた国広を、待っていたぜと言わんばかりに腕を組んで部屋の真ん中に鎮座していた。流石にそれを無視できるほど冷徹にはなれなかったので、粛々とその向かいに正座する。
「……お前、最近やけにオレを避けているようだが。オレぁ何かしちまったか?」
「そんなこと、ないよ。兼さんにされて嫌なことなんてないもの」
「じゃあ何でオレの側にいようとしねえんだ?もうオレと一緒にいるなんざ飽きちまったか?」
「……そんなわけ、ないだろ。それだけは、絶対にない!」
兼定と一緒にいることが飽きるだなんて、あり得るはずがない。主を同じくした本差と脇差。唯一無二の相棒でありながら、その実共にいられた時間は長くない。互いに刀として過ごした長い生と比べれば、あまりにも短く儚い、時間だった。
だからこそ、側にいられる時間は何よりもかけがえの無いひと時だ。それは国広も兼定もきっと同じ気持ちだと思う。
――だから。飽きるなんて、天地がひっくり返ってもあり得ない。だから。つい声を荒げてしまった。
「言ったな?じゃあちゃんと教えろよ。オレと一緒にいられねえ訳ってやつをよ」
まさか、兼定に誘導尋問されるとは思わなかった。こういったことは、自分の専売特許だと思っていたのだが。気付かぬうちに、彼も戦う力だけでない部分も成長していたようだ。流石は、国広の自慢の相棒である。
「……兼さんに、悲しい思いをして欲しくないから。幸せに、なって欲しいから」
「ぁあ?何言ってんだよ、オレは十分過ぎるぐれえ幸せだぞ」
「今は、それで良くてもさ。僕と兼さんにはいつか別れの時が来る。僕は本当ならもうこの世にはいないはずの存在なんだから、当然なんだけどね。僕はその瞬間辛いだけだけど、兼さんは違うでしょ?先のある兼さんは、それから何年も辛さを感じる瞬間に襲われる。僕は兼さんに、そんな思いをさせたくないんだ」
「……」
「それに、ね。兼さんは気付いていないかもしれないけど、主さんは兼さんのことが好きなんだよ。臣下の一人としてじゃなくて、特別な存在としてね。だから思ったんだ。きっと兼さんは主さんと結ばれた方がいい。その方が悲しい思いをしなくていいし、何より主さんはとても素敵な人だもの。兼さんと二人で仲睦まじく、心穏やかな時間を送れるはずだよ」
兼定の眉間にはどんどんと深い皺が刻まれていく。それは、恋人から突きつけられた言葉に対する怒りか。それとも、国広との未来を想像した悲しみだろうか。
「勝手なことばっか言ってんじゃねえよ」
国広を見つめる眼差しは、真剣そのものだった。
「オレの気持ちを無視して主と一緒になれ、だと?ふざけるのも大概にしとけ。オレは主のことを慕っている。でもそれは忠義を尽くす相手としてであって、惚れた腫れたの話とは別もんだ。オレのことを好いてくれている気持ちは有り難えが、オレは主と恋仲になりたいなんて思わない。なぜなら、オレは国広のことが好きだからだ。だから、国広以外とそういった関係になるつもりはねえ。それがオレの嘘偽りない気持ちだ」
真っ直ぐと国広を見据える瞳は、痛いくらいに力強い眼光を携えている。そこから視線を逸らすことなど、到底できるはずもない。
「でも、僕と一緒にいたら遠くない未来にまたお別れしないといけないんだよ……それでもいいの?」
「んなこととっくに覚悟決めてらぁ。別に、オレとお前に限った話でもねえだろ?前の主だって、死ぬまでの間に何度も大切な人との別れがあった。仮にオレと主が結ばれたとしたって、いつかは別れが来る。その時が遅いか早いかの違いだ」
「それは、そうかもしれないけど……」
「オレはもう昔のオレとは違う。確かに前の主や国広と離れ離れになった時は、どうしようもなく辛かった。……何で、オレだけ。そう何度思ったか分からねえ。でもな、歴史の移り変わりや人の営みを見ていくうちに思ったんだよ。誰だって、別れは悲しいもんだ。けどよ、それでも誰かと関わらないで生きていくなんざできっこねえ。限りある命、限りある時間。だからこそ大好きな奴と一緒にいる何でもない瞬間が、何より愛おしく思えるんだ」
言葉通り、覚悟を決めたという彼の目に一点の曇りもない。別れの未来さえも受け入れる、そしてそれまでの時間を精一杯生きる。別離の辛さをただただ嘆き悲しんでいた頃とは違うんだと、その振る舞いが示している。
「だから、悲しいこと言ってくれるなよ、国広。オレはお前とまた別れちまうその日まで、お前と一緒に過ごしたい。大好きなお前の隣にいたい。……お前は、違うのか?」
「ううん、僕も兼さんの側にいたいよ……兼さんの一番近くで、一緒にいたい」
「なら、この話は終わりだ。主には、オレから折を見て正直に話すさ。……もうオレのことを避けるんじゃねえぞ?」
「勿論だよ、ごめんね兼さん……兼さんの気持ち、全然分かってなかった」
「長年の相棒だって、言葉にしねえと分からないことくれえあるさ。今度からは、まずオレに相談しろ」
国広の頭を、背を撫でる手は余りにも温かい。頼もしい相棒の想いと優しさを肌に感じながら、国広は兼定の大きな背に腕を回した。