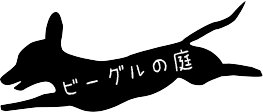きゃあきゃあと、近所に住む子供たちの賑やかな笑い声が外から聞こえてくる。ふと声のする方に視線を向ければ、みな一様に長方形の紙をその手に握りしめている。ああ、もうそんな季節か、と兼定は思った。誰と喋ることもできない自分には、こういった季節行事でもない限り時間の流れに鈍感なのだ。
きっと彼らはあの小さな紙に目一杯の願い事を託し、夜風に揺れる笹の木に色とりどりの想いを飾り付けるのだろう。キラキラと輝く黒曜石のような瞳は、兼定にとっては眩しいくらいだ。
昨日まで降り続いた雨もあがり、まだ道にはところどころ水たまりが残っているものの、見上げる空には雲に遮られることのない星々が煌めきを放っている。きっと今晩は、織姫と彦星とやらも無事に出会えたことであろう。しかし、兼定にはそれを素直に祝ってやる気持ちにはなれなかった。
かつて、七夕の晴れた夜にしか会うことのできない彼らの悲しい恋物語を初めて聞いた時は、自分たちで蒔いた種とはいえその境遇に同情したものだ。けれど、今は思う。一年に一度会うことができるかもしれない機会があるなんて、贅沢な話だ、と。
(オレは、どんなに会いたくても叶わねえってのにな――)
戦いに身を投じて散っていった主にも。そして、おそらくは彼と最期を共にした相棒にも。もう二度と、その姿を見ることはできない。
自分だけが生きて帰って来たことに、不満があるわけではない。激動の時代を駆け抜けた主の生き様を、その魂を後世に伝える役割を担ったことを、兼定は誇りに思っている。
そうはいっても、だ。心より信頼する者たちをいっぺんに失い、それから今までずっと一人で主の生家で生きてきた。どんなに孤独を感じても、耐えてきた。だからこそ、羨ましいと思わずにはいられないのだ。
「オレもせめて一年に一度、いや、一生で一度限りでもいい……」
つぶやく声は、誰にも聞こえることなく闇夜に消えていく。
すでに人としての生を終えた主は無理かもしれない。だけど、自分と同じ『モノ』から生まれた付喪神である彼ならば、あるいは――。
いつの間にか子供たちはそれぞれの家に帰った後の静寂。天の川が見守る中、兼定もまた密かに己の願いを託した。
思いもよらぬ形で彼の願いが叶うのは、まだずっと先のことである。