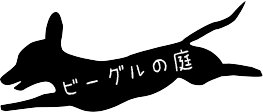もう何度目か数えることすらできない出陣を無事に終えて、オレは少し疲れた体をたっぷりと熱い湯に浸かって芯まで温め、自室へと戻ってきた。
今日は最近本丸に顕現したばかりの刀剣たちを引き連れてレベルを上げるための戦闘だったため、誰も大した怪我をすることもなく帰還することができた。
この本丸に顕現して数年が経つオレは、新人を引率しながら戦うこともすっかり手慣れたものだ。大体こんなことで躓きそうになるだろうといったことは、長年の経験で頭に叩き込まれている。
それに、オレの前の主は職務上頻繁に集団戦をしていたから、オレ自身もただの刀であった頃から仲間と共に戦うことには親しみを感じている。だからこそ、主はこうして新顔に気を配りながら戦う役目をオレに任せてくれているのだと自負している。
レベルの高い刀剣同士で敵の猛攻に耐えながら新たな合戦場で斬り結ぶことも、来たばかりの刀剣たちの成長を見守りながらサポートするのも慣れっこだ。もちろん、この本丸での騒がしくも心地良い生活も。
ただ、いつまで経っても慣れないことが、一つ。それが、未だにオレの心に暗い影を落としている。きっと死ぬまでオレはこの現実に完璧に順応できないんじゃないか、そんなことすら思えてくるほどだ。
部屋の中はしんと静まり返っており、せいぜい時折オレが身動きした時の衣擦れの音がするくらいだ。この静けさが、余計にオレは一人なんだということを思い知らせてくるものだから、一度主に頼んで『ラジオ』なる音楽を聴くことができる絡繰を借りたこともあった。結局、それくらいで気分を紛らわすことは叶わず、とっくの昔に返却してしまったが。
本来ならば、『和泉守兼定』の隣には、唯一無二の相棒『堀川国広』がいるはずだ。実際、演練で出会う別の本丸の『和泉守兼定』の側には大体の場合『堀川国広』がいる。
当然オレの隣にも、国広がいた時があった。いや、いた時があった、どころではない。顕現してからずっと、オレたちは一緒に戦ってきたのだ。一年前、オレのいない部隊で出陣した国広が折れてしまった、その時までは。
オレと国広は息の合った連携ができることから、出陣も同じ部隊が多かった。その日も最初に出陣した時は一緒の部隊だったんだ。しかし、敵の遠戦攻撃から国広を庇って怪我を負ったオレの身を案じて主は部隊から外すことを指示し、オレは手入れ部屋へ。
時間遡行軍の進軍が予想よりも早かったために、オレの回復を待っている暇はなかった。代わりの刀剣男士が編成されて再度出陣していく後ろ姿を見て、全く不安が過ぎらなかったと言えば嘘になる。
けれど、その時のオレにできることは怪我を治すことだけだった。あの時の負傷具合では、そのまま無理に進めばオレの身に危険が及びかねない。それを誰よりも分かっていたから、主はオレを外したのだ。その選択は間違っていなかったし、恨むつもりも毛頭ない。
手入れが終わったオレは、賑やかな声と共に国広たちが帰還するのを今か今かと待ち続けた。夕方には戻ると思っていた彼らは、されど日が沈んでも帰っては来なかった。
「心配なのは分かるけど、和泉守だって怪我が治ったばかりなんだから休んだほうがいいよ」
そう大和守に声をかけられて、渋々部屋へ引き上げようとした時。ドタドタと慌ただしい騒めきが表から聞こえて、オレはほとんど無意識のうちに音のする方へと駆け出していた。
そこで待ち受けていたのは、想像以上に酷い光景。無傷で帰ってきた者はおらず、一番マシな者でも中傷といった具合だ。痛みを必死に堪えながら帰還した隊長は、オレの顔を見るとハッとした表情を浮かべ、その後すぐにこの世の終わり、地獄の淵でも見てきたかのような絶望の色へと変わった。
彼らの中に国広がいない時点で、その口から発せられる言葉は推察できた。無論、それを受け入れられるかは別問題、だが。
震える声が、告げる。国広が、苛烈な死闘の末に戦場で命を散らせたことを。もう、この本丸に帰ってくることはないということを。
血に滲んだ掌に包まれた、真っ二つに折れた脇差。それを目にして自分がどんな反応をしたのかは思い出せない。あまりの衝撃に、脳が自身を守るために当時の記憶を消し去ってしまったらしい。
覚えているのは、それから数日間、もう国広の魂の欠片すら感じることのできぬ刀身を抱きかかえながら自室に篭っていたことくらいだ。最期の瞬間に側にいてやることができなかった、せめてもの償いだ。或いは、その死に顔すら目に焼き付けることができなかった後悔から来るものだったかもしれない。
数日の間に何とか気持ちを落ち着けて、いつまでもこうしているわけにはいかないと意を決して部屋を出たオレを、加州や大和守、長曽祢さんをはじめとした仲間たちは暖かく迎え入れてくれた。
こうしてオレはなんとか元の生活へと戻って行ったわけだ。オレを心配する刀剣たちの心遣いは痛いほどよく伝わってきたから、いつまでも悲嘆に暮れる姿を見せるわけにはいかなかった。
今では無事に立ち直り、時折寂しさを感じつつも平穏な生活を送れていると誰もが思っているはずだ。オレだって皆と過ごす時は、相棒が隣にいないということを意識せずにいられる。
――そうは言っても。こうして一人になればいつだって、ここに在るべき姿を探さずにはいられなかった。
オレたちの主は、一度折れてしまった刀剣を再度鍛刀することはしない、と決めている。所謂二振り目は、死した同じ刀剣の記憶を宿さない。姿形は一振り目と全く同じだが、刀であった頃の記憶は持てども本丸では生まれたての赤子と同じ。
一振り目との思い出を大切にしたい。それに、一振り目の代わりのように思われてしまうのは二振り目にとっても辛かろう、という考えから、主は決して二振り目を顕現させない。
主の決め事に異を唱える気はない。たとえ二振り目の国広がやって来たところで、オレと共に何年もこの本丸で過ごした国広とは違うのだ。
死した者が蘇ることはない。それが自然の摂理。
そう納得しようと、何度も思った。それでも国広の存在を求めてしまうのだから、人の心というのは厄介なもんだ。
大事な相棒であり、恋人。それがオレにとっての国広だった。何物にも変え難いほど、かけがえの無い存在。
一体人間たちは、大切な人を失う底なし沼のような悲しみをどうやって乗り越えているんだろう。刀の頃はどこか他人事のように思っていたそれが、今は鋭利な刃物のようにオレの心を深く突き刺していた。
それから数日経った夜。夏を間近に控え、蒸し蒸しとした空気にじわりと肌に汗が纏わりつくのを感じて、オレは目覚めた。
部屋に置かれた扇風機ではどうにもならないほどの蒸し暑さに、眠りから呼び戻されてしまったらしい。流石に今の時期から冷房を使うのは些か早すぎることは理解しているので、なんとかこのまま耐えて再び夢の中に入るのを待とうと寝返りを打つ。
――こんな時、国広が隣にいてくれたら。そのすやすやと気持ちよさそうに眠る姿を見て、微笑ましくなって、そっと抱き寄せて。多少の暑さなんてどうでも良くなるくらい心地良い気分で、眠りに就くことができるだろうに。
目を瞑って寝よう寝ようとするものの、そういう時ほど却って目が冴えてしまうのだ。明日は出陣はないとはいえ、寝不足の体を引きずって内番の仕事をするのが辛いことは重々承知している。
焦りは禁物だ。寝なければいけないと思うから、余計に寝れなくなってしまう。無心になれ。そうすれば自ずと眠くなるものだ。
そう頭の中で必死に反芻しているうちに、横向きになっていた背中を優しく撫でる感触があることに気付いた。まるで赤子をあやす母親のように、慈愛に満ちた温かさが寝間着越しに肌へと沁みてくる。
果たして、これは誰だ。たまたま通りがかった者が、寝苦しくしているオレを宥めているとでもいうのか。
いや、それはない。いかに目を閉じていたとはいえ、誰かが近づけばその気配を察せないほどオレは鈍くない。
……では。気配すら発することなくオレの元にやって来て、この背をさする存在は一体何だというのだ。
妖か、それとも――
得体の知れない何かかもしれないと考え、思わず背筋に力が入る。そんなオレの変化を敏感に感じ取った後ろの者が、落ち着かせるような声色でそっと囁く。
「大丈夫だよ。僕は、敵でもなければ、妖でもない。だから安心して」
――まさか。この声は、オレが幾度ももう一度聞きたいと願った、愛しい国広のもの。
否、そんなはずはない。国広は死んだのだ。もう、どこにもいるはずがないのだ。
夢だ。これは、寂しさからオレが作り出してしまった夢の中なんだ。こんな夢を見たら目覚めた時に虚しくなるだけだというのに、オレは馬鹿だなぁ。
さっさとまやかしの希望から解放されたくて、手を顔に添えると思い切り頬を引っ張る。
痛い。夢の中だからと遠慮なく引っ張ったから、想像以上の痛みに指を離してもなお頬がじんじんする。
それなのに。オレの背を撫でる感触は消えない。
夢じゃなきゃ、何だっていうんだ。
勇気を振り絞って、ゆっくりと振り返る。そこには、記憶が擦り切れてしまうのではないかというほど何度も思い出していた恋人が、確かにいた。
驚きのあまり何も口に出来ずにいるオレを見て、ふふっと柔らかい微笑みを浮かべる。寸分違わない、記憶の中の国広の笑い方そのままだ。
夢ではないというなら、幻覚か。目の前の国広は、孤独に耐えきれなくなったオレが作り出した、幻なのか。
瞼を擦ってみても、瞳に映る国広は消えない。遠慮がちにその体に手を伸ばすと、温かい肌に触れた。
「夢でも幻でもないよ。僕は、ここにいる。兼さんの、隣にいるよ」
その言葉に、オレが今まで心の中に抑え込んでいたぐちゃぐちゃに絡まった糸のような感情が腹の奥底から溢れ出てきて、全身が熱くなっていく。本能的な衝動に抗うことができるはずもなく、がっちりと絶対に離さぬように華奢な体を抱きしめた。
「……ごめんね。兼さんに寂しい思いをさせちゃって。戦場で斃れたことに後悔はないけど、それだけが心残りだった」
細く、それでいてところどころ節張っている指が、先ほど引っ張られてまだ少し痛みの残る頬に添えられる。微笑をたずさえたまま、ゆっくりと国広はオレの唇に己のそれを重ねた。
オレのよりも少しばかり薄く、柔らかい感触。在りし日には、毎日のように味わっていたそれが、今までの思い出を次から次へと掘り起こしては頭の中を満たしていく。
ここに、今オレの腕の中にいるのは、確かにオレの相棒であり恋人であった国広だ。オレが求めてやまなかった、国広だ。
そう思えば、じっとなどしていられなくて。体に急速に広がっていく熱に任せて、国広の体の上にのし掛かる。まるで檻の中に閉じ込めてしまうように覆いかぶさるオレを見て、満開の桜の花のような笑いが零れた。
***
艶を纏った空気が元の蒸し暑さを取り戻し落ち着いた頃。オレと国広は体を寄り添わせながら緩く抱き合っていた。掌に感じる体温がひたすらに心を穏やかにしてくれて。
しばらくそうしていた後に、どちらからともなく話し始めた。
「突然いなくなってしまってごめんね。……僕はもうこの世にはいないけど、いつだって兼さんのことを想っているよ。側にいることはできなくても、僕の心は兼さんと共に在る」
「……ああ。ありがとよ。お前が見守ってくれてるんだって思ったら、もうちっと頑張れる気がしてきた」
「……本当?嬉しいな。でも、兼さんは僕がいなくたって、かっこ良くて強い刀だよ」
「そうか?……いや、そう在ろうと必死だったんだ。心配を掛けるわけにはいかねえから誰にも言えなかったが、ずっと寂しかった。こんなにも国広はオレにとって何より大切な存在なんだって、思い知らされた」
寂しい。それはずっと胸の内に秘めていた感情だ。周りの刀剣たちに気を遣わせまいと、決して国広のことを自分から誰かに話すことはしなかった。顔に出てしまうかもしれないからと、人前では国広のことを思い出すことすら禁じていた。
口に出してしまえば、国広のいない物悲しさを我慢できなくなるのではと、怖かった。かっこ良くて強い、を自称しているくせに、随分と臆病になっちまったもんだ。
こうして素直に寂しさを言葉にすれば、少しだけ胸がすっと軽くなったような気がする。それは、他でもない国広が今オレの目の前にいるからってこともあるだろうが。
「……これから先、寂しいと思うことがあったら。どうか思い出して欲しいな、今晩のこと。話すことも触れ合うこともできないけど、僕の魂は常に兼さんの側にいることを」
「おう、分かった。オレはこれから先も、国広の分まで戦って主のことを勝たせてみせるぜ。今度こそ、きっとな。……だからよ。オレと一つ、約束してくれねえか」
「……うん。いいよ。僕に叶えられることなら、何でも」
「こいつはお前にしか叶えられやしねえさ」
――なぜなら。こんな約束したいと思えるのは、この世でただ一人。国広以外にはいないのだから。
「オレたちは刀だ。人間よりも長いとはいえ、いつかは寿命を迎える。それが『物』として生まれたオレたちの運命だ。……だから。いつかオレの本体が朽ちて消える時。そん時は、迎えに来て欲しい」
オレの背中に回された腕が解かれる。ぐいと腕を引っ張られたので、何だと思いながら国広の背中に添えていた腕を体の前に持ってくる。オレの右手を両手で包み込む国広の体温が手から全身へと伝わっていく。
「分かった……約束。兼さんのこと、誰よりも先に迎えに行くね。……でも、急いで来ちゃ駄目だよ?兼さんの力を必要としている人はたくさんいるから。僕は気が長いからね、何十年、何百年経とうともずっと、待ってる」
祈るように握られた手から、真綿で包むような国広の優しさがオレの体の隅々まで染み渡っていく。誓いの証も何もないが、この約束は絶対に果たされる。理由なんてなくたって、そう確信できる。
「……じゃあ、名残惜しいけど、僕はそろそろ行くよ。いつか会えるその時まで、お別れだね。だけど、約束したから。……またね」
「ああ……またな」
オレの手を包む両手がゆっくりと離れていく。引き止めたい気持ちはあれど、何故だか急に体が重たくなってきた。微笑む国広の顔を一秒でも長くこの目に焼き付けたくて、降りてくる瞼と懸命に戦う。
その笑顔だけで、きっとこれから先何年も、オレは生きてゆけるに違いない。
国広に届いたかは分からないが、目一杯の感謝の言葉を口ずさみながら、オレは微睡に落ちていった。
***
「おーい、いつまで寝てんのさ!早くしないと朝ご飯抜きだよー」
聞き慣れた声が耳に入ってくるのを感じて、もぞもぞと体を動かしながら目を開けた。少しばかりむすっとした顔の加州が、腰に手を当て口を尖らせながらオレを見下ろしている。
「やーっと起きたね。もう皆食べる準備できてるんだから、さっさと顔洗って来なよ」
言いたい事は伝えたということらしく、ぴしゃりと障子を閉めるとタッタッタと足音が遠ざかっていく。目覚めるのが惜しいくらい幸せな夢を見ていたようで、すっかり寝過ごしちまったらしい。
――夢?
いや、違う。だって、オレは確かに国広をこの手で抱きしめて、散々に愛し合ったじゃないか。あの温もりは、体を支配した強烈な熱は、間違いなく現実だったはずだ。たとえ、オレの隣に誰もいないとしても。
あまりにも幸福な一時だったから、今ぽつんと一人で部屋にいることにどうしても不安を感じてしまう。そんな弱気な考えを振り払うように立ち上がり、姿見の前に立って身支度を始める。
着替えようと手をかけた寝間着の合わせから覗く胸元。そこには、目を凝らさずともはっきりと見える、赤い痕が点々と色鮮やかに残っていた。忘れるはずもない。これは国広がオレにくれた、愛情の証だ。
やはり、夢なんかじゃない。オレは確かに、昨夜国広と会って心を交わしたのだ。誰に言っても信じてもらえないだろうが、オレだけがそれが紛うことなき真実であると分かっている。それだけで、十分だ。
オレは、国広との約束を果たす。そのために、今日も明日も、生きていく。
国広がいなくなって以来初めて感じる、頭から爪先まで全身を取り巻くような愛念を感じながら、オレは仲間たちの待つ食堂へと急いだ。