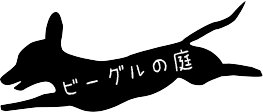桜の花もすっかり散ってしまい、新緑の葉が瑞々しく息づく頃。
毎年、この時期になると必ず目の当たりにする光景。
国広の相棒、かっこ良くて強い兼定はこの季節の訪れのたびに不調をきたす。
理由は国広が一番よく分かっている。春が緩やかに終わりへと向かい始めた頃、主の腰に差された大小の二振は離れ離れになったのだ。こうして審神者に刀剣男士として呼び出されることがなければ、それは永遠の別れとなっていただろう。
国広は遺した方だ、もちろんその時はこの魂がズタズタに切り裂かれるような思いだったが、刀としての役目を終えて朽ちた後は何も考え、感じることなどできなくなった。
――だが、兼定は。
一人遺された後も、僅かな希望に縋りながら国広の帰りを待ち続けた兼定は、どれほど絶望に打ちのめされたのだろうか。兼定の過ごした孤独の時間を考えるだけで、腹の奥を鋭利な刃物で突き刺されたような衝撃が走る。
だから、二振が別れた日が近づくと兼定の精神はどうしても平静を失ってしまう。本人もこんな風に情けない姿を晒すのは嫌だと思っているようだが、心というのは時としてどうにもならないほど自分の意志に反して暴れてしまうものだ。
そして今日が、かつて二振の運命を引き裂いたその日だ。兼定は当然の如く朝食の場に顔を出さなかったので、いつものように国広は兼定の分の膳を受け取ってお盆に乗せると、部屋への道を急ぐ。
とんとんと障子を叩いて合図して、さっと開く。布団の中はもぬけの殻だったが、代わりに部屋の隅で蹲っている大きな体が目に入ってきた。
「兼さん、ご飯持ってきたよ。しんどいだろうけど、少しは食べないと体がもたないよ。……ね?兼さんの好きな沢庵も入れてもらったからさ」
端に寄せていた文机を持ってきて、まだ温かい湯気が漂う朝食をその上に乗せる。近くで匂いを嗅げば少しはお腹が空くんじゃないかと思ったのだが、そう都合の良いものでもないようだ。
「……いらねえ」
伏せられた顔から微かに声が漏れ聞こえる。普段とは違う覇気のない声色に、このまま黙って見ていることなどどうしてもできずにそっと近づく。丸まった背を、できるだけ刺激しないよう壊れ物に触れる時のように撫でた。
すでに起こってしまった過去は変えられない。ならば、自分にできるのは今の兼定の側に寄り添うことだけだ。せめてそれくらいは、させて欲しい。
そんな国広の感情が触れる指から伝わったのか、ぐいと大きな体の中に抱き込められる。羽交い締めにでもするかのような力強さに苦しさを感じない訳ではないが、今はその苦しささえ心地良い。
長い年月の間兼定が一人味わってきた痛みを、少しでも共有できるような、そんな気がするから。
「……国広」
「なあに、兼さん」
「オレの側に居ろよ」
「……うん、勿論だよ」
「今日だけじゃねえ。これから何十年、何百年経っても、だ。ずっとオレの側にいてくれ」
――そんなの、無理だ。兼定だって分かっているはずなのに。この戦いがいつまで続くのかなど分からない。或いは戦いの途上でどちらかが折れてしまうかもしれない。それに、無事に時間遡行軍に勝利したところで。本体である刀が現存していない国広の魂は、拠り所をなくして消えてしまうだろう。
それくらいのこと、兼定が分からないわけがない。それでも、そう願わずにはいられないのだろう。たとえそれが叶わずとも、今この瞬間、闇の中に沈む心をその言葉で救って欲しいのだ。
兼定がそう望むのなら、国広が応えられぬはずもない。仮初の約束だとしても、国広の心は心底それが果たされることを望んでいるのだと伝えたい。
「分かったよ……僕はこれから先、ずっとずっと、兼さんと一緒にいる。だから、安心して?」
これは、いつか破られる誓いだ。だとしても、一時でも兼定の心に安らぎをもたらすことができるのなら。
堀川国広は喜んで、罪作りな嘘を吐こう。