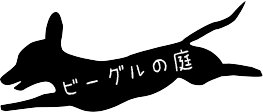――夢を、見る。
何度も、何度も、同じ夢を。大切な主を守ることができずに、何もできなかった愚かな己の、夢を。
刀剣男士として顕現するまで、夢とはふわふわとした、それでいてどこか温かい世界なのだと思っていた。刀であった頃の国広は前の主が休んでいる寝所によく控えていたので、時に幸せそうにまなじりを下げながら眠る姿を見て、きっと良い夢を見ているのだろうと微笑ましくなったことを今でも覚えている。
だから、刀である自分には縁遠いそれを、幸福の象徴のように思っていた。それが自分にとって苦しみを与える種になることなど、思ってもみなかった。
男が血に染まって地に倒れ伏す姿が眼前に広がり、ガンガンと頭を殴るような痛みに体中が蝕まれていく。
(どうしてだ。どうして僕は、何もできないの――。どうして僕は、こんなにも無力なんだ――)
いくら心で助けたいと願っても、現実では己の力で何一つできやしない。それが刀として生まれたものの宿命だ。刀はただ主の手に握られて、振るわれるのを待つだけの存在だ。
だとしたら、どうして。どうして考え、感じる意志を持たされたのだろう。この自我さえなければ、ただの道具として無機質で無感動な存在でいられたのに。
どう頑張ってもこの運命を変えられるはずもないのに、自責の念が後から後から波のように押し寄せては心を埋め尽くしていく。まるでがんじがらめにされて、指先一つ満足に動かせなくなってしまったかのようだ。
誰か。お願いだから、助けて欲しい。このどろどろと纏わりつく後悔の渦から、掬い上げて欲しい。
でないと、どうにかなってしまいそうだ――。
ハッと瞳を開けば、見慣れたはずの自室の天井が目に入る。ぜえぜえと苦しげに聞こえるのは、自らの乱れた息が奏でる音だろう。
――夢、か。
幾度も繰り返されるそれは夢だと分かっているはずなのに、それでもいつだって国広の胸をきつく締め付けていく。心の中に存在する悔悟の念を忘れるなと戒めるように、何度も映し出される光景。箱館で、前の主・土方歳三を守ることができずに死なせてしまった、光景。
きっと国広の心は、あれはどうしようもないことだったのだと割り切れないのだろう。だからこそ、この過去から逃げるなとでも言うかのように、眠りにつく度に突きつけられるのだ。
この苦しみから解放される日は、果たしてやって来るのだろうか。
そんな後ろ向きなことばかり考えているうちに、背中にびっしょりとかいた汗が体を急速に冷やしていき、思わず身震いしてしまう。
いけない、このままでは明日の出陣に響いてしまう――。
着替えるために体を起こせば、隣で眠っていたはずの存在がこちらを見つめているのに気付く。「……おい、大丈夫か? すげえうなされてたぞ」
「あ、兼さん……ごめん、僕のせいで起こしちゃったよね? すぐに着替えて寝るから大丈夫、兼さんは気にせず寝てて」
そう口にしながら予め枕元に置いていたタオルで汗に濡れた体を手早く拭き、押し入れから予備の寝間着を出してくる。その様子を、兼定は何も言わずにじっと眺めていた。
こんなことが毎晩のように起きてしまうので、兼定を巻き込まないためにも本当は別の部屋で休むべきだ。実際、顕現した当初はそのように過ごしていた。
けれど、国広がよく眠れていないことをその目の下にできた隈や疲れた表情から察したのだろう、ある時オレもお前と同じ部屋で寝起きすると言い出して来たのだ。
それでは兼定の気が休まらないだろうから大丈夫だと断る国広だったが、どうしても譲らないと半ば強引に布団を運び込まれ、結局毎晩隣で眠ることになってしまった。
そして案の定、こうして兼定を起こしては、心配をかけてしまっている。国広が寝不足で任務に支障をきたしてしまうのは自業自得だが、兼定まで同じことになってしまっては主に申し訳が立たない。
せっかく刀剣男士として再びこの世に生を受け、二度と会えないと思っていた大切な相棒と再会させてもらったのだ。自分にできる限り精一杯今の主に尽くそうと思っているのに、国広の体は言うことを聞いてくれない。
一度、夢を見ないようにする方法はないのかと主に尋ねたことがある。
けれども、疲れて深い眠りについた時は夢を見にくいとは聞くが、完全に見ないようにするのは難しいだろう、と言われてしまった。
出陣すれば己の体を存分に使って戦うため程良い疲れを感じて帰ってくるし、出陣がない時でも内番や家事手伝いを率先して行うことで体を動かすように努めている。それなのに、そんな努力を嘲笑うかのように悪夢は毎晩国広の元へ訪れては安眠を奪っていく。
冴えてしまった目は中々まどろみへと落ちていきそうもなく、明日もまた寝不足の体に鞭打って働くことになるのかとため息を溢した時、不意に温かい感覚に体がすっぽりと包まれる。風呂で使う洗剤の香りの中に混じる慣れ親しんだ香りは、間違いなく相棒のものだ。
兼定がいつの間にか国広の布団の中に入ってきて、国広はその長い腕の中にすっぽりと入って抱きしめられているようだ。とく、とくと兼定の落ち着いた心臓の鼓動の音を聞けば、寝れないと焦りを抱いていたはずの体がふわふわと沈んでいく。
「……兼さん、ありがとう。でも、暑いでしょ? おかげさまでちょっとは落ち着いたから、もう大丈夫だよ」
「別にこのまま寝ればいいだろ。……昔誰かさんにおんなじことされたからな、お返しってやつだ」
そういえばかつて兼定が付喪神として目覚めたばかりの幼き頃、眠れないのだと眉を下げ困った顔で相談されたことが何度かあった。その度に国広の腕の中に収まる小さな体を抱きしめてはその背中をとんとんと優しく叩き、共に眠りについた。
自分は兼定に指摘されて初めて思い出したけれど、どうやら彼の方はしっかりと覚えていたらしい。借りを返すだなんて、あの幼かった兼定が今では随分と義理堅いことをしてくれるものである。
でも、今はその優しさが心地よい。先ほどまでうなされていたのが嘘みたいに、その温かな体温を感じて国広はゆっくりとまどろみの中に身を委ねた。
兼定のおかげで、次の日は幾分疲れが取れたような感覚で目覚めることができた。相棒の心遣いに目一杯の感謝を述べ、国広は久方ぶりに意気揚々と出陣した。
結果としてその日の出陣の成果は上々で、多少怪我を負ったものの本丸に到着次第すぐに手入れ部屋に入れられたので傷一つ残ってなどいない。朝から夕方まで動かした体は疲労感に満たされており、美味しい夕飯を食べてお風呂にゆったりと浸かってきた今なら、ぐっすりと眠れそうな気がする。
寝ぼけ眼で兼定におやすみと挨拶を告げると、布団を首までかけて眠りに落ちていく。きっと今日は大丈夫だ、そう言い聞かせるように、何度も頭の中で呟いた。
――ああ、またか。どんなに疲れようが、お風呂にたっぷり入って体を温めようが、訪れるのはいつもの光景。主が目の前で死んでいくのを、何もできずにただただ見つめることしかできない哀れな刀の、夢。
目の前に広がる惨状からなんとか逃れたくて、もがくように体を動したおかげか、やっとの思いで現実へと帰ってくることができた。
薄暗い部屋に、汗で体を濡らし息を荒げる自分。幾度も繰り返される、脳味噌をかき混ぜられるような激しい痛み。
こんなことになってしまっているのは、本丸に刀剣男士多かれど自分だけだ。主を目の前で失った経験があるのは、何も国広だけではないというのに。
きっと、自分の心が弱いせいだ。もし自分と兼定の立場が逆転して、彼が前の主の最期を見届けたとしても、心に芯を持ったかっこ良くて強い彼はこんな風にはなるまい。
主の役に立つどころか、このままでは普通の日々を過ごすことすらままならない。歴史を守るために人の体を持ったというのに、生きることすらおぼつかぬこの身に何の価値があるというのか。
大好きな相棒や本丸で出会った仲間たちには申し訳ないが、状況が改善されない以上、自分に残された道は「刀解」しかないように思う。
(でもそうなったら、兼さんを悲しませてしまうのかな――)
己の身が消えることよりも、そちらの方が国広にとっては一大事だ。
一度は離れ離れになった揃いの大小である自分達は、長い年月を経て漸く再会を果たしたのだ。後から顕現された国広を初めて見た時の兼定の喜びようは、尋常ではなかった。その様子を見て、彼の元へ帰ることができなかった悔いが胸をチクリと刺した。
そんな兼定に再び別れを突きつけるようなことを、国広だってできることならしたくない。でも、このまま毎日苦しみ続けて刀剣男士の本懐を遂げることすらできずに生きることなど、許されはしないだろう。何より国広自身が、そんな自分を許せそうにない。
せめて、自分が消えた後すぐに「新しい堀川国広」を顕現してもらうよう、主に頼んでみようか。それならば、兼定の心の傷も新たな相棒との生活で癒やされるだろう。きっと、これが一番良い方法だ。
そう結論付け、着替えようと体を起こしたところで不意に目の前に大きな影が現れた。
また兼定を起こしてしまったという罪悪感に、気持ちが沈んでいく。ごめんねと口に出そうとするが、昨晩よりも強く抱きしめられてしまえばそれも叶わない。
「大丈夫か。……なんかつまんねえこと考えてたろ」
「……そんなこと、ないよ」
互いの表情すら窺い知れぬ闇の中だというのに、国広が何を思い悩んでいたのかすらも見透かされてしまっているのではないかと思い、反射的に否定する。
「お前がなんて思おうが、オレにとって大切な存在だってことは変わらない。だから、いちいち気なんか遣うんじゃねえよ」
「でも……僕、迷惑しかかけてないよ。ただでさえ、レベルだって兼さんに全然追いつけなくて一緒に出陣することすらできないのに、こうして兼さんに気遣ってもらってる。……そんなことしかできない自分が、情けなくて」
いつの間にか熱くなっていた目頭から、ぽろぽろと涙の粒が落ちて寝間着を濡らす。その雫と共に、先ほど頭の中で出した結論を思い切って口にした。
「だからね、兼さん……僕、主さんにお願いして、刀解してもらおうと思う。こんな毎晩悪夢にうなされてしまうような刀剣なんて、戦いでは使い物にならないから。僕だって刀だ、斬れない刀なんて必要ないことくらい分かってる。兼さんには申し訳ないけど、きっと次の『堀川国広』がすぐにやって来るから……」
だから気にしなくて良いんだよ、と続けようと思ったのに、言葉が出てこない。
否、出てこないのではない。出せないように封じられているのだ。兼定の唇によって。
押し付けられた唇は想像以上に熱くて、このまま蕩けてしまうのではないかと錯覚してしまう。
堪らず声を出そうとするが、出てくるのは艶を含んだ呻き声ばかりだ。
そのまま頬に手を添えられ、角度を変えては幾度も口付けられる。触れ合う肌から兼定の息遣いが伝わってきて、自分の鼓動も速く煩くなっていくのを感じる。
一体どうして、兼定は自分に口付けているのだろう。
国広は、兼定のことを好いている。相棒としてはもちろん、それ以上の好意を抱いている。しかし、そのことを一度だって伝えたことなどないし、伝えるつもりもなかった。
本丸で共に過ごし、戦う。それだけでも、一度消滅したはずのこの身には十分すぎるほどの贅沢だから。それ以上など望んでは、バチが当たる。
そう、思っていた。だから、こんな風に口付けを交わす日が来ることなど、想像すらしなかった。
どれほどの時間そうしていたのかは分からなかったが、次第に深くなっていく口付けに思うように呼吸ができず、苦しみ始めた国広の様子を察して兼定は唇を解放してくれた。口をだらしなく開けて新鮮な空気を吸い込もうとする国広の体を、兼定の腕が一層強く抱き締める。
「国広。……言葉が後になっちまったのは謝るがよ、オレはお前を好いている。お前に心底惚れている。……だから、二度と刀解されるだの次のお前が来るだのと戯言を口にするな。そんなことはこのオレが許さねえ」
「兼さん……。兼さんの気持ち、すごく嬉しい。僕も、兼さんのことが大好きだから。でも、だからと言って私情のために迷惑を掛けながら生き続けるなんて、僕にはできないよ……」
「昨日はあの後ちゃんと寝れたんだろ?だったらこれからも抱き合って寝ればいい。それでもうなされて起きちまって辛いなら、オレを叩き起こせば良い。オレたちはたった今から恋仲になったんだ、迷惑なんかじゃねえ。むしろ、それくらいのことはさせろよな」
「こ、恋仲……兼さんと、僕が?」
「おう。オレはお前のことが好きで、お前もオレのことが好き。なら、恋仲にならねえ道理はねえだろ?」
当然だろうと明快に笑う表情は、暗闇の中でもはっきりと分かるほど喜びの色を纏っていた。伝えまいと思っていた国広の気持ちなど一瞬で吹き飛ばすほど、明確に好意を伝えてくれた兼定。
彼のこういう意志の強さや、怖じけずに己の気持ちを素直に口にする勇気。それらはどれも自分にはないものばかりだ。きっと、彼のそういったところに惹かれたのだろう。
「ありがとう、兼さん。まだ兼さんの傍に居てもいいのなら……僕、もう少しだけ頑張ってみようかな」
「傍に居ていい、じゃなくて、傍に居て欲しい、な。そこんとこ間違えんなよ。そんでもって、もうオレに遠慮なんてするな。お前の辛さを代わってやることはできねえが、寄り添うことぐれえはできる。……分かったな?」
「……はい」
「よし、分かったら寝るぞ。明日も早いんだしな。……それとも、まだ寝れねえってんなら、さっきの続き、してやろうか?」
ニヤリと意地の悪い笑みを浮かべながら、国広の反応を窺ってくる。先ほどの続き、というのは、深い口付けのその先ということだろうか。そう考えた瞬間、顔がカッと熱くなるのを感じて、慌てて言葉を紡ぐ。
「も、もうっ、兼さんの馬鹿! 寝るよ、もう寝るから!」
「はいはい、分かった分かった。国広くんは兼さんと一緒に寝ようなー」
まるで子供をあやすように背中をさすられることに不満がないわけではないが、眠りにつかなければいけないのは事実だ。それに、兼定の体温を感じれば、心地よい眠りに誘われることも。
まるで春の陽気に包まれたような暖かさを感じながら、兼定の優しい腕の中で国広は眠りについた。
それから晴れて恋仲となった二振は、任務が終われば互いを労い、誰にも見られぬように自室でそっと口付けを交わし、抱き合いながら眠りにつくようになった。
兼定の腕の中で眠れば悪夢を見ないで済む夜もあったが、完全になくなったわけではない。うなされて起きてはもぞもぞと動く国広を、兼定は嫌な顔一つせずに優しくその背を撫でては落ち着かせてくれた。
寝不足になってしまうのは前と変わらないはずなのに、兼定が寄り添ってくれていると思うだけで、心も体も前よりずっと楽になった気がする。
だから、たとえ辛い記憶を再現するような夢を見ることも、構わないと思っていた。兼定さえ隣に居てくれたら、どんな苦しみにも耐えられる、と。
国広が己の体の異変に気付いたのは、兼定と恋仲になってしばらく経ってからのことだった。
最初は、気のせいだろうと思った。それは急激な変化ではなく、じわりじわりと侵食していくさざ波ような、緩やかなものだった。意識しなければそのまま流してしまえるほど、小さな変化。
だがそれは、次第にそれは明らかにおかしいという自覚を持つほど、大きな変化となっていった。
国広は、毎日兼定と口付けを交わす。それが恋仲になってからの二振の習慣であり、互いへの変わらぬ愛情の証だ。その行為を何よりも嬉しく思っていたし、ついついもっとと強請ってしまうこともあるくらいだ。
なのに、ある日を境に、その行為は国広の心に葛藤を与えるようになってしまった。その理由は、兼定と口付けを交わす度に、刀であった頃の記憶が薄れてしまうということに他ならない。
毎日繰り返される口付けの分だけ、徐々に失われていく記憶。それは逆風が吹く情勢の中で負け戦に主が身を投じていくような辛いものも含まれていたが、同時に新選組が輝いていた頃の楽しかった思い出も等しく消失していった。
主の腰に差されて、兼定と共に戦場に出ては敵を斬り伏せていく。屯所に戻れば、長曽祢や加州、大和守といった他の付喪神と共にたわいも無い会話に花を咲かせる。それらはどれも大切な記憶で、国広にとっては長い刀生の中でも最もかけがえの無い宝物のようなものだ。
忘れてしまうことなど、到底できない。それに、敗戦を続けながらも自分達を振るって戦うことを最後までやめなかった主との思い出だって、辛くはあれど忘れたいなどとは思わない。それも全てひっくるめて、堀川国広という刀を形づくる記憶だ。たとえ辛い記憶であろうとも、消えて良いはずがない。
だけど、それを兼定に話したところで、どうなるというのか。こんなにも国広を慈しみ、愛してくれる彼との肌の触れ合いを拒むなど、どうしてできようか。
そんなことをすれば彼は国広を気遣ってこの習慣をやめようと言い出すかもしれないが、内心どれほど悲しみの感じてしまうかなど想像に難くない。
かと言って、どれほど記憶を失うまいと気持ちを張り詰めようとも、兼定と口付け、互いの肌を感じ、唾液さえも味わう幸福に浸っているうちに、じわりと頭の中が白く塗りつぶされていくのを己の意志では止められない。昨日だって、気付けば池田屋事件が起きる少し前に自分がどうしていたのかという記憶が、いつの間にかすっぽりと抜け落ちてしまっていた。
何度も、兼定にこの事情を口にしようとした。喉の先まで出かかった言葉を、いつもあともう少しのところで飲み込んでしまう。国広の頬に手を添えて、弧を描くように緩んだ瞳や唇を目にすれば、何も言えなくなってしまう。ただただ兼定から与えられる温かさを受け入れ、堪能してしまう。
もちろん主にもそれとなく相談した。最近記憶がなくなってしまうことがあるのだが、どうにかできないか、と。
主は眉を下げて悲しそうな表情を浮かべたが、そのような事例は聞いたことがない、きっと疲れているのだろうとあしらわれてしまう。これで話は終わりだとばかりに立ち去る主をそれ以上問い詰めることもできず、打つ手のない国広は状況に流されるばかりだった。
今日もまた、いつものように風呂を済ませて部屋に戻れば兼定の腕の中に抱きすくめられる。壊れ物を扱うかのようにふわりと頭を撫でられ、その手が頬に落ちてきては柔らかく包んでくる。
口付けを、される。
分かっていても、拒むことはできない。腕を突っ張って兼定の逞しい胸を押せば、きっと兼定はどうしたんだとこの身を解放してくれるだろう。説明すれば、そうだったのか、気付いてやれずにすまないと悲しみながらも分かってくれるだろう。
でも、国広にはそれを実行できない。たとえ刀であった頃の記憶が全て消え去ってしまうとしても、今この瞬間、国広は兼定のことを深く愛しているのだから――
触れる唇がまた一つ静かに思い出を塗りつぶしていくのを感じながら、国広はそっと目を閉じて兼定に身を委ねた。
心の内で葛藤しながらも己を拒めずに受け入れてくれる国広が、この上なく愛おしい。記憶を失うということは自分の根底を崩されるようなものだ、恐ろしいはずである。
何より、国広は楽しい思い出も辛い思い出も、等しく大切なものだと思っているだろう。堀川国広とは、そういう奴だ。それを失うのは、たとえその記憶に苦しめられていたとしても、受け入れ難いはずだ。
そんな国広の想いが抱きしめる強張った体から伝わってくるが、それに構うことなく口付けを深めていく。柔らかい唇の弾力を楽しむように何度も食み、舌を差し入れては奥に縮こまるように収まっていた国広のそれを絡めとる。
たっぷりと咥内を擦り荒らし、国広の舌を啜って甘い唾液を堪能する。お返しとばかりに自分も国広に唾液を垂らしていけば、こくこくと可愛らしい音を立ててゆっくりと嚥下していく様子に堪らなくなる。
国広は知る由もないだろうが、兼定はこの口付けが国広の体にもたらす変化を心得ている。
当然だ。なぜなら、兼定自身が主に頼み込んでのことなのだから。
かつての辛い記憶の夢に苦しむ国広を見ているのは、まるで己のことのように兼定の腹の奥底まで重たくさせた。
兼定の知らない、主を目の前で失った記憶。それが何百年経った今でも愛しい相棒を苦しめているのが、許せなかった。その記憶を共有して、分かってやれない自分が憎かった。
共に体温を感じながら眠りにつけば、国広の心も安寧の中にある。たとえうなされて目覚めても、辛抱強くその背をさすれば次第に落ち着きを取り戻していく。きっと国広はそれで十分だと思っているのだろう。
だが、兼定には我慢ならない。自分の知らない国広の記憶が、誰よりも愛しく大切な相棒の心を傷つけているなど、見過ごせるはずもない。
だからこそ、主に直接相談したのだ。国広の刀だった頃の記憶をどうにかして消せないか、と。
当然主は渋った。堀川国広という刀は現存していない。今の彼を形づくるのは、その逸話や思い出なのだ。記憶を消してしまえばその存在すらも危ぶまれてしまうかもしれない、そう答えられた。
しかしその程度で諦める兼定ではない。思い出ならば、共に主の腰に在り続けた自分が国広のことを忘れなければ良いだけのことだ。無論、何があろうとも大切な相棒との思い出を、一片たりとも忘れてやるつもりなどない。だから、国広の記憶が失われてしまったとしても、和泉守兼定が在る限り、その存在は消えたりなどしないのだ。
そこまで食い下がれば、主も無碍にはできない。ましてや、自分が顕現させた刀剣男士が過去の記憶に苦しみ、刀としての本分を果たすことすら危ぶまれている状況なのだ。主とて、黙って見過ごすわけにはいかないと思っていたのだろう。
記憶を消すには、それに値するだけの強い霊力で上書きする必要がある、と説明される。条件さえ揃えば、あとはその条件を満たした時に記憶が消されるように設定すれば良いのだ、と。
しばらく考えた後、兼定は思いついたことを口にする。国広よりも遥かにレベルの高い兼定自身の霊力を与えれば、記憶を上書くに十分な条件を満たすのではないか。最初は肌を触れ合わせるのはどうかと提案してしてみたが、ただの接触だけでは弱いだろうと難しそうに顰めた顔が返ってくる。
ならば兼定の霊力を宿した体液を摂取させるのはどうだと提示したところで、主は黙りこくる。その沈黙を肯定と受け取った兼定は、ぜひそのようにしてくれと頼み込んだ。
しかし、記憶を失うことが分かっているのに国広がそれを受け入れるだろうかと問う主に、自分たちの関係が最近より深いものへと変わったことを打ち明けた。国広は躊躇いはすれど、必ず兼定を受け入れる。だからきっと上手くいく、主に絶対に迷惑はかけない、と。
こうして主の許可を貰った兼定は、国広と口付けて自身の唾液を与えることで国広の記憶を着実に消し去ろうと画策した。そしてそれはほとんど成功したと言って良い。
兼定の想像通り、聡い国広はすぐにそのからくりに気が付きはしたものの、何も知らないと思っている兼定を拒むことができずにいる。自分の根幹を成すほど大切な記憶を失う辛さよりも、今ここに存在する兼定への愛情の方が勝っているのだ。それが堪らなく兼定を喜ばせ、より一層この身を滾らせていることなど、国広は思ってもいないだろう。
それでいい。このまま口付けを交わし、過去のことなど何一つ残らず忘れてしまえば良い。たとえ自分たちが前の主と共に在った記憶を国広が忘れても、兼定が代わりにそれを覚えている。前の主には申し訳ないが、国広のためだ。悪く思わないで欲しい。
国広は、本丸で数百年ぶりに再会を果たした兼定と恋仲になったという事実とその想いさえ胸に抱いていればそれで十分だ。失われた記憶の分だけ、オレたちはこの本丸で新たに思い出を作っていけばいい。
兼定の愛情という名のゆりかごの中で、何も知らぬ赤子のように愛を与えられ、その愛を受け入れる。それ以上は何も望まない。
幸い明日は久しぶりに互いが非番の日だ、今日こそは国広に唾液だけでなく兼定の欲望の滴を与えよう。そうすれば、より強く、より早く小さな頭の中を白く染め上げることができる。それに、国広への煮え滾るような情を募らせた自分を抑えるのも、そろそろ限界だ。
「国広。……待ってろ、オレがお前を苦しみから解放してやる。だから、何も心配することなんてねえからな」
執着と呼べるほどの澱んだ情欲を抱えた兼定は、ゆっくりとそう呟くと国広の待つ部屋の障子を開いた。