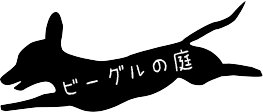1965年、6月。今日、土方歳三の佩刀・和泉守兼定は、日野市指定有形文化財として認定された。かつてこの刀を振るい戦場を駆けぬけた男の活躍を残す遺品として、多くの人に認知され、語り継がれていく。そうすることで、彼や新撰組の仲間たちが紡いだ歴史を後世に伝える役目を果たすのだ。
開け放たれ夕日の差し込む部屋でひとり感慨に浸っているのは、この刀についた付喪神・和泉守兼定だ。その美しくも力強さを感じる容貌は、在りし日の土方を彷彿とさせる。彼を振るう主が函館で戦死してから、兼定は2度と戦場で活躍することはなかった。そのために、今は誰かから見えることもなければ、もちろん意志を疎通することもできなくなってしまった。
いや、今思えば、付喪神を認識できた土方の方が特別だったのかもしれない。それほどまでに彼は偉大な人物だった。そんな土方の愛刀として数々の戦場を共にしてきたことを、兼定は何より誇りに思っている。
今日は自分と主の功績の両方が認められた、ハレの日だ。兼定は静かに目を瞑る。たとえ100年近く経ってもなお、昨日のことのように鮮明に思い出せる。尊敬する主と、そして常に己の隣にいた、相棒だった付喪神。彼らと過ごした、かけがえのない日々のことを――。
***
和泉守兼定は、主・土方歳三の誇りを象徴する刀だった。会津藩主であり、将軍の命により京都守護職に就いた松平容保公。文久3年(1863年)、彼が京都の治安を守る志士を募るため金戒光明寺にて上覧試合を開催した折に、その剣技の腕前を称賛されて拝領された刀。それが、和泉守兼定だった。
剣術を修めた一介の農家の出の青年に過ぎなかった土方にとって、それがどれほどの名誉であったかは想像に難くない。当然、彼は兼定を己の命と同じくらい大切に扱った。
本来、付喪神というのは『モノ』に長い年月をかけて蓄積した人の想いが身を結び、霊魂が宿った存在だ。それがおおよそ100年という年月がかかるものだから、九十九神なんて言われたりもする。だから、打たれて日の浅い兼定に付喪神がつくなどというのは、有り得ないはずだった。
しかし、兼定は土方の愛刀として常にその腰に差された。もちろん、飾りとしてではない。土方の所属する新選組という組織は、荒れてしまった京の治安を取り締まるのが仕事だ。長く太平の続いた世にあって、兼定は他の刀たちとは比べ物にならない速度で振るわれ、活躍していった。
そのため、なんと土方の手に渡って振るわれ始めてから僅かひと月ほどで、付喪神・和泉守兼定は誕生することとなった。初めて兼定の姿を目にした土方は、少し驚きはしたもののすぐに誇らしげな顔をして「お前が和泉守兼定か。俺は土方歳三という。お前の主ってわけだ、よろしくな」と声をかけてくれた。
生まれたばかりの兼定だったが、名乗られる前から彼が自分を使う主であることはすぐに分かった。平然と自分に接する彼を見て、人間にとって付喪神が見えるなどというのはよくあることなのかと首を傾げる。しかし、その疑問はすぐに解決した。主の斜め後ろで、遠慮がちに兼定を見つめている小柄な存在に気づいたからだ。
「打たれてからそんなに年月も経っていないのに、もう霊魂が宿るなんてすごいなぁ。よかったですね、土方さん。……あっ、自己紹介が遅れてすみません。僕は堀川国広、あなたと同じ刀の付喪神です。隣に差されている脇差、それが僕です」
ちらりと土方の腰を見やる。そこには確かに、兼定と同様に腰に差されている刀があった。兼定と比べるとかなり刀身が短いからか、付喪神の堀川の姿もまた兼定の肩くらいの大きさしかない。
「まだ分からないことも多いと思いますけど、遠慮なく何でも聞いてください。僕に答えられることなら教えますから」
屈託なく笑う顔をポカンと眺める。凛とした精悍な顔つきの土方と対照的なその姿に、緊張が少し解れた。
「ああ、よろしくな。一緒にオレたちの主を支えようぜ」
そう言いながら堀川に触れようとするが、伸ばされた兼定の手はするりとすり抜けてしまう。どういうことだと驚いている兼定に、早速堀川が説明してくれた。
「ああ、僕たち付喪神はこうして姿と魂があって話すことはできるけど、相手が人間であろうが付喪神であろうが、他者に干渉することはできないんです。あくまで『モノ』に見た目と霊魂が与えられただけ、って感じですね。この姿が見える人間も、ごく一部の人だけなんです」
「……なるほど、な。まぁただの刀だったのが考えてしゃべれるだけでも凄いのかもしれねえが、ちっと寂しいな。人間同士だったら、触ったりできるんだろ?」
「そうですね……。確かに僕たち付喪神にできることは少ないです。でも、主の相談相手になって、時には助言できるだけでも、役に立てることはありますよ。と言っても、あんまり言葉が過ぎると土方さんは短気だから怒られちゃいますけどね」
「おい国広、誰が短気だって?余計なこと言うんじゃねえよ」
嬉しそうに笑いながら軽口を叩く堀川と、窘めながらも優しい眼差しの土方。そこにはただの刀とその使い手以上の信頼関係があるように感じられた。彼らと共に過ごす時間はきっと楽しいものなんだろうなと思った兼定も、気づけば笑っていた。
てっきり付喪神というのはそんなに多くは存在しないのだと思っていたが、主のいる新選組には、他にも刀の付喪神がいた。局長・近藤勇の愛刀、長曽祢虎徹。1番隊組長・沖田総司の愛刀、加州清光。同じく、大和守安定。そこに兼定と堀川を加えた5振が、新撰組に所属する隊士の刀の付喪神たちだ。
土方は彼らの持ち主に自分の新しい付喪神である兼定を誇らしげに紹介してくれた。そして堀川と同様に、長曽祢も加州も大和守も、兼定のことを歓迎してくれた。まだ生まれて日の浅い兼定に、付喪神のこと、主たちのこと、そしてこの世界のこと。彼らは何でも教えてくれた。そのおかげで兼定はあっという間に、色んな知識を蓄えて成長していった。
皆気の良い仲間だが、中でも兼定が最も親しみを感じるのはやはり堀川だった。同じ主の元で過ごすわけだから、必然的に話す機会も増える。真面目で礼儀正しく、明るい堀川と話すのは心地よかった。
堀川は、おおよそ250年ほど前に打たれた刀であり、自分たちの中でも最も付喪神として生きた年数が長い。彼は九十九神の由来通り、100年近い月日を経て誕生したと思われるため、刀として打たれてから霊魂が宿るまでの間のことは当然全く覚えていない。
堀川物というのは、業物であるため非常に値の張る刀だ。そのため、そんな刀が新選組如きにそう簡単に買えるものか、あれは贋作に違いないと、陰で囁かれている。自分の友を悪く言われることに兼定は怒りを覚えたが、当の本人はそんなことなど全く気にしない堂々とした振る舞いであった。
「人になんて言われようとも、自分は自分の役割を果たせばいいんです。たとえ贋作であったとしても、僕は構いません。土方さんの役に立つことができれば、それでいいんです」
そんな風に語る堀川を、兼定は二本差しの『相棒』として、誇らしく思う。
堀川は、兼定のことを『兼さん』と呼んだ。他の3人のことも、もちろん『さん』をつけて呼ぶ。兼定は、局長の刀である長曽祢のことは『長曽祢さん』と呼ぶが、他の者たちは呼び捨てだ。加州も大和守もそうだし、長曽祢さんだってそうだ。堀川は自分たち付喪神の中で1番年長だというのに、何だってそんな気を使った話し方をするんだろう。
兼定は主に似て、あまり気が長い方ではない。気になったことは、すぐに聞かないと気が済まないタチだ。皆が寝静まった夜、堀川とふたりきりの時に思い切って尋ねてみた。
「なあ、なんでオレのこと『兼さん』って呼ぶんだ?オレだけじゃねえ、他の奴らにだって敬語だろ。お前はオレたちの中で1番古い刀だっていうのによ。オレなんてお前からすればまだひよっこだろ?」
「……いえ、付喪神として経た年数は違えど、皆さんはそれぞれに良いところがあって尊敬できる人たちです。特に兼さんは、僕にとって特別なんです。兼さんは土方さんにとって、侍として認められた証です。ずっと蔵に置かれたり部屋に飾られたりするだけだった僕がこうして戦場で華々しく活躍できるのは、そんな土方さんと兼さんのおかげ。僕にとってふたりは太陽みたいにキラキラと輝いている、誇らしい存在です。だから、どうかこれからも『兼さん』って呼ばせてくれませんか?」
まるで本当に太陽でも見ているかのように、眩しそうに目を細めて笑う堀川。その瞳からは兼定に対する強い信頼が感じられて、腹の奥底から温かい何かが漏れ出て来るような感覚になる。
「……ああ、もちろんだ。だけどよ、せめてオレ相手に敬語くらいはやめてくれねえか?オレたちは土方さんを一緒に支える『相棒』なんだからよ」
「……相棒、ですか」
驚きに大きな瞳が開かれる。自分なんて兼定にそんな風に思ってもらえる存在じゃない、なんてことを思っているに違いない。だが、兼定にとって堀川は、常に1番近くで戦う最も信頼できる友なのだ。
「おう、相棒だ。上も下もねえよ、土方さんを支えるってとこはおんなじだろ?よろしく頼むぜ、国広」
初めて、下の名前で彼を呼んでみる。少しの間唖然としていた国広だったが、照れながらも嬉しそうに微笑む。
「……うん、ありがとう、兼さん。これからもよろしくね」
月夜に照らされたふたりの姿がぼんやりと浮かび上がる。この日は肌寒い夜だったが、互いに相棒だと認め合うことができて、兼定の心は不思議なほど温かくなっていた。
それから兼定と国広は相棒として、ますます絆を深めていった。他者に干渉できないことは知っているけれど、土方に憧れて兼定は刀を振るう稽古を始めた。そんな兼定を国広はいつも見守って、時には助言してくれた。戦いの中、敵の気配を探って土方にそれを伝えるという付喪神ならではの活躍の仕方も、彼に教わった。
ふたりはほとんどいつも一緒にいたし、そのことを時々加州たちに揶揄われることがあっても、兼定は「相棒なんだから別にいいだろ」と堂々と宣言した。そんな兼定の言葉に国広もどこか嬉しそうにしているものだから、兼定と国広は皆が認める『相棒』になったのだ。
ある日、兼定が縁側に腰掛けて夕焼けを眺めていると、誰かがそっと隣に座る気配を感じた。ちらりとそちらを見遣れば、顎に手を当ててこちらを見つめる加州がいる。
「へぇ。珍しいね、和泉守が道場じゃなくてこんなとこにいるの。いつも土方さんの稽古をかじりつくように見てるのに」
「別にいいだろ、オレだってたまにはこうして景色を眺めたくなるんだよ。そういうお前こそ、大体稽古場にいることが多いじゃねえか」
「まーね。俺、沖田くんの剣術を見るのが好きなんだもん」
「確かに、沖田さんの剣技は新選組の中でも随一だからな」
沖田総司は、新選組最強の剣士と目される男だ。稽古場では誰よりも厳しく指導をするため、師範の近藤や鬼の副長と呼ばれる土方よりも恐れられている。そんな彼の剣術は、見る者を惹きつけてやまない圧倒的な迫力がある。兼定も、彼が指導を行うときはその見事な太刀筋に思わず見入ってしまう。
「うん。それにね、沖田くんは俺の恩人だから。……俺、扱いにくい刀だって、ずーっと蔵にしまわれてた。すっかり不貞腐れちゃっててさ。沖田くんが俺を手に取った時だって、どうせ使いにくい刀だなって言われるんだろうって、そう思ってた。だから、沖田くんがいざ俺を試しに振るった後、この刀を下さいって嬉しそうに言ってくれた時の感動は、今でも忘れられないよ。こんなに凄い腕前の人に振るわれるなんて、思ってもみなかったから。『嬉しい』ってこういうことを言うんだなって、沖田くんに教えてもらった」
ここに来るまで加州がどう過ごしていたのか、兼定は今初めて聞いた。彼もまた兼定の相棒と同様に、長い平和な時代を出番なく空虚に過ごしていた。そんな彼らにとって自分を選んでくれた土方や沖田は何にも代え難い、尊い存在なのだろう。
沖田は戦場にあっては鬼神の如き活躍を見せるが、一方で平素はとても穏やかで心優しい青年だ。屯所の近くに住む子供たちと遊んでやっているため、近所の者たちからも慕われている。加州や大和守のことも、付喪神というよりは、まるで兄弟か何かのように親しみを持って接しているところをよく目にする。
「沖田さんは刀を振るえば誰にも負けない強さを持っている上に、すごく優しい人だ。そんな人に使われるお前は、幸せ者だな」
「うん、本当にね。こんなに素敵な主はそうそういるもんじゃない。……俺だけじゃない、和泉守たちも、みんな恵まれてるよ」
夕日を見上げながら、しみじみと加州は呟く。その微笑む横顔から、沖田に対する彼の信頼の深さが伝わってくる。
「なぁ。せっかく出番をもらったんだからよ、オレもお前も、主たちのために頑張ろうぜ。人間みたいに一緒に刀を振るって戦えねえ分できることは少ないかもしれねえけどよ、きっとオレたちだって役に立てるはずだ」
「お前に言われなくともそのつもりだよ。俺は、沖田くんの力になりたい。そのために俺にできることがあるなら何でもする。そう、決めてる。……まぁ、お前も生まれたての割には頑張ってると思うよ?俺にはまだまだ及ばないけどね」
「ったく、うるせえなぁ……見てろよ、これからお前をあっと驚かせるくれえ成長してやるからな」
「ははっ、冗談だって。……でも、そうだね。ちゃんと見ててやるよ、お前の成長。堀川はなんだかんだお前に甘いところがあるからね、俺が厳しく評価してあげる」
「へいへい、望むところだぜ」
ニヤリと笑って約束を交わすふたりの元に、稽古を終えた主たち、そして付喪神たちがやって来る。こんなとこで何してたんだと聞かれたので、加州と共に何でもないと笑いながら答えた。
心より尊敬する主と、軽口を叩き合えるような頼れる仲間たちがいる。そんな穏やかで優しい日々は、長くは続かなかった。
兼定が土方の元にやって来てから1年が経とうとした頃。新選組は、その名を一気に轟かせることとなる。
元治元年(1864年)6月5日、京都の旅籠・池田屋にて潜伏していた尊皇攘夷派の志士たちを、駆けつけた新選組が奇襲。彼らを捕縛、または斬り捨てて一掃したのだ。御所焼き討ち計画を未然に防いだ、歴史に残る大活躍。しかし、その裏では思いもよらぬ悲劇が起こっていた。
近藤率いる部隊は池田屋で攘夷派と激しい戦闘を繰り広げた。その結果近藤隊の一員として戦った沖田総司の愛刀・加州清光は刀身が折れてしまった。誰の目から見ても、修復できないほどの損傷であることは明らかだ。当然、『モノ』としての役目を終えた加州清光は、付喪神としての生を終え、消失してしまう。もうどこを探しても、彼の気配は微塵も感じられない。
「……っ、どうして、僕は……こんな時に、何もできなかったんだ。……清光っ!」
親友を失った悲しみに、大和守は激しく己の無力を嘆き、体を震わせる。加州と大和守はよく些細なことで喧嘩してはいたものの、喧嘩するほど仲がいいというのはまさに彼らのことを指すのだろうと思うほど、気の合う友人だった。彼らは兼定と国広とは違い、両方とも打刀であるために共に主の腰に差されることはない。どちらか一方だけが、沖田と共に戦場に赴く。それ故に、大和守は加州の最期を見届けることはできなかった。親友のために何もできなかった自分に、行き場のない怒りを向けてしまっているのだろう。
大和守は苦痛に顔を歪めたかと思うと、情動のまま走り出してしまった。すぐに追いかけようとした国広を、長曽祢が制する。
「ここはおれに任せてはくれないだろうか。……なに、付喪神は本体からそう遠く離れることはできないのだ、すぐに大和守と一緒に戻ってくる。この中でおれだけが加州と共に戦ったのだ。加州の分まで、あいつが冷静さを取り戻せるように手助けしてみるさ」
「……分かりました。よろしくお願いします、長曽祢さん」
長曽祢はニコリと頼もしげに笑った後、すぐに大和守が走っていった後を追いかけていった。土方隊は後から駆けつけたため、兼定と国広もまた加州の最期を知らない。共に戦っていた長曽祢には、思うところがあるのだろう。
兼定は、そんなふたりから離れたところで、無惨に破壊された加州だったものをじっと見つめていた。もの言わぬ鉄屑になった、加州。
――どうして。どうして、なんだ。どうして加州が、こんなところで折れなければいけないというのだ。あんなにも沖田を慕い、その力になりたいと強く願っていたのに。こんな道半ばで死んでしまうなど、決して望んではいなかっただろうに。
それに、約束したではないか。兼定の成長を見ていてやると、そう言ったではないか。それなのに、兼定は何もできなかった。加州が折れたという知らせを聞いて駆けつけ、その無惨に壊れた刀身を見つめることしかできなかった。最後の勇姿を見届けることすら、できなかった。戦闘に出ていなかった大和守と何ら変わりやしない。他者に干渉できない付喪神というのは、いざという時にはこんなにも無力な存在だ。友を助けてやることすらできなかったこの身が、恨めしくてたまらない。
気づけば兼定はあまりの衝撃に膝から崩れ落ち、俄に瞳からはポタポタと涙が溢れていた。加州はもうどこにもいない。もう二度と姿を見ることも、話すこともできない。赤い瞳を細めて照れ臭そうに笑う顔を見ることは、この先一生ない。生まれて初めてできた大切な仲間の死という現実を受け入れることができずに、熱い雫が湧き出るのを兼定は止められなかった。絶望が、じわじわと体を蝕んでいく。
その時だった。ぐすぐすと鼻を啜ってはしゃくりあげる兼定を一喝するように、突然、鋭い声がその体を貫いた。
「泣くなっ!」
兼定はその言葉をすぐに受け止めることができなかった。夢なんじゃないかとすら思った。何故なら、うずくまる兼定を真剣な眼差しで見据えているのは、いつもにこにこ笑っていて怒ったところなど誰も見たことがない、相棒だったからだ。彼が自分に大声で叱咤するなど、思ってもみなかったからだ。
「僕たちの主は農民の出だけれど、今は刀を振るい主君のため、民のために命を懸けて戦っている。太平の世ですっかり戦うことを忘れ腑抜けてしまった武士たちよりも、余程武士らしく生きている。彼こそ、まことの侍だ。……だから、その立派な侍に振るわれる刀が、泣くものじゃない」
眉間に皺を寄せて兼定に語りかける国広の青い瞳が、ひどく綺麗なものに見えた。国広だって、悲しいに決まっている。兼定が生まれる前から、国広は加州と友人だったのだ。突然訪れた別れに何とも思っていないはずがない。その証拠に、ぐっと握りしめた拳は小刻みに震えている。それでも、誇り高い侍の愛刀として、涙は流すまいと堪えているのだろう。そんな相棒の心も知らずに、感情のままに泣いてしまったことを、兼定は恥じた。
「……ああ、お前の言う通りだな。済まなかった」
「……ううん、僕こそきつい言い方してごめん。でも、これだけは分かって欲しかったんだ。武士たるもの、軽々しく涙を見せるものじゃない。土方さんも、常々そう言ってる。だから、僕たちも泣くわけにはいかないんだ」
「分かってる。……オレもまだまだだな」
「そんなことないよ。感情が豊かなのは、兼さんのいいところだもの。……きっと、加州くんもそう思っていたと思う」
自分のために泣いてくれてありがとう、と加州は思ってくれただろうか。……いや、そんなタマでもない気がする。むしろ、もしここに加州がいたら「俺のために泣いてくれるのは嬉しいけどさ、大の男が泣くもんじゃないよ」なんて揶揄われてしまうかもしれない。そう思えば、余計に泣いている場合ではなかった。兼定は立ち上がり、涙で濡れた顔をゴシゴシと袖で拭いた。
たとえ加州が見ていなくとも、兼定は彼と交わした約束を決して忘れない。必ずや、約束は果たしてみせる。今日、相棒のお陰で兼定はまた1歩成長できた。主の名に恥じないような刀に、また1つ近づけた。自分はいい相棒を持ったものだと、つくづく思う。
「……なあ、国広。オレと1つ契りを交わさねえか?」
「……契り?」
首を傾げながら不思議そうにこちらを見つめる顔に、言葉を続ける。
「ああ。オレたちはこれから先も、土方さんと共に戦う。当然、この命、主のためなら惜しくはねえ。……だがな、唯一無二の相棒として、オレはお前にもオレの命を預けていいと思う。それくらい、オレは国広のことを信頼してんだ」
「……兼さん」
「この先何があっても、オレたちは相棒だ。オレたちの絆は、たとえどっちかが折れてなくなったとしても、終わりじゃねえ。……オレは、そう信じてる」
目を逸らさずに、揃いの浅葱色の瞳をじっと見つめる。加州だけではない、誰だっていつ折れるかなど分かりやしないのだ。死は突然襲いかかる。だが、死んで全てがなくなるわけではない。加州のことを自分たちが忘れない限り、彼は完全に死んだわけではなく、その心の中で生き続ける。これから先誰かが折れることになろうとも、それは変わらない。特に、この相棒のことは、兼定は絶対に忘れない自信がある。
兼定の真剣な思いが伝わったのか、国広は嬉しそうに微笑んだ後、きゅっと表情を引き締めて頷く。
「うん。僕にとっても、兼さんは大切な相棒だよ。それはこれから先もずっと、変わることはない。だから、たとえどっちかが先にいなくなることがあっても、僕たちはずっとずっと相棒だね」
しばらく互いを見つめた後、腰に差してある自身を模した刀を抜き、その刃を合わせる。付喪神は実体を持たぬはずだが、キン、という音が二人の覚悟を示すように鋭く響いた気がした。
池田屋での活躍により、新選組の武名は轟いた。この時が、新選組の最盛期と言えた。隊士も増え、時には内部でのいざこざもあったが、主たちは懸命にその困難を乗り越えてきた。そして池田屋事件から3年後の1867年、ついに新選組はその活躍から隊士全員が幕臣として認められるまでになった。
――しかし。大政奉還を境に風向きは変わり、新選組の活躍には翳りが見えてきた。長曽祢の主・近藤はかつての仲間に狙撃され肩を負傷し、一時的に戦線を離脱した。大和守の主・沖田は持病の労咳が悪化し、療養を余儀なくされた。
沖田が戦列を離れる日、大和守はどこか寂しそうな顔をしながら兼定たちに別れを告げた。
「僕は、最後まで沖田くんについて行くよ。……新選組の行く先を見届けられないのは残念だけど。どうか僕と沖田くんの分まで戦って欲しいな」
「もちろんだ。戦に勝って、主と共に朗報をお前たちの元に届けてみせるさ。楽しみに待っているといい」
「……うん、ありがとう。皆の吉報を待ってるよ」
そんな悲しい空気を吹き飛ばすように、長曽祢は笑った。……きっと、それは難しいだろう。時代の流れは新政府側にある。それに、沖田の病状は厳しいものとなってきている。生きて再び会う可能性は低い。誰もが心の中でそう思っていただろう。それでも、盟友との別れに湿っぽさは見せたくなかった。兼定と国広も長曽祢に倣い、笑顔で沖田と大和守を見送った。少しでも、彼らが穏やかな時を過ごせることを願いながら。
それから時を置かずして、近藤と長曽祢とも別れの時がやってくる。幕府へ忠誠を誓った新選組は今や賊軍と呼ばれ蔑まれることとなり、西洋式の最新兵器を備えた新政府軍に連戦連敗してしまう。慶応4年(1868年)、鳥羽・伏見の戦いで敗れ、江戸に戻り甲陽鎮撫隊と名前が変わった新鮮組は甲府へと向かうも、甲府はすでに新政府軍により制圧されていた。その後甲州勝沼の戦いに敗れ、流山で新政府軍に包囲されてしまい、近藤は味方を逃すために敵軍へ投降することとなった。当然、長曽祢もそれに付き従う。
「なに、そんなに悲しそうな顔をするんじゃない」
「だってよぉ、長曽祢さん……投降するなんて、いくらなんでも無茶じゃねえか」
「いや、近藤さんは『大久保大和』として出頭するのだ、まだ死ぬと決まったわけではないさ。……それに、お前たちの主が助命の嘆願をすると言ってくれているしな。だから、おれと主のいない間、新選組のことは頼んだぞ」
「……ああ、土方さんは近藤さんを絶対見捨てたりしねえ。だから……またな、長曽祢さん」
「任せてください、長曽祢さん。……近藤さんのこと、よろしくお願いします」
「ありがとう。お前たちに武運があることを祈っているぞ。……では、またな」
大和守たちとの別れの時と同様に、兼定たちは明るく努めた。……たとえ変名を名乗ろうとも、新政府軍の中に近藤の顔を知っている者がいれば、命はないだろう。そしてその可能性は、決して低くはない。それが分かっていても、希望を持たなければ心が持ちそうもないのだ。
けれども、そんなか細い希望は脆くも崩れ去った。土方は懸命に近藤の助命を嘆願したが聞き入れられることはなく、危惧した通りその正体が露呈した近藤は処刑場の露と消えた。享年、35。長曽祢がその後どうなったのかは、分からない。
「……ついに、オレたちふたりだけになっちまったな」
「……そうだね」
仲間と共に陣を敷き休んでいる土方から少し離れたところで、ふたりは共に地面に腰掛けた。長曽祢、加州、大和守。5人いたはずの付喪神は、気づけば兼定と国広だけになっていた。賑やかだったはずの新選組は、1人、また1人と数を減らしてどんどん静かになっていってしまった。その静けさが、ふたりに仲間を失った悲しみを容赦なく突きつけているように感じられる。
「……オレは、折れたくねえな。どんなことがあっても、今は土方さんの元を離れたくねえ」
「それは僕も同じだよ。土方さんが背負うものはどんどん増えていく。だから、僕たちがいなくなるわけにはいかない」
「ああ。近藤さんも沖田さんもいない今、土方さんがその意志を継いで新選組を導かなきゃならなくなった。それはきっと重責だろうな。せめてオレたちには、その重荷を下ろして何でも話してもらいてえ。それくらいしか、できねえけどよ」
「ううん、それだけだって、きっと土方さんは喜んでくれるはずだよ。旧友がいない今、気軽に本音を吐ける僕たちの存在は軽くないと思うよ」
それは、自分に言い聞かせるようだった。膝を抱える国広の指は、きつく皺ができるほど強く衣を握りしめている。土方の役に立ちたいと思いながらも、人間のようにはいかない自分に歯痒さを感じているのだろう。それは兼定とて同じだ。今ほど自分が人間であれば、実体を持って共に戦えればと思ったことはない。
けれど、できないことを嘆いても仕方ないのだ。時は待ってはくれない。兼定たちには、自分にできることをするより他に選択肢などない。
「そうだな。それに、戦闘中は土方さんの目の届かないところをオレたちが補える。これから戦いは激しくなるだろうからな、気を抜くなよ」
「うん、兼さんの言う通りだね。僕たちでしっかり土方さんを補助しよう。土方さんと兼さん、それに僕が組めばきっと大丈夫だよ」
顔を見合わせて、無理やりにでもふたりは笑った。自分たちはまだやれる。近藤と沖田の分まで戦う土方を、支えてみせる。そう、兼定と国広は信じていた。
しかし、残酷な現実は、容赦なく兼定と国広の主・土方にも襲いかかった。近藤がいなくなった新選組を指揮した土方は、宇都宮城の戦いに勝利し、宇都宮城を一時陥落した。そんな戦いの中だった。
兼定は土方の右後方、国広は左後方を注意する布陣を決めて戦うことで、敵の攻撃をすぐに察知できるようにしていた。だからこそ今まで土方は大きな怪我なく戦ってこれた。
今回も、敵の銃兵隊が接近してきたのを兼定はいち早く察知して土方へと伝えた。その言葉を受けて土方はすぐに退こうと動き出したのだが、そんな動きを見た敵兵はすぐさま銃撃を開始した。轟音が鳴り響く。何挺もの銃による射撃は嵐のように土方に襲い掛かり、避けきれずにそのうちの一つが足に命中してしまう。倒れそうになった土方を、幸いすぐに味方の兵士が駆けつけて肩を貸し退却することができたため、彼の命に別状はなかった。
だが、土方は足を負傷してしまったことで戦線離脱を余儀なくされ、会津へと護送され3ヶ月もの間療養生活を送ることとなってしまった。戦うことができない時間は、じわじわと真綿で首を絞めるように彼を苦しめた。
主と共に戦うと誓いながら、近代兵器になす術もなく敗北してしまった。刀同士での戦いであれば、決して負けはしないというのに。兼定は、己の無力さに打ちひしがれた。銃や大砲といった最新兵器を前にしてしまえば、自分はなんとちっぽけで役に立たない存在なのだろうか、と。国広は、そんな塞ぎ込む兼定や主のことをずっと励まし続けてくれた。銃は無限には撃てないため弾が尽きれば自分たちの出番も来るだろうし、今回のことが教訓になったから次こそは負けない、と。一体その言葉ににどれほど心が救われたか。
だから、兼定は信じられなかった。兼定の心も落ち着きを取り戻し、土方の怪我も治り、援軍を求めるため庄内藩(現在の山形県)に出立しようかと言う頃。兼定とふたりきりの部屋で、国広は珍しく浮かない顔をしていた。どうしたのかと声をかける前に、国広は虚な目をしてつとつとと語り始めた。
「……きっと、土方さんは最後まで幕府への忠義を貫き通すだろうね。それが近藤さんの遺志でもあるから。でも、僕は思う。きっと援軍要請は失敗する。こんな新政府軍が圧倒的優位な状況で、今更僕たち『賊軍』に味方してくれるはずがない。戦況は悪くなる一方さ」
「何だよ、んな後ろ向きな考え方すんのやめろよ」
言葉にしてしまえば、それが現実になってしまう気がして、兼定はやめさせようとする。しかし、そんな兼定の言葉など聞こえていないかのように国広は続ける。
「……だからね、土方さんは必ず、この先の戦いで命を落とすよ。近藤さんが死んだ時点で、きっとそれを覚悟しているだろうから。それにね、もう時代の流れは完全に向こうにある。それに抗うことなんて、ちっぽけな人間にはできやしないさ。土方さんがどんなに頑張ったところで、もう、流れは変えられない。……そして、土方さんと共に、僕たちもまた前時代の遺物として葬られていくんだ」
「……おい、国広。てめえ、急に何言い出しやがる」
虚空を見つめながら語る相棒はまるで、土方が死に、自分たちがいなくなってしまう未来を見通しているかのようで。兼定には、到底受け入れ難いものだった。未来なんて、まだどうなるか分からないだろう、と。
「だってそうでしょう?ずっと昔、人間は青銅の武器で戦っていた。でも、鉄器が発明され広く伝わると、あっという間に取って代わられた。……それと同じさ。僕たちは、銃や大砲によって、活躍の場を奪われたんだよ。運が良ければ生き残って美術品となるかもしれないけど、激しい戦いの中で消耗してきた僕たちがそうなるのは難しいだろうね。……こんなことなら、たとえ蔵の中であっても生き永らえる方がずっと良かったな。僕の命は、そう遠くないうちに土方さんと共に終わるんだろうから」
自嘲するように吐き捨られた言葉は、兼定の心に怒りの炎を燃え上がらせた。
(……何だって?今、こいつは何をほざいたんだ?)
沸々と胸の内が煮えたぎるように熱くなっていく。
「てめえふざけんじゃねえぞ!……生きてる時間の長さなんざ、問題じゃねえだろうが。土方さんは、どんなに贋作だと蔑まれようと、お前をずっと大切に使い続けてくれたじゃねえか。それなのに、てめえは土方さんの元に来なきゃ良かったって、本気でそう思ってんのか?土方さんのオレやお前に対する信頼を、何だと思ってやがる!蔵や床の間に飾られる何百年より、たとえ数年でも信頼できる主に振るわれて戦う方が、ずっとずっと、生きてるって言えるじゃねえか!」
顔を真っ赤にさせながら、兼定は息を切らせて必死で反論した。相棒のふざけた考えを変えたくて。きっと彼はこの辛い状況に一時的にまいっているだけなんだと、信じたくて。
けれど、返ってきた言葉は兼定の想像を遥かに上回る冷たいものだった。
「兼さんは、生まれてからすぐに活躍する機会をもらえた。そんなあなたには、僕の気持ちなんて分からないだろうね。……僕たちは、道具なんだ。たかだか50年かそこいらで死ぬ人間なんかと違って、何百年と長い時間を生きられる。けどね、死ねばそこで終わりさ。その先には何もない。生きていればこそ、なんだよ。他人の死は所詮他人事だけど、自分が死ぬってのはこの世の全てが終わることを意味しているんだ。だから、自分が生き抜くことが1番大事なんだよ。……僕は、加州くんみたいな最期はごめんだね」
「てめえ、主や仲間を侮辱する気かよ」
「そんなつもりはないよ。でも、そういう風に聞こえたのなら、心のどこかでそう思っているのかもね」
兼定を見つめる瞳は、いつものような明るさや快活さは微塵もなく。ただただ、この世に対する絶望によって冷えきった、血の通っていないものだった。
「……今口にしたこと全部、本心からそう思ってるのか?」
「もちろんだよ。こんな時に嘘ついたってしょうがないでしょ?」
憐れむような瞳が、兼定に向けられる。国広の冷徹な表情など、見たくなかった。国広には、笑顔が1番よく似合っていたというのに。
これ以上、この冷たい空気を纏った奴と論じたくない。いや、論じても無駄だろう。こいつは仲間や主よりも、自分の命の方が大事なんだ。兼定とは根本的に、考えが違うのだ。
「……そうかよ。勝手にしろ。オレはお前のこと、相棒として尊敬していた。誰よりも頼りになる相棒だと思っていた。……だが、それも今日限りみてえだな。土方さんのために命を懸けて戦うって、たとえどんなことがあろうとずっと大切な相棒だって、そう誓った日のお前は、もうどこにもいねえんだな。今のてめえには、オレの命を預けたいなんざ微塵も思わねえよ。……悪いが、もう、相棒とも思えねえ」
絞り出すように、何とか言葉を紡ぐ。自分で発した言葉だというのに、兼定が1番傷ついている。国広は、大切な相棒、なのに。誰よりも頼もしい味方だった、はずなのに。次々と仲間たちがいなくなってしまった中で、自分を支えてくれる唯一の存在だというのに。どうしてそれすらも、己から奪ってしまうんだ。付喪神という精霊でありながらも、神様とやらがいるのだとしたら、恨まずにはいられなかった。
兼定から決別の言葉を告げられた国広は、一瞬だけ寂しそうな顔を見せたが、すぐに能面のような表情に戻ると、「……そう」と何でもないことのように言い放った。こうなってしまったことに悲しんでいるのは自分だけなのかと、兼定は余計に虚しくなった。すっかり変わってしまった国広と同じ空間にいることが辛くて、無言でその場を後にした。
それから、兼定と国広の仲は他人も同然のようになった。土方の前では最低限必要なことを話す時はあれど、私的な会話はほとんど一切しなくなった。正直に言うと、あれは気の迷いだったんだ、弱音を吐いてしまった、と国広が弁明してくることを兼定は期待していた。それほどまでに兼定はこの相棒のことを信頼していたし、あんな身勝手な言葉が本心ではないと信じたかった。だが、その機会は終ぞ訪れはしなかった。あれ以来国広は兼定が主に励ましの言葉を掛けるのをいつだって冷めた瞳で見つめていたし、その表情は「気休めはよしなよ」とでも言いたげだった。
国広の言った通り、戦況は日に日に悪化していった。庄内藩はすでに新政府軍に恭順の意を示しており、土方たちは入城することすら許されなかった。土方率いる新選組の生き残りは、次なる地を仙台と定めて向かう。そこで榎本武揚が率いる旧幕府海軍と合流し、一行は一路蝦夷地へと渡った。
北へ北へと追いやられる中、それでも兼定は希望を捨てていなかった。かつて武家政権を樹立した源頼朝公は、決起した当初は負け続きだった。それでも、諦めずに味方を集めて平家を倒し武家の惣領へと上り詰めた。江戸幕府を開いた徳川家康公だって、幼い頃から何度も命の危機に晒されながらも、最終的に武士の頂点まで辿り着いたのだ。自分たちにそういった武運が訪れないとは限らないじゃないか。
しかし、そんな兼定の希望が細々に打ち砕かれる出来事が、その先で待ち受けていた。
蝦夷地に辿り着いた一行は、松前城を陥落させて五稜郭に本陣を置いた。そこで『蝦夷共和国』が成立し、城の防備に当たるも、翌1869年3月には新政府軍襲来の報が入る。そこから先は、連戦連敗だった。土方は何とか生還したが多数の死傷者が出て、兵士たちの士気は下がる一方だった。
そんな絶望的な状況の中。土方は小姓の市村鉄之助を呼びつけ、命令を下した。遺髪と写真、そして愛刀・和泉守兼定を渡し、「これを日野の家族の元に届けてほしい」と、ただ一言。その言葉が現実のものとは思えずに兼定が衝撃を受ける中、鉄之助が答える。
「土方先生、私は討ち死にする覚悟でこの地にやって参りました。……どうか、そのお役目は誰か他の者に命じてください」
瞳を滲ませて拒否する鉄之助だったが、土方は厳しく一喝する。
「それはできない。……断るとあらば、この場で打ち果たすぞ」
土方は、まだ若く将来有望な鉄之助を死なせたくはないのだろう。鋭い眼光と確固たる意志に、鉄之助は全てを察して首を縦に振る。しかし、そうはさせないと兼定は必死に声を上げた。
「ちょっと待ってくれよ、土方さん……オレは絶対に嫌だぜ!たとえこの先に待ち受けているのが悲劇だったとしてもよ、オレは最後まであんたと共にありたいんだ!……それが、刀としての本分ってやつなんだよ」
兼定は、真っ直ぐに土方の瞳を見つめて懇願した。どうか自分の気持ちを分かってほしいと、その一心で。長曽祢も加州も大和守も皆、最後まで主と共にあったのだ。自分とて、そうありたい。しかし、土方は黙って首を横に振る。
「駄目だ。……悪いが、俺はお前の持ち主だ。俺が決めたことには従ってもらう。反論は許さねえぞ」
「どうしてだよ土方さん、どうしてオレだけ置いていくんだよ!?」
「お前はこの俺の誇りだ。武士としての魂だ。どうかそれを、後世に伝えてほしい。俺の代わりに、な」
腕を組んで仁王立ちする彼が、とてつも無く大きな存在に思えてならない。兼定がどんなに足掻いたってその意志が変わることなどない、とでもいうかのように。
思わず、お前からも何とか言ってくれよと国広に顔を向けてしまった。しかし、あの日の決別以来ここ何ヶ月も碌に口を聞いていない彼が、兼定の味方をするはずもなかった。もう相棒とも思っていないのだから我関せずとでも言いたげに、そっと視線を逸らされてしまう。
そうこうしているうちに、兼定の本体は小姓の手に渡り、本陣を後にする。去りゆく背中に向かって、ポツリと「お達者で、兼さん」と声をかける国広に、兼定は答えることができなかった。
今口を開けば、出てくるのは情けない言葉ばかりだろう。どうして、お前だけが残ることを許されたんだ。お前の方が生き残りたいと思っているはずなのに。オレはたとえ刀身が折れて死ぬことになったとしても、土方さんと共に行きたいのに。別れの時に、そんなみっともない嫉妬心を口にしたくはなかった。
土方と国広の姿を見れば泣いてしまいそうだと思い、兼定は俯きながら彼らと別れた。だから、その震えながら必死に涙を堪える哀れな背中を、姿が見えなくなるまでずっと温かな視線が見守っていたことを、兼定は知らない。
それが、兼定とふたりの今生の別れとなった。土方は函館の地で戦死し、国広は行方知れず。国広だけはいつか戻ってくるのではないかとも思ったが、その日は訪れなかった。きっと、土方の亡骸と共に永遠の眠りに就いたのだろう。……たとえ、本人がそれを望んでいなかったとしても。美術品として残りたいと願った彼が消え、その考えに激昂した兼定がこうして生き残り文化財として認められたとは、皮肉なものである。
***
兼定が主と友との懐かしい思い出を噛み締める中、気づけば部屋に土方家の家人が十歳くらいになる少年を連れて入ってきていた。現在の当主である彼は、兼定の本体を見つめながら少年に土方のことを語る。その話の中に出てきた話題に、兼定は思わずどきりとしてしまった。
「兼定が文化財として認められて本当によかったね。歳三さんも安心しているかな。……でも、なんで歳三さんは堀川国広の脇差は実家に戻さなかったんだろうね?贋作かもしれないけどさ、もしかしたら、本物かもしれないでしょ?」
不思議そうに首を傾げて問いかける少年に、家長は微笑みながら答えた。
「そうだね。それを話すにはまず知っておかなければいけないことがある。残念ながら、刀を使わないお前にも私にも見えないがね、道具には付喪神と呼ばれる精霊が宿っていることがあるのだ。そして土方歳三の愛刀・和泉守兼定と堀川国広の2振には、その付喪神がついていたのさ。歳三は彼らを認識して、意志を疎通することさえできたという。それほどまでに、彼らは深い信頼関係で結ばれていたんだよ」
「付喪神……じゃあ、見えないけど今ここにも兼定がいるってこと?」
「ああ、そうだね。もしかしたら、私たちの会話を聞いているかもしれないね」
まさに今その言葉通り彼らの話を聞いているものだから、思わず微笑んでしまう。土方は、自分たちのことを手紙に残してくれていたのだろう。主の子孫にまでその存在を認めてもらえていることに、兼定は心の中が温かくなるのを感じた。
「おっと、前置きが長くなってしまった。堀川国広がなぜ帰ってこなかったのか、という質問だったね。それは、歳三が小姓に託した遺書の中に記載があった。先の戦災で文書自体は焼かれて失われてしまったのだが、私は父から教えられた内容を今でもしっかりと覚えている。……堀川国広は、心を持つモノ・付喪神だ。そして彼は、まさしく今こうして兼定が文化財となったように、兼定に生き残って歳三の刀としてその活躍を後の世まで伝える役割を担って欲しいと願った。兼定は、会津藩主の容保公より賜った、まさに歳三の武士の誇りを表す刀だからね。だから、歳三に自分が最期までお供をするから、兼定は遺品として故郷へと返してくれないかと願い出たのだ。歳三もおそらく同じことを考えていたのだろう、その申し出を了承した」
「……そっか。ふたりいるから、兼定に生き残って歴史を伝えてもらって、国広は最後まで歳三さんと一緒に戦う道を選んだんだね」
「ああ。そして、国広は一つの行動に出たんだ。兼定から徹底的に嫌われるように、別れる前にわざと彼を怒らせて大喧嘩をしたのさ」
ピクリ、と兼定の動きが止まる。その予想していなかった言葉に、思わず呼吸すらも止めてしまいそうになった。
(何だって……?あの時国広は、わざとオレを怒らせるような身勝手な言葉を口にした、とでも言うのか)
「……えっ?何でお別れしちゃうのが分かっているのに、わざわざそんな悲しいことをしないといけないの?国広にとって、兼定は一緒に戦ってきた大切な仲間なんでしょ?」
寂しそうな目をして問いかける少年。その答えは、まさしく兼定も聞きたかったことだ。もしあれが意図的に放った言葉だというのなら、なぜ国広はわざわざ自分を怒らせ、嫌われるようなことをする必要があったのか、と。
「国広は、兼定のことを誰より理解していたのさ。兼定も最期まで歳三に付き添いたいと願い出ることや、もし国広だけが死にゆく歳三と運命を共にすれば、後々まで悲しみ、心に傷を負うことを。国広に全てを押し付けて自分だけがおめおめと生き残ってしまったと、深い後悔の念に苛まれるだろうことを。きっと自分は兼定の元に帰ることはできない。だから、国広はわざと心にもないことを口にして兼定を怒らせた。自分のことを見下げた、同情するに値しないやつだと思われることで、せめてひとり残される兼定の心を救おうとしたのだ」
兼定は、その言葉を信じられなかった。あの決別から別れの日までの数ヶ月間、国広は自分の考えを改めることはしなかった。だからこそ兼定も彼が本当に変わってしまったのだと酷く落胆したのだ。……しかし、思い返してみれば。国広は兼定に負けないほど、土方を慕っていた。太平の世で長いこと使われずにしまわれていた自分に、活躍の場を与えてくれた。そんな土方には言葉にできないほど深く感謝している。だから、刀身が折れるなり朽ちるなりするその時まで、必ず主に尽くすのだと、そう在りし日に語っていた。
そんな国広が、形勢が悪くなったからといってあんな風に翻意するだろうか。たとえ名刀ではなくとも、主の名に恥じない働きをすればそれでいい。誇らしげに話したあの日の国広の言葉は、決して嘘などではなかったはずだ。
国広は感情がすぐに表に出てしまう兼定とは違って、にこにこと笑いながらも自分の気持ちを隠すのに長けていた。いつだったか、こんなことを口にしていた。
「僕の分まで兼さんが思い切り泣いたり、笑ったり、怒ったりしてくれる。それだけで僕は充分だよ。兼さんは僕の光だ。そして僕は、そんな兼さんを支える影でありたい」
その時は、大袈裟だなと笑って返事をしたくらいで、大して気に留めていなかった。だが、今思えばそれこそが国広の決意だったのかもしれない。たとえどんなことがあろうと兼定を、大事な相棒を支えてみせるという、彼の。
……だとしたら。家長が話していることは、全て。
「……そっか。でも、寂しいね。もし本当にそうだとしたら、国広は兼定に誤解されたまま、消えちゃったのかな」
眉を下げて同情する少年に、家長は微笑みながら肩を叩く。
「そうかもしれない。……だから、今日のこのハレの日に、もし兼定がこの話をどこかで聞いてくれていれば、と思ってね。なあ、兼定。国広の本心は、君もきっと分かっているはずだ。国広にとって君は、自分の全てを投げ打ってでも、己の命に代えても守りたい、大切な相棒だったのだ。どうかそのことだけは、忘れないでいてあげて欲しい」
そう、家長は兼定の本体に向けて優しげに話しかける。兼定のことは見えていないはずなのに、視線が重なった気がした。しばらく見つめたかと思うと、そろそろ夕飯の時間だよと少年を連れて、彼はゆっくりと部屋を後にした。
すっかり暗くなった部屋に残されたのは、誰からも姿の見えなくなった付喪神のみ。
自分は、何という思い違いをしていたのだろう。どんなことがあろうともずっと唯一無二の相棒だと、彼と契りを交わしたというのに。国広がどれほど素晴らしい心の持ち主だったか、たった数年の間ではあったけれど、知り抜いていたというのに。
国広は、ただひとりの相棒に嫌われて、もう相棒とは思えないとまで言われて。それでもたったひとりでその相棒の心を守り、主を最期の瞬間まで支えたのだ。
なぜだ、国広――と、兼定は問う。どうして、オレに何も話してくれなかったのだ、と。
その時、兼定の心にたった一度だけ国広に叱られた日のことが浮かび上がった。人の一生より長い時間が過ぎた今でも、まるで昨日のことのように、鮮明な記憶。
折れてもの言わぬ加州の刀身を前にして泣き崩れる自分に、泣くなと怒鳴る相棒。まことの侍の刀が泣くものではない。あの時もまた、兼定は国広に心を救われたのだ。大切な仲間を失い崩れ落ちそうになる兼定を、国広の一言が支えてくれた。
いや、それだけではない。国広の言葉は、その後の兼定を支え続けてくれた。彼の言葉があったからこそ、これまでのひとり寂しく過ごした悲しみの日々にも心折ることなく生きてこられたのだ。今日に至るまで主の誇りを守り抜いてこられたのも、国広なくしては難しかっただろう。
あの日以来、どれ程苦しいことがあっても、兼定は一度たりとも泣いたことはない。大和守や長曽祢と別れた時も、近藤や沖田の悲報を聞いた時も、戦いの中で仲間が死んでいくのを見届けた時も。そして、土方と国広と別れ、その訃報を耳にした時も。それが、在りし日に国広と交わした約束だったから。
国広、と思わず叫ばずにはいられなかった。その声は静かな部屋に響き渡る。もう一度、国広の名を声を大にして叫んだ。当然、返事はない。彼の相棒は、もうこの世のどこを探してもいないのだから。
目の前の畳が霞むように滲む。あっと思った時には、両の瞳から涙が溢れて出ていた。止めようとしたけれど、無理だった。涙は川のように勢いよく流れては、頬を伝って畳にシミを作る前に消えてゆく。崩れるように俯いて、一人嗚咽する兼定。両手で畳のい草を掻きむしるようにしながら、ただただ己のたったひとりの相棒を想って泣いた。
これより数百年の後、審神者の奇跡の力により再び相棒とあいまみえることを、彼はまだ知らない。