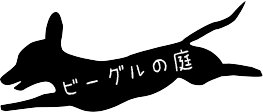「……なるほど、脇差はあなたになりましたか。よろしくお願いします、堀川国広。どうか末長い付き合いになることを願います」
どこまでも続く暗い闇の中を漂っていたはずが、気がつけば明るい光に包まれて吸い寄せられて行った。瞳を開けば、そこには見知らぬ人間がいた。真剣な瞳で自分を見つめる女性は、眉一つ動かさないまま淡々と挨拶をしてくる。
「あ……えっと、初めまして。……あなたは、僕の新しい持ち主、ということになるのでしょうか?でも、僕は消えてしまったはずなのに……それに、ここは?」
いつの間にかこの場所に立っていたため分からないことだらけで、思わず質問ばかり浴びせてしまう。女性は少しだけ黙って考えた後、襖の向こうに声をかけた。
「加州、そこにいますね。彼に説明をお願いします。顔見知りのあなたがした方がいいでしょう」
すぐに、襖の向こうに影が浮かび上がり、「入りまーす」という声と共に戸が開く。そこに立っていたのは、黒いくせっ毛を肩で束ねて垂らし、シャツとベストに黒いズボンという、少し自分の主だった男と似た服装をした男だった。切れ長の鋭い猫のような赤い瞳に見つめられて、不思議と目が離せなくなった。
「では、後は頼みます」
加州をちらりと見て、女性はすぐに部屋から立ち去ってしまった。残されたのは、堀川と加州と呼ばれた青年だけだ。
「ふーん、お前が堀川国広ね。鬼の副長の刀だからもっと厳つい見た目かと思ったけど、全然そんなことないじゃん。ま、俺はそっちの方がいいと思うけど」
顎に手を当てながら堀川の全身をジロジロと見回した後、感心したように呟く。急に現れた彼ではあったが、自分の前の持ち主を知っていることと、女性に呼ばれた名前ですぐにその正体に見当がついた。
「君は……沖田さんが使っていた、加州清光?」
「そういうこと。こうして審神者の力で人の身を得た姿ってわけ。お前もね、堀川」
「審神者って、さっきの女の人のことですか?それに、ここは一体……」
「まあ、そうなるよね。安心して、一から説明するからさ」
その言葉を皮切りに、加州は自分たちが置かれている状況について説明してくれた。今は西暦二二〇五年、そしてここは本丸と呼ばれる拠点で、審神者と呼ばれる主と彼女の力によって顕現した刀の付喪神・刀剣男士たちが暮らしている。その目的は、歴史の改変を目論む時間遡行軍と呼ばれる敵と戦い、歴史を守ること。刀剣男士は、刀に籠った人の想いやその刀自身の逸話を元に生まれ、遡行軍と戦うためにここに存在することを許されている。
俄かには信じがたい話ではあるが、歴史の中で折れてしまった彼や、箱館戦争の末に主が敗死し、その亡骸と共に消えて行った自分がこうして人の身を得ていることが、何よりもその話が現実であると証明している。
「今この本丸にいるのは俺と堀川を含めて十二人の刀剣男士と、主。一度に出陣できるのは六人までだから、その時々でメンバーは変わるけど、堀川は唯一の脇差だからね。きっとすぐに出番は来ると思うよ」
「ありがとう、大分状況が理解できました。……ここには、その。他に新撰組で使われていた刀はいるんですか?」
「ううん、俺と堀川だけだよ」
「そうですか……」
自分は、新選組副長・土方歳三によって振るわれた刀だ。そして、その隣にはいつももう一振りの刀がいた。……和泉守兼定。上覧試合の折に会津藩主より賜った、土方歳三自慢の一振り。堀川と違って後の世まで残ったはずの彼がいるのではないかと思ったが、どうやら彼はまだ呼び出されていないようだ。黙り込んでしまった堀川を気遣ってか、加州が肩に手を置いて声をかけてくる。
「まっ、最初は不安なことも色々あるだろうけど、なんかあったら言ってよ。出陣も、はじめのうちは俺が一緒に出陣するように主に言っておくからさ」
「ありがとう、加州さん。そう言ってもらえると心強いです」
「あー、ダメダメ。加州さんとか、そういう堅苦しいのいらないから。一応昔馴染みってことなんだから、もっとフランクな呼び方でいいよ」
「ふ、ふらんく……?」
「あ、そっか。えーっと、もっと気軽な呼び方でいいよってこと。加州でも清光でも、なんでもいいから。刀剣男士同士に上も下もないんだからさ、『さん』も敬語もいらないよ」
「そっか……じゃあ、清光くんって呼んでもいいかな?」
「もちろん。改めてここでもよろしくね、堀川」
手を出されたので、何だろうかと思って自分のそれを伸ばしてみると、ぎゅっと握られる。これが一種の挨拶なんだよ、と言われて、少しだけ自分がこの本丸の刀剣男士の仲間入りができたんだという実感が湧いてきた。
それから、二週間後。日課の演練への参加を終えて、本丸の廊下を歩きながら、堀川は前を歩く清光に話しかけた。
「ねえ、清光くん。この本丸って、あまり刀剣男士が多くないけど、何か理由があるのかな」
「え?」
「演練相手の人たちと対戦した後に少しだけ話すことがあるんだけどさ、刀剣男士が五十人以上いたりとか、そういう本丸ってたくさんあるみたいだから。僕らのところだけやけに人数が少ない気がして」
「……ああ、そういうことね」
意味ありげに目を伏せた清光は、共用の休憩場所となっている部屋に堀川を連れて行った。その表情がどこか浮かないような気がして、まずいことを聞いてしまったのかと堀川は内心焦った。しかし、やっぱりいいやと口にするよりも先に、清光が口を開く。
「そーね、お前もそろそろ気づく頃かと思ってたけど……今、この本丸にいるのは、お前のすぐ後に顕現された四人を入れて十六人。それ以上は増えていないよね。実を言うと、増えない、というより増やせないんだ」
「どういうこと?他の本丸はもっと大勢の刀剣男士がいるのに」
「本丸の規模っていうのはね、その本丸の主である審神者の持つ霊力に比例するんだよ。うちの本丸の主は霊力が少なくて、顕現できる刀剣男士の数も今の人数で精一杯なの。審神者になる最低限の霊力基準を満たしていないらしいからね」
そこで堀川は、顕現した時に脇差はあなたになりましたか、と主が言っていたのを思い出した。あれは、少ない霊力故に脇差という刀種の中で呼び出すのを一人と決めていて、その中でたまたま堀川が鍛刀されたからだったのだろう。
「そうだったんだ。でも、だったらなんで主さんは審神者になれたの?」
「主のお父さんがね、審神者だったらしい。……すごく優秀な人で、政府から表彰を受けるくらい成果をあげていたんだって。そんな大活躍をしていたもんだから、時間遡行軍に目をつけられてね。密かに本丸の場所を補足されて、お祝いの席かなんかで刀剣たちが油断している時に襲撃されて、殺されちゃったんだってさ」
「えっ……」
「うちの主が刀剣男士と最低限の関わりしか持たないのも、それが理由。お父さんの本丸は和気藹々としていたらしいんだけど、それが遡行軍に付け入る隙を与えたんだって思ってるみたい」
「……悲しいね。戦争だからそういうことが起こっても仕方ないってことは、分かってるけど」
「まあね。主はお父さんの分も時間遡行軍と戦いたいって思ったから、政府に働きかけて何とか特別に少数精鋭の本丸を築くことを許可してもらったってわけ」
主はいつも冷静で、淡々と自分たちに指示を出しているけれど、その心の中で父親を殺された悔しさと闘っているのだろう。喜怒哀楽をほとんど表さないから少しとっつきにくさを感じていたが、主にも胸に秘めた思いがある。こうして顕現したからには、何とかしてその力になりたいと思う。
「ありがとう、主さんのこと少し理解できた気がするよ。……でも、清光くんは寂しくないの?」
「はあ?何でそうなるのさ」
「だって、これ以上刀剣男士が増えることはないんでしょ?前に顕現可能な刀剣男士の一覧を見たときに、安定くんもいたから」
「べっつにー、あいつが来てもなんか喧嘩とかしそうな気がするからいいよ」
「そうかなぁ」
「そーなの」
その口ぶりとは裏腹に、どことなく寂しい雰囲気を纏っているのは気のせいだろうか。会える手段がないわけでないが、会うことはできない。それが却って、絶対に会えないと決まっているよりももどかしい状況なように思えてならなかった。
それからさらに時が経ち、堀川が顕現してからひと月が経とうかという頃。本丸での生活にも慣れ、出陣や内番、遠征がない時は、堀川は率先して本丸の掃除や洗濯などを行うようにしていた。やることがなくなると、途端に余計なことを考えてしまうから。
清光が説明してくれた通り、あれから新しい刀剣男士が増えることは全くない。ということは、すでにこの本丸にいないかつての相棒・和泉守兼定が本丸に現れることはない。
土方歳三の所持していたとされる堀川国広は、本当に堀川物だったのかどうかも分からない刀だ。真贋不明の自分は、兼定と共に土方に振るわれていた、ということだけが己を形づくる逸話なのだ。なのに、この本丸には兼定がいない。ならば、こんなにもあやふやな自分に存在価値などあるのだろうか。顕現可能な脇差の一覧に記載されていた脇差たちは、どれも名だたる名刀ばかりだ。きっと自分なんかより余程役に立ってくれることだろう。
そんな後ろ向きな気持ちが、気がつけば頭の中を支配する。夜に床につけば、不安で眠れないこともある。堀川自身もそんなことを考える自分が嫌になるのだけれど、どうしたって振り払うことができない。なるべく考えることができないように何かと仕事に手をつけるのが精一杯だった。
取り憑かれたかのように暇な時間を作らないようにする堀川の様子を見ていた清光は、ある日内番を終えて本丸へと帰る道すがら話を切り出した。
「堀川ってさ、いつも働いてばっかじゃん?俺、主に頼んで万屋に行く許可もらってきたからさ、この後行こうよ」
「万屋?……ああ、そういえばたまに買い物に行ってる人がいるね。でも、僕は特に欲しい物もないし」
「行ってみないと分かんないよ?せっかく働いてお給料ももらってるんだからさ、何か好きなもの買いなよ。俺も一緒に着いてくからさ。決まりね」
やや強引に約束を取り付けられてしまえば、嫌だとも言えない。まあ別に自分が何か買わずとも、清光が買い物を楽しんでいるのを横で見ていればいいか、と思い堀川は「分かったよ」と頷いた。
「あっ、この小物可愛いね。部屋に飾ろうかな〜、いや、でもあっちの棚にあったのも捨て難いし……ねえ、堀川。どっちがいいと思う?」
「うーん、そうだね。どっちも可愛いと思うけど、こっちの方が清光くんのお部屋の雰囲気に合ってるんじゃないかな?」
「あっ、確かに!いいことゆーじゃん、ありがと。じゃあこっちにしよっと。……ところで、堀川は買うもん決まったの?」
「それがね、色々見てはみたものの、何も思いつかなくてさ」
「え〜、人にはちゃんとアドバイスできるのに、堀川は自分のこととなるとさっぱりだよね。でもせっかく来たんだから、何か一つは買いなよ。俺がお会計してここに戻ってくるまでに、買うもん決めること。いいね?」
「えっ、急にそんなこと言われても」
「ダメダメ、こうでもしないと堀川は何も買わないだろうからね。じゃ、俺行ってくるから、ちゃんと決めなよ?」
悪戯っぽく笑った清光は、すたすたとご機嫌そうに会計の方へ歩いて行ってしまった。それとは対照的に、堀川はうんうんと唸るばかりだ。軽く三十分くらいは色々な商品を見てまわったが、これと言って欲しいなと思ったものはない。適当に何か選んで買ってしまおうかとも思うが、あまりに理由なく選んだら、清光のことだからそれを見透かして指摘されてしまいそうだ。それではせっかく連れてきてくれた清光の好意を踏み躙ってしまうようで、気が進まない。
どうしたものかと途方に暮れるが、そこで堀川は考え方を変えることにした。自分の欲しい物が思いつかないなら、人の欲しいものを買えばいいではないか。幸い、それはすぐに思い当たった。堀川は清光が気になる商品を探しているのを横で見ていたが、特に熱心に見ていたのは爪に塗るマニキュアだった。
清光はいつだって己を着飾ることを怠らない人だ。そうでなくては主に可愛がってもらえない、というのが彼の弁だが、堀川はそうは思わない。着飾らなくとも十分に彼は魅力的だと思うのだが、とはいえ着飾っている一つ一つのものがよく似合っているのもまた事実だ。清光が、手や足の爪に丁寧に色を塗っている姿はよく目にする。だからこそ、今日も新しいものを買うのかな、と思っていたのだが、清光が気になっていたものは他のものと比べて少々値が張っていた。だから、またお金貯めてこようとボソリと呟いて、諦めてマニキュアではない別のものを買うことにしていた。
堀川はまだ一度ももらったお金に手をつけていなかったので、それを買うのに必要な金額は持ち合わせている。ならば、清光のために買おう。その方があまり興味ないもののためにお金を使うより、ずっといい。そう思ってその小瓶を手に取ったところで、通路の向こうから清光が鼻歌を歌いながら戻ってきた。堀川が何か手に持っているのを見て、嬉しそうに目を細めてくる。
「おっ、何買うか決めたんだね。堀川のことだから結局決まらなかったよ、とか言うんじゃないかと心配したけど良かった。んで?何買うの?」
「えっと、これなんだけど……」
本人を目の前にしてこれから贈るものを見せるのは少し気恥ずかしかったけれど、控えめに手に持っていたものを見せた。当の清光は、思ってもみなかったものを見せられて、瞳も口もポカンと開けていた。
「堀川って、マニキュアとか興味あったの?意外だな」
「違うよ、これは僕にじゃなくて清光くんに買うんだよ」
「えっ」
まさか堀川が自分に贈り物をするなんて想像してなかった、とでも言うように赤い瞳がさらに大きく見開かれた。彼が驚く姿など記憶している限り見たことがなかったので、良いものを見れたかもしれない。
「じゃあ、僕もお会計してくるね」
ポカンとしたままの清光をその場に置いて、手早く精算を済ませる。可愛らしい黒地に赤い刺繍が施された包紙に、赤いリボンがきゅっと結ばれる。それが何だか清光と堀川の戦闘装束を模しているように見えて、自然と顔がにやけてしまいそうになる。さっきまであんなに頭を悩ませていたのが嘘みたいに、胸の中がスッと晴れ渡るような感覚がした。
「はい、清光くん。遠慮なく使ってあげてね」
少し戸惑った様子の清光の腕をとり、その手のひらの上に包みを乗せる。
(うん。やっぱり、こういう可愛らしいのは僕より清光くんが似合うよね)
そう心の中で独りごつと、少しだけ顔を赤くした清光がたどたどしく口を開いた。
「あ、ありがと……これ、すごく欲しいなって思ってたから、その……嬉しいよ」
「ふふ、そう思ってもらえたなら良かったよ」
「大切にするね。……でもさ、堀川。次はちゃんと自分のために買いなよ?堀川が自分で稼いだお金なんだからさ」
「はいはい、分かったよ」
「本当に分かってる〜?約束だからね」
少し頬を膨らませて唇を尖らせているけど、清光は周りに花でも舞っているんじゃないかと思うほど嬉しそうだ。そんな姿を見ていると、何故だか堀川も胸の中がじわりと温かくなった。あれだけ心を覆い尽くしていた不安な気持ちも、この時ばかりはどこかへ消え去っていた。
それから一年間、堀川は時々機会をみては主の許可を得て万屋へと足を運んだ。清光を真似て自室を飾る小物を買ってみたり、たまに趣味の料理をするための道具を買ってみたりしたけれど、イマイチどれもピンと来なかった。それよりも、清光に似合うんじゃないかと髪紐やイヤリングを買ってプレゼントをして喜んでもらえる方が、ずっと堀川の心は満足した。
そんなことを繰り返していたら、一度清光に「堀川はなんでちょくちょく俺にプレゼントしてくれるの?もちろんすごく嬉しいけどさ、自分にもちゃんとご褒美あげないとダメだよ」と言われたので、正直に清光に何か贈り物をする方が自分も嬉しいのだと告げると、彼は恥ずかしそうに顔を赤らめていた。そんな反応も可愛いな、なんて思っている自分の気持ちを、この頃ようやく自覚した。
清光のことが、特別に好きなんだということを。たくさん嬉しそうな顔が見たいし、悲しい気持ちになって欲しくない。一年前は自分という存在に不安の気持ちを抱いてばかりいたけど、今は違う。ふとした時に頭に浮かぶのは、彼のことばかり。最初は戸惑うしかなかったけど、本丸にある小説や清光がたまに観ている映画などで人間の心理というものに触れるうちに、自分の中で生まれた変化が何なのかを理解できた。
けれども、堀川はこの気持ちを彼に伝えようとは思わなかった。刀剣男士として、時に危険に立ち向かうことはあれども、基本的には本丸で彼と穏やかな時間を過ごす機会はたくさんあった。今のこの状況だって、十分すぎるくらいしあわせだ。だから、わざわざこの気持ちを伝えてそこに歪みを生じさせたくはない。臆病だな、とも思うけれど、ただでさえこの本丸には人が少ないのだ。もし拒絶されてしまったら、と思うと、どうしても一歩踏み込んだ関係になろうという勇気は引っ込んでしまう。
これでいい。このままでいい。清光だって、きっとそう思っている。堀川がそう自分に言い聞かせている中、本丸に緊急の知らせが舞い込んできた。
「あなたたちを集めたのは、先ほど政府から受けた連絡を伝えるためです。時間遡行軍と政府軍が戦っていた戦場に、検非違使が出現しました。彼らは遡行軍と政府軍の両方に攻撃を仕掛けてきて、現在劣勢であるとの知らせを受けました。検非違使が出現して時空の歪みが発生したため、大人数は送れません。そのため、少数精鋭で戦っている我々の本丸の力を借りたい、と政府より要請がありました。危険な任務となりますが、ここにいる六人にぜひとも出陣をお願いします」
部屋に集められたのは、堀川と清光を含む六人の刀剣男士だ。たった十六人で戦いを継続していることもあって、個々の戦闘力は申し分ない。全員が、主の命令を快く了承した。自分たちの実力が評価されて、指名されたのだ。ここで活躍しなければ、主の名を傷つけてしまう。それだけは、絶対に避けたい。緊張に包まれる中、各々戦支度を整えた。
戦場は、幕末の京都。この部隊に自分が選抜された理由は、言われなくとも分かる。その時代を生きた刀として、負けるわけにはいかない。籠手に結ぶ紐をいつもよりきつく縛ると、堀川は仲間と共に戦場へと向かった。
もっと派手に戦闘が行われているのではないかと予想していたが、どうやら戦況は膠着しているようだ。一見静かな京都の町には、されど渦巻くような敵意が漂っているように感じる。まずは偵察をと京都の町に詳しい自分が様子を伺っているが、中々尻尾を表さない。ひとまず仲間たちと合流しようと歩き出したところで、同じく町の中を調査している清光と出くわした。
「お疲れ。なんか変わったことあった?」
「ううん、見た感じどこかに潜伏しているみたいだね。もう少し捜索範囲を広げた方が良さそうだ」
「うん、俺の方もそんな感じ。とりあえず、一緒に合流場所に向かおっか」
二人で歩き出してからすぐに、通りの向こうからこちらへと歩いてくる集団が目に入った。忘れもしない、揃いの隊服。京都の治安を取り締まる、壬生の狼と恐れられた武闘集団、新撰組だ。きっと、あの一団の中に自分や清光の前の主もいるだろう。今日は、新選組を語るに置いて欠かせない、重要な出来事が起こった日だ。池田屋事件。歴史通りなら、この後加州清光は彼の地で刀身を折られることとなる。
清光も彼らに気付いたのか、そっとこちらを見つめる。どこか心配そうな顔で、「大丈夫?」と声をかけられた。
以前の堀川であれば、自分の存在価値というものを確かめるために、前の主の元へと駆け出していたかもしれない。彼と話せば、自分という存在が何なのか分かるのではないか、そんなことを思ったかもしれない。
けれど、今の堀川は違う。一年という決して短くはない時を本丸で過ごした、刀剣男士・堀川国広であり、主や仲間と共に歴史を守ることこそ己の誇りである。自分が偽物かどうかなんて関係ない。今の自分を必要としてくれる主と仲間がいる。それだけで、自分がここに在るには十分な理由だ。
「大丈夫だよ。清光くんは大丈夫?……いや、余計な心配だったかな」
「もっちろん。そりゃあ、沖田くんに言いたいことはあるけどさー。もっと大事に扱ってよ、とか。でも、それを後の世から来た刀剣男士の俺が伝える資格なんてない。歴史は、そこに生きる人たちが懸命に紡いだ結果なんだ。だから、今の俺にできることは、俺が折れたっていう歴史を守ること。それで十分」
「……うん。その通りだね」
「それにね、自分じゃ何もできなかった刀の時とは違って、俺は一人じゃない。今はこうして一緒に戦う仲間がいる。だから、俺は頑張れる。……頼りにしてるよ?」
「任せてよ。僕たち皆で戦って勝って、本丸に帰ろうね」
顔を見合わせて頷いた二人の横を、池田屋へと駆けていく新選組の一行が通り過ぎる。その背中を清光と共に見送った後、合流地点へと急いだ。
その後、捜索範囲を広げた結果無事に検非違使の部隊の居場所を突き止めた部隊は、堀川と清光の献策により優位に戦闘を進めることのできる地点を割り出した。地の利ならばこちらにある。それを活かすことができれば、決して勝てない相手ではない。
しかし、ここで予想外の事態が起こる。こちらが敵を万全の構えで迎え撃つ準備が整う前に、向こうから攻め込んできたのだ。政府軍と遡行軍の両方を退けた検非違使の戦闘能力は想像以上で、堀川たちは劣勢を強いられてしまう。多くの刀剣たちが、大なり小なりの手傷を負った。
だが、ここでやられるほどこの本丸の刀剣たちはやわではない。不利を悟って慌てて退いたと見せかけて事前に話し合っていた地点に敵を誘いこみ、逃げ道を塞いだ上で挟撃を仕掛ける。京都の町の地形を把握しているからこそできる戦術で、徐々に敵の数を減らしていった。ここまでは、何とかこちらの描いていた通りにことは進んだ。
けれど、戦というのは往々にして、思いもよらぬ落とし穴というのがあるものだ。残る検非違使は太刀と槍使いの二人、対するこちらは負傷者はいるものの六人全員が戦える状態だった。さすがの検非違使たちも敗北を悟ったのか、突然それまでの技巧溢れる剣術を捨てて捨て身の突撃をしてきたのだ。風を切るような速さで駆け出ていく、二つの塊。敵の狙いは、少しだけ離れた場所にいた清光だった。当然清光は果敢に応戦するが、命を捨てた者がくり出す全力の猛攻を受けきれそうになかった。
「クソッ……、こんなところで、死ねるかよ……!」
必死に刀を振るって、仲間が駆けつけるまで耐えようとする清光。その首めがけて、検非違使の最後の力が込められた、青い炎を纏った槍が襲いかかる。太刀の攻撃を防いでいた清光は、反応が遅れてしまった。避けきれそうにない、そう思ったのか、目を瞑った清光を堀川は眼前に捉えた。
そこから先は、体が勝手に動いていた。誰よりも早く清光の元に駆けた堀川は、槍の切っ先が届くよりも僅かに早く、彼の体を突き飛ばした。代わりに、堀川の胸に禍々しいオーラを纏った槍が突き刺さる。不思議と、痛みは感じなかった。それよりも、清光がどさりと受け身を取りながら地面に倒れた姿を見て、安心した気持ちの方が勝った。ああ、清光が無事で良かった。そんなことを堀川が考えていると、敵の太刀が堀川に向かって獲物を振り下ろそうとするのが視界に入る。生憎、もう避けるだけの力は残っていない。
けれど、その刀が振り下ろされることはなかった。遅れて駆けつけてくれた仲間たちが、無防備な敵の背中を尽く斬り伏せてくれたからだ。砂のように消えていく敵の姿と共に己の胸に突き立てられた槍も消え、傷口からじわじわと血が滲んでくるのが分かる。そこで初めて強烈な痛みを覚えて、思わず座り込んでしまった。
「おい、堀川!大丈夫か?」
「堀川さん、待っててください、すぐに止血しますから!」
堀川を囲うように集まった仲間たちの顔は緊迫している。それでも、堀川が落ち着くようにと励ましの声をかけながら、手当をしてくれた。少し遅れて、物凄い勢いで走ってきた清光が、今にも泣きそうな顔をして堀川の手を掴んだ。
「堀川っ!ごめん、俺、防ぎきれなくて……大丈夫だから、絶対に主が治してくれるから。だから、もうちょっとの辛抱だよ」
堀川の手を握り締める清光の手は、震え汗ばんでいた。きっと、ショックだったに違いない。それでも、堀川を心配させないように気丈に振る舞っているのだろう。その心遣いが、何よりも堀川の痛みを和らげる薬となった。
すぐに部隊は本丸へと帰還し、堀川は手入れ部屋へと入れられた。重症であったけれど、主の尽力により傷は塞がった。それは他の五人の怪我も同様だ。だが、主は明らかに浮かない顔をしていた。他の五人は、無事に全員回復したというのにどうしたのだろうと首を傾げていたが、堀川にだけは主の思っていることが理解できた。傷は治ったが、未だに堀川の体には、じわじわと内側から焼かれているような痛みが残っていたからだ。
すぐに主は政府へと連絡して、刀剣男士の肉体を研究しているという科学者が本丸に派遣された。一時間にも及ぶ検査の結果、二つだけ分かったことがある。この痛みは検非違使が今際の際に込めた呪いによるものであり、手入れでも治らないこと。そしてもう一つは、呪いは時間の経過と共に体を侵食し、最終的には堀川は知性を失い、検非違使へと堕ちるということだ。
この時、堀川は初めて、検非違使が元々は自分たちと同じ刀剣男士であることを知った。知性を奪われた刀剣男士は検非違使へと堕ち、遡行軍も政府軍も見境なく襲う獣に成り果てる。それが、今まで隠されていた検非違使という存在の正体だった。
もちろん、堀川はそんなものになるつもりはない。主も同じ気持ちのようで、見たこともないほど辛そうに顔を歪めながら「あなたに残された道は刀解しかありません」と告げられた。その言葉に異論はない。あのような姿になるくらいならば、ここで死ぬ。何の選択肢も用意されていない突然の死よりも、いくらかマシな最期ではないか。「宜しくお願いします」と一礼をすると、刀解は明日実行する、それまでに心残りのないように過ごしなさいとだけ言い残して、主は部屋を後にした。
それから十分ほど経った頃だろうか、堀川の自室の戸が開いた。音も立てずに入ってきたのは、清光だった。主から堀川の行く末について聞いたのだろう、赤い双眸はより一層赤みを強くして、体は震えていた。堀川の姿を捉えた瞳が、ゆらゆらと波のように揺れる。どさ、と音を立てて膝が畳に着く。沈黙に耐えかねて、何か飲み物でも取ってこようかと立ち上がりかけた堀川の腕を、赤い指先がぎゅっと掴んだ。
「……ごめん。謝ったってどうにかなるわけじゃないけどさ」
「清光くんが謝る必要なんてどこにもないよ。僕が勝手にやったことなんだから。後悔なんてしてないよ」
「……嘘、だよ。だって、堀川……っ、死んじゃうんだよ?明日になったら、もうこの本丸からいなくなっちゃうんだよ?そんなの、そんなのっ……、俺だったら、きっと耐えられない……!」
「……そうだね。でも、清光くんが死んじゃうより、そっちの方がずっといい」
「ふざけんなよ!!俺はよくない……全然、よくねぇよ」
掴まれた腕から、清光の震えが伝わってくる。ポツ、ポツと畳に染みが滲む。瞬く間に染みはどんどん大きくなって、畳を濡らしていく。彼に悲しい顔をさせたくないと思っているのに、こうして泣かせてしまっている。そんな自分がどうしても許せなくて、何とか悲しみが和らぐようにと言葉を探した。
「泣かないで、清光くん。僕がいなくなった後には、頼もしい新たな仲間がやって来るよ。もしかしたらそれは二振り目の僕かもしれない。いや、それよりも、君の大事な相棒の安定くんかもしれない。だから、大丈夫だよ」
懸命に絞り出した励ましの言葉のつもりだったが、それは却って逆効果だったらしい。より一層眉間の皺を深めた清光に、肩を掴まれる。
「……堀川は、分かってない。ちっとも分かってないよ。いつもはあんなに察しがいい癖に、こんな時に限って、何にも分かってないんだもん」
「……どうして?」
「俺がこの本丸でたくさんの時間を過ごして、一緒に戦って、たまに買い物に行ったりして、そんでもって俺の好みバッチリの贈り物をくれて。……そんな奴はね、お前だけなんだよ。今ここにいる、堀川国広だけなんだよ。二振り目の堀川が来ようが、安定が来ようが、お前の代わりになんかならない。なるわけない。……だって、俺が大好きなのは、お前なんだもん」
ポロポロと目尻から涙を零しながら懸命に紡がれた告白に、思わず堀川は目を見開いた。なぜなら、思ってもみなかったから。清光が自分を好いていてくれていたなんて、気づかなかった。腹のそこから沸々と喜びの波が押し寄せてくるのを感じる。でも、駄目だ。この気持ちに応えることはできない。これから消えてしまうだけの自分が清光に想いを伝えたところで、重荷になるだけだ。だから、黙って消えよう。
そんな覚悟を決めた堀川だったが、それはいとも簡単に清光の言葉によって脆くも崩れ去った。
「堀川が、好き。大好きだよ。だから、堀川が俺のせいで刀解されるなんて、嫌だ。……俺も、主に頼んで一緒に刀解してもらう」
その発言に堀川は慌てる。せっかく清光の命を守ったというのに、彼は自分と共に死を選ぼうとしている。そんなの、絶対に嫌だ。自分勝手だと思うけれど、彼には生きていて欲しい。だから、正直に自分の想いを伝えようと思った。本音で話せば、きっと彼は理解してくれると信じて。
「ねえ、清光くん。僕も君のこと、大好きだよ。だからね、大切な君を守りたいと思ったから、あの時必死になって君を庇ったんだ。君を死なせたくなかった。そこに後悔なんてあるわけがない。君にはこの本丸の始まりの一振りとして、これからも主さんや皆を支えて欲しいんだ。……それが、僕の最後の我儘。聞いてくれないかな?」
「……ずるいよ。そんなこと言われたら、嫌だなんて言えない」
「ふふっ、それが狙いだからね。嫌いになっちゃった?」
「ばーか。そんなことくらいで嫌いになれたら、こんな風に泣いてないよ。すっかり目も腫れて、不細工になっちゃったじゃん。……責任、取ってくれる?」
「……もちろん」
微笑みながら堀川を見つめる清光の体を、そっと抱き寄せる。ぴったりとくっついた体温の温かさを感じながら、堀川は少し濡れた唇にキスをした。
かつて刀であった頃、主の最後の戦いで何の役に立つこともできなかった。己の存在意義とは何だったのであろうか、と何度も自問した。しかし、今は違う。主のために剣を振るい、こうして大切な人ができた。自分の命より大事な、愛おしいと思える存在ができた。ただの刀として時代の流れに逆らうこともできずに消えていった時の自分が今の自分を見たら、きっと驚くだろう。それくらい、今この瞬間の自分は幸せ者だと思う。
触れるだけだった口付けは、次第に深いものへと変わっていく。想像していた以上に柔らかいそれに、夢中になって食らいついた。呼吸さえ奪ってしまうほど深く、何度も何度も、角度を変えて味わう。息継ぎのために開けられた唇に、そっと舌を差し込んだ。清光の咥内は熱く、差し入れた舌が焼けてしまうのではないかと錯覚してしまいそうになる。それでも、歯列をなぞり、所在なさそうに固まっていた清光の舌を絡め取る。ぴちゃぴちゃと唾液を啜る音が、堪らなく淫靡に聞こえてならなかった。
さすがに息が辛くなってきたのか、とんとんと胸を叩かれてしまったので、名残惜しく思いながらも顔を離した。つう、とうっすら残る銀糸と、顔を林檎のように赤く染めながら息を乱す清光の姿が、体に燻る炎を燃え上がらせた。未だ抱きしめたままの清光のシャツの釦を片手で器用に外していくと、上下する胸の先端にちょこんと乗った淡い色の粒に唇を添える。小さな果実のような突起を、優しく円を描くように舐めた。
「あっ……ほり、かわ……」
「……ごめん、嫌だったかな?」
「……いやじゃ、ない……ただ、声、我慢できないから、ちょっと恥ずかしい……」
「我慢しなくていいよ。清光くんの声、聞かせて?」
そういうや否や、今度は口に含んでちゅうちゅうと赤子のように吸い付く。もう片方は、先端を指の腹でクリクリと押しつぶすように回した。
「――っ、ぁあ!……あっ、やだ……きもちぃ、んっ、ァああ!」
清光の口から漏れ出てくる嬌声と堀川が胸を愛撫する音だけが、狭い部屋の中を支配する。時折軽く噛んだり、摘み取るように引っ張ったり。堀川の動き一つ一つに清光は快感を刺激されるようで、あっという間に先端がピンと立ち上がっていく。彼が自分の手で感じてくれているのだという事実が、どうしようもなく嬉しい。ちらりと視線を下に移せば、ズボン越しでもはっきりと分かるほど股間は膨らんでいた。胸を可愛がっていた指が、撫でるように清光の股間に触れる。途端に、清光の体がビクリと震える。ぎゅっと堀川のシャツを握りながら少しだけ上目遣いで見つめられると、己の股間に熱が溜まってくるのが分かる。その仕草一つ一つが堀川をこの上なく昂らせていることなど、きっと清光は自覚していないだろう。布越しに形をなぞるように、手のひらをつうと這わせる。堪らずに清光が声を上げた。
「あっ……、ほりかわ……触って、よ……」
「今も触ってるよ?」
「……っ、違くて……直接、触って欲しいの」
涙を溜めながらおねだりされれば、ひとたまりもない。もうちょっと粘ってみようかとも一瞬思ったが、これ以上やると恥ずかしさの余り拗ねてしまうかもしれない。それはそれで可愛いのだろうな、と思いながら、カチャカチャとベルトを外して下着ごと一気に脱がした。勃ち上がった性器が顔を出し、外気に晒されたことでふるふると震えている。
赤く腫れた脈打つ幹をそっと握ると、ゆっくり上下に扱いていく。トロトロと先端から先走りが溢れては堀川の指を濡らしていく。ぬちゃぬちゃといやらしい音を立てながら、気持ち良い部分を探るように愛撫を続けた。
「――ひぅ、ぁああっ……!っあ、ダメ、いっちゃ、イッちゃうから……、ぁ、……ぁああああ!」
清光の静止の声をよそに、堀川は先端の窪みを押し回す。それがトドメとなったようで、びゅくびゅくと勢いよく白濁が吐き出されて、堀川の指やシャツ、そして清光自身の腹を汚した。目をぎゅっと瞑って快感に身を任せる清光の姿は、何よりも美しく感じられた。背中を丸めて絶頂の余韻に耐える清光の背を何度か撫でた後、堀川は立ち上がった。さすがに愛しい人の痴態を見て、己の股間のものも限界が近い。けれど、呪いをこの身に宿した自分がこれ以上彼に触れるのは危険ではないかという気がして、清光が気を遣っているうちに去ろうと思ったのだ。
だが、そんな堀川の気持ちなど見透かされていたのだろう。まだ呼吸が整いきっていないにも関わらず、清光が引き止めるように堀川の腕を掴んだ。
「……どこ、行くのさ」
「えっと……厠に」
「なんで」
「……それを言わせる?」
「言ってもらわないと分かんないもん」
本当は分かっているだろうに、清光は梃でも動かないと言いたげにむすりと睨みつけてくる。仕方ないな、と息を吐きながら正直に答えた。
「僕もそろそろ限界だからさ。自分で処理してくるよ」
「そんな必要ないよ。俺がやったげる」
「……駄目だよ、これ以上は。万一清光くんの体に何かあったら、僕は死んでも死にきれない」
「はあ?今更何言ってんのさ。それにね、俺がこんなことでどうにかなると思ってんの?舐めんなよ、こちとら川の下の子、そんなやわじゃないっての」
堀川の腕を掴んでいた清光の指がベルトにかかり、強引に外されていく。無理やり逃げれば足の速さでは勝てるはずなのに、堀川の体はピクリとも動かない。大好きな人が、触れてくれる。そんな魅力的な現実に、理性が太刀打ちできようはずもなかった。
下着ごと一気に膝まで脱がされると、ガチガチに硬くなって天を仰いだ陰茎が現れる。清光の指に絡め取られただけで、感覚が飛んでしまったのではないかと思うほど気持ちよかった。愛しい清光が、己の体の最も浅ましい部分に触れている。そう考えるだけで、どんどん下腹部に熱が集まっていく。
「……もうちょっと屈んでよ。これだとやりにくいから」
清光の切れ長の美しい赤に上目遣いで見つめられながらお願いされれば、自分の意思とは関係なく勝手に体が動いて膝立ちになっていた。よく出来ましたと嬉しそうに呟いた後、そっと先端が温かい感覚に包まれた。すぐに、それが清光の咥内なのだと理解した。
「……っ、清光、くん……駄目だよ、手でやってくれれば、良いから……」
「うるさい。そんなの俺の自由でしょ」
そう言うとすぐにちろちろと雁首を舌で刺激され、一気に腰が重くなる。歯を立てないように、懸命に堀川の猛りを飲み込もうとする姿が、この世の何よりも可愛く思えてならない。時折苦しげに眉を顰めながらも、清光は喉を動かして丁寧に愛撫を続ける。舌が脈打つ筋に添えられるたびに、快感が下半身から全身へと回っていく。
「……はぁ、清光くん、もう出るから、口、離して……」
さらさらと指に馴染むくせっ毛を撫でながら堀川は清光を促すものの、清光の動きは止まらない。いや、それどころか射精を促すように激しさを増していく。何とか引き剥がそうとするも、愛する人の髪を引っ張るなんてことはもちろん出来ない。堀川にできることは、とんとんと清光の背を叩いてもういいのだと伝えることくらいだ。当然、清光は退かない。喉が引き絞られて、中のモノが圧迫される。我慢の限界を迎えて、堀川は清光の咥内に己の欲望を解き放った。それをゆっくりと、清光は喉の奥に流し込んでは飲み込んでいく。口の端から、つうと溢れ出た精液が伝って、顎から床へと落ちていく。その光景が恐ろしいほど激しく堀川の欲を昂らせた。ずる、と清光の口から解放された陰茎は、一度達してもなお硬度を保って勃ち上がっている。
「はぁ、はぁっ……すごい、いっぱい出たね。なのにまだガチガチじゃん」
「もう、飲まなくて良いのに……苦しかったでしょ、ごめんね」
「俺がそうしたかったからいーの。ねえ、まだ満足できてないでしょ?続き、しようよ」
「……清光くんは、いいの?」
「当たり前じゃん。好きな人と抱き合いたいなんて、人間からしたら普通のことでしょ?俺たちは元々は人間じゃなかったけど、今はこうして人の身がある。だから、俺は堀川と一つになりたい。それとも、堀川はそうは思わないの?」
「……ううん、そんなわけない。清光くんと繋がりたいよ。君のこと、もっと近くで感じたい」
堀川の返事を聞いて満足そうに笑うと、今度は清光の方からキスをされる。少しでも己の想いが伝わるようにと願いを込めながら、何度も、何度も口付けた。
そのまま敷いていた布団に清光を押し倒すと、誰にも触れられたことのない蕾にそっと指を這わせる。ピクリ、と清光の身体が小さく震えるが、大丈夫だと目配せをされたので、縁をなぞった後慎重に中指を押し込んでいく。清光の中は狭く、堀川の指を遠慮なく締め付けてくる。ふうふうと息を吐いて力を抜く清光はどこか苦しそうで、思わず指を引き抜こうかと思った。けれど、そんな堀川の気持ちを察した清光は「大丈夫だから……続けて」と堀川の腕を掴んだ。なるべく早くしなければと懸命に中を探るうちに、腹側に少し膨らんだ部分があることに気づいた。ゆっくりと、その膨らみを指の腹で擦る。その瞬間、ビクンと清光の身体が跳ねて、背が弓なりにしなった。
「あっ……なんか、そこ、変……ぁあ、っ、――あああん!」
「ここが、気持ちいいの?」
「ひゃっ、ダメ……、そこばっか、ああっ!ぁあ、あっ、あああ!」
堀川の指が押し上げる度に、ビクビクと清光が痙攣しながら喘ぎを漏らす。清光の意識がそちらに向いているうちに二本目の指を差し入れて、バラバラに動かし中を拓いていく。経験したことのない快感に清光は翻弄され、中の襞はより強い刺激を求めて収縮を繰り返す。もう一本指を追加しても、たちまち清光の胎はそれを受け入れて奥へと誘う。
そろそろ自分の方も限界だ。そう判断した堀川は指を引き抜くと、中途半端に膝に残ったままの下着を脱ぎ捨てて、清光の足を大きく開いて身体を滑りこませた。ドク、ドクと心臓が早鐘を打つ音が、耳から響いてくる。いよいよ清光と一つになるのだと思えば、興奮は最高潮に達した。それは清光も同じなのだろう。咥えるものがなくなった後孔はふるふると震え、時折中の媚肉を晒しては堀川を誘惑している。堀川の剛直は、これ以上にないほど張り詰めて熱を帯びていた。
「……はぁ、はぁっ……ん、堀川、来て……」
「痛かったらすぐに言ってね?すぐに止めるから」
そう言って清光の額に軽いキスを落とすと、堀川は入口にいきり勃った陰茎を押し当て、少しずつ挿入していく。指よりも遥かに太い侵入者に、清光の中はぎゅうぎゅうと容赦なく締め付けてくる。息を吐きながらも深く刻まれた眉間の皺から、清光が痛みを必死に堪えていることが伝わってくる。
「……ごめん、清光くん。痛いよね?やっぱり止めようか」
苦しみに涙を溜めながらも、清光は必死になって堀川の背に腕を回す。
「ばか、止めたら一生恨むよ……?大丈夫だから、続けてよ。……お願い」
震える瞳に懇願されれば、それを拒否することなどできるはずもない。「分かった」と短く返事をすると、堀川は中を押し拓くように腰を埋めていった。強烈な締め付けに堀川の方も多少の苦しさを感じていたが、清光の感じる苦痛は堀川の比ではないはずだ。清光は、それを耐えながら続きを求めているのだ。これくらい我慢できないようでは、男が廃る。
最も太い嵩の部分が入り込めば、後は苦労なく進むことができた。ふわりと下生えが清光の尻に触れたのを感じて、ようやく全て挿入することができたのだと安堵した。
「清光くん、全部入ったよ」
「……本当?よかった……」
未だ苦しそうに顔を歪めながらも、口だけは弧を描いて何とか喜びを伝えようとしてくれている。そんな清光の心遣いが堪らなくいじらしくて、衝動のまま唇を奪う。迎えるように伸ばされた舌を、むしゃぶりつくように絡め取っては啜り上げる。今この瞬間だけは、清光は自分だけのものだ。清光と身体を繋げて一つになっているのは、それを許されているのは、自分だけだ。そんな独占欲と満足感が湧き上がって来て、夢中になって清光の咥内を犯していく。堀川の髪に綺麗に彩られた指が差し入れられて、キスの度に髪を乱されていくことでさえ、今の堀川には欲を燃え上がらせる燃料になってしまう。溢れる唾液が互いの顔を濡らすことすら厭わず、二人は深い交接に酔いしれた。このまま、時が止まってしまえば良いのに。そうしたら、自分たちは永遠に互いの存在を深く感じられる。そんな馬鹿な考えが頭に浮かんでしまうほど、堀川の心は幸福に満たされていた。
どれほどの間そうしていたのかは分からない。けれど、いつの間にか剛直を締め付ける痛みがすっかりなくなった頃、ようやく二人は顔を離した。顔周りは互いの唾液で濡れていたけど、そんなことちっとも気にならなかった。
「……もう、そんなに痛くないから。動いて大丈夫だよ。……ううん、違うな。動いて欲しい。俺の中、いっぱいいっぱい、堀川で満たして欲しいな」
「……清光くんはさ、僕のことを煽る天才だよね」
清光の発する言葉の一つ一つが、こんなにも堀川を捉えて離さない。しかも、本人はそれに無自覚なんだからタチが悪い。そんな彼に惚れたのは自分なのだから、どうしようもないのだけれど。
顔が赤くなっていくのを感じながら、堀川はゆっくりと腰を引いて律動を開始した。堀川の肉槍が下がる度に内壁は追い縋るように引き止め、ぐいと奥をつく度に歓喜に震えてぴったりと吸い付いてくる。その蠢きが、強烈な快感を次々と堀川に与える。腰の感覚がなくなってしまったのではないかと思うほど、気持ちいい。押し寄せる快感故に清光が必死に堀川の背に爪を立てていることにすら、感じてしまう。清光の中を貫き、突き回し、揺さぶる動きを止められそうにない。
「あっ、あん、あっ、ほりか、ほりかわっ、すき、すきぃっ、……ああっ!」
「はぁっ……きよみつくん、……清光っ、大好きだよ……!」
掻き回すように奥を嬲っては、先ほど指で見つけた敏感な部分に亀頭を幾度となく擦り付ける。一層強くなる締め付けに耐えながら、清光の中を余すところなく犯していく。パンパンと結合部から響く乾いた肌のぶつかり合う音が、自分たちがまぐわっているのだという現実を教えてくれて、堀川の全身は快楽にどっぷりと浸った。これ以上に光悦を感じる瞬間などあるまい。そう感じながら、さらに腰の動きを速めていった。
「ぁあっ、ああ、……ほりかわっ、……むり、もう、イッちゃうよ……っ!」
「いいよ……一緒にイこう、清光……!」
「ぁっ、――――ぁあああああああああ!!!」
ドチュ、と一番深くまで勢いよく貫いた衝撃によって、ビクビクと震えながら清光の性器から白い粘液が飛び散っては互いの腹を汚していく。ガクガク痙攣しながら堀川にしがみ付く清光の身体を強く抱きしめたまま、堀川は何度かさらに奥を突き回してついに限界を迎えた。射精の終わりきらぬ敏感な身体は、中に埋まる猛りから精を搾り取ろうと容赦なく締め付け、耐えかねた先端からドロリとした濃厚な白濁が吐き出されては内壁を叩いていく。互いの体温と撒き散らされた欲望で、清光の胎は焼けてしまうのではないかというほど熱い。じわじわと己の精液が清光の中を塗りつぶしていく感覚の心地よさに、堀川の胸は収まりきらないほどの幸福で満たされていた。
残滓を出し切った堀川が抜けていくのを、名残惜しそうに清光の媚肉は吸い付いてくる。とろりと後孔から白濁の一部が漏れ出てくる光景に、思わず鼓動が速くなってしまう。
「……はぁっ……はぁ……すごい、気持ちよかった……」
「……うん、僕もだよ。清光くんと一つになれて、すごく気持ちよかった」
「……ねえ。さっき俺のこと、清光って呼んだでしょ」
「え、えーと……そうだったかな」
夢中になって彼の名を呼んでいたから、言われるまで気づかなかったけど。そういえば、呼び捨てにしてしまっていたかもしれない。無意識のうちとはいえ、指摘されると少し恥ずかしい。
「あのさ、二人だけの時はそう呼んでよ」
「えっ……?」
「……だって、そっちの方がなんていうか……特別っていうかさ、コイビトっぽいじゃん」
「……」
どうしてこうも彼は堀川のツボを的確についてくるのだろう。照れながらそんなことをお願いされて、嫌だなんて言えるはずもないではないか。
「……分かったよ」
「やったね。……ねえ、国広」
「……っ!」
今、彼は自分のことをなんと呼んだ?聞き間違えでなければ、『国広』と呼ばなかったか?
「俺だけ呼び捨てで呼んでもらうんじゃ不公平だからね。それに、ずっと呼んでみたかったんだよね、国広って」
「……はー……ねえ清光、これって夢じゃないよね?」
「当たり前じゃん。夢であってたまるかってーの」
ぎゅっと軽く頬をつねられる。……痛みを感じるということは、まごうことなき現実なのだろう。本当に、いくらもうすぐ死んでしまうとはいえ、こんなにも幸せでいいのだろうか。
「話の続きね。……国広がよければ、なんだけどさ。もう一回しない?」
「……」
よくないわけがない。国広にとっては、これが最後の夜だ。でも、清光だって出陣で疲れているはずだ。そんな彼に無理をさせるわけにはいかないだろうという理性と、もっと抱き合いたいという本能が脳内で鬩ぎ合う。けれど、ここは何もかも取り払った閨の中だ。理性と本能、そのどちらが勝つかなんて、分かりきっている。
「……しよう。ううん、したい。でも、しんどかったらちゃんと言ってね」
「分かってるよ。心配性だなぁ」
嬉しそうに目を細めながら抱きついてくる清光の背中を撫でながら、二人は再び快楽の渦へと落ちていった。
まもなく日が昇ろうかという明け方。二人は一睡もしていない。というのも、もう一回、なんて言ったはいいけど、一回だけで互いを求める熱が収まるはずもなく。何度も何度も体勢を変えては抱き合って、結局落ち着いたのがつい先ほどのことだ。そして、今なお二人はぴったりとくっつくように抱き合っては、時折言葉なくキスを交わす。迫り来る終わりを背中に感じながら、ただ静かに最後の時を穏やかに過ごしている。
「……もうすぐ、夜が明けるね」
「うん……」
「きっといい天気になるよ。清光は、今日は何の当番もないんだっけ?疲れてるだろうから、ちゃんと休むんだよ」
「……うん」
国広の背中に回された清光の腕に、ぐっと力がこもる。どうしたんだと視線をやると、悲しそうに下がった瞳にじっと見つめられる。
「……朝なんて、来なければいいのに」
「……清光」
「そうしたら、俺はずっと国広と一緒にいられる。こうして抱き合って、国広の存在を感じられる」
「……ねえ、清光」
「……何」
「僕も、君とずっと一緒にいられたらって思うよ。でもね、きっと終わりがあるから、僕たちはお互いのことを深く想い合うことができるんじゃないかな」
「どうして?」
「いつか別れが来るからこそ、今この瞬間を、清光と一緒にいられる時を、愛しくてかけがえのないものだって思える。僕は、そう思うな」
「……それは、そうかもしれないけどさ」
「それにね。僕はいなくなってしまうけど、僕の想いは消えない。清光を想う心だけは、消えてなくなりはしない。だから、忘れないで。もしこれから先、辛いことや挫けそうなことがあっても、僕は清光のことを見守っている。姿が見えなくても、ずっとそばにいるよ」
「……分かったよ。約束だからね?ちゃんと俺のこと、見守っててよね?俺が死んじゃう時は、迎えに来てよね?」
「もちろん。約束、だね」
そっと清光の小指をとって、自分のそれを絡める。いつだったか映画で観た、人間の約束の印だ。指を離すと、国広は脱ぎ捨てた服のポケットから取り出したものを清光に気づかれないように口に含み、柔らかい唇に己のそれを押し当てる。舌を使って清光の口内へと運ぶと、ごくりと飲み込む音が聞こえた。
「あれ……何、なんか……急に、すごい眠くなってきた……」
「昨日から一睡もしてないからね。ゆっくり休むといいよ」
「うそ……待って、嫌だよ、国広……俺、こんなんでお別れなんて……」
「ごめんね。……主さんから、眠っている間に刀解してもいいって渡された薬なんだけど。僕は、笑顔で君とお別れしたいんだ。きっと刀解される時に君の顔を見たら泣いてしまう気がする。……だから、ここでお別れさせて」
「……そんなの、勝手すぎる……バカ国広……」
「……うん。僕のこと、恨んでくれて構わない」
「……恨むわけ、ない、じゃん……」
「ありがとう、清光ならそう言ってくれると思った。……おやすみ、清光。よい夢を。……またね」
「……くにひろ……やくそく、……おぼえてて、ね……」
それ以上、強烈な襲われた睡魔に襲われた清光に国広の言葉を聞き取ることはできなかった。ただ、最後に大好きな国広の笑顔を必死に焼き付けて、清光の意識は沈んでいった。
朝日が昇りきった頃。一人の刀剣男士が、玉鋼へと還っていった。その最後は、堂々とした誇りに満ちたものだったと言う。
――それから約五十年の後。少数の刀剣男士たちで構成されていたとある本丸が、審神者の寿命により終焉を迎えた。主の最期を見届けた始まりの一振・加州清光は、笑いながら満足そうに消滅していった。その手のひらには、かつて想いを結んだ刀の形見である玉鋼の欠片が入ったお守りが、握られていた。