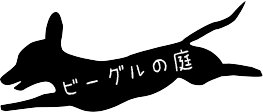暖かい風が頬を掠め、春の訪れを告げてくる。長く厳しい冬が終わり、誰もが喜ばしい気持ちで春の到来を迎える中、兼定の心は晴れやかな陽気とは対照的に荒れていた。
いつだって恋愛の終わりとは残酷なまでに心の内側を突き刺していく。これが自分の運命なのかと認めれば楽になれるのかもしれないが、人との交わりを全て断って悟りの道を極めるにはまだ二十一の兼定は些か現世に未練があり過ぎる。
和泉守兼定は、帝とその女御との間に生まれた寵児であった。美しい母の容貌を受け継いだ彼は、絹のように柔らかく光り輝くような黒髪も、すっきりとした蒼い切長の目も、立派な鼻筋も、すらりと高く均整のとれた体も、その全てが人々を魅了してやまない。
帝は彼の母を深く寵愛していたため、彼女との間に生まれた兼定のことも目に入れても痛くないと言うかのように可愛がった。記憶にうっすら残る幼少の思い出は、唯一兼定の心を慰め癒してくれる存在と言って良いだろう。
そのまま育てば何の不自由もない皇子として幸せな人生を歩んだはずだった。
しかし、運命は兼定に輝かしい未来を約束してはくれなかった。兼定が四つの頃、最愛の母が病でこの世を去ったのだ。父帝は愛する妻の突然の死に嘆き悲しみ、兼定もまた優しく誰よりも愛しい母を失ったことで深い悲しみの底に落とされた。それだけでは終わらず、不幸は連鎖して兼定に襲いかかった。
母の死をきっかけに、今まで母に帝の寵愛を独占されていた皇后や女御たちはその座を奪い返そうと躍起になり、家ぐるみで母の実家を権力の座から追い落としたのである。失意の中、祖父母もまた母を追うように病死してしまい、兼定は一人になった。
勿論父帝は健在であったが、彼には他にも何人もの皇子や皇女がいる。そして政務にも関心を持って取り組んでいた父は、兼定にばかり寄り添う時間を作るのが難しい立場にある。
幼い兼定もそのことは理解していたため、父に甘えることもできなかった。家族を次々と亡くした愛する女性の遺児を父は哀れに思い、一度は跡継ぎにすることも考えたようであるが、当然の如く周りの者たちに反対され、その上実家の後ろ盾もない兼定を権力争いの場に置けば却って辛い思いをさせてしまうと判断した。
こうして臣籍降下して「和泉守」の姓を賜った兼定は、母の実家で与えられた従者たちと共に日々を過ごすこととなった。
成長した兼定は、周りの人々に愛されることを渇望し様々な女性と浮名を流すようになった。本来惜しみない愛情を注いでくれるはずの家族を幼き日に亡くした彼は、誰よりも愛に飢えていたのである。
少しでも気になった女性には歌を贈り、その関心を誘った。美しく、歌の才にも恵まれた皇子に求愛されたとあってはそれに応えぬ女性などいなかった。共に夜を過ごせば寂しさに擦り切れてしまった胸は僅かに満たされていく。このまま彼女と愛し合い、結婚して家庭を築くのだろうと思って足繁く通うのだが、いつもその逢瀬は痛みを伴って終焉を迎えてしまう。
今まで兼定が関わりを持ってきた女性たちは、兼定の容貌の美しさや帝の子としての権勢を褒め称え、愛してきた。だが、兼定が求めているものはそのような表層的なものではなく、心の繋がりに他ならない。
容貌も権力も、両親から譲り受けたものであり、それらは兼定を構成する一部ではあるが核となるものではない。そんなものなど関係ない、ありのままの自分を愛して欲しい。女性たちに懸命にそう訴えるが、彼女たちの心を捉えているのは付属品ばかり。彼女たちが自分の求めているものではないと分かると、あっという間に気持ちは冷めていき、また次の相手を探す。
そうやって過ごすうちに、自分を真に愛してくれる者はいないのではないかという諦めが胸の内をゆっくりと絶望で満たしていく。
此度もまた、期待したような関係を築くことなく恋の炎は燃え尽きてしまった。いっそ暫くの間女性に関わるのをやめてみるのもいいかもしれない。そうすれば、自分に足りないものが分かるやもしれない。僅かばかりの希望を見い出し、兼定は内裏へと出仕して行った。
葵祭の準備のための会議で午前の時間が終わり、昼食を取りに家に帰ろうとしたところで一人の男に呼び止められた。
「よっ、和泉守。聞いたぞ、蔵人頭様の御息女と破局したそうじゃないか。今度は何が君の気に障ったんだ?」
男の名は鶴丸国永。兼定とは幼い頃より交流がある所謂腐れ縁というやつで、上流貴族の生まれにも関わらず下級官人や従者に対しても分け隔てなく気さくに接する、風変わりな男だ。身に纏う白い直衣が、その雪のような白い肌によく似合っている。
「……別に大した理由じゃねえよ、やれ父君や兄君の働きぶりを帝のお耳に入れて欲しいと強請られてうんざりしたので別れたまでさ」
「なるほどねえ……まぁ気持ちは分からんでもないが、彼女も家を代表して殿方とお付き合いし支えなければいけない立場なんだ、あまり恨んでやらないことだな」
「分かってるよ。別に恨むつもりもねえ。ただ元の何もない関係に戻っただけだ」
「そうか…そう言えば中庭の梅の木がちょうど見ごろと聞いたぞ、今から見に行こうじゃないか!」
多少なりとも気が沈んでいる兼定を気遣ってか、そんな提案を持ちかけてくる。いや、珍しいものが好きな鶴丸のことだ。ただ自分が見たいから付き合わせただけなのかもしれないが、有り難くその好意に乗ることにする。
鮮やかに咲く梅の花を見れば、心も些か落ち着きを取り戻せるはずだ。
鶴丸の言う通り、中庭では梅が実をつけて優雅に咲き誇り彩りを放っていた。悠然としたその姿に、重く沈んだ感情がゆっくりと癒されていくのを感じる。
よく見ると梅の木の周りに何人もの見慣れぬ顔が集まり、手に筆と紙を持って何やら話し合っていた。歌会でも開いているのだろうか。部屋の中で障子を開けて梅を見ながらというのではなく、わざわざ庭まで降りて来て歌詠みをするとは風流なことをするものだ。兼定の見知らぬ者ばかりということは、恐らく下級官人たちなのだろう。
そんなことを思っていたら、鶴丸が持ち前の快活さを発揮して彼らの輪に入っていく。
「お、こんなところで歌詠みとは優雅だねぇ。どうだい、俺たちも混ぜちゃくれないかな?」
「おい、なんでオレも勝手に数に入れてんだよ。第一いきなり押しかけたら迷惑だろ、そんな準備もしてねえだろうし」
「こういうのは大人数の方が楽しいだろう?筆なら書きつける時だけちょっと借りれば大丈夫さ」
そうやって鶴丸と押し問答をしていた所に、輪の中から一人の少年が歩み出て二人の隣までやって来た。
見たところまだ元服して間もない、せいぜい十三、四といったところだろうか。丸い頭は兼定の肩に届くかといった具合に小さく、首元から左右に跳ねた髪の毛がどことなく愛らしい。地味な出で立ちだが、くりくりと大きい目に整った鼻筋、淡く色づいた小さな唇は美少年と言っても差し支えない。
気遣わしげな目を震わせて、恐る恐るといった風に話し掛けてくる。
「あ、あの……筆と紙でしたら、予備のものがあるのでお貸しできます。……ただ、お二方に楽しんで頂けるような歌を詠めるか、と言われると難しいかもしれません。鶴丸様も和泉守様も、非常に素晴らしい歌の詠み手と伺っていますので」
「ははは、そんなこと気にしなくていいさ!こういうのは詠み手が楽しむことが大事なのであって、巧拙は二の次だと思うぜ?そうと決まったら早速詠もうじゃないか」
結局、鶴丸に押し切られる形で参加することになってしまった。まずは俺からと詠み始めた鶴丸は、あんなことを言っておきながら美しい響きの歌を詠んでみせた。周りの者たちもさすがだと驚きに満ちた表情で彼を讃える。
それは鶴丸に指名されて次に渋々と詠んだ自分も同様だ。名も知らぬ下級官人たち相手とはいえ、下手な歌を詠めば自分の名に傷がつく。それは偉大な父の名も汚しかねない行いだと自覚しているので、兼定は生まれ持った歌の才に驕ることなく日々その腕を磨いているのだ。幸い歌を詠むという行為を、兼定自身も好ましく思っている。
いつものように素晴らしい表現と技法だという賞賛の声を聞き、今日も満足いく歌が詠めたと安心したまでは良かった。
その後に続く彼らの歌は、お世辞にも上手いとは言い難い出来であった。鶴丸は一人一人にここが良かったとかここをもう少し違う表現にした方がいいと言った評論をかけていたが、兼定には到底そんな優しい気持ちにはなれなかった。こんなお粗末な歌会に参加するくらいなら、梅を見て高揚した気分のままさっさと帰れば良かったとさえ思う。
そんな不機嫌を隠さない兼定と目があった先ほどの少年は、不味いことをしてしまったと申し訳なさそうな顔をした後、皆に向けて声をかけた。
「あの、遅くなりましたが僕も詠みます!」
どうやら彼はまだ詠んでいなかったようだ。彼の仲間の惨状を見るに全く期待していなかった兼定は、つまらなそうにその姿をぼんやりと眺めていた。だがその期待は、良い意味で裏切られることとなる。桜色の唇から、滑らかに歌が紡がれていく。
春されば まづ咲く やどの梅の花 ひとり見つつや 春日暮らさむ*
(春になると庭に最初に咲く梅の花を、たった一人で見ながら長い春の日を過ごすことなどどうしてできましょうか)
今ここで皆と梅の花を見ているこの瞬間を何より慈しむ、彼の優しい心根が伝わってくる心地よい歌だった。今朝までのささくれだった気持ちなど、どこかに吹き飛んでしまったようだ。
「おお、これは驚いたな!まさに今こうして皆で梅の花を楽しんでいるこの時を大切に思う気持ちが伝わってくる、良い歌じゃないか!感動したぜ。君の名前を聞いてもいいかな?」
素晴らしい歌だった、そう伝えようとしたがその言葉が口をつく前に鶴丸に先を越されてしまったようだ。鶴丸の惜しみない賞賛の声に気恥ずかしそうに肩を竦めた少年は、おずおずと自分の名を口にした。
「あ、ありがとうございます……僕は、堀川国広と申します、喜んで頂けて何よりです」
「堀川か、よろしくな!まだ若いのにこんなに良い歌を詠めるとは将来が楽しみだな、和泉守もそう思うだろう?」
「ああ?……まあ、悪くないんじゃねえの」
本当は自分の心まで癒されるほど彼の歌は兼定に影響を与えたのだが、急に振られた言葉に素直に乗ることができずに素っ気ない返事になってしまった。堀川は気にしていないようだったが、兼定はどうしてかこのままで終わりたくないという衝動に駆られた。
ひとしきり詠んだということで歌会はお開きになり、鶴丸と兼定以外の者は午後からも勤めがあるため持ち場に戻るべく散って行く。
「さて、楽しい歌会も終わったということで昼飯にしようか。今日は俺の家でどうだい?仕事の話もしたいし、何より歌会の感想も語り合いたいしな」
「構わねえが……ちっと待っててくれねえか、すぐに済むからよ」
「お、どうかしたのか?」
鶴丸の返事を最後まで待たずに歩を進める。
背の高い兼定の足はすぐに襟足の跳ねた小さな背中に追いつき、彼の薄い肩を掴む。想像していた以上に頼りない肩が驚きにぴくりと跳ねる。振り返った堀川はまさか相手が兼定であるとは思わなかったのか、兼定と同じ蒼色の溢れ落ちそうなほど大きな目を見開いた。
「……和泉守様?あの、どうかなさいましたか?……もしかして、先ほどの歌会で何か粗相をしてしまったでしょうか?そうだとしたら、申し訳ありません!」
「いや、そんなんじゃねえよ……」
勢いで彼を引き止めたまでは良かったが、次の句が出てこない。どくどくと煩い鼓動が体の中に響き、思考を中断させてしまう。兼定がなぜ自分を引き止めたのか分からない堀川は、眉を八の字に下げて困った表情を浮かべている。
「すみません……せっかくの機会なので和泉守様ともっとお話ししたい気持ちはありますが、そろそろ仕事に戻らないといけないので……行ってもよろしいでしょうか?」
このままではせっかく作った堀川と話す機会が無駄になってしまう。焦った兼定は、自分でも予想しなかった言葉を口にする。
「今月の十一日に、オレのうちで歌会があるんだけどよ……お前も来いよ」
「……えっ、僕、ですか?」
「お前以外に誰がいるんだよ。十時から始まって、昼飯もうちで出すからよ。オレの家の場所は分かるな?分からねえんだったら迎えを寄越すが」
「あっ、いえ、もちろん分かりますが……そうではなくて、僕のような身分の者が和泉守様主催の歌会に参加させて頂くなんて、畏れ多いと言いますか…」
「んなもん関係ねえよ、お前の歌が聞きたくて主催者のオレが呼ぶんだ、誰にも文句は言わせねえ」
どうしたものかと暫く悩んでいた堀川だったが、兼定の意志が変わらないことを悟ると分かりましたと頷く。
「よし、決まりな。楽しみにしてるからよ、風邪引いたりするんじゃねえぞ?」
「はい、勿論です。お誘い頂きありがとうございます、ではまた当日にお会いしましょう」
晴れやかな笑顔を向けた後、足早に堀川は去っていった。勢いに任せて誘ってしまったが、彼の歌を気に入ったことも、もう一度聞きたいということも、そして大して仲良くもない貴族たちとの歌会が彼が来るというだけで楽しみになったことも本当だ。
鶴丸を待たせてしまったと慌てて振り返り戻ろうとすると、すぐ目の前ににやにやと笑った顔が見えた。
「珍しいこともあるもんだなぁ。和泉守が出会ったばかりの少年を自分が主催する歌会に誘うとは、明日は雨でも降るのかね?よほど堀川のことが気に入ったと見えるぞ」
心の中を見透かされたかのような言葉に、慌てて反論する。
「うるせえ、そんなんじゃねえよ!ただ、オレにおべっか使う奴らとの歌会なんざ疲れちまうから、一人くらい違った奴を誘っても良いかもしれねえって思っただけだ!」
「ははは、そんなにむきになると怪しいぞ?まぁ、そういうことにしておくか。俺も参加するから、楽しみにしてるさ」
鶴丸も参加することをすっかり忘れていたが、彼ならば歌の腕前も気遣いも申し分ない。仕方ねえなと呟きながら、二人帰路へとついた。
***
そうしてやって来た歌会当日。真面目にも朝早く出仕して仕事をこなしてきたという堀川は、十時丁度になろうかという時に現れた。
せっかく誘って頂いたのに遅くなって申し訳ないと謝る姿に、まだ始まっていないから安心しろと声をかけ、部屋に案内する。そこにはすでに何人もの招待客が歓談しながらも、互いの近況や人間関係を探ろうとする湿った空気が漂っており、始まる前から兼定は心が沈んでいく。
この歌会自体も好き好んで開いた、というものではない。帝の子である兼定と交流を持つことで己の出世に少しでも有利になりたい、という気持ちが明け透けに見える貴族たちにぜひと頼まれて断り切れずに開催したのだ。そんな兼定の気持ちを汲んで鶴丸が自分も参加しようと名乗り出てくれたことを、今更ながら有難く思う。
今日は忙しいであろう中で都合をつけてくれた堀川も来たのだ、いつもよりは歌を詠むことを楽しみ良い一日だったと振り返れるに違いないという期待を胸に、開始の音頭をとった。
時刻はもう少しで夕方の四時になろうというところで、会は終了を告げた。次の開催も楽しみにしております、と張り付いた笑顔で機嫌をとる貴族たちを見送り、他に残った者がいないことを確かめると、初めて会った日と同じように兼定は国広を引き止めた。
「今日はありがとうございました。個人のお宅で開かれる大規模な歌会は初めてだったので緊張しましたが、とても良い経験になりました」
「そりゃあ良かったぜ。……だがな、お前本気出して歌を詠んでなかったろ?せっかくお前の歌を楽しみにしてたんだからよ、手ぇ抜くなんてしてくれるなよ」
「……手を抜くだなんて、そんなことしていませんよ。この間はたまたまいつもより良い歌が詠めただけで、これが本来の僕の実力です。期待して頂いたのにお応えできずにすみません」
「……あの後気になったからお前の上官や同僚にお前のことを聞いてみたが、皆口を揃えて素晴らしい歌の腕前だって褒めてたぜ」
「え、えーと……そうなんですね……」
大方気を遣って周りに合わせた形で歌を詠んだのだろう。この前の堀川の連れほど酷くなかったとはいえ、今日の招待客のほとんどが兼定や鶴丸、堀川には及ばない実力だ。
そんな中で下級官人の自分が目立つようなことがあってはいけない、と心配りをする辺りがこの少年の気配り上手で心優しいところだ。前回実力を発揮したのだって、つまらぬ歌にすっかり退屈した兼定を少しでも楽しませそうと思ってのことだろう。
全く、兼定よりもずっと若いだろうに大したものである。
「お前の気遣いができるところはオレも気に入っている。でもな、オレはお前の歌が好きで誘ったんだぜ?次はちゃんと本気出してくれよな」
「わ、分かりました……あ、次、も呼んで頂けるんですか」
「おう、聞けばお前漢学にも秀でてるそうじゃねえか。オレも漢学を学ぶのは好きでな、今度うちでじっくり話したいと思ってるんだが、いいだろ?」
「……和泉守様にそう言っていただけるなら、僕なんかで良ければぜひ」
「お前なんか、じゃなくて、お前がいいんだよ。……あと、その和泉守様っていうのも堅苦しいからやめろよな。オレはお前のこと友人だと思ってるんだから、もっと気さくに話してくれよ」
「友人、ですか……僕と、和泉守様が」
「身分の差がーとか言うのは無しな、そんなつまんねえこと気にするほど心狭くねえからよ。それとも、お前にとってはオレなんてまだ親しくない他人か?」
「そんなことありません!親しくさせて頂いて……いえ、親しく思っています。こんな僕ですが、よろしくお願いします、兼定様」
「もう一声。様はいらねえよ、他の奴らの前ではちょっとって言うならオレたち二人の時だけでもいいからよ」
「……じゃあ、兼さんって呼んでもいいですか?」
「おう、いい響きじゃねえか、気に入った!オレはお前のこと国広って呼ぶからな」
「はい、兼さん!今日、呼んでもらえて嬉しかったです。またお話ししましょう」
沈みゆく夕日に照らされた国広の姿が段々と遠くなって、人々が忙しなく行き交う街並みに消えていく。思えば友人と呼べる存在は幼少の頃よりの仲である鶴丸を除けば兼定にとって初めてである。
親しい友ができたというのはこんなにも心を弾ませるのかと驚いた兼定は、まるで童のように次に国広に会う日を待ち望んでいた。
その日をきっかけに、兼定は国広との親交を深めていった。
歌や文筆に優れた十六の少年(思ったより年長で驚いた、と言った際はひどいですと怒られてしまったが)は、その才能を見込まれて外記に任ぜられ忙しい日々を送っているようだったが、兼定が誘いをかければ人懐っこい笑顔で喜び時間を作ってくれた。
兼定の家に呼んで本を手に漢文や歌の解釈について語り合ったり、題目を決めて歌を作り互いの腕を磨いていく時間は何よりも自分の心を弾ませた。最初は畏まった所が抜けきらなかった国広も、徐々に打ち解けて今ではすっかり旧来の友のように砕けて接してくれるようになった。
勉学に励む利発な少年との交流は兼定に新たな気付きを与え、兼定もまた国広に自分が学んできた知識を惜しみなく伝えていく。国広と出会う前はどのように日々を過ごしていたか忘れてしまうほど、彼との時間は兼定の生活に彩りをもたらしてくれた。
一度、たまには自分の家ではなく国広の家に行ってみたいと申し出た時、彼は珍しく浮かない顔で黙ってしまった。もちろん無理にとは言わないが、国広がどんな家で生まれ育ったのか見てみたいのだと正直に話すと、ぽつぽつと今まで口にしなかった彼の家の事情を教えてくれた。
国広の祖父は学者としての才を認められて立身したひとかどの人物であったが、その実力を妬んだ者たちによって謀られ、その地位は剥奪されてしまい一族は没落したという。汚名を返上することなく祖父は病死し、国広の父は祖父の権力を頼みにしていたため、遺された母子を見限って屋敷への通いは途絶えてしまった。愛する父の死と夫の裏切りに絶望した母もまた、程なくして病死してしまう。親しい家族を失った国広は酷く悲しんだが、厳しくも優しい祖母と二人で慎ましく暮らしているうちにいつしか心の傷は癒えたのだった。
祖父の遺した蔵書で勉学に励み、こうして兼定と知り合って仲良くなれたのだから感謝しているのだと穏やかに微笑む顔には、その悲しい境遇など微塵も感じさせなかった。
それならば家を訪ねても問題ないだろうと言うと、国広の給金だけでは手伝いの者を雇うことも難しいため、手入れもままならず寂れた広い屋敷に二人だけというもの哀しいところを見られたくないのだと返ってくる。
そんなことは全く気にしないと押し切って訪問すれば、兼定は彼と彼の祖母に手厚くもてなされた。もちろん客観的に見れば普段兼定が他の貴族の家で受ける豪奢を尽くした歓待には遠く及ばないのだが、堅苦しい気遣いのない温かさを感じる雰囲気の中食べた祖母と二人で作ったという手料理は、不思議と兼定の舌に染み渡るような優しい味がした。
すっかり堀川家を気に入った兼定は、頻繁にその門を叩いてはささやかだが楽しい時間を過ごすようになった。
そうして兼定が国広と出会ってからもうすぐ一年の歳月が経とうという頃だった。
国広を愛しみ育て、また兼定のこともまるで自分の孫のように接してくれた祖母がこの世を去ったとの知らせが舞い込んだ。冬の寒さに体調を崩しがちだったことは知っていた。兼定も少しでも温かく過ごせるようにと上等な衣を贈り、ありがとうねと感謝された日は記憶に遠くない。春の訪れはすぐそこだったというのに、それを見ることなく逝ってしまった彼女との思い出を反芻すると、自然と涙が流れていた。
唯一の家族を失った国広は、一体どれほど辛い思いをしているのだろうか。きっと誰にもその辛さを明かすこともなく、一人あの広い屋敷で悲しみに暮れているのだろう。
その寂しい背中を想像して居ても立っても居られなくなった兼定は、少しでもその悲しみを自分が和らげることができたらと思い彼の職場を訪れるが、どうやら喪に服すために出仕していないようだ。肝心な時に国広の役に立つことができない我が身が恨めしい。
会いたいという切実な気持ちをなんとか己のうちに押し留め、喪が明ける日が分かったら教えてほしいという手紙を従者に託し、兼定は国広に会う前の変わり映えない日々を鬱屈と過ごすこととなった。
桜が間も無く満開となり見ごろを迎えようかという時に、ようやく国広から喪が明けたため今日から出仕しているとの知らせが届く。早速彼の顔を一目見ようと仕事場へと向かうと、いつもの小柄な姿を捉えた。
「……っ国広!……その、ばあちゃんのこと、残念だったな。もうあの笑顔も見れねえし声も聞けねえと思うと、すげえ寂しいわ」
「兼さん、……ありがとう、そう思ってもらえて祖母もきっと喜んでいると思います」
切なげに笑う姿は、最後に会った時と比べて少しやつれてしまっている。どれほどの悲しみを抱えて日々を過ごしてきたのかがそこから垣間見え、彼をこれ以上一人にしてはいけないと焦る気持ちが口をつく。
「喪が明けたばっかで悪いけどよ、三日後の昼にオレの家で花見の宴を開くことになってるんだ。良かったら参加しねえか?……いや、違うな。参加して欲しい、お前に」
「……うん。ありがとう、せっかくだからお邪魔させてもらおうかな。兼さんのおうちの桜はすごく綺麗だって、前に教えてくれたものね」
兼定の気遣いに気付いたであろう国広は、快く承諾してくれた。元々花見の宴を開くことは決まっていたが、国広が来てくれる以上はなんとしても心安らぐような一日にしたいと思い、兼定の意識はすっかり三日後の花見のことで一杯になった。
***
あっという間に時は流れ、花見の日の当日。いつかの歌会の時のように仕事を終えて約束の刻限丁度にやって来た国広を、兼定はこれ以上ない程の歓待でもてなした。
酒が呑めない国広のために今までの交流の中で知りうる限りの好物を用意させ、桜の一番よく見える席に彼を座らせた。自分には勿体無いと固辞する彼に納得してもらうのは些か大変ではあったが、最後にはありがとうと申し出を受け入れてくれて安堵する。
目を細めて桜の散る様を見つめる横顔は、三日前と比べれば普段の色を取り戻しつつあるようだった。
夕刻になり宴はお開きとなり、先ほどまで賑やかな声で満たされていた部屋は静寂に包まれている。他の客と共に帰ろうとした国広の腕を掴み、夜桜もまた格別に美しいから付き合えと縁側に座らせる。顔を出し始めた夜の帳がひらひらと舞う桜の花弁を縁取っていく。
しばらくの間、互いに話すこともなくただ静かに闇に沈んでいく空と庭を彩る桜をぼんやりと眺めていた。会えない時間が長かったからか、こうして隣に座っているだけで兼定の心は温かい気持ちで満ちていた。きっと国広も、少しばかりはそう思ってくれているはずだ。言葉など交わさずとも、通じ合うものが確かにそこにはあった。
どれほど経った頃だろうか、ようやく国広が口を開く。
「今日はありがとね、兼さん……一人でいるとどうしても辛い気持ちばかり頭をよぎるから、こうして楽しい所に連れて来てもらってすごく助かったよ。兼さんの言っていた通り、とっても綺麗な桜だね……昼間の明るい中で見るのも良いけど、夜に見るとまた違った顔になるなんて素敵だなぁ」
「礼を言われることのほどでもねえさ。大事なやつが辛そうにしてたら、誰だって力になりてえと思うだろ?お前の気持ちが少しでも楽になったっていうなら、それで十分だ。……この桜にはオレも昔、母上が死んで悲しかった頃に慰めてもらったことがあってよ。きっとお前のことも癒してくれんじゃねえかな、って思ったんだよ」
「そう、だったんだね…兼さんはすごいね、お母様も、お祖父様とお婆様も小さい頃に亡くなられて、それでも悲しみに潰されることなく立派に成長して。……ちょっと自分が情けなくなっちゃったな」
「んなことねえよ。勿論その時は悲しかったけど、今のお前の方がばあちゃんと一緒の思い出がたくさんある分、辛さも大きいのは当然だ」
「……僕、おばあちゃんが死んでしまって、これで本当に一人ぼっちになっちゃったんだなって思って、寂しくて、苦しくて……でも、違ったね。僕には、こうして辛い時に側にいてくれる兼さんがいる。そんなことも忘れて、一人で殻に篭ってしまっていた。……僕は、兼さんと出会えて、本当に良かった。……ありがとう、兼さん。あなたの存在がどれだけ僕を支えてくれているか、どうしても伝えたかったんだ」
すっかり暗くなってしまった中で表情ははっきりと見えなかったが、震えながらも真剣に兼定に気持ちを伝えようとする声と、微かに闇の中できらりと光った雫から、国広が涙を流していることを悟る。
出会ってから一年、国広が泣いている所を見るのは初めてだ。その涙に兼定の心は激しく動揺する。国広には泣き顔なんて似合わない。にこにこと笑っている姿はいつだって兼定の心を安らげてくれるのだ、そう思った時には兼定の腕は自然と国広の顔に伸びて、その眦から流れる水滴を拭っていた。
「馬鹿、泣くんじゃねえよ。……お前の役に立てたなら良かった。寂しい時は遠慮なく頼れよな。その代わり、オレもそうなった時はお前に頼らせて欲しい。いいだろ?」
「……うん、勿論。兼さんには貰ってばっかりだから、僕にもお返しさせて欲しいな」
「そんなことねえよ。こうして夜桜見物に付き合ってくれるだけでも、十分オレだって貰ってると思うぜ?……じゃあそうだな、ここで一つ、桜の歌でも詠もうじゃねえか!それで貸し借りなしってことで」
「ええっ、そんなことでいいの……?……分かった、兼さんに負けないくらい良い歌を詠んでお返しさせてもらうね!」
「上等だ!お前を驚かせる歌を詠んでやるからな!」
兼定の提案で湿っぽい空気もすっかりなくなり、我ながら良いことを思いついたもんだと心の中で自賛する。自分から言い出したからには、国広にとびきりの歌を贈らなければと思考を切り替えた。
「よし、できた!オレからいかせてもらうぜ?」
「もうできたの?さすが兼さん、早いね!……拝聴させて頂きます」
国広がこちらに体を向け、瞳を輝かせながらオレの句を待っていることが宵闇の中でも伝わってくる。一呼吸置いてから、詠み始める。
世の中に たえて桜の なかりせば 春の心は のどけからまし*
(世の中に桜というものがなかったならば、春になっても桜の花の咲く楽しみや散る悲しさなどに心騒ぐこともなく、のどかな気持ちでいられるでしょうに)
「……なるほど、確かにそうかもしれない。桜が好きな兼さんが詠んだからこそ、深みを感じる良い歌だね」
「まぁな、好きだからこそ良くも悪くも気持ちが揺さぶられちまうもんだなと思ってよ」
「……ねえ兼さん、僕の歌はこの歌に対する返歌でも良いかな?」
「……ほお?そりゃあ楽しみだな、聞かせてくれよ」
散ればこそ いとど桜は めでたけれ 浮き世になにか 久しかるべき*
(桜は散るからこそ素晴らしいのです。この憂い多き世の中でいつまでも変わらずにいられるものはありません)
この世に変わらないものはない。きっと最愛の祖母を亡くしたから今だからこそ、詠めた歌なのだろう。桜だけではなく、人間も皆いずれは死にゆく生き物だ。だからこそ、人は誰かを愛おしいと思わずにはいられないのだ。
「……中々良いものが詠めたと自分では思ってるんだけど、どうかな?」
「このオレに返歌してくるんだ、よほどの出来じゃなかったら揶揄ってやろうと思ったが……良い歌だな。桜も、人間も、限りがあるからこそ今を咲き誇る姿は美しいんだろうな」
「……うん。だからこそ、人は桜を愛でるし、人を愛するんだろうね」
ゆったりとした時が流れる。悲しい顔を見たくない、限りある時間の中で自分の側で笑っていて欲しい。それが恋なんだと気づけば、すんなりと自分の心の中に入ってきた。
自分は、国広に恋をしている。今まで沢山の女性と関係を持った時は、こんな気持ちにはならなかった。今思えば、あれは恋と呼べるものではなかったのだろう。兼定はとにかく愛が欲しかった。だから徒に女性たちに歌を贈っては愛を求めた。愛して欲しいと強請るくせに、自分から人を愛したことなどなかった。彼女たちもそれを見抜いていたからこそ、兼定を愛してはくれなかったのだろう。本当に愚かだった。
国広を何より愛おしく思うからこそ、此度ばかりは間違えたくはない。
「大分遅くなってしまったから、そろそろお暇するね」
「悪いな、こんな時間まで付き合ってくれてよ」
「ううん、楽しい時間をありがとう。……そうだ、兼さんに一つ伝えなければいけないことがあるんだ」
先ほど国広への想いに気付いた兼定は、もしかすると国広も自分のことを想ってくれてそれを伝えてくれるのではないかと僅かに期待してどきりとしたが、国広の口から出てきた言葉はそのような甘い考えを打ち砕いた。
「実は、もうすぐあの家を出なければいけなくなったんだ」
「……は?どういうことだよ?」
「……僕も出て行きたいなんて思ってないよ。あの家は僕のおじいちゃんが亡くなった後におばあちゃんに所有権が移っていたんだけど、おばあちゃんが亡くなったことで僕の父にその権利が移ることになって……」
「……っな、なんでだよ?お前の親父さんはあの家にもう十年近く来てないんだろ?今更どこにそんな権利があるっていうんだよ」
「どうやら、結婚する時にそういう約束を結んでいたみたいでね…ちゃんと証拠となる書類も出されてしまった以上、父のものだということは覆らない。……取り壊して、土地をどこかの貴族の方に売却することまで決まっているって言われた」
「そんな理不尽なことあっていいのかよ……そうだ、オレから父上に頼んでなんとかならないか聞いてみるから」
そう言い切る前に、珍しく国広が声を荒げる。
「それは絶対に駄目だよ!!こんなことに帝のお手を煩わせるわけにはいけない。……何より、僕は兼さんとは対等な関係でいたいんだ」
「……国広」
「……偶に言われるんだよね、兼さんと仲良くしているのは出世のためだろう、って。……身分の違いはどうしようもないけど、そんな風に思われるのは辛いんだ」
「お前がそんな奴だって思ったことなんて一度もねえよ」
「うん、ありがとう。……でも、僕のためにそこまでしてくれたら、きっと兼さんは僕に利用されたんだって口にする人が出てくると思う。僕がなんて言われようと構わないけど、兼さんのことを悪く言われるのは嫌なんだ」
自分が苦境に立たされている時でさえ兼定のことを思ってくれる国広が愛おしい。なんとしてでも力になりたいと思っているのに、そうすることすらも彼の心を痛めてしまうというならば、どうすればいいのだろうか。
「……あの家を出たら、お前はどこに行くんだ」
「父の正妻の方の家に小さな離れがあるから、そこに住まわせてもらうか、大学寮で寝泊まりする部屋を貸してもらうことになるかな。…どちらにせよ、今までのように兼さんと会うのは難しくなるかもしれない……ごめんね」
――国広と会えなくなる。その言葉に、兼定の覚悟は決まった。これから先国広のいない生活など考えられない。人の生は存外短いのだ、迷っている時間など惜しい。
「……お前、この数日で宿直の当番はあるか?」
「え?……ないけど、それがどうしたの?」
「明日の晩、お前の家に行く。話したいことがあるんだ。……今日はもう遅いから帰りな、それともうちに泊まってくか?」
「そ、それは大丈夫だよ、子どもじゃないんだからちゃんと帰れます!……明日の夜だね、分かった。おやすみなさい、兼さん」
「あぁ…おやすみ、国広」
月が二人を優しく照らしている。どうか国広に自分の想いが伝わるようにと月に祈りながら、兼定は床に着いた。
次の日は、国広に自分の気持ちを伝えることで頭が一杯になり、仕事にも中々身が入らなかった。(こんなところを見られたら、駄目だよ兼さん、なんて叱られちまうな。)
仕方なく、今日だけは許して欲しいとばかりに足早に内裏を後にする。すぐにでも国広の家に向かいたかったが、彼はまだ仕事場でせっせと働いている頃だろう。逸る気持ちを気力でなんとか落ち着けて、夕日が沈みゆく頃合いに出発した。
いつもなら何も考えず気軽に叩いていた門戸も、今日に限ってはこれから先のことを考えて思わず手が震えてしまう。大丈夫だ、己の気持ちをはっきりと伝えれば、国広だって考えてくれるはずだと勇気を奮い立たせ、鼓舞するように門を叩く。すぐに馴染みある姿がひょこりと扉から顔を出し、兼定を迎えてくれた。
「早かったかもしれねえと思ったが、大丈夫だったか?」
「うん、ちょうどさっき帰ってきたところだよ。今、お茶を持ってくるから待っててね」
そう言って立ち上がりかけた国広の腕を、強い意志を持って掴む。
「……えっと、どうしたの?ちょっとお茶を淹れて来るだけだよ?」
「……いらねえ。オレは今日お前んちに茶を飲みにきたわけじゃねえからな。座ってオレの話を聞いて欲しい」
いつになく真剣な表情で見つめる兼定の表情に国広は驚いたようだが、すぐにその場に座り穏やかな瞳で見つめ返す。
「分かった。……まさかとは思うけど、昨日のお父君に僕の家のことを相談するって話じゃないよね?そのことなら本当に大丈夫だから」
「ああ、違うから安心してくれ。……国広、今日から三日間、毎晩お前の家に通う。明後日にその約束を果たしたら、オレと恋仲になって欲しい」
「……え?」
想像もしていなかったであろう兼定の言葉に、国広は目を大きく開けて固まってしまった。それはそうだろう。友人だと思っていた男にこんなことを言われたら、誰だって驚くに違いない。
男女の結婚の際は男が女の家に毎夜通い、三日目の夜に餅を食べることに倣っての約束だ。自分達は男女ではないが、兼定にとって一生の相手となりたいのは国広に他ならない。だからこそ、自分の気持ちが本物であるということを三日かけて証明して見せようと思ったのだ。
「オレはお前のことが好きだ。友人としてでなく、恋人として一生を添い遂げたいと思ってる」
「……そ、そんなこと、できないよ……」
「……なんでだ?オレが男だからか?オレと恋仲になるなんて考えたこともなかったか?なら、この三日間で考えて欲しい。オレは残りの人生、お前と一緒にいたいんだ。オレがどれほどお前を愛しているか、三日かけて伝えてみせるから」
「……そもそも兼さんが僕なんかと恋仲になるなんて、許されるはずないよ。周りの方にだって絶対に反対される。兼さんは帝のご子息なんだから、ちゃんとした家の女の人と結婚して、子供に恵まれて、幸せになるべきなんだ」
「オレの幸せはオレが決める。そしてそれはどこの誰とも知れない貴族の女と結婚して子供を作ることじゃなくて、お前と一緒にいることだ。身分なんて関係ねえ、見てくれや権力やらじゃないオレ自身を見てくれる国広のことが好きだから、一緒にいたいんだ。第一、跡継ぎにもなれないオレが子供なんて作っても争いの種になるだけだ、そんなこと気にする必要もねえよ」
「……」
「……国広。お前に会えない間、気づいたらずっとお前のことばかり考えてた。悲しんでいるだろうお前のために何もできない自分が、悔しくてたまらなかった。また会えなくなるなんて、オレは嫌だぜ。オレは、生まれて初めて誰かを愛するってのはこういうことなんだって思い知った。この気持ちに気づいたからには、もうお前とただの友人には戻れない」
「……兼さんの気持ちは、すごく嬉しい。でも、今は良くてもきっと後悔すると思う」
「未来のことは分からねえ。でも、今ここでお前に気持ちを伝えない方が絶対後悔するだろうってことは間違いねえな」
「……ずるいな。そんなかっこ良い事ばっかり言うんだもん」
「知らなかったのか、オレは都でも随一のかっこ良い男だと評判だぜ?……一気に色々と伝えて悪かった、お前を困らせたいわけじゃねえんだ。オレの気持ちに対する返事は明後日で良い。でもちゃんと明日も来るから、待っててくれ」
「……気が変わったら、いつでも言ってね。僕、平気だから」
「オレを舐めるなよ、そんな生っちょろい覚悟でお前のこと好きになってねえからな。……今日のところは帰る、また明日な」
「……うん、また、明日」
まだ信じられないとでも言うような複雑な表情を浮かべながら、牛車に乗り込む兼定を国広は見送ってくれた。
「おっと、忘れるところだったぜ。……これ、お前に気持ちを伝えたくて詠んだ歌なんだ。形に残るものを渡さないと、今日のことは夢だったなんて思われちゃ敵わねえからな。目の前で読まれると流石に恥ずかしいからよ、オレが見えなくなったら読んでくれ」
そう言って想いのこもった歌を書きつけた紙を少年の手に握らせる。これを読んで国広はどう思ってくれるだろうか。少しでも想いが伝わることを願い、今度こそ屋敷を後にする。
告白の緊張から解放された心臓は、ようやく鼓動を落ち着かせる。国広に自分を想って眠りについて欲しいと思いながら、揺れる牛車の中で目を閉じた。
昨日とはまた違った緊張に包まれた心を落ち着かせるために一呼吸置いた後、兼定はゆっくりと門を叩く。会いたくないと言われてしまったらどうしようかと気持ちが陰るが、また明日と返事をしてくれたことを思い出して、なんとか平静を保つ。少し気まずさを滲ませた顔で、国広が扉を開けてどうぞと招き入れてくれる。
床の間に案内された兼定は、何か話したいけどどう切り出せば良いのかと迷うような視線を向けてくる国広をじっと見守る。しばらくして、ようやく国広が口を開いた。
「……今日も、来てくれたんだね。忙しいのにごめんね」
「何言ってんだ、オレから言い出したことなんだから当たり前だろ?例え嵐が来ようが這ってでも来てやらぁ」
「兼さんなら本当にやりかねないからなぁ……歌、読んだよ。ありがとう、すごく素敵な歌だね。読んだ後、気づいたら胸が温かくなってた」
そう言って昨日手渡した紙を取り出し、照れたように微笑んでくれた。
きみにより 思ひならひぬ 世の中の 人はこれをや 恋といふらむ*
(あなたによって思いというものを学びました。世の中の人は、これを恋というのでしょう)
国広への想いを浮かべたら、驚くほどするすると筆が進みこの歌ができた。嘘偽りない、兼定の気持ちをまっすぐに表現した歌だ。誰かを愛おしいと思う気持ちは、間違いなく国広によって教えてもらったものだ。
よく見ると、手の中の紙は昨日と比べてしおれてしまっている。まるで濡れてしまった後に乾いたような――そこまで気づいた時、国広が涙を流しながら読んだことを悟る。その涙は、嬉し涙なのだろうか、いや、そうであって欲しい。
「……んで?返事は明日で良いって言ったけど、そんなもん必要ないってなら今日聞かせてくれても良いんだぜ?」
「……ごめん、もう少し気持ちを整理する時間をくれないかな。僕も歌で気持ちを伝えられたらと思ったんだけど、うまくまとまらなくて」
「ああ、分かった。お前が真剣にオレとのことを考えてくれてるならそれだけで十分嬉しいさ。オレの気持ちは変わらない。だから、明日もちゃんと来る。……その時には、返事を聞かせてくれ」
「うん、分かったよ」
「……国広」
「……どうしたの?」
「愛してる。……おやすみ」
そう耳元で囁くと身を翻して屋敷を後にする。兼定の言葉が耳に届いた瞬間国広の顔が真っ赤に染まるのが見えた。その愛らしい反応をじっくり見たいと後ろ髪を引かれる気持ちはあったが、きっと兼定も顔も同じくらい赤くなっているであろうことは、顔から感じる熱からして間違いない。
情けない顔を見られまいと逃げるように去ってしまったことを少し後悔したけれど、また明日会えるんだと思えばすぐにその後悔も消えていった。泣いても笑っても、明日国広は兼定への返事を用意して待ってくれているのだ。それがどんなものであろうと受け入れようと決心し、家への道を急いだ。
次の日は昼前から雨が降り出し、どうか夜までには止んでくれと祈りながら政務に励んだ。しかし、そんな兼定の切なる祈りを嘲笑うかのように雨足は強まり、夕刻には風も吹いてきてついに嵐となった。
昨日あんなことを言ってしまったのが良くなかったのかと自省しながらも、今日ばかりは天気を理由に家で呑気に過ごすわけにはいかないのだ。こんな天気で今から出かけるのかと諌める従者に丁寧に詫びを入れ、なんとか牛車を走らせてもらう。
しばらく揺れたところで、その歩みが止まる。どうしたのかと声をかけると、なんとこの嵐で橋が崩れてしまったのだという。見れば確かに目の前の橋は無惨にも中途で破壊され、どう頑張っても渡ることは難しそうだ。二つに裂けた橋が自分たちの未来を暗示しているようで、首を振ってその考えを頭から振り払う。
都のはずれにある国広の家には、この橋を通らなければかなり遠回りとなってしまう。それでも、このまま諦めて家に帰るわけにはいかないのだ。三日間通って自分の思いを示すと告げたのは、他でもない自分だ。覚悟を決めた兼定は、牛車を降りると従者が止めるのも聞かずに己の足で国広の家に向けて駆け出した。
幾度も水たまりに足を取られそうになりながら、それでも兼定は一度も立ち止まることなく走り続けた。
息を切らしながらも、兼定はようやく国広の家を視界に捉えた。すっかり濡れ鼠となってしまった体は冷たくなってしまったが、心は燃えさかる炎のように熱い。風で開いてしまったままになっている門を急いでくぐろうとした時、小さな影が見えてあっと思った瞬間にはぶつかっていた。よろめく肩を慌てて支えると、それは誰よりも会いたかった想い人であった。
「す、すみません!……っあ、兼さん……!」
「よお、国広。こんな天気でどこに出かけるつもりだ?ちゃんと行くっつったろ、待っててくれねえと困るぞ?」
揶揄うように笑って言葉をかける兼定とは対照的に、国広は必死の形相をしており、その目にはぽろぽろと涙が溜まってはこぼれ落ちてゆく。
「っ兼さん……!良かった、無事だったんだね……橋が崩れたってさっき近所の人が話しているのが聞こえて、僕、ここに来る途中で事故にでも巻き込まれてしまったんじゃないかって思って……僕がもっと早く気持ちを伝えていれば、こんなことにはならなかったのにどうしようって、居ても立っても居られなくて……ごめんなさい……!」
言い終わるや否や、その細い腕を懸命に兼定の背中に回して抱きついてくる国広を、しっかりと二本の腕で抱き止める。堰を切ったように、国広が想いを言葉に乗せて紡いでゆく。
「兼さんっ……僕、兼さんのことが、好きです。もし兼さんが死んでしまって、二度と会えなくなってしまったらって想像したら、胸が苦しくてたまらなかった。僕に会えなくなるのは嫌だって言ってくれた兼さんの気持ち、ようやく分かったよ……ずっとずっと、好きでした。それに気付くのが遅くなってごめんね……」
「オレがお前を遺して死ぬわけねえだろ……でも、ありがとな。お前の気持ちが聞けてすげえ嬉しい。大好きだぜ、国広」
轟々と降りしきる雨の中、ゆっくりと体を離す。兼定を見上げる顔は涙に濡れていたが、その瞳は幸せの色を纏っている。そのことが嬉しくて、ゆっくりと弧を描いた唇に口付けた。
***
ずぶ濡れになって意味をなさなくなった着衣を脱ぎ捨てた兼定に、兼定の体格に合う替えの着物がないのだと慌てた国広を捕まえて、その濡れた衣服を剥ぎ取る。互いに一糸纏わぬ姿になったことに動揺しながらも、なんとか顔を赤らめながらこれで体を拭いてと布を差し出してくる姿に、逸る鼓動は止まりそうもない。
乱暴に髪と体を拭くと、兼定が力を込めれば折れてしまいそうな身体を茵の上に押し倒す。
「……っか、兼さん、ま、待って……そのままじゃ、寒いでしょ……」
「三日も待ったんだ、もう待てねえよ。それに……」
赤く色づいた耳に口を近づけて息を吹きかけながら、そっと艶かしく囁く。
「お前が温めてくれるんだろ?」
「……っ!!」
息を呑む音を感じながら、国広の唇に己のそれを重ねる。蕩けてしまうのではないかと思うほど柔らかい感触を味わいながら、二度、三度と角度を変えて口付けてゆく。
強ばった体から徐々に力が抜けていくのを見て安心すると、舌で唇をなぞるように愛撫する。甘ささえ感じるそれを、ねっとりと心ゆくまで舐めていく。呼吸をしようと薄く開かれた口の中に、すかさず舌を捩じ込む。びくんと跳ねた顔を片手でそっと包み、口の中で縮こまっていた国広の舌に自分のものを絡ませて舐めとった。
「……っふ……!」
僅かに溢れる声に体が熱くなっていくのを感じる。捕まえた舌に吸い付くと、兼定の肩に添えられていた手に力がこもるのが分かる。
心から愛する人との口付けがこんなにも己の身も心も昂らせるということを、兼定は初めて知った。その甘い唾液をもっと味わいたくて、歯列をなぞり咥内を余すところなく舐め回していく。
最初はされるがままだった国広も、少しずつ自分から舌を使って兼定の舌を啜ってくる。拙くも懸命に兼定に応えようとするその動きに国広も自分を求めているのだと感じ、夢中で呼吸すらも奪うような深い口付けを交わしていく。
流石に苦しくなったのか国広が頬を包む兼定の手を掴んできたので、名残惜しい気持ちを抑えて唇を離す。二人の舌を繋ぐ唾液がつうっと糸を引いて光るのが見えて、堪らなく唆られる。
必死に息を吐いて呼吸を整える国広の首筋にそっと口を押し付けると、一気に強く吸い上げる。兼定の舌が首筋を這う度に、その小さな体がびくりと震えて吐息が零れる。
何度も吸い付いた後にようやく唇を離すと、その白い首筋にはいくつもの紅い痕が浮かび上がっており、己の中の独占欲が満たされていくのを感じる。この透き通るほど白く柔い肌に触れて良いのは自分だけなのだ、と。
指でその痕をなぞりながら、滑るように鎖骨へと触れていく。手のひらに吸いつくような肌は触れているだけでも心地良い。ゆっくりとその手は鎖骨の下に降りていき、胸元に飾られている二つの突起に辿り着く。
「あっ……かねさっ、んんぅっ……」
突起を弾き、指の腹で押しつぶすように捏ねていくうちに、乳頭がぷっくりと膨らんでくる。美味しそうに実った果実のそうなそれを満足気に眺めた後、尖って主張を始めた先端に舌を這わせる。優しく舐めとられるだけで、国広の呼吸が乱れていく。舌先でちろちろと乳頭を舐めてから乳を求める赤子のように乳暈ごと吸いつくと、我慢できずに声が漏れてくる。
「ぁあっ……うっ、かねさん、それ、やだっ……はぁ……っ」
乳首を弄られて感じていることが恥ずかしいのか、それとも初めての快楽に身体がついていかないのか、潤んだ瞳から涙がはらりと落ちる。その雫を指で掬いとりながらも、痛々しいほど尖った乳頭に吸い付き舐め回す舌の動きは止まらない。
ぷくりと腫れた粒に噛み付くと、痛みさえも快楽として拾い上げた身体が弓なりに反って震え上がる。まるで兼定にもっと弄ってほしいと言わんばかりの体勢に、一層激しく頂きを舐め啜る。
すっかりと兼定の手によって快楽を生む淫粒となった胸飾りは、てらてらと兼定の唾液で濡れて淫猥な色を浮かべている。その姿に嬉しそうに目を細めると、そっと脇腹を上から下へとなぞっていく。擽ったさに捻られようとした腰を手で優しく押さえると、すでに腹につきそうなほど上を向いているその小柄な体格に見合った大きさの陰茎に触れる。
「すげえな……口と胸だけでもうこんなに勃っちまってるぞ?」
「……えっ、嘘……」
まさか触れられてもいないのに立派に勃起しているとは思っていなかったのか、先ほどまで快楽に揺れていた瞳が見開かれる。羞恥に耐えかねて顔を覆い隠そうとした手を掴み、茵の上に押さえる。
「ちゃんと見ろよ、オレの手で気持ち良くなってるお前の姿。……好きなやつと肌を合わせてこうなるのは当たり前だ、オレだって今すげえ気持ち良いぜ」
「で、でも……変、じゃない?」
「全然。お前の気持ち良さそうな声、もっと聞きたい。……だから、我慢なんてするなよ」
宥めるように言い聞かせると、大きな手でそっと陰茎を握り込む。可愛らしい大きさのそれは兼定の手の中にすっぽりと握り込まれてしまい、脈動していることが肌を通して伝わってくる。自分の手によって国広が高まり感じているということがたまらなく光悦を誘う。
ゆっくりと上下に擦っていき徐々に力を込めて扱けば、快感に腰が持ち上がる。裏筋に指の腹を当ててぐりぐりと刺激すると、快楽に我慢できなくなった唇から嬌声が漏れる。
「ぁああっ!そこ、っだめぇ……きもちい、…から……っ!」
「国広……可愛いな。もっと声、聞かせてくれ」
亀頭に指を這わせると、先走りが指に粘つきながら絡みついてくる。それを掬っては竿全体にゆっくりと塗り付けると、手の動きに合わせて脈打っていくのを感じる。もう片方の手で重くなった陰嚢を握り、手の中で転がしていくと鈴口から溢れ出す先走りの量が増していく。
すっかり濡れてしまった指で愛撫の速度を早めていけば、頭の上から聞こえてくる愛らしい喘ぎが一層強くなってくる。限界が近いことを悟ると、蜜を垂らす尿道口に親指を添えて粘液と共に押し回す。
「……っはぁ、あぁっ、かね、さっ……でる、……でちゃう、から、……て、……はなし、てっ―――ぁああ!」
「……いいぜ。このまま出しちまいな」
そう言うと先端に爪を立てて、かりかりと引っ掻く。度重なる愛撫に耐えきれなくなった性器からどくどくと脈打ちながら白濁が吹き出し、兼定の指の隙間から飛沫を上げて飛び散る。痙攣しながら全てを吐き出した国広は、荒れた息を整えながら潤んだ瞳で兼定を見上げてくる。
「はぁっ……ぁ、ごめん、兼さん……手、汚しちゃったね」
「んなことねえよ、すげえ旨えぞ」
そう言いながら指に付着した国広の種を音を立てて艶かしく舐めとっていく。見せつけるような姿に、顔を赤らめながら慌てて止めようとする。
「っな、何してるの……!き、汚いから駄目だよ、吐き出して……!」
「もう飲んじまった。ご馳走さん」
にやりと笑った顔に信じられないと呆れる国広が可愛くて、顔を引き寄せて尖らせた唇に食らいつく。今度は国広の方から舌を入れて、兼定の舌をちゅうちゅうと吸ってくる。その積極的な姿に下半身が熱を持ち、ずしりと重たくなるのを感じる。堪らず己の熱源を国広の腿に押し付けると、ごくりと息を呑んだのが分かる。
「あ……ご、ごめん、僕ばっかり気持ちよくなっちゃって。今度は僕がするから」
「へえ、積極的で嬉しいねえ。……でも済まねえな、今は早くお前の中に入りたい」
耳元で囁きながら、硬く閉ざされた後孔に触れる。誰にも触られたことのない場所に感じる感触にびくりと身体が震える。
このままでは国広が苦しいだろうと判断して、先ほど脱ぎ捨てた直衣から丁字油の瓶を取り出して指に馴染ませると、ゆっくりと後孔に中指を押し込んでいく。油の手を借りてもなお中はきつく、異物である兼定の指の侵入を拒むようにぎゅうぎゅうと締め付けてくる。その壁を傷つけないように慎重に抜き差しを繰り返す。
「……国広、大丈夫か?……痛かったら言えよ」
「うん、大丈夫……」
額に汗を浮かべて苦しげに顔を歪めながらも続けて欲しいと先を促す姿に、早く快楽を与えてやりたいと指の抽送の速度を上げていく。
徐々に馴染んできたのか兼定の指を曲げるだけの空間ができると、探り当てた腹側の小さなしこりを撫でるように押す。すると、今までとは明らかに違う反応で国広の中が震え、逃れようと浮き上がる腰を抱え込みながら狙いを定めて快楽を引き出すと、艶を帯びた声が顔を出す。
「――っ、んぁああっ――!……っな、そこ、へんに、なっちゃ……やぁっ……!」
「……なるほど、ここが気持ち良いとこだな?」
ようやく善いところを見つけたと弾む気持ちのまま、ぐりぐりと指で強く擦り付ける。感じたことのない愉悦に国広の身体は浜に打ち上げられた魚のようにびくびくと震え、指を咥える壁はもっとと強請るように締め付けてくる。
「ぁっ!んあ!ぁあ!あっ!」
ぐっとしこりを押し上げる度に止まらぬ喘ぎが喉をついて響き渡る。
一度吐き出して萎えてしまったはずのものは芯を持ち、兼定の指の往復に合わせてふるふると揺れている。二本、三本と指の本数を増やすと、中でばらばらに曲げて拡げていく。見たこともないほど乱れて高く嬌声を上げる姿にこれ以上我慢できそうもなく、勢いよく指を引き抜く。
散々解された孔は咥えるものを失ってひくひくと震え、それが兼定の熱を欲して口を開けているように感じられる。いきり立った雄を入り口に押し当てると、先走りを縁に塗り込むように押し付ける。
「……国広。挿れるぞ。……最初は痛えと思うけど、ちょっとだけ我慢してくれ」
「……はぁっ……うん……僕も、兼さんが欲しい。だから、……来て、兼さん……」
自分と比較にならないほど長大な陰茎を押し当てられて恐いだろうに、微笑みながら兼定の唇に優しく口付ける国広を、何より愛おしく思う。なるべく優しくしてやりたいと思うのに、こんな時ばかりは自分の逸物の大きさが少し疎ましい。
それでもここで止められるはずもなく、国広の細くそれでいて引き締まった足を掴んで大きく開くと、愛らしい蕾にゆっくりと己の欲望を押し込んでいく。
指で慣らしたとはいえ、指よりも質量のある熱に中が強く締め付けてくる。痛いほどの締め付けに思わず腰を引きそうになるが、ふぅふぅと息を吐いて必死に痛みを逃そうとする国広の顔が目に入り、ぐっと腰を進めていく。最も張り出した部分が中に収まると、そこから後は一気に中へ入って行く。
「っはぁ……国広。入ったぞ、分かるか?」
「……う、ん。兼さん、すごく熱い。今、僕達繋がってるんだね」
「お前の中もすげえ熱い。……お前と、ひとつになってるって思うと、幸せだな」
この世で一番愛おしい者と身体を繋いで、その存在を感じることに至福を覚える。国広が自分の腕の中にいる、それだけで他は何もいらない。
すぐに動いては痛いだろうと、しばらく動かずに馴染んでいくのを待ちながら、額に、瞼に、鼻に、頬に、耳に、唇にと口付けていく。擽ったそうにしながらも幸せそうな表情に愛しさが募り、身体を抱き締めて口付けを深めていく。互いの唾液を交換するように、舌を絡めて啜り合う。次第に熱のこもった切ない声が漏れて、兼定の熱が国広に馴染んできたのを感じる。
ゆっくりと小刻みに抽送を始めれば、兼定を包み込む内壁が欲を孕んで吸い付いてくる。肌同士がぶつかる乾いた音が闇の中に響き渡り、昂った熱が下肢を一層熱く煮えたぎらせていく。雁首まで抜けそうなほど引いた剛直を、貫くように一気に挿入する。
「……国広……っ!愛してる…誰よりもお前を愛してる……っ!!」
「ひあぁっ!……あぁ、かねさ、あっ、あぁんっ!」
譫言のように愛の言葉を伝えながら、幾度も奥を抉っていく。どこからが国広でどこからが自分なのか分からなくなるほど、欲望のまま強く叩きつけて兼定の色に染め上げていく。結合部からは、どちらのものとも知れぬ体液がぐちゅぐちゅと淫らな音を立てて互いの身体を濡らす。
「あっ……、あっ、兼さん……!…僕も……、愛して、る……!!」
兼定の首に腕を回して縋りつきながら、想いを必死に伝えてくる国広の身体を軋むほど力強く抱きしめる。
もう、兼定のものだ。誰でもない、自分を選び愛してくれる彼との間に一部の隙間も作りたくないとばかりに、張り詰めた怒張を最奥に押さえ付けて腰を揺さぶる。己を犯す逞しい雄から精を搾り取ろうと、兼定の形に押し開かれた柔壁が蠢いてきつく締め上げてくる。
「っ……出すぞ、お前の中に……国広っ……!」
「……あああっ、……ぼく、も……でちゃう……やあっ、あああっ、ぁああ―――!」
身体を震わせながら国広が白濁の液を吐き出すと同時に、中を穿つ兼定を根本から締め付ける。極上の快楽に包まれながら、焼けるような熱を国広の中に放つ。兼定の性器が痙攣しながら、国広の腹の中に欲望を吐き出していった。
乱れた息が整うのを待たずに、兼定は身体を起こして力の抜けた国広の身体を抱き上げる。膝の上に乗せると、己の逞しい胸に擦り寄る姿が愛らしくて桜色の唇を優しく啄む。労わるような口付けが、次第に色を持っていく。
未だ国広の中に在る雄が再び熱を帯びていくのを感じて、そっと耳元に口付けた後に囁く。
「……国広。まだ足りねえ。もう一回してもいいか……?」
「……うん。いいよ、兼さん……」
許しをもらった兼定は、国広の腰を掴むとゆっくりと律動を開始した。
***
どれだけ眠っていたのだろうか、重い頭がまどろみの中から意識を掬い上げた。目を開ければ、夜の時間が終わりを告げ、もう間も無く太陽が顔を出そうかという時刻であることが分かる。
あの後、これ以上は無理だと国広が音を上げるまで、幾度となく愛し合った。胸に散らばる鬱血が、その情交の激しさを物語る。眠りにつく時には胸に頬を寄せて幸せな表情を浮かべていた温もりが、どこにもいない。
起き上がって愛しい恋人を探しに行こうと衾を押し退けた時、後ろから足音と共に少し掠れた声が聞こえてきた。
「あれ、もう起きたの?……おはよう、兼さん」
照れたように微笑む顔に返事をすると、細腕を引いて体を腕の中に閉じ込める。
「っあ、兼さん、駄目だよ……もうすぐ夜が明けるんだから」
「分かってるよ、せっかくの後朝に誰かさんが隣にいなくて寂しかっただけだ」
「ご、ごめんね……兼さんの着替えがないかなと思って探してたんだ」
「こんな時まで世話焼きなんだから仕方ねえな」
少しばかり悪態をつきながら手元を見ると、着替えの他に紙を握っているのが目に入る。
「あ……これ、兼さんのことを想って読んだ歌なんだ。……もらってくれる?」
当たり前だと笑いながら、整った字で書かれた紙に目を滑らせる。
筑波嶺の みねより落つる 男女川 恋ぞつもりて 淵となりぬる*
(筑波山の峯から流れてくる男女川が小さなせせらぎからやがて深い淵をつくるように、私の恋心も時とともに思いが深まり、今は淵のように深い恋心になりました)
「……きっと、ずっと前から兼さんのことが好きだって気持ちは心の中にあったんだと思う。それが一緒にいる間に積もっていって、ようやく自分でもその気持ちに気付いて認められた。……改めて、兼さんのことが大好きです。僕を恋人にしてくれて、ありがとう」
「オレも、お前のことがずっと前から好きだったんだと思う。一緒に夜桜を見た時に、自分の気持ちに気付けた。……こっちこそ、オレの恋人になってくれてありがとな、国広」
いい加減夜が明けてしまうからと強引に服を着せられた兼定は、渋々と国広に見送られながら玄関の戸を明ける。
しかし、大切なことを伝え忘れていたと思い出して振り返ると、不思議そうに首を傾げた国広がどうしたのと声をかけてくる。その問いかけに答える前にそっと抱き締める。
「悪い、大事なこと言い忘れてた……お前、オレの家で一緒に住むぞ」
「……ええっ!僕が、兼さんと……?」
「おう、父親の正妻の家だの大学寮だの、そんなとこに行かせてたまるかよ。部屋なら余ってるから問題ねえ」
「で、でも、そんなことしたら噂になっちゃうよ……」
「今更だな、こんなことまでしちまった仲なのによ」
そう言うと目ざとく首筋の痕を見つけて、息を吹きかける。忽ち国広の顔が沸騰したように熱くなっていくのが見える。とんとんと軽く胸を叩いて抗議の意を伝えてくる。
「も、もうっ、兼さんの馬鹿っ!」
「ははっ、悪い悪い。……冗談はさておき、オレは本気だからな。お前が嫌だって言っても、何がなんでもうちに引き摺り込んでやるから覚悟しとけよ?」
「兼さんは言い出したら譲らないからなぁ……うん、分かった。こんな僕で良ければ、一緒に住ませて下さい」
「お前とじゃなきゃこんなこと言わねえよ。……後朝の別れを惜しむのも悪くはないが、オレはお前とずっと一緒にいる方が嬉しいからな」
「……うん。僕も、兼さんとずっと一緒にいたいな」
見つめ合いながら笑い合う二人を、朝の光が静かに照らして包んでいく。
この先の未来に何があったとしても、こうして笑い合って生きていこう――
完
〜作中で引用した和歌の一覧〜
*「春されば まづ咲く やどの梅の花 ひとり見つつや 春日暮らさむ」万葉集 山上憶良
*「世の中に たえて桜の なかりせば 春の心は のどけからまし」古今和歌集 在原業平
*「散ればこそ いとど桜は めでたけれ 浮き世になにか 久しかるべき」伊勢物語 作者不明
*「きみにより 思ひならひぬ 世の中の 人はこれをや 恋といふらむ」伊勢物語 在原業平
*「筑波嶺の みねより落つる 男女川 恋ぞつもりて 淵となりぬる」後撰集 陽成院