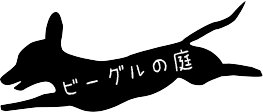夕日が鮮やかな赤色を纏って水平線に沈む中、ジリジリジリ……と鳴くセミの声が辺りに響き渡る。間も無く日没を迎えようという中で懸命に声をあげる姿を、夕涼みのために縁側に腰をかけた二人が見守っている。
「ったく、こんな時間まで元気なもんだな」
生憎とこちらは朝早くから畑に駆り出され、このクソ暑い中野良仕事に勤しむ羽目になったのだ。たっぷりと労働して汗をかいたおかげで、体は少々の火照りと疲労感に包まれている。夕暮れを迎えてもなお衰えを知らずに鳴き続ける彼らが、ほんの少しばかり羨ましい。
「セミは鳴くのが仕事だからね」
隣に座る相棒は、微笑ましそうに目を細めて木々にとまる彼らを見つめる。
「そうかもしれねえけどよぉ、一日中鳴いてんだろ?もういい加減休めばいいじゃねえか」
「そういうわけにもいかないんだよ。僕たちみたいな壊れない限り生き続けるモノや、何十年も生きる人間と違って、セミは地上に出てから一週間しか生きられないんだから。限られた時間の中で、精一杯鳴いているんだよ」
それを聞いて、兼定の中の彼らを見る目が変わる。一週間など、あっという間だ。数百年生きて来た自分にとっては、瞬き一つで過ぎ去ってしまうようにさえ感じる。そんな短い期間しか生きれない中で懸命に鳴く彼らは、一体どんな思いなのだろうか。兼定が思案する中、国広が言葉を発する。
「七年くらい地中にいて、地上に出てからたった七日で死んじゃうんだって。その七年間は、一体何のためにあるんだろうね」
「……分かんねえけど、力を蓄えてるんじゃねえか。いつか外に出た時に、腹の底から目一杯鳴けるようにな」
「なるほど、ね」
兼定の答えが正しいのかは分からないが、少なくとも国広は納得したようだ。うんうんと頷いた後、ポツリと呟く。
「ちょっと似てるかもね。……僕と」
兼定にしか聞こえないほど小さなその声は、どこか寂しさを含んだように感じる。国広の言わんとすることは、すぐに理解できた。
堀川国広は、和泉守兼定よりも古くに打たれた刀だ。打たれた時のことは覚えていないが、太平の世を過ごした国広は、長く使われることもなく飾られるか、蔵にしまわれたままだった。そして、偶然にも前の主に見出されたことにより、一転して活躍の場を与えられた。闇夜に煌めく国広の刃の美しさは、今でも鮮明に覚えている。
――しかし。その躍進も長くは続かなかった。主が歴史の表舞台で活躍したのは、十年にも満たない短い時間だった。主の死とともに、彼の刀身も行方不明となり消えてしまった。
長き時を使われることなく過ごしながらも、わずか数年、歴史に名を残す主に振るわれ活躍し、消えていった。それが、長き時を地中で過ごし、わずか数日だけ夏の風情を彩るように鳴いて死んでいくセミと似てると言いたいのだろう。
「……そうかもしれねえな。けどよ、今は違うぜ?お前の隣には、オレがいるんだからな」
何の因果か実体を持って生まれることができた以上、今度ばかりは国広を短い生で死なせはしない。そっと国広の肩を掴むと、嬉しそうに微笑みながら寄り掛かってくる。
いつの間にか日は沈み、セミたちの鳴き声も聞こえなくなっていた。