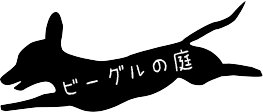「おめでとう、清光!」
パンパン、と景気良く銃にも似た破裂音が響き、各々が手にしていた筒状のものからヒラヒラとした紙束が飛んでは花びらのように舞う。その色彩豊かな紙が降り注ぐ中、当の清光はポカンと口を開けて部屋の中を見つめていた。
主に呼ばれて広間の戸を開けた瞬間こんなことになったものだから、何が起こったのか、まだ理解が追いつかない。けれど、広間に集まった刀剣男士たちや主が皆嬉しそうに清光を見て笑いかけているのと、先ほどの言葉で、自分を祝ってくれていることは分かった。
「……えっと、よく分かんないけど、今日なんかあったっけ」
「なんだ、清光。覚えてなかったのか。と言っても、私も他人のことを言えたわけではないけどね」
「あ、もしかして主が俺と本丸を始めた日?」
「正解!清光の誕生日みたいなものだからね、お祝いしようってことでこっそり準備していたんだ」
「そっか。ありがとね、主。それに皆も」
「よし、じゃあ主役は特等席についてもらおうか。今日はご馳走を用意したんだ、たっぷり楽しもう!」
ここにいる全員の顔が見渡せる席に連れていかれると、賑やかな宴が始まった。清光はこの本丸の始まりの一振りであり、主と初めて出会ってから今日でちょうど1年が経ったことになる。最初は数振りだけで出陣しては怪我をして、少ない資材で何とか手入れして……と中々大変な日々を送っていたが、いつの間にか共に戦う仲間も増え、苦戦することもほとんどなくなった。挫けずにここまでこれてよかった、なんてしみじみと感慨に耽っていると、酒を飲んで上機嫌になった主が隣にやってくる。
「清光には苦労をかけたね。まだ戦いは続いているから油断はできないが、ここ最近は安定した戦果を上げられるようになった。ここまで支えてくれて、本当に感謝してる」
「そう言ってもらえたら、刀冥利に尽きるよ。俺、主に選んで貰えて良かった。こんなお祝いの席まで作ってくれるし」
「ははは、喜んで貰えたようで良かった。じゃあ、後で堀川に礼を言っておくといいよ」
「え、堀川?……なんで?」
思いがけない人物の名前を出されて、清光は首を傾げる。
「ひと月くらい前に堀川が近侍をしていた時にね、来月は本丸の一周年の日で、つまり清光の誕生日みたいなもの。せっかくだからお祝いの席を作りましょうって言われたんだ。そこで初めて私もそのことを思い出して、もちろんだと返事をしたんだよ。今日の準備も堀川が誰よりも率先してやってくれたんだ。流石は手伝い好きと言うだけあるね」
「ふーん、そうだったんだ。……分かった、後で声かけるよ」
「うんうん、ぜひそうして欲しい。では清光、今日は潰れるまで付き合ってもらうよ」
「え〜……明日に響いても知らないよ?」
顔を赤くしながら杯を差し出してくる主に酒を注ぎながら、清光はチラリと遠くの方で追加の酒や料理を運んでくる世話好きな刀剣男士を見つめた。酔っ払った相棒の相手をしているうちは、彼をつかまえることは難しいだろう。もうしばらくはかかりそうだなと思いながら、清光は主に酒の入った杯を手渡した。
それから一刻が過ぎ、酔い潰れたものは広間ですやすやと眠り、それ以外の者たちも部屋で眠りについた頃。清光はようやく目当ての人物を見つけ、縁側に座る隣に腰掛けた。
「お疲れ、お勤めご苦労さん」
「清光くんもね、酔い潰れた主さんの介抱してたんでしょ?」
月明かりに照らされた、海のように青い澄んだ瞳がこちらを向く。あれだけ忙しなく動き回っていたのに、その顔には疲れなど微塵も感じない。
「まーね。俺はそんなに飲んでないし、布団まで運ぶだけだから大したことなかったよ」
「そっか、でも今日の主役だったからね。そっちの方でもお疲れ様」
屈託なく笑う表情はいつも通りの爽やかなもので、影でこっそりと清光のために準備をしていたなど少しも気づかなかった。きっと主が言わなければ、自分が発端となったことも清光に伝えなかったに違いない。
「あのさ、ありがとね。今日のこれ、堀川が提案して準備してくれたんでしょ?」
「ああ、主さんに聞いたの?ダメだなぁ、主さんが発端ってことにしておいた方が喜びますよって言ったのに」
「……何でさ」
「清光くん、主さんのことすごく大切に思ってるだろうから」
確かに、自分にとって主は大切な人だ。こうして姿形を得て、昔の仲間と再会したり、刀を手に戦うのも全て、主が刀剣男士として呼び出してくれたお陰だ。前の主には最期まで共にいられなかった分、今の主とは長く側にあって役に立ちたいと思っている。
けれど、主に負けないくらい、仲間たちだって大事な存在だ。刀の時には思わなかったけど、一緒に戦ったり、なんてことない話をしたり、そんな時間を過ごすのは想像していた以上に心地よい。
あまり仲間内で優劣をつけるつもりはないけれど、それでもやはり、新撰組で共に振るわれた刀剣たちは自分にとって特別な存在だ。かつて同じ時間を過ごした、気心が知れる親しい仲だと思っている。だから、そんな風に思われてしまうのは少し寂しい。もちろん、堀川のこうした心遣いのできるところは彼の美点だとは思うのだが。
「そりゃそうだけどさ、堀川が俺のためにしてくれたってのだって嬉しいよ。堀川はその時まだこの本丸にいなかったのに、覚えてくれてたんだもん」
「そう言ってもらえるなら良かったよ」
「ねえ、何で覚えてたの?それに、わざわざこんな席まで用意しようなんて、普通思わないでしょ」
「うーん、そうだね……」
堀川は空を仰ぐように顔を上げ、少しだけ眉が下がる。そんなに言いにくい理由なのだろうか。自分と堀川の間に、何か困ったことが起きたことなどなかったはずだが。特に思いつく出来事もなく考えている清光をちらりと見遣った堀川は、ぽつぽつと語り始めた。
「僕にとっては、忘れられなかったから。刀だった頃に、君が折れてしまった時のこと」
細められた瞳に映っているのは、きっと夜空ではなく血の匂いの漂う池田屋なのだろう。攘夷志士と新撰組隊士たちの剣戟の火花が散る中、床の畳に突き刺さった刀。それは、誰が見ても明らかに修復が難しいであろうほど無惨に折れてしまった、加州清光。主の行く末を見届けることなく、志なかばで散っていった刀だ。
「あの時は、それがどういう気持ちだったのか分からなかったけど……今なら分かるよ。僕は、君が折れてしまって、悲しかったんだ。易々と何でも斬り捨ててきた、そんな鋭い刀だった君がもう二度と振るわれることなく、ただの鉄屑へと還っていくことが、無性に悲しかったんだ。だから、この本丸で君に会えてすごく嬉しかったよ。奇跡って、本当にあるんだね」
「……そう、だったの」
もちろん刀であった時はお互い話すこともできなかった身だ。堀川が自分に対してこんな気持ちを持っていたことなど、知るはずもなかった。
むず痒いような、それでいて不思議と胸の中がぽかぽかと温かい、これは何と言ったら良いのだろう。刀剣男士となって一年、未だにこの感情というものには知らないことばかりで驚かされる。それでも、これは嫌な気持ちではないと思う。歴史の片隅に打ち捨てられた刀の自分を、こうして忘れないでいてくれた存在がいる。それは、きっとしあわせなことなのだろう。
「ありがと、堀川。今日のこともだけど、俺のこと、忘れないでいてくれて」
「どういたしまして。清光くんは大切な仲間だよ、今も昔もね」
目尻を下げて笑いかける顔を見ているだけで、何だか心臓が落ち着かない。どうしてだろうか、堀川の顔など毎日見ているはずなのに。そろそろ部屋に戻って寝ないと明日に響くはずなのに、縫いとめられたように体は動かない。まだここを離れたくないんだと、抵抗するかのように。
「僕はもう少しここにいるけど、清光くん明日出陣じゃなかったっけ?そろそろ戻った方がいいんじゃないかな」
堀川の言う通り、なのだけど。もう少しだけ、彼の隣にいたい。何を話すわけでなくても構わない。ただ、隣にいるだけでいい。自然と言葉が口から溢れていた。
「……そうだけど。もう少し、ここにいちゃダメ?」
「ううん、全然。最近忙しくて清光くんとゆっくり話すことも中々なかったから、僕ももう少し一緒にいたいな」
それから、二人はしばらくの間語り合った。昔のこと、この本丸で起きたこと、たくさん、たくさん。気付けば睡魔に誘われた清光は船を漕ぎ、ぽすりと堀川の肩に頭を預けた。堀川は清光をおぶろうとしたけれど、声をかけても反応しないほど深い眠りに就いてしまったようで自分の首に腕を回して捕まってもらうことも難しそうだったので、そっと抱き上げた。
胸にしなだれかかる温もりを感じながら、堀川は微笑んだ。その寝顔が愛らしいのはもちろんのこと、ここまで自分に気を許してくれているのだと思えば、自然と顔が綻ぶ。
恐らく彼は、堀川の彼に対する気持ちに微塵も気づいていないだろう。当然だ、そう悟られないように心がけているのだから。あくまで親しい仲間として、徐々に距離を縮めていく。自分の存外臆病なところに苦笑したくもなるが、仕方あるまい。先ほど清光にも言ったように、こうして自分たちが再び会えたこと自体が、奇跡なのだ。堀川も清光も、歴史という川の流れの途中で沈み、消えていった刀剣だ。それが何の因果かこうして巡り合えた。それを奇跡と呼ばずして、何と言おう。
故に、このチャンスを逃したくはないのだ。気まぐれで飄々としているけれど、実は仲間思いで愛情深い。そんな彼に、どうしても想いを受け入れて欲しいと思うのは、我儘だろうか。たとえ何年かかったとしても、構わない。いつか彼と想いを通じ合わせることができれば、それでいい。
気付けば彼の部屋に到着していた。綺麗に敷かれた布団に、そっと力の抜けた体を横たえる。ううんと声を上げながら体を縮こめる様は、心臓に悪い。瞳にかかる前髪をそっと流してやると、規則正しく寝息を立てる顔がよく見えた。
体に布団をかけながらも、その寝顔から目が離せなかった。我慢するのは得意、のはずなのだが。さすがに想い人のこんなにも無防備な姿を前にして、何とも思わないほど堅物ではない。
しばらく見つめた後、迷いながらもその顔に己のそれを近づける。ごめんね、と心の中で謝りながら、触れるかどうかの軽いキスをした。思っていたよりも柔らかい感触にもっとこうしていたいという欲が顔を出すが、そこは鋼の意志ですぐに体を起こした。
これ以上は、彼が起きている時。彼が受け入れてくれる時まで、待とう。
――大丈夫、待つのは得意だろう?そう己に言い聞かせながら、堀川は自室へと急いだ。