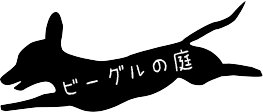小さな本丸の恋の話
「……なるほど、我が本丸の脇差はあなたになりましたか。よろしくお願いします、堀川国広。どうか末長い付き合いになることを願います」
どこまでも続く暗い闇の中を眠るように漂っていたはずが、気がつけば明るい光に包まれて吸い寄せられて行った。眩しさを感じやっとの思いで瞳を開くと、そこには見知らぬ人間がいた。真剣な瞳で自分を見つめる女性は、眉一つ動かさないまま淡々とこちらに挨拶してくる。
「あ……えっと、初めまして。……あなたは、僕の新しい持ち主、ということになるのでしょうか? でも、僕は消えてしまったはずなのに……それに、ここは?」
目が覚めたかと思えばいきなり彼女の前に立っていたというわけなので、とにもかくにも分からないことだらけだ。思わず挨拶もそこそこに、目の前の女性に質問ばかり浴びせてしまう。女性は少しだけ黙って考えた後、襖の向こうに向かって声をかけた。
「加州、そこにいますね。彼に説明をお願いします。縁のあるあなたが話した方がいいでしょう」
すぐに襖の向こうに人の形をした影が浮かび上がり、「入りまーす」という軽快な声と共に戸が開く。そこに立っていたのは、黒い少々くせのある毛を肩で束ねて垂らし、シャツとベストに黒いズボンという格好をした男だった。切れ長で鋭い猫のような真紅の瞳が印象的で、不思議とその姿に目が離せなくなった。
「では、後は頼みます」
彼の方をちらりと見て一礼すると、女性はすぐに部屋から立ち去ってしまった。残されたのは、堀川と加州と呼ばれた青年だけだ。
「ふーん、お前が堀川国広、ね。あの鬼の副長の刀だからもっと厳つい見た目を想像してたけど、全然そんなことないじゃん。ま、俺はそっちの方がいいと思うけど」
堀川の全身を見回した後、感心したように呟く。急に登場した青年ではあったが、自分の前の持ち主を知っていることと、先ほど女性に呼ばれた彼の名前からすぐにその正体に見当がついた。
「君は……沖田さんが使っていた、加州清光?」
「話が早くて助かるよ、そういうこと。かつて刀だった加州清光が、こうして審神者の力で人の身を得た姿ってわけ。お前もね、堀川」
「審神者って、さっきの女の人のことですか? それに、ここは一体……」
「まあ、そうなるよね。安心して、一から説明するからさ」
その言葉を皮切りに、加州は自分たちが置かれている状況について説明してくれた。今は西暦二二〇五年、自分達が活躍した幕末の世からおよそ三百五十年経った時代。ここは本丸と呼ばれる拠点で、審神者という主と彼女の力によって顕現した刀の付喪神・刀剣男士たちが暮らしている。その目的は、歴史の改変を目論む時間遡行軍と呼ばれる敵と戦い、歴史を守ること。刀剣男士は、刀に籠った人の想いやその刀自身の逸話を元に生まれ、遡行軍と戦うためにこの世に存在することを許されている。
俄かには信じがたい話ではある。しかし、戦いの中で折れてしまったはずの加州や、箱館戦争の末に主が敗死し、その亡骸と共に歴史から消えて行った自分がこうして人の身を得ていることが、何よりもその話が現実であることを証明している。
「今この本丸にいるのは、俺と堀川を含めて十二人の刀剣男士と、主。一度に戦場に出陣できるのは六人までって決まりがあるから、その時々で顔ぶれは変わるけど、堀川はこの本丸で唯一の脇差だからね。きっとすぐに出番は来ると思うよ」
「ありがとうございます、大分状況が理解できました。……ここには、その。他にも新選組で使われていた刀はいるんですか?」
「ううん、俺と堀川だけだよ」
「そうですか……」
堀川国広は、新選組副長・土方歳三によって振るわれた刀だ。そして、その隣にはいつだってもう一振りの刀がいた。……和泉守兼定。上覧試合の折にその剣の腕前を称賛され会津藩主より賜った、土方自慢の一振り。堀川と違って後の世まで残ったはずの彼がここにいるのではないかと期待したが、どうやら呼び出されていないようだ。
黙り込んでしまった堀川を気遣ってか、加州が肩に手を置いて声をかけてくる。
「最初は不安なこともあるだろうけど、なんかあったら遠慮なく言ってよ。出陣も、はじめのうちは俺が一緒に出陣するように主に頼んでおくからさ」
「ありがとう、加州さん。そう言ってもらえると心強いです」
「あー、ダメダメ。加州さんとか、そういう堅苦しいのいらないから。一応昔馴染みってことなんだしさ、もっとフランクな呼び方でいいよ」
「ふ、ふらんく……?」
「あ、そっか。えーっと、もっと気軽な呼び方でいいよってこと。加州でも清光でも、なんでもいいから。刀剣男士同士に上も下もないんだからさ、『さん』も敬語もいらないよ」
「なるほど……そういうことなら、清光くんって呼んでもいいかな?」
「もちろん。改めてここでもよろしくね、堀川」
さっと手を差し出されたので、何だろうかと思って自分のそれを伸ばしてみると、ぎゅっと握られる。これがうちでの挨拶なんだよ、と言われて、自分がこの本丸の刀剣男士の仲間入りができたのだという実感が、少しだけ湧いてきた。
それから、二週間後。初陣も無事に大した怪我なく終えて、少しずつ本丸での生活に慣れてきた。今日も日課の演練への参加を終えて、本丸の廊下を歩きながら、堀川は前を歩く清光に話しかけた。
「ねえ、清光くん。この本丸って、あまり刀剣男士が多くないけど、何か理由があるのかな」
「え?」
「演練相手の人たちと対戦した後にお互いの本丸について少しだけ話すことがあるんだけどさ、刀剣男士が五十人以上いたりとか、そういう本丸ってたくさんあるみたいだから。僕たちのところだけ、やけに人数が少ないような気がして」
「……ああ、そういうことね」
意味ありげに目を伏せた清光は、共用の休憩場所となっている部屋に堀川を連れて行った。その表情がどこか浮かないように見えて、まずいことを聞いてしまったのかと堀川は内心焦った。しかし、やっぱりいいやと口にするよりも先に、清光が口を開く。
「そーね、お前もそろそろ気づく頃かと思ってたけど……今、この本丸にいるのは、お前のすぐ後に顕現された四人を入れて十六人。それ以降は一人も増えていないよね。実を言うとね、増えない、というより増やせないんだ」
「え、どういうこと? だって、他の本丸にはもっと大勢の刀剣男士がいるのに」
「本丸の規模っていうのはね、その本丸の主である審神者の持つ霊力に比例するんだよ。霊力が多ければ、その分たくさんの刀剣男士を顕現して使役できる。だけど、うちの本丸の主は霊力が少なくて、顕現できる刀剣男士の数も今の人数で精一杯なの。審神者になるための最低限の基準を満たしていないらしいから、当然他の本丸よりずっと少ない人数になっちゃうよね」
そこで堀川は、顕現した時に「我が本丸の脇差はあなたになりましたか」と主が言っていたのを思い出した。脇差なんて自分の他にも呼べるだろうに我が本丸の脇差とはどういう意味だろうと思っていたが、あれは、少ない霊力故に元々数の少ない脇差という刀種の中で呼び出すのを一人と決めていて、その中でたまたま堀川が鍛刀されたからだったのだろう。
「そうだったんだ。でも、だったらなんで主さんは審神者になれたの? 霊力が少ない人は、審神者にはなれないんでしょ?」
「普通はそうだね。ただ、主のお父さんはね、審神者だったらしいんだ。……すごく優秀な人で、時間遡行軍を何度も退けていたから政府からの評価も高かった。でもそれだけ活躍していたものだから、当然敵である時間遡行軍にも目をつけられちゃってたみたいでね。密かに本丸の場所を捕捉されて、お祝いの席かなんかで刀剣たちが油断している時に襲撃されて、主のお父さんは殺されちゃったんだってさ」
「えっ……」
「うちの主が刀剣男士と必要最低限の関わりしか持たないのも、それが理由。お父さんの本丸は和気藹々としていたらしいんだけど、それが遡行軍に付け入る隙を与えたんだって思ってるみたい」
「……そう、なんだ。悲しいね。戦争に犠牲は付きものだってことは、分かってるけど」
「……まあね。主は、殺されてしまったお父さんの分も、時間遡行軍と戦いたいって思った。だから政府に必死で働きかけて、何とか少数精鋭の本丸を築くことを許可してもらったってわけ」
主はいつも冷静で、淡々と自分たちに作戦を伝えたり指示を出しているところしか見たことがない。その心の中を推し量ることは難しくて、正直何を考えているのか分からなかった。けれど彼女は、無表情な仮面の内側で父親を殺された悔しさや憤りと闘っているのだろう。喜怒哀楽をほとんど表さないから少しとっつきにくさを感じていたが、そんな主にも胸に秘めた思いがある。こうして顕現させてもらったからには、何とかしてそんな彼女の力になりたいと思う。
「ありがとう。主さんのこと、少し理解できた気がするよ。数少ない中で顕現してもらったんだから、期待に応えないといけないね。……でも、清光くんは寂しくない?」
「はあ? いきなり何でそうなるのさ」
「だって、この本丸にこれ以上刀剣男士が増えることはないんでしょ? 前に顕現可能な刀剣男士の一覧を見たときに、安定くんもいたからさ」
「ああ、そうゆうことね。べっつにー、あいつが来てもなんかしょっちゅう喧嘩とかしそうな気がするからいいよ」
「そうかなぁ」
「そーなの」
その口ぶりとは裏腹に、どことなく寂しい雰囲気を纏っているのは気のせいだろうか。会える手段がないわけでないが、この本丸の仲間として会うことはできない。それが却って、絶対に会えないと決まっているよりももどかしい状況なように思えてならなかった。
それからさらに時が経ち、堀川が顕現してから早くもふた月が経とうとしていた。本丸での生活にもすっかり慣れ、出陣や内番、遠征がない時は、堀川は率先して本丸の掃除や洗濯などの雑事をするようにしていた。……やることがなくなると、途端に余計なことを考えてしまうから。
清光が説明してくれた通り、あれから新しい刀剣男士が増えることは全くない。ということは、現時点でこの本丸にいないかつての相棒・和泉守兼定が現れることはないのだ。
土方歳三が所持していたとされる堀川国広は、本当に堀川物だったのかどうかも分からない脇差だ。真贋不明の自分は、兼定と共に土方に振るわれていた、ということだけが己を形づくる逸話なのだ。だというのに、この本丸にはその兼定がいない。ならば、こんなにもあやふやな自分に、存在価値などあるのだろうか。顕現可能な脇差の一覧に記載されていた脇差たちは、どれも名だたる名刀ばかりだ。彼らの中の誰かが顕現していれば、きっと自分なんかより余程役に立っていたことだろう。
そんな後ろ向きな気持ちが、気がつけば頭の中を支配していく。夜に床につけば、不安で眠れないこともある。堀川自身も悲観的なことを考える自分が嫌になるのだけれど、どうしたって振り払うことができない。なるべくそういったことを考える隙を作らないようにと、何かと仕事に手をつけるのが今の自分にできる精一杯だった。
毎日せっせと掃除しているから十分に綺麗な廊下を、それでも無心になるためにと雑巾掛けをする。ふと、背後に人の気配を感じた。誰だろうかと振り返るよりも先に、声がかけられる。
「毎日精が出るねー。俺には真似できる気がしないな」
「お疲れ様、清光くん。今日は畑当番だったっけ? 暑かったでしょ」
「まーね。本丸も思ったほど涼しくなくて残念」
「今日は風が少ないからね。あっ、僕冷たいお茶持ってくるよ。待ってて」
バケツに雑巾を入れてそそくさと立ち上がると、厨房へと向かう。道中で掃除用具を棚にしまい込み、冷蔵庫と呼ばれる便利な機械によって程よく冷やされた麦茶の入れ物を取り出した。残暑が厳しいこの季節には、ぴったりの飲み物だ。
余っていた茶菓子を添えてお盆に乗せ先ほどの場所に戻ると、暑そうに手をパタパタと振って風を作っている清光の姿があった。堀川が戻って来たのに気づいてお礼を言いながら、冷たいコップを受け取る。
「ふう、生き返ったー……」
麦茶を一気に喉へ流し込んで幸せそうに休息する清光を横目に、堀川の思考はまたも深い澱みへと落ちていく。どうすれば、自分は己を認められるのだろう。主や仲間たちは、決して堀川のことを軽んじたりはしていない。それどころか、頼りにしてくれている。なのに、心の中に棲みつく負の部分が、それを受け入れられない。
お前にできることは、別に他の刀にだってできる。それをお前は誰かに必要とされたくて、無理やり仕事を見つけて働いているだけだ。みっともない、哀れな刀。主を守れなかった、役立たずな刀。頼みの相棒もいない、惨めな刀。お前なんて、別にいなくたって――
「ねえ、堀川。聞いてる?」
その言葉が、堀川を闇の底から掬い上げてくれた。ハッとして横を見ると、心配そうな顔をした清光がこちらを見つめている。
「ご、ごめん。ちょっとぼーっとしてたみたい」
「……堀川さ、働きすぎじゃない? ちょっとは休んだ方がいいよ」
「心配かけてごめん、でも大丈夫だよ。何かしている方が落ち着くんだ」
清光に納得してもらえるようにと慌てて紡いだ言葉は、どうやら信用に足るものではなかったらしい。少しの沈黙の後、眉を顰めた清光がそっと呟いた。
「……何か悩み事があるなら相談してよ。それとも、堀川にとって俺はそんなに頼りない?」
「そんなことないよ。清光くんはこの本丸で最初の刀剣男士だし、僕にとっては昔馴染みでもあるし、とっても頼りにしてる」
「じゃあ、教えて。何がそんなに堀川を苦しめてるのかを、さ」
じいっと真剣な顔つきで言葉を待ってくれている清光。大したことではないからと一蹴するのは簡単だが、これ以上誤魔化しては彼の堀川に対する心遣いを蔑ろにすることになる。それは、嫌だ。観念した堀川は、すっと一呼吸置いた後に、ポツポツと語り始める。
「……僕はね。他のみんなみたいに誇れる逸話もなければ、刀剣としての価値も怪しい。だから、不安になるんだよね。兼さんがいないこの本丸で、僕が存在する意味があるのかって」
「……主も俺も、他のみんなも。堀川がいてくれてよかったって思ってるよ?」
「うん、分かってる。その気持ちは伝わっているし、すごく嬉しいよ。でも、やっぱり僕自身が納得できていないんだと思う。兼さんの相棒だったという逸話しか拠り所のない僕が、兼さん抜きに価値なんてあるわけないだろうって」
ぐるぐるととぐろを巻いて腹の底に溜まっていた気持ちを言語にして吐き出してみると、幾分か楽になったような気がする。けれど、こんな重たい感情を聞かされた清光は違うだろう。やはり口にしない方がよかったと思い謝ろうとするよりも早く、清光が言った。
「まあ、そういうの全く気にしないってのは難しいよな。俺だって、沖田君が本当に使っていたのかっていう確かな証拠があるわけじゃないし? 劣等感っていうのかな、そういうの他の刀剣たちに感じていないわけじゃないよ」
「……そうなの?」
清光は、少し気分屋なところもあるけどなんだかんだ言って面倒見がいいし、戦場では勇猛果敢に戦う頼もしい存在だ。言葉少ない主にも信頼されていて、当然自信に満ちているのだろうと思っていた。だからこそ、彼にこんな後ろ向きで情けない話はしたくないと思っていたのだ。
「うん。でもさ、それって俺たちがただの刀だった頃の話じゃん? すごい逸話や美術的な価値を持っていようがいまいが、この本丸で刀剣男士として活躍することの方が大事だと思うんだよね。昔のことなんてどうにもならないけどさ、今の俺が頑張ればその分だけ主に認めてもらえる。何より、俺が自分のことを、歴史を守ってるすごい奴なんだぞって認められる。……堀川も、そういう風に考えてみたら?」
「……今の僕が、頑張る……」
「そっ。兼定の分まで活躍してやるぞーって感じで頑張ればいいじゃん」
「……清光くんも、安定くんの分も戦うぞって思ってるってこと?」
「……なんですぐあいつが出てくるかねー。まっ、そういう気持ちもほんの少しだけ持ってあげていないこともないかな」
「……そっか。うん、そうだよね」
確かに今の自分を兼定が見たら、きっと怒られてしまうに違いない。鬼の副長の脇差が、腑抜けてんじゃねえぞ。せっかく選ばれたからには、オレの分もちゃんと活躍しろよな? そんな声が、どこからか聞こえたような気がした。背筋が自然と伸びる。
「ありがとう、清光くん。君の言う通りだね。主さんのために、そして前の主たちの歴史を守るために、今こうして刀剣男士になった僕が戦う。それが僕たち刀剣男士の誇りで、一番大切なことだ。……僕は、つまらないことに囚われていたな」
「急に人の身を得たんだもん、思い悩むことくらい当然あるでしょ。一人でしんどい時は、何でも相談しなよ? 俺たち、仲間なんだからさ」
仲間、か。前の主も、こんな気持ちを持って戦っていたのだろうか。だからこそ彼は、最後の最後まで仲間の気持ちを背負って戦い続けたのかもしれない。志半ばで斃れていった同胞たちの分まで、自分が戦い抜いてみせるのだ、と。
ならば、自分も彼のように戦いたい。どんなに厳しい状況であろうとも、主のため、仲間のために。
堀川の表情が和らいだことに満足した清光は、いいことを思いついたと上機嫌に提案してきた。
「よっし、暗い話はお終い! なんかぱーっと楽しいことしよっか。あっ、そうだ。俺、主に頼んで万屋に行く許可もらってくるからさ、今から行こうよ」
「万屋?……ああ、そういえばみんな時々買い物に行ってるね。でも、僕は特に欲しい物もないし……」
「行ってみないと分かんないよ? せっかく働いてお給料ももらってるんだからさ、何か好きなもの買ってみなよ。俺も一緒に着いてくからさ。決まりね」
やや強引に約束を取り付けられてしまったが、すっかり乗り気になっている清光に嫌だとも言えない。きっと彼は堀川の気分を少しでも明るいものにしようと思って提案してくれているに違いない。別に自分が何か買わずとも、清光が買い物を楽しんでいるのを横で見ていればいいかと思い、堀川は「分かったよ」と頷いた。
<中略、ここから先R-18>
微笑みながら堀川を見つめる清光の体を、そっと抱き寄せる。ぴったりとくっついた体温の温かさを感じながら、堀川は涙で少し濡れた唇にキスをした。
かつて刀であった頃、主の最後の戦いで堀川は何の役に立つこともできなかった。戦の主役が銃や大砲へと変わり、自分の出番はなくなっていった。己の存在意義とは何だったのであろうか、と何度も自問した。
しかし、今は違う。主のために剣を振るい、こうして大切な人ができた。自分の命よりも大事な、愛おしいと思える存在ができた。ただの刀として時代の流れに逆らうこともできずに消えていった時の自分が今の自分を見たら、きっと驚くだろう。それくらい、今この瞬間の自分は幸せ者だと思う。
触れるだけだった口付けは、次第に深いものへと変わっていく。想像していた以上に柔らかいそれに、夢中になって食らいついた。吐息さえ奪ってしまうほど深く、何度も何度も、角度を変えて味わう。
「は、ぁ……っ、ん……っ」
唇の隙間から、甘い吐息が溢れる。僅かに開いた唇に、そっと舌を差し込んだ。清光の咥内は熱く、差し入れた舌が焼けてしまうのではないかと錯覚してしまいそうになる。それでも、歯列をなぞり、所在なさそうに固まっていた清光の舌を絡め取る。ぴちゃぴちゃと唾液を啜る音が、堪らなく淫靡に聞こえてならなかった。
さすがに息が辛くなってきたのか、とんとんと胸を叩かれてしまったので、名残惜しく思いながらも顔を離した。つう、とうっすら残る銀糸と、顔を林檎のように赤く染めながら息を乱す清光の姿が、体に燻る炎を燃え上がらせた。未だ抱きしめたままの清光のシャツの釦を片手で器用に外していくと、上下する胸の先端にちょこんと乗った淡い色の粒に唇を添える。小さな果実のような突起を、優しく円を描くように舐めた。
「あっ……ほり、かわ……」
「……ごめん、嫌だったかな?」
「……いやじゃ、ない……ただ、声、我慢できないから、ちょっと恥ずかしい……」
「我慢しなくていいよ。清光くんの声、聞かせて?」
そういうや否や、今度は口に含んでちゅうちゅうと赤子のように吸い付く。もう片方は、先端を指の腹でクリクリと押しつぶすように回した。
「――っ、ぁあ!……あっ、やだ……きもちぃ、んっ、ァああ!」
清光の口から漏れ出てくる嬌声と堀川が胸を愛撫する音だけが、狭い部屋の中を支配する。時折軽く噛んだり、摘み取るように引っ張ったり。堀川の動き一つ一つに清光は快感を刺激されるようで、あっという間に先端がピンと立ち上がっていく。彼が自分の手で感じてくれているのだという事実が、どうしようもなく嬉しい。
ちらりと視線を下に移せば、ズボン越しでもはっきりと分かるほど股間は膨らんでいた。胸を可愛がっていた指が、撫でるように清光の股間に触れる。途端に、清光の身体がビクリと震える。ぎゅっと堀川のシャツを握りながら少しだけ上目遣いで見つめられると、己の股間に熱が溜まってくるのが分かる。その仕草一つ一つが堀川をこの上なく昂らせていることなど、きっと清光は自覚していないだろう。布越しに形をなぞるように、手のひらをつうと這わせる。堪らずに清光が声を上げた。
「あっ……、ほりかわ……触って、よ……」
「今も触ってるよ?」
「……っ、違くて……直接、触って欲しいの」
涙を溜めながらおねだりされれば、ひとたまりもない。もうちょっと粘ってみようかとも一瞬思ったが、これ以上焦らすと恥ずかしさの余り拗ねてしまうかもしれない。それはそれで可愛いのだろうな、と思いながら、カチャカチャとベルトを外して下着ごと一気に脱がした。勃ち上がった性器が顔を出し、外気に晒されたことでふるふると震えている。
赤く腫れた脈打つ幹をそっと握ると、ゆっくり上下に扱いていく。トロトロと先端から先走りが溢れては、あっという間に堀川の指を濡らしていく。ぬちゃぬちゃといやらしい音を立てながら、気持ち良い部分を探るように愛撫を続けた。裏筋、雁首、亀頭。清光の屹立を余すところなく、丁寧に扱き上げる。
「――ひぅ、ぁあ、あっ……! っあ、ダメ、いっちゃ、イッちゃうから……、ぁ、……ぁああああ!」
「……可愛い。いいよ、そのまま力抜いて」
「ひっ、いいっ、ぁ、うぁ、ぁああア……ッ!」
清光の静止の声をよそに、堀川は親指で先端の窪みを押し回す。それがトドメとなったようで、我慢していた白濁がびゅくびゅくと勢いよく吐き出されて、堀川の指やシャツ、そして清光自身の腹を汚した。目をぎゅっと瞑って射精の快感に身を任せる清光の姿は、この世の何よりも美しく感じられた。
背中を丸めて絶頂の余韻に耐える清光の背を何度か撫でた後、堀川は立ち上がった。愛しい人の痴態を見て、さすがに己の股間のものも限界が近い。けれど、呪いをこの身に宿した自分がこれ以上彼に触れるのは危険ではないかという気がして、清光が気を遣っているうちに去ろうと思ったのだ。
だが、そんな堀川の気持ちなど見透かされていたのだろう。まだ呼吸が整いきっていないにも関わらず、清光が引き止めるように堀川の腕を掴んだ。
「……どこ、行くのさ」
「えっと……厠に」
「なんで」
「……それを言わせる?」
「言ってもらわないと分かんないもん」
聡い清光に分からないはずがないだろうに、梃でも動かないと言いたげにむすりと睨みつけてくる。仕方ないな、と息を吐きながら堀川は正直に答えた。
「僕の方も、そろそろ限界だからさ。自分で処理してくるよ」
「そんな必要ないよ。俺がやったげる」
「……駄目だよ、これ以上は。僕を蝕むこの呪いのせいで、万一清光くんの体に何かあったら、死んでも死にきれない」
「はあ? 今更何言ってんのさ。それにね、俺がそんなことくらいでどうにかなると思ってんの? 舐めんなよ、こちとら川の下の子、そんなやわじゃないっての」
堀川の腕を掴んでいた清光の指がベルトにかかり、強引に外されていく。無理やり走って逃げれば足の速さでは勝てるはずなのに、堀川の身体はピクリとも動かない。大好きな人が、敏感な場所に触れてくれる。そんな魅力的な現実に、理性が太刀打ちできようはずもなかった。
下着ごと一気に膝まで脱がされると、ガチガチに硬くなって天を仰いだ陰茎が現れる。期待を膨らませ、腹につくほどいきり勃った雄に、清光が触れる。赤く彩られた指に絡め取られただけで、感覚が飛んでしまったのではないかと思うほど気持ちよかった。愛しい清光が、己の体の最も浅ましい部分に触れている。そう考えるだけで、どんどん下腹部に熱が集まっていく。
「……もうちょっと屈んでよ。これだとやりにくいから」
清光の切れ長の美しい朱に上目遣いで見つめられながらお願いされ、自分の意志とは関係なく勝手に体が動いて膝立ちになっていた。よく出来ましたと嬉しそうに呟いた後、そっと先端が温かい感覚に包まれた。すぐに、それが清光の咥内なのだと理解した。
「……っ、清光、くん……駄目だよ、手でやってくれれば、良いから……」
「うるさい。そんなの俺の自由でしょ」
そう言うとすぐにちろちろと雁首を舌で刺激され、一気に腰が重くなる。歯を立てないように、懸命に堀川の猛りを飲み込もうとする姿が、この世の何よりも可愛く思えてならない。時折苦しげに眉を顰めながらも、清光は喉を動かして丁寧に愛撫を続ける。慣れない手つきが、却って堀川を昂らせていく。
清光の初めてを、こうして今自分が貰っている。そのことが、呆れてしまうほど堀川の心を喜ばせている。舌が脈打つ筋に添えられるたびに、痺れるような快感が下半身から全身へと回っていくのを感じる。
「……はぁ、清光くん、もう出るから、口、離して……」
さらさらと指に馴染む猫っ毛を撫でながら堀川は清光を促すものの、清光の動きは止まらない。いや、それどころか射精を促すように口淫は激しさを増していく。何とか引き剥がそうと試みるものの、愛する人の髪を引っ張る、なんてことはもちろん出来る訳がない。肩を押して強引に引き離すこともできなくはないだろうが、清光にそんな乱暴なことをするなど嫌に決まっている。
結局堀川にできることは、とんとんと清光の背を叩いてもういいのだと伝えることくらいだ。当然、清光は退かない。喉が引き絞られて、中のモノがぎゅうっと圧迫される。
遂に我慢の限界を迎えて、堀川は清光の咥内に己の欲望を解き放った。それをゆっくりと、清光は喉の奥に流し込んでは飲み込んでいく。口の端から、つうと溢れ出た精液が伝って、顎から床へと落ちていく。その艶かしい光景が、恐ろしいほど激しく堀川の欲を昂らせた。ずる、と清光の口から解放された陰茎は、一度達してもなお硬度を保って勃ち上がっている。
「はぁ、はぁっ……すごい、いっぱい出たね。なのにまだガチガチじゃん」
「もう、飲まなくていいのに……苦しかったでしょ、ごめんね」
「俺がそうしたかったからいーの。ねえ、まだ満足できてないでしょ? 続き、しようよ」
「……清光くんは、いいの?」
「当たり前じゃん。好きな人と抱き合いたいなんて、人間からしたら普通のことでしょ? 俺たちは元々人間じゃなかったけど、今はこうして人の身がある。だから、俺は大好きな堀川と抱き合って、一つになりたい。それとも、堀川はそうは思わないの?」
「……ううん、そんなわけない。清光くんと繋がりたいよ。君のこと、もっと近くで感じたい」
堀川の返事を聞いて満足そうに笑うと、今度は清光の方からキスをされる。少しでも己の想いが伝わるようにと願いを込めながら、堀川も負けじと、何度も、何度も口付けた。
二人で歩く道
轟々と唸りを上げる水流。もみくちゃにされた自分の体がどうなっているのか、確認する術もない。刀剣男士として身体能力は人間のそれをはるかに凌駕するとはいっても、自然の力には敵わないようだ。助けを求めようにも、口を開いたところで水を飲むだけで、声を発することすらできない。走馬灯のように、刀だった頃や本丸で過ごした記憶が頭の中を埋め尽くす。
仲間たちが己を呼ぶ声は、水音にかき消されてしまった。抵抗することを諦めた体は、吸い込まれるように一人流れに呑み込まれていく。それと共に、意識も混濁の淵に沈んでいった。
*
今日も照りつける陽光は眩しく、ジリジリと農作業に勤しむ村人たちを熱気で包み込む。春が終わりもうじき雨期を迎えようかというこの時期は、蒸し暑さを感じて作業の手も遅くなってしまいがちだ。
もう一刻ほどは田植え作業をしているからか、少しばかり腰が痛い。赤く塗られている爪の間には、すっかり土や泥が入り込んで汚くなってしまった。畑仕事は嫌いではないが、こうして体が汚れてしまうのだけはどうしても苦手だ。そろそろ昼飯時だし休憩するかという声がかかり、待っていましたとばかりに作業を中断して土手へと上がった。
木陰には田植えをしていた村人たちが集まり、各々持ってきた昼食を広げている。清八は何も持ってきていなかったが、こちらだと手招きする老婆の方へ向かうと、彼女は手製の握り飯と冷たい水の入った竹筒と共に出迎えてくれた。
「いつもありがとう」
「いいのよ、疲れたでしょう? たんと召し上がれ」
手を合わせていただきますと口にして、お清と二人で和やかな昼食の時間を過ごす。清八がもぐもぐと咀嚼するのを、嬉しそうに皺だらけの目尻を細めて見守られるのにもようやく慣れてきたところだ。
一見すると孫と祖母、といった風の清八とお清であるが、自分たちに血の繋がりはない。それどころか、ついひと月ほど前までは見知らぬ他人だったというのだから、慣れというのは凄いものだ。
清八は、およそひと月ほど前、お清と彼女の亭主である長兵衛によって命を助けられた。
その日山に山菜を取りに出かけた老夫婦は、帰り道川下に見慣れぬ大きな塊があることに気づく。恐る恐る近づいてみると、川岸に打ち上げられている人間が目に入った。昨晩は嵐だったから、きっと川に落ちて流されてしまったのだろう。瞳を閉じたまま動かないボロボロの青年には、まだ息があった。これは大変、すぐに手当をしなければと老体ながらも青年を自宅まで何とか運んだ彼らは、甲斐甲斐しく看病した。その甲斐あってか、その日の夜に青年は目を覚ます。
それが、清八と老夫婦の出会いだった。
青年は記憶の一切をなくし、己が何者かも分からぬ有様だった。行く当てもなく途方に暮れる彼を哀れに思った二人は、それならばこの村で一緒に暮らそう。いつか記憶が戻れば元いた場所に帰ればいいし、戻らなくとも新しい人生をここで過ごせばいい。と優しく声をかけてくれた。
後から聞いた話だが、彼らにはかつて清八と同じ年頃の息子がいた。彼は戦のために徴兵され、出陣先の見知らぬ土地で戦死し、その骨の一片すら夫婦の元には帰って来なかったという。きっと、青年に死した息子を重ねているのだろう。彼らにもらった『清八』という名前も、その息子と同じ名前だというのだから。
記憶が戻らない以上、老夫婦の死した息子に代わって彼らと共に暮らす生活に不満はない。長兵衛とお清はとても親切で、村人に清八が受け入れてもらえるようにとこうして一緒に働きながら交流する場を作ってくれている。
山あいにある小さな村には、滅多に見知らぬ者が訪れることはない。最初は余所者である清八に対して冷たい態度をとってくる者もいたが、村のために働く清八を見て仲間だと認めてくれたらしく、今では軽口を叩きながら共に働いている。村長だけは未だに清八のことを信用していないようだが、真面目に働いていればいつかは認めてくれるはずだ。素性の知れぬ己が何不自由ない穏やかな生活を送っていることに、清八は受け入れてくれた長兵衛とお清、そして村人たちに感謝の念を抱くばかりだった。
握り飯を食べ終えて一息ついていると、何やら後ろに座っている若い女たちの楽しそうな声が聞こえてくる。いつものように村の中の色恋沙汰でも話しているのかと思ったが、どうやら今日は違うようだ。
「なぁ、聞いたか? 今日旅の者が来て村ん中を歩いて回っちょるらしいんだけど、これがまたおっとこまえなんだってさあ!」
「ええ、本当? どんな人じゃろう、見てみたいなぁ」
「なんでも、綺麗な海みたいな色の目ぇして、みたこともねえ異人みたいな格好してるんだって! 腰に刀差してたらしいから、お侍さんかもしれねえ」
「へええ。それだったらすぐに分かりそうじゃ。後で探しに行くべさ!」
村の男衆たちは、きゃあきゃあと楽しそうに盛り上がる彼女たちを微笑ましそうに見守っている。だが、清八だけは彼女たちの話のある一点に、少しだけドキリとした。もちろん、考えすぎだとは思うのだけれど。
岸に打ち上げられていた清八が身に纏っていたのは、いかにも異人が着ていそうな服と刀だった。目が覚めた時はすでに老夫婦の家にあった着物を着ていたが、後からこれを着ていたのだと見せてもらった。膝丈ほどある黒い羽織と、白いピッタリとした留め具がたくさんついている肌着。その上には羽織と同じ色の袖のない、これまた留め具がたくさんある布。中でも珍しいのは、踵が細く尖った履き物や、耳についていたという金色の飾りだろう。
こんなものは見たこともない、と老夫婦は驚いていた。最初清八にはその意味が分からなかったけれど、こうして村人たちの服装を見渡せば、その服装が異様だったことがすぐに理解できた。
一体、自分はどこからやって来たのだろう。何者なのだろう。刀を帯びていたということは、侍だったのだろうか。異人のような格好と刀、という共通点だけで心がざわつくのはいくら何でも早計だと思うけど、その旅人のことが気にならずにはいられなかった。そろそろ再開するぞ、と声をかけられて、清八は思考を振り払うように作業へと没頭していった。
今日は集中したおかげか、夕暮れ時になるよりも前に仕事を終えることができた。早く帰って休もうと家路を急ぐ清八だったが、道の先で先ほど昼食の時間に盛り上がっていた女たちの一団がガヤガヤと賑やかに話しているのが見えた。囲うように立っているのでよく見えなかったが、どうやら女たちは中心にいる一人に対して矢継ぎ早に話しかけているようだ。
相手は先ほど話していた旅の者なのだろうと、すぐにピンときた。興味はあったが、彼女たちの輪の中に割り込んでまで話しかける勇気はない。
諦めて通り過ぎようとした時、不意に視線を感じたのでちらりとそちらを見ると、女たちの間からこちらを見つめる青年と目が合った。
(――なんだ。これは)
清八の胸の中に、強い違和感のようなものが生まれた。言葉にはできない、嬉しいのか悲しいのか、はたまた恐ろしいのかも分からない、不思議な感情が。ドク、ドクと鼓動が勝手に速くなっていく。
青年は清八を見て驚いたようにその大きな瞳を丸くした。陽の光を反射した海のように澄んだ色の瞳に、ポカンと見つめる清八の姿が映っている。紺色の羽織に黒い籠手、胸元に赤い紐を結んだ出でたちは確かに異人のようではあったが、彼によく似合っていた。
すぐに女たちに視線を戻した青年は、迷いなく問いかけた。
「すみません、彼は?」
その言葉に一斉に彼女たちがこちらを振り返ったものだから、途端に居心地が悪くなる。少し気まずそうに肩を竦めている清八のことなどお構いなしに、おしゃべりな女たちは清八が最近村にやって来た記憶のない青年だということを説明していく。その話を聞いて青年は少し考え込むように口に手を当てて俯いた。
早くこの何ともいえない空気から逃れたくて、清八はおずおずと口を開く。
「……あの。俺、そろそろ帰らないといけないので。すみません!」
「あっ、待って!」
引き止める青年の声を振り切り、逃げるように清八は家への道を急いだ。なぜだろう。全力疾走したわけでもないのに、心臓がバクバクと煩く鳴っている。こんなこと、目を覚ましてから一度だってなかった。自分の体に起きた得体の知れない変化が恐ろしく感じられて、気がつけば畑道を必死に走っていた。
どうやら旅人の青年は、この村を気に入りしばらく逗留することにしたらしい。素性の知れない青年のことを村長や周りの村人たちは訝しんだようだが、彼のことを歓迎する女たちに押し切られる形で滞在を許可した。今、人の住まわなくなったまま放置されていた古い家に、彼は一人で暮らしている。生活の手伝いを申し出る女もいたようだが、その全てを丁重に断ったと聞いている。
彼は、名を『堀川国広』と名乗った。その名前を人伝てに聞いた時も、清八の胸はざわついた。一体自分はどうしてしまったというのだろうか。彼はただ村に立ち寄った旅の青年、それだけなのに。彼の何がこんなにも己の心に波紋を生むのか、清八には検討もつかなかった。
だから清八は、できる限り堀川との接触を避けていた。その態度が伝わっていたのかどうかは分からないが、彼の方も自分から清八に話しかけてくることはしなかった。たまに遠巻きに見られているような気がすることもあるが、自意識過剰かも知れないと思い気に留めないようにしていた。
堀川が村に住むようになって二週間が経った頃、いつものように作業を中断して昼休憩をとっていると、また若い女たちの噂話が聞こえてくる。
「ねえねえ、ちょっと聞いてよ。最近堀川さん、夜遅くに時々北の山の方に歩いていくのを見かけるらしいよ。あんな何にもないとこに、何でだろうな」
「さあ?……あっ、もしかしたら、隣の村に親しい女でもいるんじゃ? そうだとしたら悲しいなぁ」
「そうじゃなくても、あんたとは恋仲にならんから安心しなって。それに、もしそうならわざわざこの村に住むより隣村に住むじゃろ」
「それもそうだわ。ああ、もしかして北の山に生えてる珍しい薬草でも探してるんじゃねえか? なんでも夜になると白く光って、煎じると恐ろしい効能があるって話だ」
「ああ、私は触れるだけで死んでしまう毒薬が作れるって聞いたことある。本当かどうか知らんけど、そんなおっかねえもん、商人でもねえ堀川さんが欲しがるとは思えねえよ」
「そりゃそうだわ」
相変わらず、女性というのは噂話が好きなようだ。しかし、彼女たちが話す内容は確かに少し気になる。堀川は何故そんなことをしているのだろう? 北にある山は険しく、特に夜は土地勘のある者でさえ一人で出歩くには危ない場所だ。獣や山賊などが潜んでいつ襲いかかってくるかもしれない。いくら刀を持っているとはいえ、自分だったら絶対に行かないだろう。
そうまでして出かけるのだから、あながち好きな女に会いにいくというのも見当違いな憶測ではないのかもな、と思いながら清八は仕事へと戻った。
その日の晩、清八は寝苦しさを感じて目が覚めた。すぐに目を瞑ってみたものの、中々寝つけそうにない。こんな時は水を飲めば多少は落ち着くことを知っていたから、井戸へ水を汲みにいくために外へと出た。夕刻から降り始めた雨は上がり、屋根からぽたぽたと雫が滴り落ちている。ぬかるんだ地面に気をつけながら裏手にある井戸に向かって歩いていると、ふと暗闇の中で人影が動くのが目に入った。
……あれは、堀川、だろうか。村に住むようになってからは簡素な着物に身を包んでいるため以前に比べれば目立たなくなったが、あの特徴的な跳ねた襟足は彼に間違いないだろう。山の方へと迷いなく歩いていく姿に、今日聞いたばかりの噂が早くも真実であったことを知る。
そのまま井戸に向かうこともできたが、何となく彼が何をしているのか気になってしまい、清八は気づかれないように慎重な足取りでその後を追った。
木々が生い茂る山の中、少し歩いた先の開けた場所で、堀川は懐から見たこともない四角い金属のようなものを取り出すと、そこに向かって何か喋り始めた。何を話しているのか、その詳しい内容は距離があるためにはっきりとは聞こえない。断片的に、「まだ」とか「時間が欲しい」といった言葉が聞き取れるくらいだ。
辺りに他の人間がいるようには思えないが、明らかに誰かに向かって話しかけている。もしかして、彼は忍の者か何かなのかと思っていると、堀川のさらに向こうの方で動く人影とキラリと光る刃物が目に入った。この辺りの山は、山賊や夜盗が旅人や商人を襲うといったことが珍しくない。堀川は話すことに意識を向けているせいか、迫る脅威に気づいていないように見える。咄嗟に清八は叫んだ。
「危ない!」
その声に気づいて堀川がこちらに顔を向けたのと同時に、得物を抜いた二、三人の男たちが彼へと走り寄ってきた。あっという間に彼を囲み、ニヤニヤと下品に笑う。
「おい、坊主。身につけてるもん全部置いてけ。そしたら、命だけは助けてやるよ」
武器を手に脅しをかけられる姿を見て、清八は後悔した。声をかけるのが、遅すぎた。自分がもう少し早く気づいていれば、きっと走って逃げられただろうに。清八がそんな悔恨の念を抱いている中、堀川は凛とした声で「それはできません」と答えた。一瞬で周囲の空気が殺気立つのを感じた。
ああ、このままでは堀川が殺されてしまう。あんな風に複数人の武器を手にした男たちに取り囲まれてしまっては、堀川の勝ち目は薄いはずだ。何か助太刀できるような、武器になるようなものはないか。
必死になって見つけた大きめの石を賊に向かって投げつけようとしたその時、堀川は腰に差した脇差を抜いた。そして一気に距離を詰めると、目にも止まらぬ速さで男たちを次々と峰の部分で斬り捨てていく。あまりにも、圧倒的な疾さだった。雨上がりの地面はぬかるんで足を取られてしまうだろうに、堀川の足捌きはそんなことを一切感じさせなかった。男たちは誰一人、まともに反応することすらできなかった。
その研ぎ澄まされた剣技を前に勝機がないことを悟った賊たちは「クソッ、覚えてろよ」と捨て台詞を吐くと、ほうほうの体で立ち去って行った。
すっとこちらを振り返る堀川と目が合う。危機が去って安心しきっていた清八であったが、ふと自分が彼の後をこっそりとつけてしまっていたことを思い出した。
「あの、ごめんなさい。……その、後をつけちゃって」
「全然いいですよ。危ないって教えてくれてありがとうございます、助かりました」
無垢な少年のような笑顔で礼を言われたものだから、緊張の糸が一気に切れた。後をつけられたというのに、そのことを気にしている様子は微塵もない。
何だ、思っていたよりも気さくでいい人ではないか。なんで彼のことを避けていたんだろうという気持ちからか、自然と声が溢れた。
「……ううん、これくらい当然ですよ。助けようと思ったのに、簡単にやっつけちゃうんだからすごいなぁ」
「そうですか? でも、ありがとうございます。その石で、僕に加勢してくれようとしたんですよね」
未だに握りしめたままの石を指差されて、慌てて地面へと放る。一瞬で何人もの敵を倒すほど強い堀川相手にこんなもので助太刀しようと思っていたのが、少し恥ずかしかった。
「い、いや、これは、他に何もなかったからつい……」
「嬉しいです。そうまでして、僕のこと助けようとしてくれたんですね。一歩間違えば君だって危なかったかもしれないのに」
「そうかもしれないけど……見捨てて俺だけ逃げるなんて、できないですよ」
堀川のことを怪しんでいたのは事実だが、彼が旅人でありながら村人の仕事を手伝っていることは知っている。そんな人が危ない目に遭おうとしていると分かっていながら何もせずに自分だけ逃げるなんて情けない真似は、ごめんだ。そう思ったからこそ、咄嗟とはいえ声が出たのだろう。
「……そういう優しいところは、変わらないんだね」
ボソリと聞こえるか聞こえないかの声で、堀川が呟いた。少し伏せられた瞳は、嬉しそうな、それでいて何か手の届かないものを見るように切なげな、不思議な表情をしている。今の言葉はどういう意味だろうかと問いかけようとするが、それよりも先にいつもの笑顔に戻った堀川が声をかけてくる。
「君は、勇気がある人ですね。助かりました、本当にありがとうございます。お礼といってはなんですけど、困ったことがあったら何でも相談してください。今度は僕が力になりますから」
「そんな大層なことはしてないですよ。……でも、そうですね、もしもの時は頼らせてもらうかもしれないです」
「もしもの時だけと言わず、いつでも気軽に頼ってくれていいですよ。こう見えて、お手伝いは得意な方ですから」
「うーん。そこまで言ってくれるなら、お言葉に甘えることにします。……あの、俺相手に敬語なんて使わなくていいですよ? 俺、ただの農民なんですから」
「じゃあ、君も僕に敬語はなしで。僕だってただの旅人なので。ね?」
「……えっと、いいんですか?」
「もちろん。改めて、堀川国広です。よろしく」
「俺は清八って言います。こっちこそよろしくね、堀川さん」
差し出された手に己のそれを近づけると、ぎゅっと握られた。何故だかそれは初めてのようには感じられなくて、けれど清八の胸の奥をぽかぽかと温かくしてくれた。
<中略>
遠くで祭囃子の音が聞こえる。堀川と二人、こうして何をするわけでもなく一緒にいるだけなのに、心はいつになく満たされていた。
そういえば、堀川と一緒にいるようになってから、記憶がないことに対して不安を感じることも随分と減ったように思う。彼といる時間は、不思議と清八に穏やかな安らぎを与えてくれる。ずっとこうしていられたらいいのにな、なんて少女じみたことを考えていると、ぽつぽつと堀川が口を開く。
「……ねえ、君はまだ辛い? 記憶がないこと」
出会って間もない時、清八は「俺はどうして記憶が戻らないんだろう」と彼に弱音を吐いたことがある。自分としては軽くぼやいたくらいの感覚でいたけれど、優しい彼のことだ。きっとそのことをずっと気にかけてくれていたのだろう。
「……ううん。もう、あんまり気にしなくなったかな」
「本当に?」
「うん。記憶がなくてもさ、きっと俺は俺なんだと思う。根っこの部分は、変わらない気がするんだ。それにさ、今の俺には長兵衛にお清、村の人たち……それに、堀川さん。大切な人がたくさんできた。だからもう、記憶が戻らなくても別にいいかなって」
「そっか。……うん、僕もそう思うよ。君は君だ。記憶が戻ろうが戻るまいが、君の根底にある部分は変わらない。これから先、ずっとね。自分自身でそう思えるようになったなら、良かった」
……なぜだろう。良いことだと口にしているはずなのに、堀川の笑顔は、どうしてかとても寂しそうに見えた。
「……刀剣男士の記憶なんて、もう君には必要ない。『清八』として生きていく方が、きっと幸せなんだね」
ポツリと独り言のように放たれた言葉の意味が、清八には理解できなかった。でも、堀川が辛そうなことだけは、理解できた。どうしてそんなに苦しそうなの、と声をかけるよりも先に、堀川がこちらを見つめてそっと手を握ってきた。
突然のことに少し驚いたけれど、それよりも触れた指先から伝わってくる体温の温かさが心地良かった。あまりに心地良かったものだから、問いかけようとした言葉は喉奥に消えてしまう。
真剣な眼差しが、清八を捉える。喋ろうと口を開いては躊躇して閉じ、といったことを何度か繰り返した後、意を決した唇が動いた。
「……清八くん。君にお別れを言わないといけない」
……嘘。どうして、そんなこと。突然の言葉に、少しの間思考が停止する。握られた手に汗が滲み、耳のすぐそばで鳴っているんじゃないかと思うくらい心臓の音が煩い。堀川は、旅人だ。この村にずっと住むわけじゃない。だから、いずれは村からいなくなる。それは理解していた。けれど、こんな風になんの前触れもなく別れを告げられるなんて、思っていなかった。
急にどうしたのだと詰め寄ろうとした瞬間、堀川は眉間に皺を寄せて後ろに視線を向けた。清八は、堀川の顔が急に強張った原因を一瞬理解できなかった。しかし、ガサガサと草を踏みしめ掻き分ける音から、何者かがここに近づいてきていることをすぐに察した。
こんな賑やかな夜だというのに、また夜盗でも現れたのか。祭りに乗じて、物盗りでもしていたのだろうか。全くもって、迷惑な話だ。
そんなことを思っていた清八だったが、隣にいる堀川の表情はいつになく深刻なものだった。賊など簡単に追い払ってみせた堀川がどうして、と思った時には、堀川は握っていた手を離し素早く立ち上がって腰の刀を抜き、音のする方へと駆け出し始めていた。
「ここにいると危ない。すぐに祭りの会場か村に戻るんだ、いいね」
「えっ、でも、堀川さんはどうするのさ」
低い声で指示を出した堀川の背中が、みるみるうちに遠ざかって小さくなっていく。清八の問いには答えずに宵闇に紛れた方角から、キン、キンと刃が交わる音が響いてきた。相手が何者なのかは分からないが、少なくともこの間の賊たちよりもはるかに強い敵と戦っているのだろう。
……こうしている場合じゃない。悔しいけれど、清八一人が加勢したところで彼の役に立つとも思えない。それよりも早く助けを呼んだ方が助力になるだろうと判断して、すぐさま走り出した。
<中略、ここから先R-18>
返事と共に触れるだけのキスを返すと、くしゃりと堀川の表情が緩む。本丸で共に過ごしていた頃ですら、こんなにも幸せそうな顔は見たことがない。自分だけに見せてくれる顔だったらいいな、なんて思っていると、首筋にキスを落とされる。
強く吸われて、ピリッと痛みを感じたかと思えば、堀川の指がそっと脇腹を撫でて、そのまま胸の方に上がってくる。最初は様子を伺うようにふにふにと優しく触れていたけれど、だんだんとその手つきは欲を引き出すような動きに変わっていった。少しずつ硬くなっていく先端を押し回されて、じわじわと快感が滲み出てくる。
声を出さないように敷布をぎゅっと握りしめて耐えている清光の姿を見て、堀川は少し意地悪っぽく笑ったかと思うと、指の動きはそのままに片方の突起に舌を這わせて先っぽをつんつんと刺激してきた。抜けるような快楽が胸から身体中に駆け抜けて、思わず声を上げてしまう。
「ぁあっ! ぁ、……んっ、ふぅ、んん……っ!」
「駄目だよ、清光くん。声、我慢しないで? 大丈夫、僕にしか聞こえてないから」
「だ、だって、恥ずかし、……ぁ、ぁああん! やぁ、あんっ、すっちゃ、だめぇ……!」
乳輪ごと口に含まれたかと思えば、すかさずちゅぱちゅぱと音を立てながら吸われる。思わず彼の髪に指を差し入れるが、全く気にした風はなく胸への愛撫は続けられる。
てらてらと濡れた乳首は、普段の柔らかさは姿を消してピンと豆粒のように硬く立ち上がっていた。舐め回す舌にもっとと強請るようにその存在を主張しているような、そんな風に己の身体が浅ましいものへと変わっていっているように思えて、清光の身体はますます熱を帯びていく。
下腹部の熱は最高潮に達し、完全に勃ち上がった己の性器が堀川の引き締まった腹に当たっている。先端から漏れ出る先走りがぬるぬると堀川の腹筋を汚しているのを感じてしまい、思わず恥ずかしさの余り顔を背けてしまう。そんな清光の反応を目ざとく感じとったらしい堀川は、上向いた清光自身に指を添えてそっと包んだ。
最初は撫でるように優しい手つきだったが、次第に気持ちいい部分を探り刺激するような、明確な意志を持った動きに変わっていく。
「……あっ、はぁ、……んっ、あ、ほりか、だめ、……っ、もう、でちゃう……っ!」
「いいよ。清光くんのイくところ、僕に見せて?」
その言葉とともに、裏筋を指の腹でグリグリと押される。雷に打たれたような強い快感が、頭のてっぺんから爪先まで駆け抜けた。
「ぁ、っ……ぁあ、イくっ……――っぁ、ぁああああああアア‼」
仰け反りながら身体を震わせ、必死に堀川の背中に腕を回して爪を立ててしがみつく。ドクドクと勢いよく、迸りが二人の腹を汚していった。どろりと濃い白濁がポタポタと堀川の腹から己の腹へと滴り落ちる光景が、堪らなく扇情的に見える。
射精が落ち着いてもなお、清光の身体は熱く火照ったままだ。よく出せましたと言うように先端をすりすり撫でた後、堀川はゆっくりとまだ緩く勃ち上がったままの清光のモノを咥えた。ぬるぬるとした舌がくびれの部分を丁寧になぞり、ゾワゾワと気持ちよさが下半身を支配する。
「んっ、はぁ……っ、うう、……やだ、そこ、……きたな、いから、……ああ、ああっ!」
静止の声など聞こえていないかのように、堀川の舌は清光自身に絡みついては的確に快楽の種を摘み取っていく。喘ぐ清光の反応を見て大丈夫そうだと判断したのか、陰茎を口で愛撫しながら腹に残ったままの精液を掬うと、ピタリと閉じた窄まりへと塗りこめていく。くちゅくちゅと艶かしい水音が耳に届いて、ますます身体を熱くさせた。円を描くように縁をなぞられて、開かされた足が震える。
慎重に入れられていく堀川の指を拒むように己のナカは収縮し、侵入者を締め付けた。痛みに思わず顔を顰めていると、すかさず口に咥えられたままの性器を喉で扱かれ、甲高い喘ぎが喉から出てくる。舌で鈴口をチロチロと舐められ、痛いくらいの快感が全身を支配する。
清光が口淫に意識を向けている間に、堀川は指を奥へと忍ばせていく。恐らくまだ痛みは感じているのだろうけれど、陰茎を刺激されて感じる愉悦の方が上回っているせいで全く気にならなかった。
清光が強い悦楽に耐えながら敷布をぎゅっと握りしめていると、突然電流のような衝撃が走った。一層高い嬌声が上がり、背がしなる。一体何なんだと下腹部へ視線を向けると同時に、腹の中に埋められたままの指がある一点を擦る。するとまた先ほどのように衝撃が走る。ビリビリと、まるで電気を流されているようにすら感じるそれは、今まで経験したことのない、強烈な快感だった。
「ああっ⁉ あっ、うぁ、だめ、……っ、ああ! イッちゃ、イッちゃう……やめっ、あああ‼」
いつの間にか二本に増えた指で、引っ掻くように膨らみを刺激される。同時に陰茎を咥えたままの口が窄められ、圧迫される。性器と後孔、前と後ろを同時に可愛がられて、多幸感と共に鮮烈な光悦が清光を包み込む。
必死に口を離すように堀川の肩を叩くが、清光を弄り回す舌の動きは止まらない。それどころか、射精を促すように激しくくびれや尿道口を舐め回し、突かれる。じゅるじゅると先走りと唾液が混ざった啜られる音が、官能的に響いて理性の糸を切っていった。
「ああっ、堀川、ほり、かわ……っ! あああ、だめ、もう、でるっ、――あああん‼」
ぐいと胎内のしこりを押し上げられたことにより我慢の限界を迎えた陰茎から、清光の欲望が溢れ出てくる。それは瞬く間に堀川の口内を満たしていったが、溢れてくることはなかった。
どうやら彼は吐き出されたものを飲んでいるらしい。ごくごくと上下する喉が、それを物語っている。ずず、っと精管の中に残っていた残滓まで残らず飲み干すと、ようやく堀川は口を離した。二度も達した清光自身はさすがに萎えてしまっているものの、ベタベタに濡れた竿から堀川にどれほど可愛がられたのかがありありと伝わってくる。
「……俺、汗かいちゃったから汚いのに。堀川のばか、飲まないでよ」
「清光くんの身体に汚いとこなんてあるわけないじゃない。それに、すごく美味しかったよ」
「……そんなわけないじゃん」
「うーん、本当なんだけどなぁ」
そう苦笑しながら差し入れられたままになっていた指を引き抜かれると、今度は震える蕾に舌が添えられる。蛇のようにぬるぬるとした感触が、這うように中へと入って来た。舌先で肉襞をぴちゃぴちゃと舐められると、先ほどとはまた違った快感が身体に染み込んでくる。
「なっ、ちょっと、ダメ、そこは、ほんとに汚いから、舐めちゃやだ、……っあ!」
「清光くんのナカ、ひくひくしてて可愛いね」
「そんなとこっ、かわいくな、い、……ひあっ、ああ、んああ!」
舌先を器用に動かされる度にもたらされる気持ちよさに、内腿がひくひくと反応し身悶える。舌の届く範囲まで丹念に舐められた後、ようやく解放された。
指と舌の両方で解された中は、ぱくぱくと震えながら中の媚肉を晒している。力の入らない足を抱えられると、大きく開かされる。
その先に、腹につくほど硬く勃ち上がった堀川の性器が見えた。濡れた先端がぬらぬらといやらしく光っていて、今からあれに犯されるのだと考えるだけで、堪らなく欲を掻き立てられる。指や舌でも相当気持ちよかったと言うのに、それを遥かに上回る質量で貫かれてしまったら、自分はどうなってしまうのだろう。