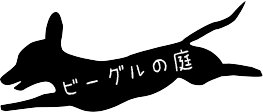その夜、本丸を嵐が襲った。轟々と叩きつけるように響く風と、時折ゴロゴロと雷鳴を轟かせる音が本丸中に響き渡る。雷が落ちたせいか、一部の電気が使えなくなってしまい、辺り一帯が暗闇に沈む。こんな状況では寝る前の時間を楽しむことも、眠りにつくこともままならない。
僕達を気遣う主さんが大丈夫かと心配しながら『耳栓』という音を多少なりとも防ぐことができる道具を配ってくれた。有り難く頂戴して、明日の内番の任に備えて床に就く。横で寝苦しそうに寝返りを打つ兼さんは、明日からは確か出陣のはずだ。
どうか彼がぐっすりと寝れますようにと祈りながら、薄れゆく意識に身を委ねた。
次の朝は昨晩の大荒れの天気が嘘のように、心地よい澄んだ空気と晴れ渡った青空が待ち受けてくれた。これなら仕事も捗りそうだな、なんて思いながら、僕はまだ夢の中にいる兼さんを横目に着替えをすませ、朝食の支度をするべく廊下を進む。
何だかいつもより騒がしいような気がする。もしかして、まだ昨日の電気の不具合が残ったままなのだろうか。だとすれば、厨房もいつも通りには使えないのかもしれない。
一先ず状況を確認しようと、人の声がする広間の戸を開けて挨拶をする。
「おはようございます、どうかしましたか?」
「ああ、おはよう……堀川か」
振り返って少し驚いた様子の主さんが真っ先に目に入ってくる。僕が朝早く起きてくることなど別に珍しいことでもないのに、どうしたんだろう。
次いで、主さんの向かいに立った人物に目をやる。それはどう見ても、僕の相棒の兼さんで……。
あれ、おかしいな。兼さんはまだ部屋で寝ていたはずだ。僕を追い越してここに来ることなど、できるはずないのに。もしかして、僕はまだ寝ぼけているのかもしれない。
そんなことを考えているうちに、兼さんの顔が驚愕の表情を浮かべ、それからすぐに喜びに打ち震えたかと思えば、僕の方に猪の如く突進するように迫ってくる。
あまりの速さに避けることもできず、その両の腕にひしと抱きしめられる。体が軋むほどの力強さに、現実へと意識が戻ってきた。
「あ、あの……兼さん?ど、どうしたの?」
「どうしたもこうしたもねえよ……お前、国広だよな?オレの相棒の、堀川国広で間違いねえよな?」
「も、もちろんそうだけど……」
「……会いたかった。ずっと、会いたかった。会うことなんてできねえはずだったのに、神様って奴の気まぐれか?……何にせよ、感謝しなきゃいけねえなあ」
顎から滴る雫が、彼が涙を流していることを示している。まるで本丸で何百年ぶりに再会した時のような反応に、僕は困惑を隠しきれそうもない。これはどういうことなのかと主さんに視線を移すと、複雑そうに眉を顰めて説明を始めてくれる。
「堀川、落ち着いて聞いて欲しいのだが……お前が顕現する前に、一振り目の『和泉守兼定』がいたことは以前話したな?戦場で散ってしまった一振り目、それが今お前の目の前に立っている兼定の正体だ」
「え……ええ?ど、どういうことですか?折れてしまった刀が蘇るなんて、そんなことあるんですか?」
「私も聞いたことはないが……昨夜の嵐によって、この本丸のシステムは一時ダウンした。今朝までに何とか復旧したが、おそらくその障害の影響でかこの一振り目の兼定が現れた。折れる瞬間までのこの本丸で過ごした記憶を持って、な」
一体どういう原理かは分からないが、先ほどまで自分の隣で寝ていた兼さんとはまた別の兼さんがこうして僕を抱きしめているという現実がある以上、主さんの言葉を信じるより他ない。
前に、聞いたことがある。確か、主さんと加州さんと話していた時のこと。
この本丸には、かつて『和泉守兼定』がいた。本丸の黎明期、まだ短刀ばかりの中で一振り目の兼さんは鍛刀され、貴重な戦力として腕を振るった。頼もしい刀剣男士であった彼は、しかし予期せぬ検非違使の襲撃から仲間を守るために殿として戦い、壮絶な戦闘の末に折れてしまったと言う。
その話を聞いてあまり時間が経たぬうちに二振り目の『和泉守兼定』、今現在も本丸で活躍する兼さんが顕現したため、頭の片隅に仕舞われていた記憶だった。
「和泉守は、堀川にすっごく会いたがっていたんだよね……今ここにいないのが、残念だな」
少し切なげな顔をして加州さんが語ったことを思い出す。今、こうして渾身の力で僕を抱きしめる兼さんを前にして、ようやく彼の話したことが実感を持って伝わってくる。
「ごめんな、国広……死んじまったはずのオレが突然現れて、その上こんな風に泣きついて……驚いたよな。でも、済まねえ……もう少しだけ、こうしていても良いか……?」
そんな、この世の終わりのような表情を浮かべた彼の頼み事を断れる者など、地獄の閻魔大王でもなければいないだろう。
「うん、もちろん大丈夫だよ。僕の方こそごめんね、もっと早く顕現していれば兼さんに会えたのに……」
「お前がそんなこと気にする必要ねえよ……何の因果かこうして出会えたんだ。オレはそれだけで、今まで生きてきた中で一番幸せだぜ」
ぽたぽたとこぼれ落ちる涙から、震える腕から、彼がどれほど僕のことを想ってくれていたのかが伝わってくる。そんな様子の彼をただただ傍観することなど憚られて、その背に腕を回そうかと思った時。広間の入り口を威勢よく開く者が現れた。
「ふあぁ……まだちっとねみいな。よお主、おはようさん。そっちにいるのは国広、っと……?」
あまり良いタイミングとは言えないところに、僕の相棒、二振り目の兼さんのお出ましだ。僕を抱きしめる存在を視界に入れると、眠たげな目は一気に見開かれて、全速力でこちらに走ってくる。その勢いのまま、僕に抱きつく兼さんを引き剥がした。
「おい、てめえ何国広に抱き着いてやがる!?つうかその見た目……どういうことだよ?」
「ってえなあ……なるほど。お前が、二振り目の『和泉守兼定』か」
涙で腫れた目を擦りながら落ち着いて兼さんを見つめる一振り目とは対照的に、兼さんは訳がわからないとばかりに僕と一振り目、そして主さんを交互に見つめる。
まあ少し落ち着きなさいと宥めた後、主さんが先ほど僕に話した内容を兼さんに説明してくれた。
「……状況は理解したがよ。未だに信じられねえな。折れた刀、しかもよりによってオレが目の前にいるなんて」
「まぁそうなるわな。オレだって突然気付いたらこの本丸にいて驚いたし、夢か、それかここが天国って奴か?って思ったからよ」
二人の兼さんが顔を突き合わせて話している姿は何だか不思議な光景だ。同じ刀は一振りしか顕現させないという主さんの信条のため、この本丸に一振り目と二振り目が同時に存在することはない。
だから、見慣れぬ状況を目にした多くの刀たちが驚いていたし、一振り目と親交のあった刀たちは彼との思わぬ再会にこの上なく喜んでいた。
無理もない。死というのは、突然振りかかる厄災のようなものだ。彼と永遠の別れが訪れるなど、誰もその時が来る瞬間までは分からないのだから。
兼さんへの説明が終わった後、主さんはこの障害、もといバグを解消するために政府へと直接足を運んで説明して来ると言って出かけて行った。その間、一振り目の面倒は堀川が見るように、との言付けを預かった。
兼さんは少し不満気だったけど、一振り目がどういう最期を遂げたのかは聞き及んでいる。僕との再会を心待ちにしてくれていたというのも、同じ『和泉守兼定』だからこそ誰よりも理解しているのだろう。
渋々、仕方ねえなと呟きながら了承してくれる。
兼さんは今から数日の間は出陣のため本丸を空ける。どう考えても、一振り目の兼さんのお世話をするのは、僕が適任だろう。
「じゃあオレは行ってくるけどよぉ……あんまり国広に迷惑かけるんじゃねえぞ。それから、時間は大切に使えよ」
「んなこと言われなくたって分ぁってる。……まぁ、気い使ってくれるのは有り難てえけどな。出陣、気を付けて行ってこいよ」
僕と一振り目を交互に見やって少し名残惜しそうにしながら、兼さんはゆっくりと歩いていく。遠くなっていく背中にいってらっしゃいと声を掛ければ、へいへいと手を振りながら応えてくれる。
主さんと兼さんが留守の間は、僕が責任を持って一振り目の兼さんが楽しく過ごせるようにお手伝いしなきゃ。そう思えば背筋が自然と伸び、やる気が満ち溢れてくる。
隣で兼さんの背中を見送っている一振り目の兼さんは、眩しいものでも見るかのような、まるで自分には手の届かないような何かを見ているような、少し寂しい表情をしているように感じられた。
面倒を見るといっても、僕にも自分の仕事というものがある。今日は長曽祢さんと一緒に馬当番の任に当たる予定だ。申し訳ないけど、兼さんにも手伝ってもらわなければいけない。
僕の相棒の兼さんは内番のお仕事があまり好きではない。だからきっと彼も嫌がるかと思っていたので、よっしゃあやるぞ!と意気揚々と馬小屋を掃除していく姿を目にして驚きを隠せなかった。
「何だ、随分とやる気満々だな……何かあったのか?」
長曽祢さんも首を傾げながら生き生きと作業に勤しむ兼さんを見守っている。ぼんやりしていたら兼さん一人に仕事を任せることになりかねない。
慌てて自分も箒を手にして追随した。おれの仕事も残しておいてくれよ?と嬉しそうに笑う長曽祢さんと、オレが長曽祢さんの分も働いてとっとと終わらせてやるよ、と笑顔を見せる兼さん。
いつも以上に賑やかで、それでいてとても平和な一日になりそうだ。僕はジャージの袖を捲ると、二人のやり取りを横目に作業を始めた。
予想していたようにいつもより早く仕事が終わり、長曽祢さんは今日非番の浦島くんに一緒に遊ぼうよと強請られる。まだ片付けが残っているからちょっと待っていろと声をかける長曽祢さんに、後はオレと国広でやっとくから弟の相手してやりな、と優しい助けの声がかかった。
済まんな、と頭を下げた長曽祢さんの背中が去っていく。二人きりの馬小屋で、先ほどからずっと気になっていたことを問いかけてみた。
「兼さんって、内番が好きなの?その、もう一人の兼さんは、あんまり内番のお仕事が好きじゃないから」
「はっはっは、そうだろうなぁ。オレだって別に好きな方じゃなかった。でもな、戦い以外でもこうして体動かして、主のために働くってのも良いもんだ。もうこんなこともできなくなっちまったからこそ、そう思えるようになったんだよ」
「……そっか。兼さんは大人なんだね」
「あいつよりも生きてる時間は短いけどな。失ったからこそ、気付くもんがあるのさ」
その言葉は、ずしりと重みを持って伝わってくる。今こうして僕の隣にいる彼は、確かに一度その命を失って。それでも、何の因果か再び生を受けた。
いつまで続くか分からない不安定な命を、ここに在る一瞬一瞬の時間を噛み締めるような、そんな切ない言葉。
それになんと返せばいいか分からずに、押し黙ってしまう。そんな僕の様子を見て、がしっと肩を組んで場の空気を明るくしてくれる。
「んな辛気臭い顔すんなよ!オレは今こうして国広と一緒にいられてすげえ嬉しいんだぜ?お前にも、できればオレと一緒の時間を楽しんで欲しいんだよ」
「……うん、そうだよね。僕も、兼さんと会えて、こうして一緒にお仕事して、お喋りすることができて……とっても嬉しいよ。本丸に戻ったら休憩しよう?僕、うんと美味しいお茶を淹れるから!」
「国広の淹れた茶ぁ飲めるのか、そりゃあ楽しみだな!そうと決まれば、ちゃっちゃと片付けるぞ!」
「はい、兼さん!」
時間の許される限り、彼の側にいよう。彼が生きているうちにできなかった分まで、うんと。そう、僕は心の中で密かに決心した。
兼さんは僕の淹れたお茶を、うまいうまいとそれはそれは僕が照れてしまうほど何度も口にして褒めてくれた。厨房で会って一緒にお茶をすることになった歌仙さんも、最初はうんうんと頷いてくれたが、兼さんがいつまで経っても賛辞をやめないものだから、少し驚いていた。
きみは本当に堀川くんのことが好きなんだね、と微笑みかける歌仙さんに、あったりめえだろ、国広はオレの自慢の相棒だからな!と胸を張って答える姿は、少し気恥ずかしくも嬉しかった。
兼さんの相棒として相応しい存在であるようにと日々心掛けている僕にとっては、一番の褒め言葉だから。もう十分だよと言おうとするけれど、彼に褒めてもらうのが心地よくて、ついつい喉奥にその言葉を引っ込めてしまう。
そんな僕たちのやり取りを、微笑ましそうに目を細めて見つめる歌仙さん。何気ない時間が、何よりも幸せに感じられた。
夕飯を済ませてお風呂に入った後、僕はいつものように兼さんの髪を梳かす。毎日の習慣だからと一振り目の兼さんにも同じように対応したら、身を任せながらも驚きの表情を浮かべてじっと見つめられる。
「……お前、いつもこんなことしてんのか?」
「え?うん、そうだよ。あっ、でも兼さんが僕にやらせてるわけじゃないよ?僕の方から、手伝わせて欲しいってお願いしてるんだ」
「ほおー?随分と羨ましいことだなぁ」
「そうかな?今日は……ううん、兼さんがここにいる間は、僕にやらせて欲しいな。……駄目かな?」
「んな訳ねえだろ。ありがとな、国広に髪の毛触ってもらうの、すげえ気持ち良いわ」
目を細めながら嬉しそうに笑う姿が、毛繕いをされている猫みたいでちょっと可愛いな、なんて思ったのは内緒だ。かっこ良くて強い刀を自称する兼さんにとって、可愛いなんて言われるのは心外だろう。
きっちりと艶めく髪を整え終わって道具を片付けていると、後ろから視線を感じる。
律儀に僕の寝る準備が終わるまで待ってくれているのだろうか。あまり待たせてはいけないとテキパキと片付け終えて、お待たせと振り返ろうとしたところで、腕をぐいと引っ張られる。
そのまま兼さんの腕の中に倒れ込む形になった僕を、しっかりと二本の腕に抱き止められた。
「兼さん?どうしたの……?」
もぞもぞと顔を出して兼さんの表情を窺う。形容し難い表情を浮かべた兼さんの顔が、そっと近づいてくる。
「国広に会えた、それだけで十分過ぎる程の幸運だってのは分かってる。……分かってるんだが、こうして側にいると、どうにもな。それ以上を求めちまう。……オレはいつからこんなに贅沢もんになっちまったんだろうな」
それ以上、とは何を指すのだろうか。僕がそれを口にするよりも早く、唇に何かが触れる。少しかさついた、それでいて柔らかな感触。
僕は、これをよく知っている。……当然だ。僕と兼さんは、この本丸で過ごすうちにただの相棒だけでなく、恋仲になった。だから、兼さんの唇の触り心地を知らないはずなどない。
──尤も。今僕と唇を合わせているのは、僕の恋人の兼さんではない。そう思った瞬間、頭の中がサーっと凍てついて冷たくなっていく。兼さんの寝間着の合わせ目を引っ張ると僕の意図が伝わったのか、そっと唇が離れていく。
名残惜しい、などと感じてはいけない。彼は、僕の恋人と同じ姿だけど、僕の恋人ではないのだから。
「あ、あの……兼さん」
「済まねえな……お前と二振り目が『そういう関係』だってのは知ってる」
「……えっ」
誰から聞いたのだろうか。長曽祢さんや歌仙さんがそんなことを話すようには思えないけど。きっと、加州さんか大和守さんが話したんだろうな。
「それを知っていながら、お前にも、二振り目にも悪いとは思っている……けどよ、どうしても、止められねえんだ。オレは、お前のことが大好きだ。相棒として、そしてそれ以上に。生きているうちから自覚はしてたが、ここでお前と過ごすうちに、その想いはどんどん強くなっていった」
震える腕が、声が、伝えてくる。彼の言葉の一つ一つが、とても真剣で、真っ直ぐな気持ちを持って発せられているのだと。
「最低な本差だと軽蔑してくれても構わねえ。……だから、どうか。今晩だけは、オレをお前の恋人の『和泉守兼定』の代わりだと思ってくれねえか?」
……一振り目の兼さんを、僕の恋人の二振り目の兼さんと思う、だって?
「……無理だよ。そんなこと」
「……そうだよな。当然、だよな。オレはとんでもねえクソ野郎だな。本当に済まねえ……お前の気持ちを、一番に考えるべきだってのによ」
縋るように見つめる瞳が、悲しみに歪められていく。
――違う。違うんだ。心優しいあなたにそんな寂しい顔、して欲しくない。させてたまるものか。警鐘を鳴らすように煩く響く心臓の音に逆らうように、兼さんの顔に手を伸ばす。
「だって、あなたは二振り目の兼さんとは違う。……僕にとって大切な、一振り目の兼さんなんだもん。僕のことを死ぬ瞬間まで待ってくれた、仲間のために命を懸けることができる、そんな素敵な刀なんだ。……だから、代わりだなんて、そんな悲しいこと言わないで」
「国広……」
驚きと嬉しさが混じった瞳を見つめ、掌で包んだ兼さんの顔に自らのそれを近づける。
ああ、ごめんなさい、兼さん。あなたから見れば、これは立派な裏切りだ。たとえ姿形は同じ『和泉守兼定』だとしても、決して許されることじゃない。
──でも。どうしても、僕は彼を拒絶できない。一人で戦い、戦場にその命を散らせた彼を、愛おしいと思わずにはいられない。僕の本能が、彼を受け入れたいと、叫んでいるのだ。
そのまま今度は僕の方から口付ける。まだその唇は少し震えていたが、僕の口付けが深くなるにつれて、緩やかに落ち着きを取り戻していった。
恐る恐る、彼の舌が僕の咥内へと入り込んでくる。ぎこちない動きが何だか新鮮で、そして愛おしく感じられて。それを迎えにいって絡めれば、体ごと褥の上に押し倒される。
夢中になって抱き合う僕たちを、夜の帳が包んでいった。
***
こうして、僕と一振り目の兼さんは契りを結んだ。彼は、壊れ物にでも触れるように優しく、僕を抱いた。比喩などではなく、本当に僕の全身は余すことなく舌で舐められ、愛撫され。
ぐずぐずに蕩けた僕を傷つけないように、それはそれは慎重に、彼の猛りに貫かれた。逐一僕の身体を気遣って大丈夫かと尋ねてくる様子が堪らなくて、浅ましくも自ら腰を押し付けて乱れてしまったように思う。
思い出すと顔が熱くなってしまうが、紛れもなく僕の意志で行ったことなのだから、どうしようもない。次の朝目が覚めて、彼に抱きしめられているうちに眠ってしまったのだと分かった時は、胸の奥が温かくなった。
それで、気がついてしまった。
二振り目の兼さんのことを恋人として愛おしく想う気持ちとは別に。一振り目の兼さんのことを
好いている自分の気持ちに。
最低なのは、一振り目の兼さんなんかじゃない。僕の方だ。二人の刀を同時に好いてしまった、僕の方なんだ。
身支度を整えた僕たちは、ごく普通の相棒として振る舞った。誰も、僕たちが『特別な関係を持った』などとは思わないだろう。
僕自身、何事もなかったかのように振る舞う兼さんを見て、昨晩のことは夢だったのではないかと思ったくらいだ。
もちろん、夢な訳などない。前の日と同じように寝支度を整えて部屋に戻ると、さも当然のように抱きしめられ。愛を囁かれて、優しく褥に寝かされる。僕に覆いかぶさる兼さんを受け入れるのも、心の中でこそ葛藤はあれど、身体は拒否しなかった。
彼の肉体も、魂も。いつ消えてしまうともしれない、儚い存在だ。明日目が覚めたら、跡形もなくその存在が消え失せていたとしても不思議ではない。
そんな現実を考えるだけで恐ろしくなってしまい、狂ったように彼を求めてしまう。一瞬でも長い時間、彼と愛し合いたい。そんな気持ちが抑えきれない。
次の日は、酷かった。僕は元々非番だったけれど、ざあざあと雨が降っていたこともあり、大した家事手伝いもできず。昼間過ぎからひっそりと部屋に篭っては、貪るように身体を繋げた。
何度も何度も、腰を叩きつけられ。腹が膨れてしまう程、彼の欲望をその中に受け止めた。それなのに、夜も我慢できずに、求め合う。理性の箍がどこかに消え去ってしまったかのように、爛れた時間を過ごした。
そして、現実は残酷に終わりを告げてきた。次の日は前日の疲れから昼前まで寝てしまい、遅めの昼食を終えた頃。出陣していた兼さんの部隊が無事に帰還したのだ。
意を決した僕は、大好きな恋人を出迎えた。それは甘い時間を過ごすためなどではなく。彼に全てを話し、謝罪する。到底許してもらえるはずなどもないが、隠しておくことなど僕の矜持が許さない。
畏まっていざ話そうとした時に、部屋の襖が開く。タイミングが悪いな、なんて部屋の入口を見やると、政府から帰ってきた主さんと一振り目の兼さんが連れ立って入ってくるのが見える。ひどく深刻そうな面持ちに、今から告げられることが良い知らせではないことが察せられた。
「やあ、二人とも揃っているね。兼定が帰ってきて早々に悪いが、大事な知らせがある。彼、一振り目の処遇なのだが……単刀直入に言う、彼の命は今日を最後に失われる。政府に何とか彼が存在し続けていられるようにと進言したが、不具合を放置することは法に反する行為だと、聞き入れてはもらえなかった。明日の朝までには、一振り目の魂と肉体は、消えてしまう。それが政府の下した処置だ……力及ばずに済まない」
深々と頭を下げる主さんの隣に立つ一振り目の兼さんは、重たい悲しみを帯びた、しかしどこか安心したような表情を浮かべている。悪い予想が当たってしまった衝撃で呆然としてしまった僕に代わって、兼さんが懸命に食い下がる。
「……主、何とかならねえのかよ。そもそも一振り目がこうして現れたのは、政府のシステムの不具合が原因だろ?つまり、政府のせいじゃねえか。それなのに、勝手な都合ではい消えますなんて、そんなのおかしいだろ?」
自分と同じ存在が隣にいる。それに違和感を感じるどころか彼を必死になって庇う兼さんの優しさに、ちくちくと罪悪感が胸を突き刺していく。こんなにも思いやりのある人を、僕は裏切ってしまった。
それに、一振り目が消えてしまうというのに、僕には何もすることができない。主さんのように政府に抗議することすら、僕には許されていないのだ。一振り目の兼さんは、僕をこの上なく大切にしてくれたと言うのに。
こんなにも己に無力を感じたのは、前の主の命を助けられなかった時以来だろう。今度も僕は、大切な人の命を守ることができない。
「本当に申し訳ない。私の力では、政府の考えを変えるには至らなかった。兼定は、命を賭して私に尽くしてくれたと言うのに……情けない限りだ」
「おいおい、あんまり主を責めるなよ。オレのためにここまでしてくれたってだけで、臣下として十分すぎる名誉だぜ。それに、お前や国広も。オレのことを惜しんでくれる、その気持ちだけでオレは満足だよ。だから、これ以上とやかく言うのは無しだ。いいな?」
「……他でもないお前がそう言うなら、仕方ねえな」
不満気な表情は収まらないが、当の本人が納得しているということで兼さんも渋々引き下がる。僕はといえば、彼に掛ける言葉も見つからず押し黙るばかりだ。
俯く僕の肩がポンポンと叩かれたので顔を上げると、そこには精一杯笑う一振り目の顔があった。
「オレのことを気にかけてくれてありがとな。最後に目一杯、楽しい思い出作ろうぜ」
一番辛いのは、あなたのはずなのに。なんでこんな風に笑って、僕を気遣えるのだろう。その気丈な姿に思わず込み上げるものがあるが、顔の表情筋に力を入れて何とかそれを抑え込む。
彼が涙を流さないのに、僕だけが泣くわけにはいかない。
「うん、分かったよ兼さん。楽しい一日にしようね」
誰も何とは言わず、その日の夜は早めに夕飯を済ませて賑やかな宴会が催された。僕も兼さんも、一振り目も。酔ったおかげで今日の記憶がなかった、なんてことだけは避けたかったので、お酒は飲まなかったけれど。
皆それぞれが自分の特技を持ち寄ってはそれを披露し、場を盛り上げてくれた。お前も一緒にやろうと若干強引に舞台に連れてこられた一振り目の兼さんは、少し照れながらも格別に楽しそうに笑っていた。
本当に、この本丸の刀剣たちは素晴らしい人たちばかりだ。その礎を作った一振り目がいたからこそ、こんな素敵な本丸へと育っていったのだと思う。
今の本丸の雰囲気を、少しでも一振り目の兼さんが触れる時間ができて。別れは辛けれど、それだけは本当に良かったと思う。戦いに明け暮れるばかりだった彼には、最後くらい安らぎのひと時を過ごして欲しい。
お手伝いをしながらも、壇上に立つ兼さんの勇姿を見守らずにはいられなかった。
華やかな時間にも必ず終わりはやって来る。日付が変わるより少し前に、名残惜しくも宴はお開きとなった。片付けを手伝おうとする僕に、加州さんと大和守さんが堀川はもういいから部屋に戻りな、と声をかけてくれた。
本当は、早く兼さんたちの待つであろう自室に戻りたいと思っていた。それ故、ここは彼らの好意を有難く受け取ることにしよう。
足早に広間を後にすると、明かりの灯る自室の前までたどり着く。二人で何やら話をしているようで入室しても良いのか迷ったが、一振り目の兼さんに残された時間は少ない。それに、昼間に話しそびれてしまった大事なこと全て、兼さんに話さないといけない。
肺いっぱいに空気を吸い込んで深呼吸し、入るよと告げて障子を開く。ほとんど瓜二つの顔が同時にこちらを向いて出迎えてくれる光景がなんだかおかしくて、今日までのことが夢だったんじゃないか、なんて思ってしまう。
「あの、兼さん……僕、昼間に話そうとしていたことを話さなきゃいけないと思って。聞いてくれる?」
兼さんがそれに返事をするよりも早く、一振り目の兼さんが声をあげる。
「国広、多分お前が今から話そうとしているオレたちのことだが……お前がいない間に、オレの方からこいつに話した。結果がどうあれ、きっかけを作ったのはオレだからな」
「そう、なんだ……」
事情を聞いたはずの兼さんは怒って当然だというのに、その顔に怒気は感じられず、難しそうな表情をしている。彼が何を感じているのかは分からない。だけど、僕にできることは唯一つしかない。
「ごめんなさい、兼さん。一振り目の兼さんがきっかけを作ったにしても、受け入れたのは僕の判断だ。兼さんのことが好きな気持ちは今も全く変わらない。だけど……こんな裏切り、許されるはずない。……僕のことを見限って当然だと思う。勝手なのは分かってるけど、最後にどうか謝らせて下さい」
深々と頭を下げて、床につける。こんなことで兼さんの心の傷が癒えるはずもないだろうけど、そうせずにはいられなかった。
そのまま暫くの沈黙が続いた後、服の衣擦れの音とともに僕の肩に手が置かれる。
「顔を上げろよ、国広。確かにお前らのことを聞いて何も感じなかったわけじゃねえが、お前ら二人を置いて出る判断をしたのはオレだ。こうなる可能性があることも頭にあった。それでも無理やり引き離したりしなかったのは、こいつの気持ちをオレが誰より一番理解してるからだ」
恐る恐る顔を上げた先にあった兼さんの顔は、許しを施す聖母の如き温かさを纏っていた。あまりの落ち着きぶりに、隣に座る一振り目は申し訳なさそうに体を竦めるばかりだ。
「お前に一目会いたい。会ったら会ったで、一緒にいたい。触れ合いたい。愛し合いたい。そういう気持ちが芽生えるのは、オレにも覚えがあるからよく分かる。ましてやこいつは、オレ以上に国広を待っていた時間が長いんだ。国広のことを特別に好いちまうのも無理ねえよ。そんな事情を知っているお前が、こいつのことを拒みきれねえのもな」
「……たとえ兼さんがそう思ってくれていたとしても、簡単に許しちゃ駄目だよ。僕がもし逆の立場だったら……兼さんのように思える自信は、ないな」
「そこまで気にしてくれているとは嬉しいねえ。もちろん、今晩ばかりはオレも本丸にいる以上譲るわけにはいかねえよ。とはいえ、こいつも今日が本当に最後なんだ……国広の側から離れたくねえだろうさ。そこで、オレから提案なんだが……」
悪巧みでも思いついたようにニヤリと笑う兼さんの言葉の続きを、僕も一振り目も恐々としながら黙って待つ。
「一丁、三人で楽しもうじゃねえか?」
***
ぱんぱんと肉を打ち付ける音が耳に響いてくる。四つん這いの格好で一振り目の兼さんに貫かれ、思うようにその剛直を抜き差しされている。いつもなら堪らず上がる嬌声は、しかし今宵は少しばかりの呻き声だけだ。
理由は単純。僕の口は塞がっている。最愛の恋人、二振目の兼さんの欲望渦巻きそそり立つ陰茎を頬張っては、懸命に舌を使って愛撫しているからだ。
兼さんの衝撃発言を、僕よりも早く一振り目は否定した。この数日の間だけでも十分すぎる思いをしたのだから、自分がそこに混ざるなどとんでもない、と。
しかし、兼さんは引かない。最後くらい愛しい奴と繋がりたいと思わないわけがない。命尽きようとしている時に遠慮なんていらねえ、と。
結局兼さんの説得により一振り目は最終的に了承し、二人がそれでいいのならばと僕もそれに続いた。『和泉守兼定』が求めている以上、僕が断る理由などどこにもないのだから。
もちろん三人でそういった行為をしたことなどないので、どうすればいいのかと思っていたが、当然オレら同士でどうこうしたいなんて思わねえよな?と顔を合わせた兼さんたちによって引き寄せられると、前から後ろからの愛撫が始まる。
僕の弱いところなんて知り尽くしている二人によって触れられれば、身体は容易く欲を孕んで昂っていく。あっという間に達してしまった僕を嬉しそうに見つめたかと思えば、二人の手によって蕾を解されて、今に至る。
国広にばかり負担をかけてすまねえなと謝られたけど、そんなこと気にする必要なんてないんだ。僕自身が、兼さんを愛して、抱き合いたいと思っている。これは僕が望んだことなのだから。
必死に打ちつけられる腰の動きが早まるにつれて、僕も舌の動きを兼さんが感じてくれる部分に集中させる。後ろで攻め立てる陰茎が前立腺を擦り上げる度に口を離してしまいそうになるところを、ぐっと堪えて深く咥え込んだ。
「ぐっ……国広……もう、イキそうだ……っ!」
腰を休めることなく、一振り目の掠れた声が聞こえてくる。
僕もだよ、という言葉は当然声になることはない。しかし、ぎゅうぎゅうと締め付ける内壁を肌伝いに感じ取ってくれているに違いない。
「はっ……オレも、混ぜろよ……」
兼さんがそう言い終わる前に僕の顔を掴むと、喉奥を突くように激しく抜き差しされる。著大なそれは瞬く間に僕の喉全てを埋め尽くして、呼吸を圧迫してくる。絶対に離すことのないように目一杯口を広げて迎え入れる。
前から後ろから行われる激しい抽送、その何度目かの後に、どくどくと熱い迸りが体内に吐き出される。上からも下からも、愛する存在の種を吐き出される至福に、僕の先端からも欲望が溢れてくる。
両方の口で余すことなく白濁を呑み込んだ後、それを塞いでいた二つの楔から解放された。注がれた精液を何とか全て飲み干して息を整えていると、兼さんの手によって優しく敷布の上に寝かされる。
覆いかぶさるように上からのし掛かる瞳には、野獣のような鋭い眼光の中に欲望の色が混ざっていた。
「悪いな、全然収まらねえわ……次はオレに入れさせてくんねぇ?」
幼子のような甘えの中に宿る、隠しきれない艶やかな声。それを拒絶することなどできるはずもなく、うんうんと懸命に頷いた。
兼さんが嬉しそうに歯を覗かせたかと思えば、力の入らない僕の両脚は高く掲げられ胸につきそうなほど折り曲げられる。流れるように押し当てられた猛りは、先ほど一振り目が注いだ滑りを借りていとも簡単に侵入してくる。
ぐりぐりと前立腺を抉るように捏ね回す動きに、我慢できずに喘ぎをあげた。
「あっ……ああ!か、かねさ、そこばっか、だめぇっ……!!」
「んなこと言って、気持ちいんだろ?すげぇ締め付けてるぜ……っ!」
兼さんに口に出されると、余計に意識してしまう。僕の肉襞が、もっともっととねだるように、奥へ奥へと誘い込むように、ぎゅうぎゅうと彼の雄を締め付けている、その蠢きを。
恋人になってから何度も兼さんに愛されたそこは、貪欲に与えられる刺激を零すまいとしている。随分といやらしい身体になってしまったものだと恥ずかしい気持ちもあるが、それが他でもない兼さんによってそうさせられたのだと思えば、何よりも嬉しい。
横で僕らの交合を見つめている一振り目の存在を忘れてしまったかのように、激しく腰を振っては互いの良いところを求め合う。たった数日離れていただけなのに、兼さんとこうして身体を繋げることが何よりの褒美のように感じられた。
「んっ、あっ、はぁ、兼さ、ぼく、もう、限界……」
「ああ、オレもだ……一緒にイこう、な……!」
先端まで引き抜かれたと思った瞬間、一気に奥まで入り込んだ先端が敏感な部位を叩く。そのあまりの衝撃と快感に、頭の中がチカチカと光り、何も考えられなくなる。
びくびくと震えながら己の腹に吐精する僕を見守りながら、兼さんもまた胎内に欲望を撒き散らす。二回目とは思えないほど大量の精液が腹を犯していく感覚に、絶頂は中々僕を離してくれなかった。
全てを吐き出した兼さんが引き抜かれる動きすらも、今の僕にとっては快感を呼び起こす種にしかならない。抜かれてしまった陰茎を名残惜しんでひくつく窄まりを二人に見られているのだと思うと、己の身体の浅ましさに全身が熱を帯びていく。
「やべえな……抱き合ってる時もそうだけどよお、こうして側から見てると……国広が可愛く見えて仕方ねえな」
そう呟く一振り目の兼さんの股間のものは、すっかりと元気を取り戻して空を見上げている。
「そりゃ国広だからな……オレもまだ完全に収まんねえし。というわけで、ここで一つ相談があるんだが」
先ほど三人で楽しもう、と口にした時と同じような口ぶりに、僕は悪い予感がしてならない。訝しむ僕に気づいているのやらいないのやら。そのまま兼さんは続きを言葉にする。
「オレらのをいっぺんに入れるってのはどうだ?」
………………。
ん?思わず聞き流してしまいそうになったけど、何だって?それは、僕が兼さんたちの逞しい逸物を二本同時に、ってこと?
「おい、それはいくら何でも無理だろ……国広の身体のこと考えたらきついぜ」
「そ、そうだよ!一振り目の兼さんの言う通り、無茶だよ!」
僕を気遣う一振り目に便乗して必死に抗議する。そりゃあ僕だって、できることならそうしてあげたいけど。流石に僕の体の大きさを考えると、厳しいだろう。
「大丈夫だって。さっき入れた時もすんなり入ったし、国広ん中柔らかいからいけると思うぜ?」
「そ、それはそうだけど……」
「お前だってちょっと興味あんだろ?最後なんだから心残りはねえ方が良いに決まってる」
それを言われると弱い。一振り目の兼さんにとって、今夜が正真正銘、最後の夜だ。彼に心残りを作って欲しくなんてない。
「わ、分かったよ。でも、本当にきつかったら、止めてね……?」
「おう、当然だ。決まり、な!」
「安心しろ、国広。お前が本当にしんどそうだったらすぐに止めるからな」
不安そうな僕を思いやって頭をよしよしと撫でてくれる一振り目の温もりが、僕に僅かばかりの勇気をくれている気がした。
「じゃあ、いくぞ……?」
僕の腰を掴んだ一振り目の兼さんが、恐る恐る僕の顔を伺いながら合図をくれる。
横たわった僕は、その身体の下で僕の身体を支える兼さんによって既に貫かれている。少しばかり空いた隙間に一振り目が指を入れて確認すると、昂る灼熱が押し当てられる。
ねじ込むように、狭い入り口を割り入ってくる。無理やりこじ開けられる痛みは想像以上のもので、本能が危険を告げ身体中から脂汗が滲み出てくる。
「ううっ……──、ぐ……ぁ、う」
「大丈夫か、国広?」
まるで僕が死んでしまうのではないかと思うほど心配そうに揺れる瞳に、何とか笑みを作って応える。
「う、ん……大丈夫、だから……続けて……」
「……本当にヤバかったらすぐに言えよ?」
こくこくと首を振る僕を見届けると、再び挿入が始まる。皮膚が裂けてしまうかのような鋭い痛みが、後孔から下半身へと響いていく。血が滲んでしまってはいないだろうか。それを確認する気力も湧かず、ただただこの苦痛が過ぎ去るのを耐える。
ぐぐ、っと雁首までが中に埋められたのを感じる。一振り目の様子を見るに、裂けてしまっているわけでもなさそうだ。自分のことながら、驚かずにはいられない。
とはいえ、限界まで引っ張られていることは間違いない。ズキズキと絶え間ない痛みが身体を冒していくのを、一振り目の背中をぎゅっと抱きしめることで何とか堪えている状態だ。
「すげえな、ちゃんと入ったじゃねえか」
「入ったけどよぉ、まだ先っぽだけだぜ?……それに、国広もしんどそうだし、やっぱりやめた方がいいんじゃねえか?」
力の篭る腕で縋りつかれている一振り目の兼さんには、僕が苦しんでいることも伝わってしまっているんだろう。遠慮がちに見つめながらも、そっと僕の身体を撫でてくれる。
こんな優しい兼さんのためだからこそ、たとえ辛くてもここまで来て止めたいなどとは思わない。
「ん……やだ、止めないで、兼さん……」
片手を僕を撫でる一振り目に、そしてもう片方の手を後ろから抱き抱える兼さんに添える。彼ら二人を同時に感じ、愛し合う機会など今夜しかないのだ。だから、僕は大丈夫だ。兼さんたちのためなら、もう少しだけ、頑張れる。
「……分かった。ありがとな、国広。ゆっくり動くからな」
首を伸ばして、一振り目が僕の額に口付けを落とす。少しでも痛みが和らぐようにと、念じるかの如く。不思議と、先ほどよりも痛みがマシになったような感覚がする。
緩やかに、一振り目の肉楔が埋め込まれて行き、その動きに合わせるように今度は後ろにいる兼さんが腰を引く。硬く張り上がった二本の槍が、互いを慰め合うように擦りながら、交互に狭筒の奥を突く。
僕の中の弱いところ、敏感なところの全てが、余すことなく暴かれては鬩ぎ合う切っ先に蹂躙される。休む間もなく快楽の波が押し寄せ、今までに感じたことのない強烈な愉悦に指先一つ動かすこともままならず、全身の震えが止まらない。
「ぐう、ああっ、ひゃああああ、ん!んぁッ、あ、かね、さっ、きもち、い、よぉッ……!」
「ああ、オレもだぜ……ぎゅうぎゅう締め付けて、そんでもって魔羅が擦れ合って……堪んねえほど気持ち良い、ぜ……!」
兼さんが後ろから腰を掴む腕に段々と力が入り、打ち付ける腰も激しさを増していく。一振り目もまた、余裕のない表情で懸命に兼さんと息を合わせるように抽送を続ける。
「はぁッ……国広……やべえ、腰、止まんねえ……!」
ぐちゅぐちゅと結合部からは引っ切りなしに淫らな水音が響き、僕らの交合の激しさを物語っている。僕の胎内で絡み合う剛直の脈動すらはっきりと感じられて、それだけでもどうにかなってしまいそうなほど気持ち良い。
最早痛みなどどこかへ消え去り、後に残ったのは理性も思考をも奪い去る鮮烈な快感のみ。兼さんたちの動きに合わせて幾度となく身悶える身体は、散々良いところを擦り上げられてもう限界だ。
「うが、ぁあ、イく、イッちゃ、う、んああああッ!!」
肉襞がぎちぎちと兼さんたちの陰茎を離さぬように吸い付き、締め上げながら、絶頂を迎える。痙攣する身体に合わせて蠢く内壁の締め付けに耐えかねた兼さんたちもまた、どくどくと僕の腹の中に熱を注いでいく。
二人分の熱が弾ける感覚に、腹の中が灼けてしまうのではないかと思うほど熱くて、そしてそれ以上に気持ちよくて。目の前が白く明滅して、意識が薄れていく。たっぷりと子種を孕む心地よさに身を任せながら、僕はゆっくりと瞳を閉じた。
***
それからどれくらい経ったのだろうか。気怠さと少々の痛みを感じながら目覚めた僕は、ハッと大事なことに気付く。
今、何時だ。兼さんは、一振り目の兼さんは、どうなった……!?
慌てて体を起こした僕を、隣で体を横にしながら少し驚いた様子で見つめる、視線。紛れもない、一振り目の兼さんだ。彼がまだここに存在していることが、嬉しくて。
思わずその逞しい体に抱きついてしまう。全身の体重をかけて飛びついたのに、彼はびくともせずに背中に腕を回して受け止めてくれた。
「兼さんっ、良かった!ごめんね、僕、いつの間にか寝てたみたいで……でも、本当に良かった。兼さんがまだここにいてくれて」
「気にすんなよ、無理させちまったのはオレらの方なんだ。大丈夫か?体、痛くねえか?」
きちんと整えられた寝間着の上から、労わるように腰を撫でられる。
「うん、大丈夫だよ。ちょっとだけ痛いけど、平気。……そういえば、兼さんは」
そう尋ねる前に目線を横に向ければ、すやすやと眠る兼さんの姿が目に入る。
「ああ、あいつなら出陣で疲れちまったから先に寝るって。……多分、オレに気い遣ってくれたってのもあるけどよ。じゃあな、ってそれだけ言って寝ちまった」
兼さんらしい、不器用ながらも一振り目を思いやる姿が目に浮かぶ。僕の恋人は、ちょっと強引なところもあるけれど、本当に優しい人だと思う。
僕が寝ている間に行われたであろうやりとりを想像して微笑んでいると、柔らかい感触が額に、頬に降ってくる。
「てなわけで、あいつの気遣いに甘えさせてもらう……国広。最後は、こうしてお前を抱きしめていてもいいか?」
「もちろんだよ。兼さんが嫌だって言っても、絶対に離してあげないんだから」
兼さんの背中に回した腕はそのままに、彼の唇に己のそれを重ねる。今ここにいる互いの存在を確かめるような、口付け。先ほどまでの深く激しいものとは異なり、触れるだけのそれは、しかし心の中まで繋がっているような温かさをもたらしてくれる。
何度も何度も、離れるのを惜しむようにどちらともなく角度を変えては触れ合う。どれほどの間そうしていたのかは分からない。ようやく唇を離した僕たちは、隙間など作らないというほど強く抱きしめ合う。
「……なあ、国広。本当に、ありがとな。たった数日だったけど、もう一度お前に会えて。一緒に働いて、何気ないことを話して。そして、こうして愛し合えて。オレはきっと、この本丸で今一番幸せだって、胸を張って言えるぜ」
「僕の方こそ、ありがとう。兼さんと少しでも多くの時間を一緒に過ごせて。たくさんたくさん、好きだって言ってもらえて。僕の方こそ、この本丸で今一番幸せだよ」
兼さんと過ごした、たった数日の、それでもかけがえのない時間。次から次へと頭に浮かんでいく。どれもこれも、素晴らしい思い出だ。
「オレはここで消えちまうが……もし。もしも、この先お前が折れちまったり、刀剣男士としての役目を終えて消えちまうことになって。こいつと離れ離れにならなきゃいけない、なんてことになっちまったらよ。……その時は、必ずオレが迎えに行く。お前を一人ぼっちになんてさせねえ。絶対にな」
本当に、呆れるくらい、優しい人だ。自分が死のうって時に僕の未来を心配してくれるなんて、とんだ大馬鹿者だ。きっとそんなところに、僕は惹かれたんだろうな。
「うん……ありがとう、兼さん。僕は、あなたのことを置いていってしまったのに。本当に……兼さんは、優しいな。僕、こんなに幸せでいいのかな」
「んなこと気にすんなよ。ただ、オレは、一人の寂しさを知ってるからよ。お前にまであんな思い、して欲しくねえんだ。それだけなんだ、最後くらいかっこつけさせてくれよ」
「……兼さんは、最高にかっこ良い、僕の自慢の相棒だよ。僕は、兼さんのことを忘れない。もしまた会えることができたとしたら、絶対に兼さんのことを覚えているからね」
「……ああ、嬉しいな。もしそうなったらよ、一緒にいような」
急に、強烈な眠気に襲われる。視界がぐにゃぐにゃと揺れて、強制的に夢の世界に連れていかれる感覚。
せめて、最後に一言。彼に届くように、声を擦り絞る。
「うん。今度は兼さんを置いていったりしないから。一緒にいようね」
僕の声は、兼さんに届いただろうか。歪んでいく視界の中で、兼さんが見せてくれたとびきりの笑顔を最後に、僕の世界は真っ暗になった。
***
ちゅんちゅん、と朝の訪れを告げる鳥の鳴き声が耳に届き、ゆっくりと瞼を持ち上げる。朝日が障子を通して部屋の中を照らし、戸を開くまでもなく今日がお天気であることを知らせてくれる。
眠る前まで確かに自分を包んでいたはずの温もりは、跡形もなく消え去っている。彼の霊力の欠片すら、感じることはできない。
覚悟していたとはいえ、本当に一振り目の兼さんは消えてしまった。その事実に、陽気な気候とは対照的に僕の心は沈んでしまう。
彼とまた会える保証なんてどこにもない。未来がどうなるかなんて、誰にも分からないから。でも、たとえそうだとしても、一縷の望みを持つことくらいは許されるだろうか。
僕が考え事をしているうちに、隣で眠っていた兼さんがもぞもぞと体を動かし、欠伸をしながら目を擦って目覚める。今のこの少し空虚な気持ちを共有したくて、そっと口に出す。
「兼さん、おはよう。……一振り目の兼さん、行っちゃったね……」
「ふぁあ……おう、おはよう。一振り目の、オレ?何のことだ、お前まだ寝ぼけてんのか?」
「え?そんなことないよ、だって寝る前まで一緒にいたじゃない」
「何言ってんだよ。昨日は数日ぶりに本丸に帰ってきて、ようやく国広に会えたって思って、一緒に抱き合って。そのまま疲れて寝ちまったじゃねえか。……覚えてねえのか?」
どうやら、冗談じゃなく本当に、一振り目の兼さんのことなど知らないという口ぶりだ。それは兼さんの顔を見たら分かる。一体、どういうことなんだろう。
これ以上話しても兼さんが覚えていない以上はどうしようもないと思い、この場を収めて朝食を食べに食堂へと繰り出す。兼さんが覚えていなくても、他の刀剣が覚えているかもしれない。そんな僅かな可能性にかけて、隣に座った加州さんにそれとなく聞いてみる。
「あの、加州さん。その……一振り目の兼さんのこと、覚えてますか?」
「ん?突然どうしたのさ。そりゃあ長くなかったとはいえ大変な時期を一緒に過ごした仲間だもん、忘れないよ」
「えっと、そうじゃなくて……昨日まで、その一振り目の兼さんがこの本丸にいたこと、なんですけど」
「……え?何それ、そんな夢でも見てたの?そっか、それはちょっと羨ましいな。俺も夢の中でも良いから、もう一度くらいあいつと話したいな」
「……そうですよね。何でもないです。変なこと聞いてすみません」
その後、加州さんだけでなく他の刀剣たちにも何人か尋ねてみたけど、一振り目のことを覚えている人は一人もいなかった。もしかして、あれは僕が見た夢なんじゃないか。そんな不安が頭をよぎるが、彼に触れた温もりをまだ覚えている体が、決して夢なんかじゃないと訴えている。
こうなったら最終手段だ。僕は、夜に皆が寝静まった頃合いを見計らって、主さんの部屋へと足を運ぶ。当然控えていた近侍にどうしたのかと聞かれるが、それよりも先に主さんが部屋に入って欲しいと声をかけてくれる。
近侍にぺこりと頭を下げた後、失礼します、と挨拶をして戸を開ける。僕が来るのを予期していたかのような落ち着いた佇まいで、主さんが待ち構えていた。
「やあ、堀川。きっと私のところに来ると思っていたよ。……聞きたいのは、一振り目の和泉守兼定のことだろう?」
「じゃあ、やっぱり……!夢なんかじゃなかったんですね」
「ああ、彼は確かに昨日までこの本丸に存在していた。だが、政府の命令でね。彼がここにいたことは他の刀剣たちの記憶から消すように言われたんだ」
「そう、だったんですね……でも、だったらどうして」
「どうして堀川だけが覚えているのか、だね。なんてことはない、私のささやかな抵抗であり、同時に何もしてやれなかった彼へのせめてもの餞だ。彼にとって一番大切な存在のお前にだけは、覚えていて欲しいと思った」
「……主さん。本当に、ありがとうございます。僕、兼さんと約束したんです。絶対、兼さんのことを忘れないって」
「そうだったのか。それなら尚更良かった。……もうあの和泉守とお前が会うことはないかもしれない。それでも、どうか彼のことを、心の片隅にでもいいから忘れないでいてくれないだろうか。私からも、お願いするよ」
「……はい。主さんと一振り目の兼さんに誓って、必ず」
僕は本当に幸せ者だ。政府の命令に少しでも反するなんて、きっと勇気の要ることだろう。それでも主さんは、僕のため、そして兼さんのためにそうしてくれた。心から、主さんの刀剣としてこの本丸に顕現したことを誇りに思う。
そんな主さんの願いを、無碍にするはずがない。
それに、約束したから。それは叶うことのない約束かもしれない。でも、もしもう一度会うことがあれば、きっと今度は一緒にいよう、と。
月明かりが静かに主さんと僕を照らす。兼さんもその様子をどこかで見てくれているような、そんな気がした。