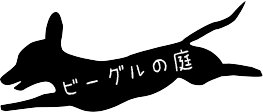凍てつく寒さに身を震わせる冬が終わりを告げ、春の暖かな陽気が冬眠を終えた動物たちと共に顔を出し始める中、僕たちはようやく江戸の町並みが目に入ってくる所までやってきた。京都を出発してから早十六日。中山道の宿場町で寝泊まりする日々も、ようやく終わる。目的の場所に無事に辿り着くことができそうだという安堵から、心なしか足取りも軽くなっていく気がした。
脇を固めるお供の二人も、遠目からでも分かるほど活気に満ちた多くの建物と人々がひしめく江戸の町を見て、どこかそわそわとしている。謁見が終わった後は、京都に帰る前に少しばかり寺社を巡るのも良いかもしれない。せっかくの機会だ。きっと僕の生涯で、江戸にそう何度も来る機会などないだろうから。
事前に伝えられていた屋敷に到着し、荷物を解いて少しばかり休憩をする。先ほど使者がやって来て、急なことで申し訳ないが謁見は明日の午後である旨を伝えられる。ならば、今日は疲れた体をゆっくりと休めよう。いくら普段から僧侶として檀家を巡るため歩くことには慣れているとは言え、京から江戸への道のりは想像していたよりも長く険しいものであった。この距離を常日頃よりたったの三日ほどで行き来する飛脚の強靭さに、改めて尊敬の念を抱かずにはいられない。
とはいえ、この疲労が明日に響くことなどあってはいけないのだ。
僕は、この度京都のとある寺の院主に就任することとなった。弱冠十六歳での就任というところに、作為的なものは感じる。しかし、だからといって抗議してみたところでどうにかできるものではない。僕の出自を鑑みてのことだろうが、それならば与えられた役割をきっちりと果たすのみだ。
僕、堀川国広は公家の出である。すでに跡を継ぐ兄がいた為に幼くして寺に出されたのだが、それも今となっては良かったと思っている。宮中という狭い世界で限られた権力の椅子を争うよりも、こうして世の人々のために役立つ仕事をしている方が、ずっと生きている実感を得られるのだから。
勿論、楽しいことばかりではない。不慮の死や無惨な死を遂げた人を弔う時は、たとえそれが見ず知らずの人間だとしても胸を痛めつけられる。でも、自分たちの祈りによって無念のうちにこの世を去った人や遺された人たちの魂を安寧に導くことができるなら、この責務に生涯を捧げることを誇らしくさえ思う。だから、たとえ院主という位を貰っても、自分のやることは変わらない。市井の人たちと交流し、彼らの生活を支えていく。それが僕の生き方だ。
体を休めているうちに時刻はあっという間に夜を迎え、僕とお供の二人は初めての江戸の食事を頂いた。献立は、米飯に味噌汁、香の物、そして魚の煮付けだ。京のものよりもずっと濃い味付けの料理に、従者の年若い方の少年は目を白黒させていた。年長の方は「京の味付けの方が上品です」とぶつくさ文句を言っていたが、なんだかんだ箸が進んでいるところを見るに、言葉ほど嫌な訳でもなさそうだ。
僕自身も、話には聞いていたとはいえここまで料理の味がその土地によって変わるのだと感心せずにはいられなかった。どのように味付けをしているのかを下働きをしている者に聞いて、京都に帰った後に自分でたまに江戸風の料理を作ってみようか。確か江戸の醤油は関西の薄口醤油に対して濃口醤油と呼ばれている。それを貰って帰れば、作るのは難しくないだろう。そんな好奇心を抱きながら、明日に備えて常よりも早めに床に着いた。
『謁見』というと仰々しくて思わず体が緊張で震えてしまいそうになるが、十中八九決められた形式通りの言葉を述べて、将軍様よりこれまた決められた言葉が返ってくるだけだろう。先代も、拍子抜けするほどすぐに終わったと言っていた。そう思えば、張り詰めた心も幾分和らいだ気がする。
将軍の側近と思われる厳めしい男に部屋に入るように促され、歩を進めようとしたところで思い出したかのように言葉をかけられる。
「本日は将軍様が火急の御用のため、代わりにご嫡男で次期将軍であられる兼定様がご対応なされることになりました。とはいっても、くれぐれも失礼のなきようお願い致す」
「承知致しました」
後継の兼定様、か。確か僕より五つほど年上の若い青年だったように記憶している。生憎それ以上の詳しい情報は持ち合わせていないが、特別に気負う必要もないだろう。
ふぅと軽く息を吐いた後、謁見の間に足を踏み入れ、所定の場所に座して平伏する。
御簾があるためよく見えないが、向こうに人の気配を感じる。視線を浴びているような気がして、ぴったりと畳につけた額からじわりと汗が滲んで来た。控えている侍が僕のことを説明し終えたのを確認すると、震える喉から声を振り絞る。
「失礼仕ります、此度は院主就任の挨拶に参りました」
「表を上げよ」
想像よりも凛とした声に背筋を伸ばしながら、ゆっくりと顔を上げる。ぼんやりと見える人影の方へと顔を向けると、御簾越しにじっと見つめられた。
「……へえ、随分と若いんだな。年は幾つになる」
形式通りのやり取りをするだけだと思っていたため、想定外の質問が飛んできて思わず心臓がびくりと跳ねる。落ち着け、聞かれたことにしっかりと答えれば良いだけだ――。
「十六になります。まだ若輩の身ではありますが、精一杯院主の務めを果たす所存です」
「その年で院主ということは、元々は貴族の出か」
「……はい、公家の堀川家の三男にございます」
「なるほどな、後継ぎとなる男子はすでにいるからと寺に出されたか。……嫌ではないのか、ひとり親元を離れて勝手に決められた道を進むのは」
随分と踏み込んだ質問をしてくるものだな、と少し辟易してしまう。僕の出自など聞いて楽しいものなのだろうか。なんと答えようか少し迷ったものの、ここは正直に話すことにした。
「正直に申し上げますと、最初は慣れぬことばかりで寂しく、辛うございました。しかし、世に出て苦しむ人々を目の当たりにすれば、そこから目を背けることなどできません。彼らのために祈ることこそが己の天命なのだと、受け入れることができました。なので、今はとても充足しております」
「……そうか。ならば良い、存分に励め。京都より遠路はるばる江戸に赴いての挨拶、大義であった」
「有り難きお言葉にございます」
下がれと側近に目配せをされたので、そそくさと立ち上がって謁見の間を後にする。若き後継様には、年若い院主が物珍しかったのだろう。思ったより多く受け答えをしたことに、今更ながら緊張がぶり返してきて堪らず息を深く吐き出した。
<中略>
「……おい、長曽祢さんよぉ。なんでこいつがいるんだ?」
いつもよく目にする仏頂面とは異なり機嫌の良い表情を浮かべながら道場へと足を踏み入れた兼定様が、眉を顰めながら聞いてくる。長曽祢さんがそれに答えるよりも先に、僕は勢いのまま切り出した。
「突然のことで申し訳ありません。今日は兼定様と一度だけ試合の機会を頂きたく、参上しました」
「嫌だね。なんでオレが貴族出身のお坊ちゃんと試合なんざしなきゃならねえんだ?暇つぶしにもならねえよ。分かったらさっさと帰るんだな」
深く眉間に皺を寄せながら、いかにも不機嫌そうな声色でばっさりと切り捨てられてしまう。せっかくこの一年間今日のために努力してきたのだ、ここで引き下がるわけにはいかない。僕がなんとか食い下がろうとする前に、長曽祢さんが口を開く。
「まあまあ、一度くらい良いではないですか。おれは堀川に一年ほど稽古をつけていますが、誰よりも熱心で上達速度も早いです。つまらない試合にはならないことは、おれが保証しましょう」
「……はぁ、他でもない長曽祢さんにそう言われちゃあなあ。……ちっ、しょうがねえな、一度だけだぞ」
「ほ、本当ですか⁉ありがとうございます‼」
念願叶ったことの嬉しさの余りに、自分でも驚くほど大きな声が出てしまう。長曽祢さんにもらったせっかくの機会だ、無駄にしてなるものか。
「おい、念のため言っておくがよぉ……もし手加減なんざしたら、その首を刎ねてやるからな。本気でかかって来いよ」
「はい、勿論です!……あの、僕からも一つお願いしてもよろしいでしょうか?」
「……用件によるな」
「もし僕が勝てた時は、兼定様の身の回りのお世話をさせて下さい!」
急な申し出になってしまうけれど、僕は本来そのためにここに連れてこられたのだ。
ちらりと兼定様の顔を伺うが、しばらく真一文字に結ばれたままの唇は動かなかった。出過ぎたことを願い出てしまったかと不安になってきたけれど、すでに口に出してしまった以上はどうしようもない。
僕が頭の中で焦りを抱いているうちに、ふう、と息をついた兼定様がようやく答えてくれる。
「良いぜ。オレがお前に負けるなんざ有り得ねえからな。分かったらとっとと準備しろよ」
やった!今まで碌に会話もできなかったのに、すごい前進だ。これ以上進めるかどうか、後は僕にかかっている。
ここまで来れたのは自分一人の力ではない。後押しをしてくれた人のためにも、負けられない。腹の奥が緊張でぐっと重くなるのを感じながら、僕は防具を身につけ始めた。
<中略>
ここからR-18
技巧など微塵もない、ただひたすらに互いの熱を求めるだけの口付け。それが、この上なく気持ち良い。息継ぎしようと少し開いた口に兼さんの舌がすかさず入り込んできた時は少々驚いたけれど、自然と己のそれを絡ませては、彼の蜜のように甘い唾液を貪ることに浸っていた。
ちゅっ、ちゅと絶え間なく響く音。片時も離れたくないとでも言うように、体も口も、ぴったりとくっ付けて触れ合う。寒さなどもう毛ほども感じず、熱に浮かされたように兼さんの唇や咥内を味わっていた。
どれだけの間そうしていたかは分からない。流石に呼吸をするのが苦しくなってきて唇を離したときには、どちらのものとも分からぬ唾液で、互いの唇は濡れていた。僕らの間をつうと流れる銀糸が、灯りを受けて光を反射する。その光景が例えようもないほど淫らなものに見えて、思わず顔がカッと熱を帯びていくのを感じた。
兼さんもそう思ったのかもしれない。勢いよく褥の上に押し倒されたかと思えば、首筋に舌を這わせながら着流しの合わせに大きな手が添えられ、帯をするすると解かれていくのが分かる。息つく間もなく帯が剥ぎ取られ露わになった肌を撫でながら、熱を纏った声で囁かれた。
「……国広。今宵、お前を抱きたい。……いいか?」
触れるだけの口付けを唇に落としながら見つめる兼さんの瞳からは、轟々と燃え盛るような欲望の色が見てとれた。こんな薄く柔らかくもない僕の体に彼が欲情してくれているという事実が、何よりも嬉しい。
「うん。……僕も、兼さんに抱いて欲しい」
力の入らない体で、ふにゃりと笑う。その反応に満足してくれたである兼さんは、「痛かったらすぐに言えよ」と呟くと、先ほどまで舐められていた首筋に少しばかりの痛みが走る。
それは一瞬のことで、たちまち痛みは甘やかな痺れと変わっていく。ちゅ、ちゅと音を立てながら、首から鎖骨にかけて何度も繰り返される。恐らくは彼に今夜の情交を忘れぬよう、証を刻み込まれているのだろう。そんな兼さんの独占欲を内心嬉しく思って微笑んでいたのも束の間、脇腹を撫でていた手が胸まで上がってきて、二つの飾りを捉えた。
くりくりと捏ね回すような指の動きに声が出てしまいそうで、済んでのところで唇を噛んで堪えた。そんな僕の反応が気に入らなかったのか、指先に力がこめられてぐりぐりと押し潰すような動きに変わる。ピリピリとした痺れの中にも快感を見つけてしまい、背に敷かれた布をぎゅっと掴んで必死にやり過ごそうとした。そんな様子を見ていた兼さんが、顔だけを上げて僕の方をじいっと見つめてくる。
「……おい。声、我慢すんな。国広の声、オレに全部聞かせてくれよ」
羞恥心が咄嗟に顔を出して抗いそうになる。でも、愛しい人の頼みだ。どんなに恥ずかしいことだとしても、応えたいと思うのが人というものだろう。
意を決して力の入った体を緩めて唇を開いたのと同時に。兼さんの口が僕の左の粒をぱくりと咥えて、ちゅうちゅうと赤子のように吸い付き始めた。
「あああっ!あ、っう、やぁ、んんっ、あ、ああ!」
想像していた以上に大きな声が口から溢れて、たちまち顔が熱くなっていく。こんな痴態を見られて、兼さんに幻滅されてしまわないだろうか。そんな僕の不安をよそに、満足そうな表情の兼さんが口を開いた。
「あー……すげえ、可愛いな。堪んねえ。もっと見せてくれよ」
ニヤリと不敵に笑ったかと思えば、舌先でちろちろと先端を舐められ、先ほどよりも強く吸われる。抑えることができずに漏れ出る嬌声が、夜の静けさに響き渡った。
乳首はすっかりとピンと上向いて勃ち上がり、乳暈までもが心なしか膨らんでいるように見える。兼さんの愛撫によって快楽を拾い上げるだけの部位となってしまった尖りが、もっと愛して欲しいと主張するように震えている。
ようやく兼さんの口から解放された頃には、左の乳首は彼の唾液で濡れそぼって妖しく光っていた。自分の体の一部がこんなにも淫猥な形に変わってしまったと己の体の浅ましさに恥ずかしさと覚える中、そんな僕の気持ちを見透かしたように兼さんがはにかみながら事実を突きつけてくる。
「国広のここ、やらしくなっちまったな。そんなに気持ちよかったか?」
「……兼さんの、意地悪」
あれだけ声をあげて喘いでいたのだ、僕が感じていたことなど百も承知だろう。むすりと膨れる僕を見て、兼さんの眉根が下がる。
「悪い悪い。国広があんまりにも可愛いもんだからよお。……お詫びに、こっちも可愛がってやるからな」
そういうや否や、今度は右の突起を口に含んだかと思うと一気に吸い上げた。予想していなかった突然の快感に、体がぶるりと震えてしまう。
「ああっ‼あ、だめ、兼さん、……っ、そこ、きもちい、からぁ……っ!」
「きもちいならいいじゃねえか。もっと乱れちまえよ。お前の感じてる姿、もっと見てえ」
僕の抗議に耳を貸してくれるはずもなく、わざと大きな音を立てて吸い付いたかと思えば、円を描くようにねっとりと舐め取られる。じくじくと胸から全身に快感が染み込んでいく。僕の口から漏れ出る嬌声と、兼さんが胸を愛撫する音だけが部屋を支配していく。
ふやけてしまうのではないかと思うほど散々吸われた後に解放された乳首はぷくりと腫れ、てらてらと光っていた。それを嬉しそうに見つめたかと思うと、兼さんはゆっくりと脇腹をなぞる。それすらも今の僕には快楽を孕んだ刺激として感じてしまい、思わず身を捩らせてしまう。
へその周りを舐めながら、首筋と同じように痕を残している動きに気を取られている隙に、兼さんの指が下穿きへと辿り着く。誰がどう見ても盛り上がって見える布地は、一点にじわりと染みが浮かんでいる。その滲んでいる部分を、大きな手で揉み込むように触れられた。
「ぅ、ふぅ、んんっ、あっ……」
「まだ触ってもいないのに、こんなになっちまったなぁ。やらしい」
布越しに揉まれるのも気持ち良いのだけれど、どうしても決定的な刺激にはなり得ない。張り詰めているであろう陰茎を解放して欲しい。無意識のうちに、目尻に涙を溜めながら兼さんに強請るように懇願した。
「兼さ、あっ、触ってぇ……」
「今だって触ってるだろ?」
意地悪な笑みを浮かべながら、兼さんが次の句を発する。
「ちゃんとおねだりしてみろよ。そしたらお前の言う通りにしてやるから」
頬に触れるだけの口付けを落とし、優しい手付きで兼さんが残酷な提案を突きつけてくる。もちろん、僕に抵抗するだけの力などない。恥ずかしさに顔に熱が集まっていくのを感じながら、やっとの思いで口を開いた。
「……直接、触ってほしいの。……その、僕の、魔羅に……」
最後の方は掠れるような声だったので、果たして兼さんにちゃんと聞こえたのかは分からない。けれど、満足そうに目を細めながら「いい子だ」と言う言葉と共に額にご褒美の口付けをもらう。
兼さんの指が僕の下穿きを掴むと、一気にずり下げられた。反動でぷるんと揺れる陰茎が顔を出す。胸への愛撫ですっかりと硬くなったそれは、腹につくほど反り返っている。もう用はないとばかりに投げ捨てられた下穿きが宙を舞っているのをぼんやりと眺めていると、温かいものに性器が包まれ脈動する。兼さんの大きな手が淡い下生えを撫でてから、先端から蜜を溢す昂りを握りゆっくりと上下に扱き始めた。
鈴口から滲み出る先走りを掬っては、竿全体に塗り込めてぬちゃぬちゃと音を立てながら擦られる。もう片方の手で膨らんだ陰嚢を揉むように刺激され、我慢していたものが急速に迫り上がってくる。
「ああっ、兼さん、んっ、僕、もう、出ちゃう……っ!」
「いいぜ、出しちまえよ」
兼さんの親指が、カリカリと引っ掻くように蜜を垂らす口を刺激する。それがとどめとなり、僕は兼さんの手の中に白濁を撒き散らした。
「やっ、ぁあ、あっ、んあああああっ‼」
最後の一滴まで絞り出すように、竿を素早く擦られる。射精後の独特な倦怠感に僕は身動きできず、肩を上下させながら呼吸をするので精一杯だった。
そんな僕の頬をすりすりと撫でながら、触れるだけの口付けをくれる。