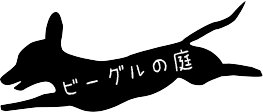「近侍お疲れ様、加州。今日はゆっくり休みなさい」
「ありがと、主。またいつでも呼んでよ」
そう声をかけながら静かに主の部屋の扉を閉めると、夜風が顔にあたる。部屋の中が暖かかっただけに、その冷たさが身に染みていく。清光は自室へと急いだ。
またいつでも呼んで欲しい、と口にはしたけれど、その機会がそうすぐには来ないことくらい分かっている。自分達の本丸には、百振り近い刀剣男士がいる。そして、主は心優しい人だ。だから、平等に全員と話す機会を設けようと、日替わりで近侍を変えては身の回りの仕事を任せてくれる。刀剣男士たちを分け隔てなく可愛がってくれる愛情深い主を持てたことは全くもって幸運としか言いようがないのだが、少しだけモヤモヤとした気持ちを抱いてしまっているのもまた事実だ。
誰かに、愛されたい。それが、清光が刀剣男士として生まれてからずっと心の中に抱えている想いだ。でも、主は自分を特別視してくれているわけではない。あくまで本丸にいる百振り程の刀剣男士たちの中の一振りとして、清光のことを可愛がってくれているに過ぎない。
それで十分じゃないかと己に言い聞かせてはいるのだが、どうしてもどこか満たされない気持ちを払拭することができないでいる。主は何も悪くないのに、こんなことを感じてしまっている自分が、嫌だった。
早いところ寝てしまおう。そしたらきっと、こんなジメジメとした気持ちも疲れと一緒に振り払えるはずだ。そう思って、清光は早々と床に就いた。
次の日の朝は、早めに寝たからか思ったよりも調子良く目覚めることができた。朝の日差しが障子の隙間から部屋へと入り込み、小鳥のさえずりが一日の始まりを告げてくれる。今日は良い一日になりそうだ。
早速顔を洗おうと共用の洗面所に立つと、鏡に映る自分の姿が見える。中々手強そうな寝癖がついているのを見て、思わずため息が出た。毛先が柔らかい清光にとって、寝癖は天敵だ。あちこちにはねた髪の毛を大人しくさせるには、短くない時間を使って格闘しなければいけない。
これは風呂場で濡らして乾かした方が早いかな、と思っていた矢先、自分の横に立つ気配を感じ取った。
「おう、清光。おはよーさん」
「おはよう、清光くん」
まだ少し眠たそうに欠伸をしている和泉守と、眠気など微塵も感じない爽やかな笑顔で挨拶をしてくる堀川。彼らはかつて同じ主の元で使われた刀たちではあるが、こういったところは対照的だ。
「おはよ、和泉守、堀川」
二人に返事をしてから、自分の作業へと意識を戻す。とりあえず顔だけ先に洗おうと洗顔料を手に取り、丁寧に泡立てていく。顔全体に広げてから、ぬるま湯でゆっくりと洗い流した。さっぱりとしたからか、清々しい気分になってきた。
ちらりと横目で二振りの様子を見ると、和泉守がご機嫌そうに笑っていた。清光ほどではないが少しだけついていたはずの寝癖は、綺麗さっぱりなくなっていつも通りの髪型になっていた。この短時間で直すなんてすごいな、と思ったが、すぐにその理由は察せられた。横に立つ堀川の両手には、寝癖を直すための水が入った霧吹きと、髪を梳かすための櫛が握られていた。器用な堀川が、テキパキと整えてやったに違いない。
「ヘヘっ、いつものかっこ良い和泉守兼定に決まったな。今日は出陣だから時間がねえなとちっとばかり焦ってたんだが、助かったぜ。手伝ってくれてありがとな、国広」
「ううん、どういたしまして」
そのやり取りを見て、胸の中が少しざわついた。このざわめきが何なのか、清光は心得ている。嫉妬だ。困った時は相棒に助けの手を差し伸べてもらえる和泉守に、少しばかり嫉妬しているのだ。我ながら、仲間に対してこんな気持ちを持ってしまうなんて心が狭いなと心の中で苦笑する。
すっかりいつもの調子を取り戻した和泉守は「さっさと着替えて飯いくぞ」と堀川に声をかけてから上機嫌に自室へと帰っていった。自分も朝食の時間に間に合うように、早いこと風呂場に行って寝癖を直さないと。清光が歩き出そうとしたところで、じいっとこちらを見ていた堀川と目が合う。何だろう、何か用事でもあるのかな、と考えていたところで、堀川が口を開いた。
「あの……もし清光くんさえ良ければ、清光くんの髪の毛も整えても良いかな?」
「えっ?」
「そんなに時間はかからないと思うんだけど……余計なお節介だったらごめんね」
「い、いや、そんなことないけどさ」
思わぬ提案に言葉が上手く出てこない。まさか、堀川が自分のことを気にかけてくれているとは思ってなかった。もちろん、堀川は優しいし、周りのことをよく見ていて気を配れるいい奴だ。だけど、和泉守に一緒に朝食に行くぞと言われていたわけだし、当然堀川もすぐに部屋に戻るものだとばかり思っていた。
堀川は、和泉守の世話をしながらもちゃんと清光のことを見てくれていたのだ。困っているだろうその気持ちを察して、手伝いの手を差し伸べてくれたのだ。ちょっとむず痒いけど、嬉しい。でも、和泉守のついでってだけじゃないかと思う自分もいて、ほんの少し複雑だ。素直に好意を受け取れば良いのに、こういうところは自分の悪い癖だと思う。とはいえ、断る理由もない。
「……じゃあ、お願いしてもいい?」
「もちろん! お手伝いなら任せてよ」
ニコニコと人好きのする笑顔を浮かべながら、堀川は清光の髪の毛に触れる。さらさらと髪の毛を梳かしながら、寝癖直しの水を吹きかけていく。その堀川の手つきは優しくて、気持ちよくて、先ほどまで心に燻っていた後ろ暗い感情がすうっと引き潮のように消えていくのを感じた。
あっという間にぴょんぴょんと自由にはねていたはずの寝癖は直り、いつも通りの髪型へと姿を変えた。世話好きを自称しているだけのことはある、見事な腕前だ。
「こんな感じで大丈夫かな?」
「うん。堀川って本当に器用だよね。ありがと、助かったよ」
「喜んでもらえて良かった。じゃあ、また後でね」
朝日を浴びて眩しいくらいの笑顔を残して、堀川は廊下の先へと歩いて行った。もう少しだけ、髪の毛に触れていて欲しかったなぁと名残惜しく思いながら、清光もまた着替えるために自室へと向かった。
その朝の出来事をきっかけに、清光は何となく堀川のことを気にするようになった。毎日意識して過ごしていると、だんだんと堀川がいつ頃起きてくるのか分かるようになってきた。堀川は几帳面な性格だから、規則正しいリズムで生活をしている。だから、清光は少しずつ、違和感を持たれないように気をつけながら堀川が起きて来る時間に合わせて起きるようになった。和泉守が一緒の時は遠慮してそこまで話さないけれど、堀川一振りの時は清光の方が積極的に話しかけていく。そうして顔を合わせる機会が増えるにつれて、二振りは少しずつ親しい間柄になっていった。
「ご機嫌みたいけど、なんかあったの?」
「……安定って鈍いよね、見てわかんないかなー」
「……ああ、もしかして髪の毛のこと? それ、自分でやったの?」
「ううん、堀川がしてくれたんだよ」
綺麗な三つ編みに結われた髪を手で触りながら、清光は答える。堀川は、時間がある時は清光の髪の結び方をアレンジしてくれる。普段から身だしなみに気を遣っている清光のために、どうやら色々と考えてくれているらしい。可愛く着飾ってもらえることももちろん嬉しいが、何よりも堀川の心遣いが、心地良い。
「兼さんはいつものスタイルしかしないから、こんな風に違った感じにセットするのは初めてなんだ。『オレは今ので十分かっこ良いんだからこれでいいんだよ』って言われちゃうんだけど、髪型が変わると気分も変わって楽しいよね」
……。清光の髪に触れながら、嬉しそうに相棒のことを話す堀川を思い出すと、何だか胸がモヤモヤする。別に、堀川が和泉守のことをよく話題にするのは今に始まったことではないのに。最近、どうにも落ち着かない。
「さっきまで上機嫌だったのに、なんで急に落ち込んでるのさ」
「……何でもないけど」
「……ふーん。まぁ、気が変わって相談したくなったら話してよ」
何かを察したような顔をしながら、安定は立ち上がって部屋を出ていった。心の中に漂う靄が何なのか、自分でもまだよく分からない。でも、もしどうしたらいいか分からない、とまで思いつめるようになったら、お言葉に甘えて安定に相談させてもらうことにしよう。
それから数日後、清光は主に召集されて出陣することになった。部隊長に指名され、気分はこれ以上ないくらい高まっている。主に他の仲間たちを任せられるほど信頼されているという事実が、清光に自信を与えてくれるのだ。その期待に応えられるような活躍が自分にはできる、そう自負している。
一緒に出陣するメンバーの中には、堀川がいた。よろしくね、と笑顔で声をかけられると、なぜか心臓がドクンと跳ねた気がした。動揺を悟られないように、よろしく、とぶっきらぼうに返すのがその時の清光にできる精一杯だった。
他の出陣メンバーは比較的最近この本丸にやって来たいわゆる新人たちで、古参の清光はその引率役を任される形となった。堀川は、きっと自分のサポート役として選ばれたのだろう。新人を引き連れるということだから、今日の出陣先の戦場は、敵があまり強くないところだ。もちろん、敵が強くないからといって油断するつもりは毛頭ない。戦場はそんな甘い場所ではないということを、実戦で使われた清光はよく理解している。深く深呼吸をした後「じゃあ行くよ」と他のみんなに声をかけて、清光率いる部隊は本丸を発った。
「よっし、こんなもんかな。誰も怪我とかしてない?」
大丈夫です、と抜丸を筆頭とした新顔たちが口々に答える。横に立つ堀川も、もちろん清光も傷一つ負っていない。何戦かして新人たちの戦闘経験も積めたので、ここで引き揚げてもいい。でも、貴重な実戦の機会に張り切っているみたいだし、もう少しくらい戦ってもいいかもしれない。まだ余裕はあるわけだし。
「じゃあ、もう少しだけ頑張ろっか」
そう清光が言い終わるかどうかのタイミングで、突然ドォンと大きな音が響く。どうやら、雷が落ちたようだ。暗い雲が空を覆ってきていたから、もしかしたら雨が降るかもしれないなとは思っていた。しかし、雷が鳴るのは予想外だった。自分たちの本体は刀、つまり金属で出来ている。したがって、当然ながらあまり雷と相性は良くない。たった今口にしたばかりの言葉をいきなり覆すのは部隊長として少々気が引けるが、この場合は仕方ないだろう。
「……っ! みんな、構えて!」
突然、堀川が顔を強張らせながら叫んだ。その声に抜丸たちは慌てて刀を鞘から抜く。すぐに、ピリピリと張り詰めた空気が流れた。
雷が落ちたと思しき場所から、ゾロゾロと一団がこちらに歩いてくる。時間遡行軍ではない。……この、禍々しいオーラを放っているのは。
「加州、あいつらは何だ」
槍を構えて敵をじっと見据えながら、人間無骨が尋ねてくる。
「……あれは、検非違使だよ。遡行軍とは違う、でも、間違いなく俺たちの敵だ」
まさか、検非違使が現れるとは思ってもみなかった。少なくとも、今までこの戦場で検非違使と遭遇したという報告はなかった。だから、今回も出てこないだろうと、そう思っていた。
この状況は、かなりまずい。検非違使の強さは、部隊のメンバーのレベルによって変わる。あいつらの強さは、どういうわけか部隊で一番レベルが高い刀剣男士と同等のものになる。つまり、この中で一番レベルが高い清光の、九十九と同等の強さということだ。堀川も清光に近いレベルだが、他の四振りは十から二十前後だ。当然、まともにやり合えばこちらが圧倒的に不利ということになる。
敵の薙刀が先陣を切って襲いかかってくる。武器のリーチの長い無骨が迎え撃つが、その戦力差は歴然だった。それは、他の三振りも同様だ。清光と堀川がカバーに入るが、二振りだけでは間に合いそうにない。
清光は、この部隊の隊長だ。全員で無事に本丸に帰って来るんだよ、そう出陣前に主に言われたことを思い出す。主の信頼を裏切るような真似は、絶対にしたくない。大切な主に悲しい顔をさせるわけにはいかないのだ。部隊長の務めは、必ず果たす。それに、大切な仲間を守るのは、部隊長でなかったとしても、自分にとっては当たり前のことだ。刀剣男士・加州清光の誇りにかけて、仲間の誰も折らせはしない。
清光はいくつもの小石を手ににぎりしめると、検非違使たちに向かって思い切り投げつけた。その視線が一気にこちらへと向く。
「こっちだ! 俺が相手になってやる!」
その挑発に、複数の検非違使が即座に反応して襲いかかって来た。よし、これでいい。
「清光くん、無茶だ!」
堀川の静止の声が聞こえてくる。もちろん、無茶は承知の上だ。だが、この中で囮役に適任なのは、客観的に見てレベルの高い打刀の自分だろう。脇差の堀川は、奇襲やサポート向きだから。
「堀川、部隊長命令! みんなを安全なとこまで連れてって! それまで俺が時間を稼ぐから」
「……っ、了解」
苦虫を噛み潰したような顔をしながら、堀川は急いで他の四振りを検非違使から遠ざけて安全地帯へと誘導していく。その集団を追いかける検非違使が一体だけいたが、最後尾についていた堀川の手であっという間に倒された。流石は鬼の副長の脇差、判断が早い。清光の指示に対して思うところはあるのだろうが、それでも今は最善策だと理解し、感情を押し殺して迅速に動いてくれる。だからこそ、清光は彼を信頼して、自分の役目を果たすことに集中できるのだ。
(堀川は俺の期待に応える働きをしてくれている。なら、俺も頑張らないとだね)
刀を握り直して、眼前に迫る五体の検非違使の中の先頭を走る槍に向かって駆け出した。清光の首筋に向けて放たれた槍をすんでのところで躱すと、そのまま懐に入って胴を横に一閃する。真っ二つになった体が、瞬く間に崩れ落ちていった。だが、一体倒しただけで喜んでいるわけにもいかない。先頭の槍のすぐ後ろを走っていたもうニ体の槍が、それぞれ自分に突きを放って来るのが見えた。両方は躱しきれないだろう。致命傷を避けて、受けるしかない。槍の穂先が肉を抉るのを感じながら、清光は刀を振り下ろした。
もう、ここまで退避させれば安全だろう。周りに敵の気配も感じない。四振りとも全速力で走ってきたから多少息は切らしているが、見たところ怪我はしていない。
「僕は、清光くんの援護のために戻ります。時間遡行軍の気配は感じないので新たに敵が来ることはないと思いますが、警戒は怠らないでください。もし敵が現れた場合は、迷わず転移装置を使って本丸に戻ってください。僕と清光くんは後から戻ります」
重たい空気が流れる。無理もない、いざという時は自分と清光のことを見捨てて逃げろ、と言われているようなものだ。本丸で一緒に過ごした時間はまだ短くとも、仲間を追いて逃げるなど御免だと思うのが人情というものだ。堀川とて、逆の立場だったら同じ思いになっただろう。だが、そうも言ってられないのが戦場の厳しさだ。
「……うム、分かった。だが、必ず生きて帰って来い。此レの後輩の相棒を死なせたとあっては、会わす顔がない」
人間無骨が、じいっと見つめながら言葉を返してくる。死ぬなよ、とその瞳が強く語りかけている。
「もちろんです。じゃあ、行ってきますね」
四振りに背中を見送られながら、元来た道を急いで駆けていく。もっと、もっと速く走らなければ。今この瞬間も、清光は一振りで検非違使と戦っている。一対一なら清光が負けるはずないが、一対五となると話は変わってくる。圧倒的不利な状況でありながら、彼は自分たちを逃すために最も危険な役目を買って出てくれたのだ。
主がこの部隊に自分を抜擢してくれたのは、清光の補佐を期待してのことだろう。清光もそう思ってくれたからこそ、他の仲間たちの命を自分に託してくれたのだ。その指示を完遂した以上、ここから先の行動はこの堀川国広の意志に任されている。そして、堀川の考えることは一つだけだ。
清光を絶対に死なせたくない。少々マイペースなところもあるけど仲間想いで、寂しがり屋な彼を、一人ぼっちで死なせたりするものか。
肺にたっぷりと息を吸い込み、足の回転速度をさらに上げる。血の跡が、地面に点々とこびりついているのが見える。これは、検非違使のものだろうか。それとも、まさか清光の――。
そんな不安が湧き上がるのとほとんど同時に、人影が見えた。刀を握りしめている、あれは、誰だ。近づくと、黒いコートが目に入ってきた。ところどころ、血が滲んでいる。脇腹のあたりは、服が裂けて肉が抉られているのが見える。誰がどう見たって、重傷だ。刀を持つ腕も、震えている。今にも、崩れ落ちてしまいそうだ。
堀川の気配に気づいたのか、ゆっくりとその顔がこちらへ向く。切られた頬から血が流れて、端正な顔を赤く染めている。血と同じくらい真っ赤で綺麗な瞳が、堀川を捉えた。
「堀……川……戻って、きて……くれたんだね」
口の端を緩ませて、絞り出すように震えた声で言葉を紡ぐ。口の端から、じわりと血が滲む。
「遅くなってごめん……! もう大丈夫だよ、清光くん。だから、僕に任せて君は休んで」
痛々しいほど傷つけられた清光の姿に胸が締め付けられる。自分にもっと力があれば、彼はこんな傷だらけにならなくて済んだかもしれない。……いや、反省は後だ。今は一刻も早く、清光を本丸に連れて帰らなければ。
「あと、一体、倒しきれて、ないんだ……ごめん……後は、まか、せた」
喋りながら、清光の体がゆっくりと傾く。倒れそうになった体を抱き止めて、慎重に横に抱き抱える。大丈夫、まだ息はある。恐らく骨が折れて肺に刺さっているのだろうか、ヒューヒューと苦しそうだが、ちゃんと呼吸はしている。本丸に帰れば、すぐに主が治してくれる。もう少しの辛抱だ。
ざっ、と草を踏み締める音がした。少し顔を上げると、傷つきながらも獲物を構えてこちらを睨む太刀の姿が視界に入ってきた。禍々しい呻き声が、大地を震わせる。検非違使の握る太刀には、べっとりと血がついていた。この太刀が清光を斬ったと思うと、腹の奥がぐつぐつと熱く沸き立っていくのを感じる。
「……悪いけど、僕は急いでるんだ。君に構ってる時間が惜しい。だから、一瞬で決めさせてもらうよ」
そっと清光の体を地面に寝かせると、静かに怒った青い瞳が敵の姿を捉える。腰に差した脇差を素早く抜いて、堀川は検非違使に斬りかかった。
これはきっと、夢に違いない。たった一振り、視界におさまり切らないくらい大勢の敵と戦う自分。周りには味方となってくれる者などいない。でも、文句を言っても仕方がない。無心で刀を振い続ける。息を切らしてもなお、戦い続ける。もう腕が上がらない、となった時に辺りを見渡すと、あんなにたくさんいたはずの敵はいなくなっていた。全部、清光が倒したのだ。でも、清光の方も限界だ。地に伏して、体から力が抜けていく。
一人ぼっちで、死ぬのか。また、戦いの末に一人寂しく死んでしまうのか。
そう思うと、急に恐ろしくなった。体が冷たくなって、心まで冷えていくのが分かる。思わず、泣き叫びそうになった。誰でもいいから、助けてくれ、と。でも、それが言葉になることはなかった。誰かが、抱きしめてくれたから。閉じかけていた瞼にうっすらと映るのは、懐かしい浅葱色だった。
ゆっくりと、意識が覚醒していく。瞳に映るのは、見慣れた本丸の天井だった。ああ、帰ってきたのだな、と理解した。体のどこも痛くない。主が手入れをしてくれて、自分の部屋に寝かされているのだろう。
(俺は、一人で検非違使と戦ってた。傷を負いながら四体は倒したけど、残りの一体は傷を負わせたのに中々倒せなくって、そんなことをしているうちにどんどん体が重くなっていって。それで、確か……)
誰かの気配を感じて、振り返った気がする。そしたら、そこに堀川がいた。他のみんなを連れて安全な場所まで逃げて、すぐに清光の元に駆けつけてきてくれたのだろう。息を切らし、汗を流しながら清光を見るその姿に、一気に安心したのを覚えている。その先の記憶がないので、きっと安心したことですぐに気を失ってしまったんだろう。堀川が、もう一体の敵を倒した上で本丸に連れ帰ってくれたに違いない。後で、お礼を言わないと。
そう思って顔を横に向けると、今しがた心に思い描いていた人物が視界の中にいた。上着を脱いで、正座をしながらうつらうつら船を漕いでいる。恐らく、眠ったままの清光の様子を側でずっと見守ってくれていたのだろう。堀川だってかなり疲れているはずだ。みんなを逃がしながら検非違使と戦って、すぐに清光の元に戻って来て、残りの敵を倒して意識のない清光を連れて帰ってきたわけなのだから。それなのに、ずっと隣にいてくれた。清光のことを、心配してくれていたのだ。
あまりにもじっと彼のことを見つめていたからか、ぱちっと目が開く。ハッとこちらを見た浅葱色の瞳が、潤んでいる。今にも泣きそうな表情のまま、絞り出された「良かった……ッ」という言葉と共に、強く抱きしめられる。無意識のうちに、清光の頬は緩んでいた。
「清光くん。僕は、肝が冷えたよ。……一振りで検非違使たちを引きつけて戦うなんて。もう、あんな無茶は二度としちゃダメだからね」
優しい口調で、諌められた。普段だったら、ちょっぴり反省しながらも、堀川は心配性なんだからなぁ、とからかっていたかもしれない。でも、今はそんな気は起きなかった。全身が震えてしまいそうなくらい、胸が温かくて堪らないからだ。
力強く己を抱きしめる腕から伝わる熱が。清光の無事を喜びわずかに目尻から流れる雫が。嬉しくて、たまらなかった。
「ごめん、もうしないよ。……助けてくれてありがとね」
「ふふっ、どういたしまして」
はにかみながら清光を腕の中から解放する堀川に向かって、自然と言葉が出てきた。
「あのさ……俺、堀川のことが好きだよ」
堀川の浅葱色の瞳が、ゆっくりと見開かれる。少しの沈黙の後に、堀川は恐る恐る口にした。
「……それは、仲間として、ってことかな?」
「もちろん仲間として信頼してるし、好きだけど。それ以上に、その……一人の男として、堀川が好きってこと」
清光の告白に、驚いた瞳はさらに大きく開く。何の前置きもなくこんなことを言われるなんて思ってもいなかっただろうから、無理もない。清光も、いきなり告白するつもりなんてなかった。自分の思考よりも先に、体が勝手に動いてしまった、ということだろうか。人間の体を持つというのは、時に理性よりも本能が前に出てしまうことがある、ということなのかもしれない。
「……ごめん、こんなこと急に言われても迷惑だよね」
「そんなことないよ」
真剣な表情で、堀川が首を横に振る。
「僕も清光くんのことが好きだよ。でも、この『好き』っていうのが清光くんが言ってくれたような特別なものなのかどうかは、まだよく分からないんだ。曖昧な返事になってしまってごめんね」
「ううん、否定されないだけでも嬉しいよ。……あのさ。俺は堀川と一緒にいる時間が欲しいし、できれば俺のことを特別に好きだと思ってもらいたい。だからね、俺の気持ちに対する返事は、これから一緒に過ごす中で考えてくれないかな」
「……僕に考える時間をくれるってこと? 清光くんがそれでいいって言ってくれるなら、僕はもちろんいいけど」
「良かった。あっ、でも変に意識しなくていいからね? 自然体で接して欲しいっていうか……」
「あはは、分かってるよ。これからもよろしくね」
少し緊張感に包まれていた空気が、堀川の笑顔と共にパッと明るくなる。緩く握手をしながら、清光はその暖かい温度に心地よさを感じていた。
それからというもの、清光はできる限り堀川と一緒に過ごす時間を作るように心がけた。人間の恋人同士というのはどんなことをするのかと自分なりにリサーチし、庭を散歩したり、外に出かけたりと積極的に誘っていった。
相手を惚れさせるにはまず胃袋を掴むことから、なんて謳い文句を信じて料理を振る舞ってみたこともある。結局、残念ながらそこまで美味しいと思えるものはできなかったのだけれど。当の堀川は「すごく美味しいよ、僕のために作ってくれて嬉しいな。ありがとう」なんて言いながら喜んで食べてくれたものだから、その笑顔が見れただけでも挑戦して良かったな、なんて思えた。
そんなある日。清光は新たな試みとして、畑当番を鯰尾に頼んで代わってもらうことにした。「加州さんって畑当番好きでしたっけ?」なんて怪訝な顔をされたけど、なんとか誤魔化して了承を得ると、すぐに畑へと向かった。
鯰尾の言うように、清光は畑当番は好きではない。馬当番にしろ畑当番にしろ、汚れることは嫌いだ。戦闘以外で汗をかくのも、あまり好きじゃない。普段なら、むしろ誰かに代わってもらえたらどれほど嬉しいか、なんて思っているくらいだ。
にも関わらず自分から志願したのには、当然ながら理由がある。今日のもう一振りの畑当番は、堀川国広だ。思い返せば、今まで堀川と一緒に内番をしたことは一度もなかった。だから、仕事を口実に少しでも一緒に過ごせるならと思い立ったわけだ。
さんさんと日差しが降り注ぎ蝉の鳴き声が響く畑の中で、意中の彼はすでに作業を開始しようとしていた。少しドキドキしながら声をかけると、跳ねた襟足が風になびき、振り返る。不思議そうに眉を下げながら、堀川が尋ねてきた。
「あれっ、どうしたの? 確か今日は鯰尾くんが当番だった気がするんだけど」
「そうだよ。でも、堀川と一緒にいたいなって思ったからお願いして代わってもらったの」
恥ずかしい言葉を口にしている自覚はあるので、それを悟られないように得意げに話すと、「えっ」と短い声と共に驚いた様子の堀川の頬が、少しずつ赤くなっていく。慌てて堀川はその表情を隠すように手で覆う。清光の知る限り、初めて見る反応だ。
珍しい表情が見れたものだと内心胸を弾ませながら「じゃあちゃっちゃと仕事しますか」と清光は作業を始めようとする。すると、まだ若干頬が赤いままの堀川が待ったをかけてきた。
「植える作業は僕がやるから、清光くんは水やりと今日の分の収穫をお願いしてもいいかな」
「いいけど、堀川一人で全部植えるのって大変じゃない?」
「そんなことないよ。それに、ほら。清光くん、せっかく爪を綺麗にしてるんだから、土とか泥が入っちゃったら大変でしょ? だから、そういう作業は僕に任せて」
堀川は、清光が何故畑当番が嫌いなのか、その理由をちゃんと理解してくれた上で、こうして気遣ってくれる。彼のこういう優しいところが、愛されてるなぁって思えて、清光は好きなのだ。そう改めて実感して、思わず顔がニヤけてしまいそうになる。
「……ありがと」
そう、聞こえるか聞こえないかの小さな声で返事をすると、清光は赤くなっているであろう顔を見られないようにとすぐに自分の担当する作業を始めた。一緒に畑当番をするといっても、別々のことをしているわけだから、大して話をする時間があるわけでもない。なのに、今日は嫌なはずの仕事が何故か楽しく感じられる。恋とはこんなにも人を変えてしまうものなのかと自分でも驚きながら、清光は作業へと没頭していった。
その日の夜は、いつもよりいい気分だった。畑作業を終え、堀川となんでもないことを喋りながら本丸に帰ってきて一緒に風呂に入り、労働の後の美味しい夕飯を食べ、充実した一日だったなと思い返しながらそろそろ寝ようかと準備をしていた。
トントン、と扉を叩く音が聞こえる。夜に誰かが訪ねてくるなんて珍しいな、と思いながら「誰?」と尋ねる。遠慮がちに、「夜の時間にごめんね、まだ起きてるかな。ちょっとだけ話がしたいんだけど」と答えた声は、堀川のものだった。
恋心を抱いている相手に寝間着姿の自分を見られるのは少しだけ抵抗があるが、堀川がわざわざ清光を訪ねて来たことの喜びには勝てない。「大丈夫だよ」と声をかけると、すぐに戸が開く。ゆっくりと部屋に足を踏み入れた堀川の表情は、真剣そのものだった。
きっと前にした告白の返事をしに来たんだろうと、直感した。そうでなければ、こんな強張った顔で部屋にやって来たりはしないだろう。緊張した様子を見るに、これは断られる方かな。腹の底が重たくなるのを感じる中、堀川が目の前に座ってくる。ドクドクと、心臓の鼓動が速まっていく。手が汗ばんでいるのを感じながら、清光は自分の膝をぎゅっと握りしめて堀川の言葉を待つ。
すう、と一呼吸置いた後、堀川ははっきりと口にした。
「僕も、清光くんのことが特別に好きだよ」
てっきり断られるものだとばかり思っていたので、清光は一瞬固まってしまう。少し遅れて脳が状況を把握し、「えっ」と口にしたのと同時に、ぐいと腕を引かれて抱き寄せられる。あっという間に堀川の顔が迫って来たかと思えば、柔らかい感触を唇に感じた。キス、されている。急な展開に脳みそが中々追いついてくれない。でも、唇に触れる温かい感触は、紛れもなく本物だ。そんなことを考えているうちに、そっと熱が離れていった。
少しだけ顔を赤らめながらも、堀川は清光をまっすぐ見つめながら、口を開く。
「……今日、清光くんが畑当番に来てくれて、すごく嬉しかったんだ。清光くんは、当番はあまり好きじゃないのに、僕と一緒にいたいって気持ちでそれを乗り越えてくれた。それがすごく嬉しくて、照れながら気持ちを伝えてくれた清光くんのことを、可愛いなって思った。もっと清光くんの色んな表情が見たい。怒った顔も、笑った顔も、拗ねてる顔も、照れてる顔も、全部見せて欲しい。きっとこの気持ちが、『特別に好き』ってことなんだな、って気づいたんだ」
頬に指を添えられながら、真剣に想いを伝えられる。堀川の真摯な想いを受け取って、負けじと清光も今の自分の気持ちを口にした。
「……俺もさ、すごい嬉しかったよ。堀川と一緒に畑当番やれたことはもちろんだけど、俺のこと気遣ってくれて。分かってもらえてるんだなって、思ったから。それにね、発見もあったんだ。好きじゃないことも、堀川と一緒だって思ったら楽しくできたよ。俺、本当に堀川のことが大好きなんだなって、改めて思った」
話終わると、今度は清光の方からキスをした。背中に腕が回り、抱きしめられる。
「人間の体にも慣れたと思ってたけど、全然だね。僕、今すごくドキドキしてる」
「俺も。誰かを好きになるって、すごいな」
「うん。恋についてはまだまだ知らないことだらけだから、これから一緒に色んな初めて、見つけていこうね」
「……それは、俺と恋仲になってくれるってことでいいんだよね?」
「もちろんだよ。改めて、これからもよろしくね」
清光を抱きしめる腕の力が強くなり、そっと額に口付けられる。触れられたところがじんと温かくて、思わず口の端が緩んだ。そしたら堀川と目があって、どちらともなく笑い合った。
一緒にいるだけで、気持ちが通じ合ってるなと思えるだけで、こんなにも心が満たされる。恋って、苦しいこともあるけれど、それ以上に優しい。
その日から、二振りの関係は「恋」という特別な名前を持つようになった。